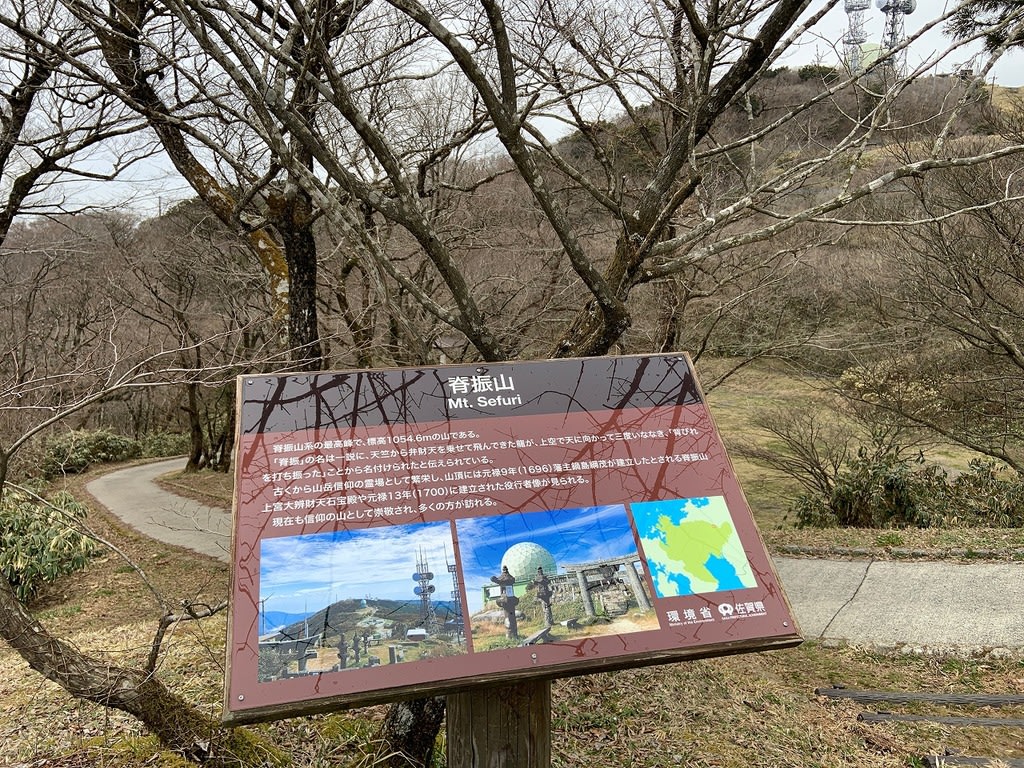2023年3月22日(水)
今回の九州移動の最後は佐世保市の虚空蔵山の予定。西海市の峯岳を終えてからの途中に西海橋公園があった。まったく予定も下調べもしていなかったので時間調整ついでに立ち寄った。
長崎県の大村湾は海域は琵琶湖の約半分ほどらしいが、外海の佐世保湾とは針尾島との間に二つの瀬戸で繋がっている。その一つ針尾瀬戸にかかる西海橋の両岸に整備されているのが西海橋公園だ。たまたま西海橋南岸の駐車場に立ち寄り時間があるので少し散策してみた。
広く整備された公園は平日でもあり人はほとんどいない。桜も咲き出した公園内を散策して少し観光気分も味わうことが出来た。

駐車場や公園は無料

桜も咲き出している

大村湾を見渡せる


公園は広くて整備が行き届いている


手前は一般国道の西海橋、奥がパールラインの新西海橋 旧針尾送信所の電波塔が残る
最後の山ランは針尾島にある虚空蔵山(209m)。佐世保市が公園として整備しており山頂近くの無料駐車場に車をおいて登った。山頂からは大村湾や佐世保港、西には五島列島も望むことが出来た。先客が下山されたのを待って7MHzのアンテナを張り、コンディションは余りよくなかったがCWで九州から関東まで7局と交信することが出来た。

山頂へ階段を登る

虚空蔵山山頂

三角点の周りにベンチなどあり

山名プレートも発見

山頂から大村湾

佐世保港には軍艦が浮かぶ

遠くには五島列島が見えた
これで今回の九州移動を終了する。フェリー2泊、現地2泊3日だったが中日は雨に降られ予定していた山のすべては回れず11座(14市郡)での山ランとなった。しかし山ラン未踏の福岡県、佐賀県、長崎県の山頂に足跡を残すことが出来、残すは福島県、宮城県の2県となった。