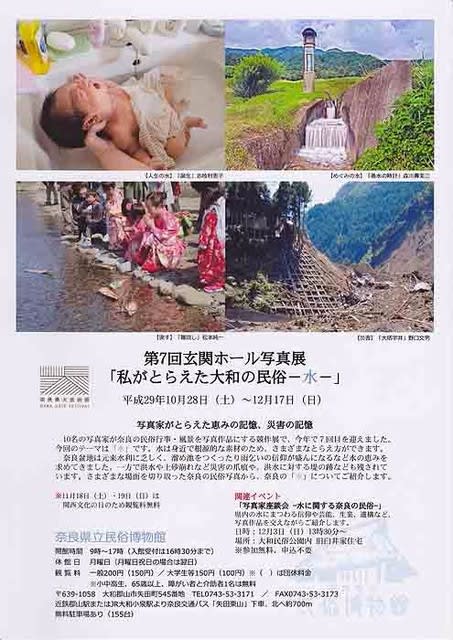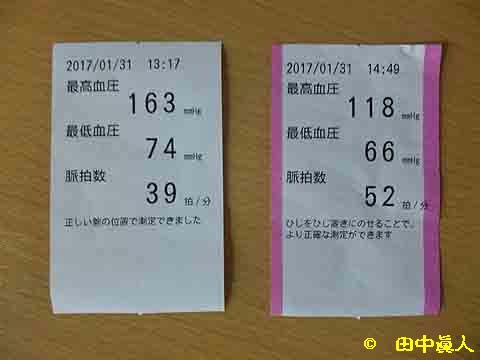奈良県の吉野町から一目散に北上する。
目的地は午後1時から餅花祭をされると聞いていた京都府南部の木津川市相楽清水に鎮座する相楽(さがなか)神社だ。
つい先月の1月15日は御田祭行事を拝見したばかりだ。
観覧者はまま多いと聞いていた餅花祭の日は固定日の2月1日。
この日は水曜日であるから平日になる。
鳥居を潜って拝殿を見たら黄色い帽子ばかりがやたらと目立つ。
帽子を被っていた子どもたちは神社向かいにある相楽小学校の3年生。
赤帽子は4年生になると云ってくれた先生方に承諾を得て撮らせてもらうが顔写りはご法度。
後方から撮るのであればと伝えられて、郷土の祭事を勉強する姿をとらえさせてもらった。
地域の郷土祭礼を学ぶことはとても大切なことである。
学校教育に活かすのは机上学習だけで済ますのではなく、見学、或いは実習などの体験学習が大切であると思っている。
これまで奈良県の行事を取材してきたが、生徒を見学させている地域はごくごく僅かの一握り。
相楽小学校の取り組みは大いに賛成したいから、撮る被写体にうしろ向き生徒の黄色い帽子を入れ込むことにした。
ところが、後方についた私のことを知った子どもたちが振り返って、「ボクも私も撮ってー」というから困ったものだ。
さて、相楽神社の餅花祭には大きな特徴がある。
相楽神社の氏子域は旧相楽村の「大里」、「曽根山」、「北之庄」の三カ大字。
座中組織がそれぞれにあり、すべてが集まって九座にもなる。
南の座は六座。
南前座北、南前座南、南中座北、南中座南、南後座北、南後座南である。
北の座は三座。
北前座、北中座、北後座である。
その座ごとに奉納される串挿しした餅花を飾る土台の藁包はヒョウタン型である。
形を調える土台の内部に泥粘土を詰めているそうだ。
丸く作った餅のてっぺんに朱色で十字。
ひと串に餅の数は2個もあれば3個挿しもある。
串をよく見れば一本ではなく2本である。
ということは2本に挿し分けた餅の数が5個である。
餅は紅白の紙片を挿したところにある。
敢えて云うなら、餅は元々その紅白の紙片に供えられていたものを串に挿すようになったのでは・・と思ったぐらいだ。
ヒョウタン型に作った藁包に一体何本の二股竹串を挿しているのだろうか。
その件については座によって若干の本数違いがみられるようで、12本或は10本になるようだ。
餅は米粉で作った餅というから味覚は団子であろう。
これを花に例えてモチバナの名がある。
良く見れば十字もあれば、ぽちょっと塗った丸型もある。
どういう意味があるのか知らないが、朱の色は食紅。
持ち帰って焼いて食べると話していた。
この餅花を竹串で挿している土台の藁包は「ションマラ」と呼んでいる。
作るには相当な手間がかかる。
特にこのヒョウタン型に作る藁包は人手もいることから、だいたいが1月末の日曜日に各座で作っていると話していた。
「餅花」を被写体に撮る人は割り合い多く見られ、ブログなどでアップする人もおられる。
行事がよくわかるブログもあれば、オコナイの一つとして紹介するブログも。
写友人のMさんもSさんアップされているので参考に・・・。
行事がよくわかる歴史探訪ブログもあれば、オコナイ定義を述べたブログもある。
昭和59年10月に発刊された京都府立山城郷土資料館編集する展示図録の『企画展―祈りと暮らし―』が手元にある。
相楽神社の餅花祭のことについては「木津町相楽のモチバナ」の項で紹介していた。
前項に「モチバナ」があるから全文を紹介しておこう。
「花は稲の稔りを予兆するものとして、特別な感情をもって眺められてきた。正月に各家でモチバナを作り、供えるものも、年頭にあたって豊作を祈る切実な願いからであった。南山城地方のモチバナ風習はすでに過去のものであるが、各地に伝承されている。南山城村の田山ではナリバナと云って神棚に福神として祭るエビス・ダイコクへ元旦に供えた。京田辺市の旧田辺町・大住のモチバナは孟宗竹の枝に餅を付けて神棚の花立てに飾った。小正月に餅を枝から外してホウラクで煎って食べた」という各家固有の習俗があった。
こうした民家で作っていたモチバナは京都南山城地方だけでなく奈良県御杖村・神末にもあった。
平成3年に発刊された中田太造著の『大和の村落共同体と伝承文化』に記載があった。
竃の神さん、いわゆる三宝荒神さんに三段重ねの「ナラシノモチ」と呼ぶ餅を供える。
クロモジの枝に小さくしたモチをたくさん付ける。
稲の穂の形に作って神棚に供える。
これをナリバナと称していた。
ナリバナはメマツ(雌松)、オマツ(雄松)、フクラソ(フクラシ)、カシノキ、サカキの5種の木とともに供えた。
同村桃俣の住民は水に浸けておいた「グ」と呼ぶ大豆を入れた餅を搗いて、柳か竹の小枝にちいさく千切ってくっつけていた。
このモチは保存しておいて「ナワシロシメ」の際に炒った。
一升枡に入れて田んぼの水口に供えて豊作を願った。
こうした行為は隣村の曽爾村でもあったナリバナ風習である。
今では見ることのない民家風習の「ナリバナ」の形は奈良市旧都祁村の上深川・元薬寺で行われていた初祈祷行事にあった。
平成21年2月7日に取材したものであるが、近年になって作るのが面倒になって廃れてしまった。
今尚、モチバナを飾るオコナイ行事をされている三重県名張市の鵜山・福龍寺に見られる。
平成25年1月13日に拝見したナリバナの大きさに驚いたものだった。
また、モチバナの名称でオコナイ行事を飾っていた奈良県宇陀市榛原の長峯・長安院の修正会である。
平成27年1月3日に拝見したモチバナ(長峯では繭玉と称する)も古来から継承してきた貴重な在り方である。
三つの事例は寺院行事であるが、いずれも真言宗派の寺院である。
正月初めに村の安全、豊作を願う修正会はオコナイとも称されているが、本日に拝見する餅花祭は相楽神社行事である。
京都府立山城郷土資料館が編集した展示図録の『企画展―祈りと暮らし―』に、相楽神社の餅花祭のことを掲載している。
「モチバナは各戸で作られて祭られるが、南山城では1カ所。相楽神社では氏神の祭りとしてモチバナが作られる。モチバナは団子状の餅を12本の竹串に5個ずつ、粘土を芯にした藁包にさしたもので、前日の夕方から神社に奉納される。朝方にかけ各座の当によって作られる。昼からはモチバナで飾られた拝殿で神楽を舞ったあと、12本のうち1本は神主に、残りは当屋から座子に配られる。このモチバナは宮座行事のなかに、モチバナ習俗を取り入れられた珍しい一例である」と書いてあった。
展示図録の『企画展―祈りと暮らし―』に書いてあった藁包の名称は「※ ショマラ」。
粘土を固めて練って藁で包んだとか、モチバナは粳米4に対して餅米は1の割合。
粉にして混ぜ合わせ、蒸して搗いたもので、最後に朱を入れて出来上がる、と製作工程を伝えていた。
「餅花」の文字を逆さに配置替えしたら「花餅」である。
「花餅」は「けひょう」と称される仏事語。前述した修正会・オコナイに、その「花餅(けひょう)」が供えられる。
平成23年1月2日に拝見した奈良県大和郡山市の矢田町・金剛山寺(通称矢田寺)の修正会も事例の一つとして挙げておく。
気になるのはこれまでモチバナ事例を紹介したなかには神社行事例はなく、寺院行事ばかりである。
明治10年以降は相楽神社の名になったが、江戸時代は八幡宮と称されてきた相楽神社に神宮寺と想定される真言宗派の不動寺があったそうだ。
不動寺は文化元年(1804)に無住となり、その後の廃仏毀釈令がでた明治時代に廃寺となり撤去されたと伝え聞く。
これまで4例の真言宗派寺院における正月年頭に行われる修正会・オコナイを紹介してきた。
ここ相楽神社もまた、神宮寺の真言宗派寺院があったのである。
以前も書いたが、江戸時代は神仏混淆の神社・寺院行事であった。
寺院が廃れて神社行事に統合された事例は多くある。
奈良県内だけでも相当数の事例があり、ここで紹介するには字数が多くなるので省かせていただくが、「餅花」の形態は寺院時代の名残、継承であることは否めない。
さて、肝心かなめの「餅花」である。
広い拝殿の天井に吊った竿にぶら下げた「餅花」に圧倒される。

一つ、一つの餅花がいまにも舞い降りてきそうな壮観な景観に見惚れて思わず見上げてしまう。
そのすべてに前述した座名を記した札に名前を記している。
南前座北、南前座南、南中座北、南中座南、南後座北、南後座南、北前座、北中座、北後座の九座のトウヤ(当屋)たちが精魂込めて作った奉納「餅花」の印しである。
昨今は業者に依頼して作ってもらっているようなことも聞くが・・・。
吊っている「餅花」に九座ではない奉納者の名前がある。

記した札にある名前は「小学校三年有志一同」である。
この写真では学校名が見えないが、黄色い帽子を被って見学している相楽小学校の3年生が奉納者である。
これもまた学習の一環。
寄進することによって郷土の行事に愛着をもつということだ。
費用、作業はともかく、このような郷土学習は他地区においても増えて欲しいと願うのである。
神事は午後1時より始まる。

小学生は座って拝見してくれたので後方にいる人たちは見やすくなったことだろう。
神事を務めるのは村神主の宮守さん。
本殿に向かって祓詞を述べて、神事に神楽を舞う巫女を祓う。
続いて献饌、祝詞奏上である。
餅花を献上されたトウヤ(当屋)たちはどこにおられるのかわからないが、宮守など白装束姿の4人が並んで座っていた。
これより始まるのは巫女さんが舞う神楽である。

手前にあるのは1月15日・御田祭神事の際、午前中に行われた「粥占(かゆうら)」の結果である。
この日の観覧者にも見ていただこうとする配慮のような気がする。
1月15日の御田祭に田植え所作をされた巫女さんと同一人物であるように思える。
本殿に向かう巫女さん。
左手に鈴。
右手に扇を持って舞う神楽。

太鼓打ちのドーン カッと縁を打つ音の調子に合わせて擦り鉦も鳴らす。
シャンシャンの音も聞こえる鈴舞は三方それぞれに頭を下げて拝礼する。
太鼓打ちの音をよく聞いておれば、ドーン カッ、ドーン カッ、ドーン カッ・・の連打である。
それを繰り返すのかと思えば違った。
よく見ておれば区切りがあることに気づく。
それはどの時点か・・。
頭を下げるのは三方。
四方拝ではなく三方拝である。
北に南にシャンシャン。
そして本社殿に向かって頭を下げている。
それは数回繰り返す作法。
その都度に打ち鳴らす太鼓の音色がドーン カッ、ドーン カッ、ドーン カッ・・の連打。
本社殿拝の場合だけは〆るドン、ドン、ドンであった。
こうして神楽舞を終えたら再び登場する宮守さんである。

その姿を撮っていてはじめて気がついた社殿の餅花。
座はどこであるのかわからないが、拝殿の餅花もそうだが相楽神社の神さんに奉納していることがよくわかる情景である。
そして撤饌。

きっちりとした作法で恭しく御供を下げる
こうして餅花祭の神事を終えたら撤収である。

供えた餅花は竿から外して下ろす。
それぞれの座中・奉納した当屋が下げる。
聞いたところによれば土台の「ションマラ」の重量は10kg。
餅花だけでも10kgもあるから合計すれば20kg。
相当な重さは架けるのも労力はいるが、下げるときも力が要る。
抱え方が拙ければ餅花を落としかねない。
二人の力を合わせて慎重に下ろしていた。
奉納した「小学校三年有志一同」も2人の担任先生が下ろしていた。

神社からいただいた撤饌もコウジブタに載せて運ぶ子どもたち。
神事中も降っていた小雨も増加傾向。
急いで支度を済ませて小学校に戻っていった。
二股の竹串は「ションマラ」に挿していた部分である。
この映像でわかるように、「ションマラ」は云っていた通りに、中身は泥粘土で作られていたのである。

北および南の座小屋ではそれぞれの座中氏子が餅花を貰っていた。
持ち帰った餅花は焼いて食べる。
そうすれば無病息災になると信じられ、貰いにくる人もあれば、地区に戻ってから当屋が配るのを待っている座中もいる。
地元民の岩井忠敏さんが所蔵する資料より抜粋した神社の「餅花祭の由来書」を宮守さんからいただいた。
若干、読みやすく補正した全文は「相楽神社の祭神は仲哀天皇(父)、神功皇后(母)、応神天皇(子)。神功皇后が朝鮮征伐の際、応神天皇の子守役の武内宿禰が浜の土で団子を造り、串に挿し、母君一行の武運長久を祈願したことより、相楽神社では当時より、2月1日に氏子が毎年交替で餅花を供え、村内の人々の繁栄と健康を祈願し、その餅花を下げてくださる儀式」である。
仲哀天皇(父)、神功皇后(母)、応神天皇(子)は八幡神の三柱(足仲彦命、気長足姫命、誉田別命)であるだけに尤もらしいが・・・。
宮守、座中が云うには、その説もあるが、他にもあると云う。
一つは「郡山大名の参勤交代の折に、神社前を通過。子どもを泣かせないために餅を串に挿してあやした」。
殿さんが通った道のお馬を下りたとされるババサキ(馬場先)の小字がある。
当時の神社は広く、現在の小学校地も境内であった。
小学校東側、100mほど東に向かえば往来した郡山街道がある。
もう一説は「平安遷都の折、相楽の八幡宮が奈良の大安寺八幡宮が京の都の裏鬼門にあたる男山八幡宮(石清水八幡宮)に向かう際に、当社の宮守が歓んで守護する一行に餅をふるまい接待した」である。
子どもをあやしたという説も三柱祭神由来、守護接待説も後付け説のように思えて仕方がない。
前述したように餅花は寺院行事。
年頭に願う村の安全と豊作を願う修正会・オコナイの名残としか考えようがない、と思うのであるが・・。
歴史、地理的背景は木津川だよりブログを参考にした。
(H29. 2. 1 EOS40D撮影)
目的地は午後1時から餅花祭をされると聞いていた京都府南部の木津川市相楽清水に鎮座する相楽(さがなか)神社だ。
つい先月の1月15日は御田祭行事を拝見したばかりだ。
観覧者はまま多いと聞いていた餅花祭の日は固定日の2月1日。
この日は水曜日であるから平日になる。
鳥居を潜って拝殿を見たら黄色い帽子ばかりがやたらと目立つ。
帽子を被っていた子どもたちは神社向かいにある相楽小学校の3年生。
赤帽子は4年生になると云ってくれた先生方に承諾を得て撮らせてもらうが顔写りはご法度。
後方から撮るのであればと伝えられて、郷土の祭事を勉強する姿をとらえさせてもらった。
地域の郷土祭礼を学ぶことはとても大切なことである。
学校教育に活かすのは机上学習だけで済ますのではなく、見学、或いは実習などの体験学習が大切であると思っている。
これまで奈良県の行事を取材してきたが、生徒を見学させている地域はごくごく僅かの一握り。
相楽小学校の取り組みは大いに賛成したいから、撮る被写体にうしろ向き生徒の黄色い帽子を入れ込むことにした。
ところが、後方についた私のことを知った子どもたちが振り返って、「ボクも私も撮ってー」というから困ったものだ。
さて、相楽神社の餅花祭には大きな特徴がある。
相楽神社の氏子域は旧相楽村の「大里」、「曽根山」、「北之庄」の三カ大字。
座中組織がそれぞれにあり、すべてが集まって九座にもなる。
南の座は六座。
南前座北、南前座南、南中座北、南中座南、南後座北、南後座南である。
北の座は三座。
北前座、北中座、北後座である。
その座ごとに奉納される串挿しした餅花を飾る土台の藁包はヒョウタン型である。
形を調える土台の内部に泥粘土を詰めているそうだ。
丸く作った餅のてっぺんに朱色で十字。
ひと串に餅の数は2個もあれば3個挿しもある。
串をよく見れば一本ではなく2本である。
ということは2本に挿し分けた餅の数が5個である。
餅は紅白の紙片を挿したところにある。
敢えて云うなら、餅は元々その紅白の紙片に供えられていたものを串に挿すようになったのでは・・と思ったぐらいだ。
ヒョウタン型に作った藁包に一体何本の二股竹串を挿しているのだろうか。
その件については座によって若干の本数違いがみられるようで、12本或は10本になるようだ。
餅は米粉で作った餅というから味覚は団子であろう。
これを花に例えてモチバナの名がある。
良く見れば十字もあれば、ぽちょっと塗った丸型もある。
どういう意味があるのか知らないが、朱の色は食紅。
持ち帰って焼いて食べると話していた。
この餅花を竹串で挿している土台の藁包は「ションマラ」と呼んでいる。
作るには相当な手間がかかる。
特にこのヒョウタン型に作る藁包は人手もいることから、だいたいが1月末の日曜日に各座で作っていると話していた。
「餅花」を被写体に撮る人は割り合い多く見られ、ブログなどでアップする人もおられる。
行事がよくわかるブログもあれば、オコナイの一つとして紹介するブログも。
写友人のMさんもSさんアップされているので参考に・・・。
行事がよくわかる歴史探訪ブログもあれば、オコナイ定義を述べたブログもある。
昭和59年10月に発刊された京都府立山城郷土資料館編集する展示図録の『企画展―祈りと暮らし―』が手元にある。
相楽神社の餅花祭のことについては「木津町相楽のモチバナ」の項で紹介していた。
前項に「モチバナ」があるから全文を紹介しておこう。
「花は稲の稔りを予兆するものとして、特別な感情をもって眺められてきた。正月に各家でモチバナを作り、供えるものも、年頭にあたって豊作を祈る切実な願いからであった。南山城地方のモチバナ風習はすでに過去のものであるが、各地に伝承されている。南山城村の田山ではナリバナと云って神棚に福神として祭るエビス・ダイコクへ元旦に供えた。京田辺市の旧田辺町・大住のモチバナは孟宗竹の枝に餅を付けて神棚の花立てに飾った。小正月に餅を枝から外してホウラクで煎って食べた」という各家固有の習俗があった。
こうした民家で作っていたモチバナは京都南山城地方だけでなく奈良県御杖村・神末にもあった。
平成3年に発刊された中田太造著の『大和の村落共同体と伝承文化』に記載があった。
竃の神さん、いわゆる三宝荒神さんに三段重ねの「ナラシノモチ」と呼ぶ餅を供える。
クロモジの枝に小さくしたモチをたくさん付ける。
稲の穂の形に作って神棚に供える。
これをナリバナと称していた。
ナリバナはメマツ(雌松)、オマツ(雄松)、フクラソ(フクラシ)、カシノキ、サカキの5種の木とともに供えた。
同村桃俣の住民は水に浸けておいた「グ」と呼ぶ大豆を入れた餅を搗いて、柳か竹の小枝にちいさく千切ってくっつけていた。
このモチは保存しておいて「ナワシロシメ」の際に炒った。
一升枡に入れて田んぼの水口に供えて豊作を願った。
こうした行為は隣村の曽爾村でもあったナリバナ風習である。
今では見ることのない民家風習の「ナリバナ」の形は奈良市旧都祁村の上深川・元薬寺で行われていた初祈祷行事にあった。
平成21年2月7日に取材したものであるが、近年になって作るのが面倒になって廃れてしまった。
今尚、モチバナを飾るオコナイ行事をされている三重県名張市の鵜山・福龍寺に見られる。
平成25年1月13日に拝見したナリバナの大きさに驚いたものだった。
また、モチバナの名称でオコナイ行事を飾っていた奈良県宇陀市榛原の長峯・長安院の修正会である。
平成27年1月3日に拝見したモチバナ(長峯では繭玉と称する)も古来から継承してきた貴重な在り方である。
三つの事例は寺院行事であるが、いずれも真言宗派の寺院である。
正月初めに村の安全、豊作を願う修正会はオコナイとも称されているが、本日に拝見する餅花祭は相楽神社行事である。
京都府立山城郷土資料館が編集した展示図録の『企画展―祈りと暮らし―』に、相楽神社の餅花祭のことを掲載している。
「モチバナは各戸で作られて祭られるが、南山城では1カ所。相楽神社では氏神の祭りとしてモチバナが作られる。モチバナは団子状の餅を12本の竹串に5個ずつ、粘土を芯にした藁包にさしたもので、前日の夕方から神社に奉納される。朝方にかけ各座の当によって作られる。昼からはモチバナで飾られた拝殿で神楽を舞ったあと、12本のうち1本は神主に、残りは当屋から座子に配られる。このモチバナは宮座行事のなかに、モチバナ習俗を取り入れられた珍しい一例である」と書いてあった。
展示図録の『企画展―祈りと暮らし―』に書いてあった藁包の名称は「※ ショマラ」。
粘土を固めて練って藁で包んだとか、モチバナは粳米4に対して餅米は1の割合。
粉にして混ぜ合わせ、蒸して搗いたもので、最後に朱を入れて出来上がる、と製作工程を伝えていた。
「餅花」の文字を逆さに配置替えしたら「花餅」である。
「花餅」は「けひょう」と称される仏事語。前述した修正会・オコナイに、その「花餅(けひょう)」が供えられる。
平成23年1月2日に拝見した奈良県大和郡山市の矢田町・金剛山寺(通称矢田寺)の修正会も事例の一つとして挙げておく。
気になるのはこれまでモチバナ事例を紹介したなかには神社行事例はなく、寺院行事ばかりである。
明治10年以降は相楽神社の名になったが、江戸時代は八幡宮と称されてきた相楽神社に神宮寺と想定される真言宗派の不動寺があったそうだ。
不動寺は文化元年(1804)に無住となり、その後の廃仏毀釈令がでた明治時代に廃寺となり撤去されたと伝え聞く。
これまで4例の真言宗派寺院における正月年頭に行われる修正会・オコナイを紹介してきた。
ここ相楽神社もまた、神宮寺の真言宗派寺院があったのである。
以前も書いたが、江戸時代は神仏混淆の神社・寺院行事であった。
寺院が廃れて神社行事に統合された事例は多くある。
奈良県内だけでも相当数の事例があり、ここで紹介するには字数が多くなるので省かせていただくが、「餅花」の形態は寺院時代の名残、継承であることは否めない。
さて、肝心かなめの「餅花」である。
広い拝殿の天井に吊った竿にぶら下げた「餅花」に圧倒される。

一つ、一つの餅花がいまにも舞い降りてきそうな壮観な景観に見惚れて思わず見上げてしまう。
そのすべてに前述した座名を記した札に名前を記している。
南前座北、南前座南、南中座北、南中座南、南後座北、南後座南、北前座、北中座、北後座の九座のトウヤ(当屋)たちが精魂込めて作った奉納「餅花」の印しである。
昨今は業者に依頼して作ってもらっているようなことも聞くが・・・。
吊っている「餅花」に九座ではない奉納者の名前がある。

記した札にある名前は「小学校三年有志一同」である。
この写真では学校名が見えないが、黄色い帽子を被って見学している相楽小学校の3年生が奉納者である。
これもまた学習の一環。
寄進することによって郷土の行事に愛着をもつということだ。
費用、作業はともかく、このような郷土学習は他地区においても増えて欲しいと願うのである。
神事は午後1時より始まる。

小学生は座って拝見してくれたので後方にいる人たちは見やすくなったことだろう。
神事を務めるのは村神主の宮守さん。
本殿に向かって祓詞を述べて、神事に神楽を舞う巫女を祓う。
続いて献饌、祝詞奏上である。
餅花を献上されたトウヤ(当屋)たちはどこにおられるのかわからないが、宮守など白装束姿の4人が並んで座っていた。
これより始まるのは巫女さんが舞う神楽である。

手前にあるのは1月15日・御田祭神事の際、午前中に行われた「粥占(かゆうら)」の結果である。
この日の観覧者にも見ていただこうとする配慮のような気がする。
1月15日の御田祭に田植え所作をされた巫女さんと同一人物であるように思える。
本殿に向かう巫女さん。
左手に鈴。
右手に扇を持って舞う神楽。

太鼓打ちのドーン カッと縁を打つ音の調子に合わせて擦り鉦も鳴らす。
シャンシャンの音も聞こえる鈴舞は三方それぞれに頭を下げて拝礼する。
太鼓打ちの音をよく聞いておれば、ドーン カッ、ドーン カッ、ドーン カッ・・の連打である。
それを繰り返すのかと思えば違った。
よく見ておれば区切りがあることに気づく。
それはどの時点か・・。
頭を下げるのは三方。
四方拝ではなく三方拝である。
北に南にシャンシャン。
そして本社殿に向かって頭を下げている。
それは数回繰り返す作法。
その都度に打ち鳴らす太鼓の音色がドーン カッ、ドーン カッ、ドーン カッ・・の連打。
本社殿拝の場合だけは〆るドン、ドン、ドンであった。
こうして神楽舞を終えたら再び登場する宮守さんである。

その姿を撮っていてはじめて気がついた社殿の餅花。
座はどこであるのかわからないが、拝殿の餅花もそうだが相楽神社の神さんに奉納していることがよくわかる情景である。
そして撤饌。

きっちりとした作法で恭しく御供を下げる
こうして餅花祭の神事を終えたら撤収である。

供えた餅花は竿から外して下ろす。
それぞれの座中・奉納した当屋が下げる。
聞いたところによれば土台の「ションマラ」の重量は10kg。
餅花だけでも10kgもあるから合計すれば20kg。
相当な重さは架けるのも労力はいるが、下げるときも力が要る。
抱え方が拙ければ餅花を落としかねない。
二人の力を合わせて慎重に下ろしていた。
奉納した「小学校三年有志一同」も2人の担任先生が下ろしていた。

神社からいただいた撤饌もコウジブタに載せて運ぶ子どもたち。
神事中も降っていた小雨も増加傾向。
急いで支度を済ませて小学校に戻っていった。
二股の竹串は「ションマラ」に挿していた部分である。
この映像でわかるように、「ションマラ」は云っていた通りに、中身は泥粘土で作られていたのである。

北および南の座小屋ではそれぞれの座中氏子が餅花を貰っていた。
持ち帰った餅花は焼いて食べる。
そうすれば無病息災になると信じられ、貰いにくる人もあれば、地区に戻ってから当屋が配るのを待っている座中もいる。
地元民の岩井忠敏さんが所蔵する資料より抜粋した神社の「餅花祭の由来書」を宮守さんからいただいた。
若干、読みやすく補正した全文は「相楽神社の祭神は仲哀天皇(父)、神功皇后(母)、応神天皇(子)。神功皇后が朝鮮征伐の際、応神天皇の子守役の武内宿禰が浜の土で団子を造り、串に挿し、母君一行の武運長久を祈願したことより、相楽神社では当時より、2月1日に氏子が毎年交替で餅花を供え、村内の人々の繁栄と健康を祈願し、その餅花を下げてくださる儀式」である。
仲哀天皇(父)、神功皇后(母)、応神天皇(子)は八幡神の三柱(足仲彦命、気長足姫命、誉田別命)であるだけに尤もらしいが・・・。
宮守、座中が云うには、その説もあるが、他にもあると云う。
一つは「郡山大名の参勤交代の折に、神社前を通過。子どもを泣かせないために餅を串に挿してあやした」。
殿さんが通った道のお馬を下りたとされるババサキ(馬場先)の小字がある。
当時の神社は広く、現在の小学校地も境内であった。
小学校東側、100mほど東に向かえば往来した郡山街道がある。
もう一説は「平安遷都の折、相楽の八幡宮が奈良の大安寺八幡宮が京の都の裏鬼門にあたる男山八幡宮(石清水八幡宮)に向かう際に、当社の宮守が歓んで守護する一行に餅をふるまい接待した」である。
子どもをあやしたという説も三柱祭神由来、守護接待説も後付け説のように思えて仕方がない。
前述したように餅花は寺院行事。
年頭に願う村の安全と豊作を願う修正会・オコナイの名残としか考えようがない、と思うのであるが・・。
歴史、地理的背景は木津川だよりブログを参考にした。
(H29. 2. 1 EOS40D撮影)