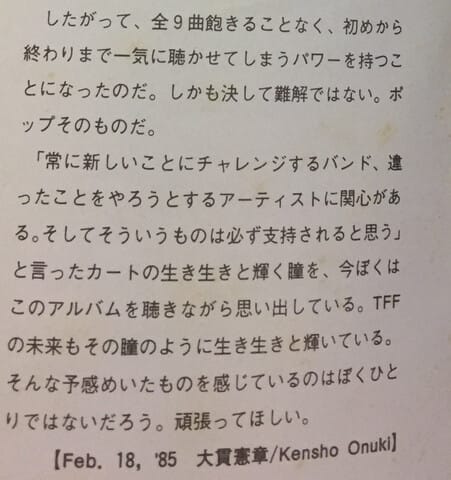前回『序章』にて書いたとおり
(詳しい意義については以下バックナンバーをどうぞ)
↓
https://blog.goo.ne.jp/12mash/e/8bdc829b72111e9df30b90dc66750021
今日から『1985年』の意味ある盤を何枚か取り上げていく。
さあ、栄えある第1回は?
『Tears For Fears / シャウト(Songs from the big chair)』

今まで当店『ジェリーズギター』でも、決して誰にも語って来なかった・・・そんな秘密をも初めて告白しながら、この盤を書き進めていきたい。
85年・・・この春に俺は『中学入学』を果たし、無事『中学生』となり数週間後には野球部へと入部するわけだが、この盤を買うキッカケは小学校を卒業した春休みであった。とにかく当時の俺はFMラジオばかりを聴いていて、当時隔週で出版されていた『FM Station』という雑誌を欠かさすに購入していたんだ。とにかくこの雑誌には2週間の主要FMの番組表が網羅され、音楽情報記事も満載であった。あの当時は最新のヒット曲はモチロン、海外で行われたライブ番組も豊富にプログラムされていて、穴の開くほど番組表を眺めながらテープに録音していく(エアチェックという)予定の番組に赤ペンで丸をつけるのが楽しみだったんだよ!
さて、この『ティアーズフォーフィアーズ(以下TFF)』を最初に耳にしたのもラジオであり、その曲とは当時ヒットしていた『Everybody wants to rule the world』である。正直に言うと『信じられないくらいガツーンと来た!』しかもその理由は「この曲、ビートルズみたい!」っていう感じでね(笑)。そしてすぐに『お馴染みの中古レコード屋さん』へ向かったんだ。
当時の俺は藤沢駅の南口にあった『中古レコード屋さん』に暇さえあれば行っていたんだけれど、残念ながら店舗名を覚えていないんだ。確か『ディスク~』とか『~ディスク』だった様な気がするが、俺は「中古レコード屋さん」と言っていたんだよね。現オーパの裏手に有った小さなお店で、俺の、いや『ジェリーズ』の原点、ソレは間違いなく『このお店』にあると言えるね。
店長のおじさんがレジ奥の丸椅子に俺を座らせてくれて、色々と様々な盤を聴かせてくれた・・・。素晴らしい体験だったな。映画『ニューシネマパラダイス』の音楽版だね。買ってくれたお客さんに「ありがとうございました~」とか店員気取りで言っちゃってさ。で、とにかくそこへは気になった曲があると書き留めて出掛けるんだ。今まではそれでシングル盤を購入していたのだが、このTFFは物凄くLPが欲しかったのを覚えているよ。
多くの人は『新譜なんて中古に出ない』とお思いだろうが、ところがそうでもなくて『買ったはいいが、気に入らない』という人も結構いるし、発売から時間が経たずに手放せば高価で買い取ってくれる・・・ということもあり、「まあ持って無くてもテープに録音して売っちゃおうか」という人も多い時代だったんだ。とは言え『おじさん』に紙を見せると「うちにはまだ入って来てないなぁ・・・」と言われちゃってね。「そうですか・・・」としょぼんとしている俺を見て「ちょっと聞いてみるよ」と、どこかへ電話をしてくれたんだ。そして電話が終わると「1週間後には間違いなく店に有るから、もう1度おいでよ!」と言ってくれてね。この1週間は待ちきれない思いだったな。そして1週間後に1700円で手に入れた国内盤を本当に本当に繰り返し聴いたもんなんだ。
そして『大貫憲章』先生が書くメンバー「カート・スミス」へのインタビューをも交えたライナーノーツも、それこそ穴が開くほど読ませて頂いたワケなのだが・・・そこで、だ。幼少の俺は氏の書かれている巻末の一文がどうしても理解できずに日々悶々とした春休みを過ごしたのである。それは「決して難解ではない。ポップそのものだ。」という一節なのだが、「コレのどこがポップなんだ?」と英和辞書を片手に試行錯誤で訳しながら氏に対して疑問を抱いていた毎日だったんだよねぇ。
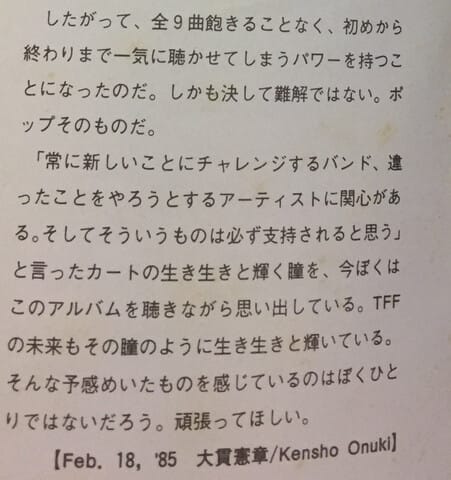
実際このアルバムに入っている曲は全てと言っていいほど『問題定義された詞』で溢れ返り、ポップな詞やラブソングは皆無!先出のヒット曲も「誰もが世界を操りたがっている!」と世界のリーダーたち・・・特に当時の冷戦を思わせる歌詞であったし、もう1つの革新的なサウンドメイクとクールなギターソロが続く長編ヒット曲『Shout!』も「上からの押し付けと戦え!」って取れる曲なんだよ。次に来るウィリアム・グレゴリーのサックスソロがグイグイと迫り、メル・コリンズのサックスが好サポートする『The working hour』だって通常のポップロックからは大いに逸脱しているアレンジが施されているし、終いにゃ「自分自身で今までの価値観はすぐにでも変えられる!」みたいなことを歌うわけですよ。
ぐったりとクタビレてB面に裏返すとメンバーの『ローランド・オーザバル』が奏でるグランドピアノの美しさと幻想的世界が渦巻く名曲『I Believe』からメドレーとまでは行かないまでも、曲間を無くし何らかの形でつなげていく手法が取られ、ラストはブライアン・イーノの『アンビエント感』とビートルズの『No9』が混在したかのような『Listen』という良い意味で奇妙な曲でエンディングを迎えてしまう・・・しかも歌詞カードでは『Found a brave world』と記されているものの、確実に『Found a brave(New)world』と歌われており、当時『brave new world』を辞書で調べると『シェークスピア作品』やら『ハクスリーの小説』やら・・・今までの曲が深い歌詞だっただけに、最後の最後も良く分からない『リスナーへの警告』で終わっているみたいでね・・・

この様に、聴くたび聴くたび「どこがポップなんだよ!」と突っ込む中学生であったわけだが、今聴いてどうかって?ソレは今も変わらないわけですよ!(笑)大貫先生には申し訳ないのだが、声を大にして言いたい「全くポップじゃないし、むしろ難解なアルバムなんですよ!コレは!」ああ、スッキリした(笑)
とにかく、幼少期の俺にゃ「評論家だか、なんだか知らねぇが、このアルバムの事を本当に分かってんのかねぇ?」とハートに火がついたワケですよ。「俺の方が絶対に理解出来てる!俺が評論家になったる!」みたいな大いなる夢が生まれたキッカケが本作であり、コレ以降「出るアルバムは何でも聴いて評論家になってやる!」と意欲が湧いたもんさ。
内容的には今聴いても『斬新で、普遍的メッセージに溢れた怪作』と言ってイイし、『全く古くならないアルバム』でもある。
誰も言わないかもしれんが、ポピュラー音楽史においても『重要な作品』であることには間違いなく、それ以上に成長期の自分が熱心に聴いた身として『大人は勿論のこと、子供たちにこそ聴いて欲しい作品』とも言えるね!あの時コイツを手に入れることが出来、俺は「本当にラッキーだった」と思うよ。このアルバムを聴いていなければ今の俺は間違いなく存在していないし、人間形成的にも『親以上に影響を与えた作品のひとつ』だと言えるからね。
そう考えると『中古レコード屋さんのおじさん』そして『大貫先生』にも感謝せざるを得ない。
「ロックンロールで戦争は終わらないが、ひとりの人生を変えることは出来る・・・」
まさしく、ボノの言うとおりに俺は育ったのだと思うよ。
しかし、このアルバムの歌詞が40年後の今(2025年)でも警鐘として受け取れてしまう世の中なんて・・・
子供の頃は想像もしなかったし、ホント残念でならないな。
Love & Peace!
《編集長& Jerry's Guitarオーナー「Mash」筆》
ご意見・ご感想・記事投稿・編集長の執筆、演奏、講演依頼などは『コメント欄』か『ハードパンチ編集部』までどうぞ!
https://hardp.crayonsite.com
編集長『MASH』が経営するギター専門店『Jerry's Guitar』公式サイトはコチラ
https://jgmp.crayonsite.com/