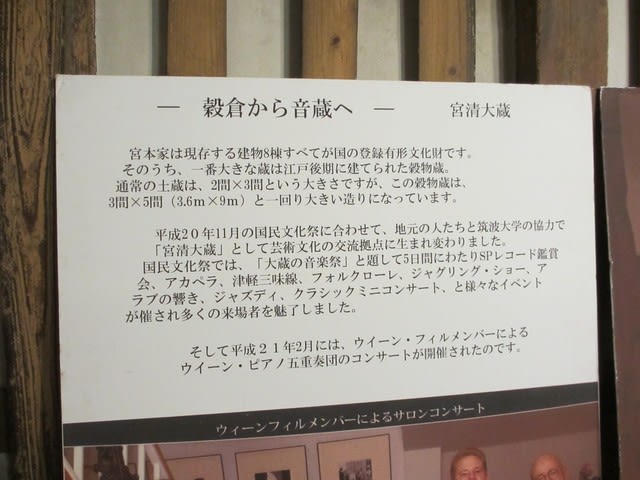5月13日(日)、静岡市清水区蒲原(JR東海道線新蒲原駅徒歩7分)にある「
旧五十嵐歯科医院(旧五十嵐邸)」(H12年:国登録有形文化財)を訪れました。
午後から強雨で翌日仕事がある娘夫婦は帰宅しましたが、毎日が日曜日の我々夫婦はもう1泊沼津で宿泊して帰ることにし、蒲原宿に来ました。
「由比宿」には何度か来たことがありますが「蒲原宿」は初めて。

旧五十嵐邸は旧東海道蒲原宿の街道沿いにあり、大正期以前に町屋建築として建てられ、当主の故五十嵐準氏が東京歯科専門学校(現東京歯科大学)を卒業した大正3年(1914年)頃に歯科医院を開業するにあたり、町家を洋風に改築。


その後、西側部分を増築、更に東側を増築し、一体的な洋館として改築。敷地面積は546㎡、延床面積355㎡

中庭から見た母屋。

四室が縦に並ぶ町家の間取り

1階の中の間に設置された金庫。入れ歯に使用する金などが保管されていたそうです。

富士と松原の欄間に花鳥風月が描かれた襖。


1階の通り土間を持つ純粋な町家。2階の診療室には洋風の階段を上がる。

2階の診療室。ガラス窓が多い構造で、採光・換気が良く、開放的な空間。床はリノリウムで和洋折衷の造り。

診察椅子

2階西側の座敷。特別な人の待合室に使用されていた部屋。

中庭には診療用の水を組み上げたポンプや池などがあります。

中庭。

2階から見た北側の中庭。蔵と赤いトタン屋根の建物(非公開)までが五十嵐家。更に奥に見えるのが東名高速道路。
ウナギの寝床のように奥行きがあります。

トイレの外壁「なまこ壁」と装飾が施された窓ガラス。今では作れる人がいないそうです。

御勝手(おかって)

かまど(へっつい)

五右衛門風呂・・・。洗出しの流し、氷を入れる冷蔵庫、網戸入りの食器棚などの装置もありました。
「志田邸」
志田邸は木造2階建、切妻造、平入で、西側の平屋部は昭和初期の増築。土間の戸口に大戸の痕跡、道路に面した開口部に蔀度を残し、蒲原宿の往時の佇まいを今に伝えています。

安政年間(1855年頃)に再建された元商家で、国登録有形文化財。屋号を「やま六」といい、しょう油・味噌・油などを扱っていました。

玄関横の部屋は「店の間」と呼ばれる「商いの部屋」で箱階段や火鉢などな備えられている。
今日まで電気を引いたことのない、安政建築そのままの部屋です。

「蔀戸(しとみど)」や店の間・中の間など商家の面影がよく残されています。
(蔀戸は風雨と陽を遮る戸で、上から3分の2は吊り、下3分の1は取り外す方式)

明治時代の五月飾り。中の間は一間半(一畳半)の縁なしの畳が使用されている。

昔のお膳、食器類など。

明治年間に増設された西側平屋の8畳の座敷。

醤油の醸造所の土壁。下は三和土(タタキ)、周囲は竹を芯にした土壁で囲み、外側は石積の防火構造となっています。

屋号の「やま六」の看板。この醤油工場は東海道の宿場内でほぼ当時のまま現存・公開されている唯一の工場と言われているそうです。
この日は、東京在住のオーナー(志田威さん)がちょうどいらっしゃって、展示物などを詳細に解説してくれました。
東海道は五十三次ではなく、実は五十七次だそうです。初めて知りました。
志田邸の後は、旧五十嵐歯科医院のガイドボランティアの方に紹介して頂いた蒲原の味処「
よし川」で昼食。
この時間は土砂降りで往生しました。

定番の「桜海老としらすの紅白定食」、あーちゃんは「桜えびの黄金丼」を注文。

桜えびは由比の揚げ方と違うとのことで食べやすい物でした。(桜海老としらすが水揚げされたのは由比漁港です。)
「和泉屋」

江戸時代「和泉屋」の屋号で旅籠として使われていた国登録有形文化財。看板かけや2階の手すりは天保年間当時のままのもの。

右側のみ、「お休みどころ」として無料開放されています。

玄関を入ったところ。館内では織り・染め・銀細工・粘土クラフトなどの体験もできるそうです。

昔の排煙口?。現在はトップライト(明り取り)になっています。
この日は生憎の雨で寒い日でしたが「蒲原宿」を堪能することが出来ました。
これから「静岡県富士山世界遺産センター」へ向かいます。(別ページで後日紹介します)