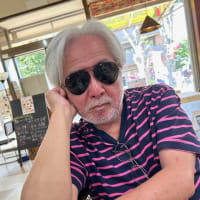【連載】頑張れ!ニッポン㉒
パワー半導体のユニークな出荷先
釜原紘一(日本電子デバイス産業協会監事)

▲三菱重工神戸造船所(同社HPより)
深海艇用のパワー半導体を担当した
半導体製品は一般的に汎用製品、すなわち何にでも使える製品が多い。しかし、中には特定の出荷先に向けた製品もある。私が担当していたパワー半導体で、今でも印象に残っているものに「深海艇用」の製品があった。
それは「しんかい2000」という深海艇向けの製品で、同艇は日本初の本格的な深海の有人潜水調査船として1981年に三菱重工神戸造船所で完成したものである。海洋科学技術センター(現: 海洋研究開発機構略称JAMSTEC)が所有し、2002年11月まで運航された。
私はこの「しんかい2000」用の大電力ダイオードの開発に携わった。深海艇はバッテリーでスクリューを回して動くが、その仕組みでダイオードが使われる。深海艇を開発し製造を担当する事に決まった三菱重工(株)神戸造船所(神戸市和田岬町)に、何回も出向いて技術打合せを行った事が思い出される。
ところで、私が勤務していた三菱電機㈱のことに触れたい。もともとは三菱重工㈱の造船部門の電機工場が分離独立してできた会社で、創業以来100年以上経っている。創業の経緯が頭にあるせいか、三菱重工で打合せをしていると、何となく我々が下請け会社のような気分になったものだ。
直近の三菱重工の売り上げは、連結ベースで4兆6500億円に対し、三菱電機の売り上げは同じく5兆2800億円と上回っているのだが…。

▲しんかい2000(海洋研究開発機構のHPより)
南鳥島近海の海底に眠るレアメタル
話はそれたが、「しんかい2000」は深さ2000メートルの海底に潜って海底の調査を行う。2000メートルもある深海では200気圧の圧力がかかるので、その圧力に耐える構造が必要である。我々が暮らすこの地上の気圧は大体1気圧だから、その200倍の圧力がかかるというわけだ。
我々が当時製造していた大電力用のダイオードは、圧力に対してかなり強い構造になっていたので、200気圧に耐えられる見込みはあると思っていた。その実証試験は三菱重工の高砂製作所で行われたが、実用に十分こたえられることが実証されたのである。 記録によると、「しんかい2000」の完成は1981年だから、開発したのは今から50年前の1970年代だったことになる。上述の通り、同艇は2002年に引退したが、後継の深海艇「しんかい6500」が1989年に完成している。
この時、私は既に本社勤務となっており、同艇については何も知らないが、深海艇の事は「しんかい2000」の開発に関わったこともあり、今も関心を持ち続けている。
我が国初の深海艇である「しんかい2000」は、日本周辺を中心に様々な海域に潜航し、相模湾・初島沖で化学合成を行うシロウリガイのコロニーを発見、沖縄トラフでは熱水噴出現象を発見するなど、日本の深海研究の進展に大きく貢献してきた。
後継となる「しんかい6500」は6500メートルまで潜る能力を有しているが、2016年にレアメタル(希少金属)を含む鉱物が密集する海域を、南鳥島近海の海底で確認する事に成功している。
レアメタルは、スマートフォンや電気自動車などに欠かせないが、今は輸入に頼っている。東大の加藤泰浩教授(地球資源学)は「日本のEEZ(排他的経済水域)を開発できれば、国産の資源を活用して産業化できる可能性がある」と話す。
日本は世界一の「深海大国」
日本は、領海とEEZ内で5000メートル以深の体積が世界1位の「深海大国」である。「しんかい6500」は2040年代に設計上の寿命を迎えるが、文部科学省は後継の有人機をつくる技術が途絶えていることや、コストの問題もあり無人機を優先して開発する方針を決めたとの事である。
私はここで非常に残念に思うのは、深海艇の開発でも技術が継承されていないという事だ。半導体でも最先端の製造技術が十分に継承されていない事が問題になっている。
余談になるが、東日本大震災の時原発事故が起こったが、それ以来原子力関係の技術者は減少傾向にあると言われている。原子力分野でも技術が継承されなくなるのではないだろうか。
何か問題が発生するとマスコミは寄ってたかってバッシングする傾向があるように思う。一時の感情に囚われることなく、将来を見据える洞察力を持つジャーナリストはいないのか。

▲しんかい6500(日本財団図書館より)
また話がそれてしまったが、深海についての研究や海底資源をめぐっては各国の探査機開発競争が激化しており、日本もウカウカしていられない。
有人機の後継船をめぐっては、2015年にJAMSTECが「しんかい12000」構想を公表し、2020年代後半にも運用を始めるとしていたが、その計画はとん挫し、上述の様に今後は無人機の開発を優先するとの事だ。
JAMSTECは「しんかい6500」を寿命まで使った後、AI(人工知能)を搭載した無人機を導入し。有人機により窓から深海を観察する代わりに、VR(バーチャルリアリティー)技術で無人機のカメラを通して観察できるシステムを開発する案を示している。
上述のように、深海にはレアメタルのような資源が豊富にある事が期待されており、我が国としてはこの分野の開発は継続して力を入れていくべきだろう。

【釜原紘一(かまはら こういち)さんのプロフィール】
昭和15(1940)年12月、高知県室戸市に生まれる。父親の仕事の関係で幼少期に福岡(博多)、東京(世田谷上馬)、埼玉(浦和)、新京(旧満洲国の首都、現在の中国吉林省・長春)などを転々とし、昭和19(1944)年に帰国、室戸市で終戦を迎える。小学2年の時に上京し、少年期から大学卒業までを東京で過ごす。昭和39(1964)年3月、早稲田大学理工学部応用物理学科を卒業。同年4月、三菱電機(株)に入社後、兵庫県伊丹市の半導体工場に配属され、電力用半導体の開発・設計・製造に携わる。昭和57(1982)年3月、福岡市に電力半導体工場が移転したことで福岡へ。昭和60(1985)年10月、電力半導体製造課長を最後に本社に移り、半導体マーケティング部長として半導体全般のグローバルな調査・分析に従事。同時に業界活動にも携わり、EIAJ(社団法人日本電子機械工業会)の調査統計委員長、中国半導体調査団団長、WSTS(世界半導体市場統計)日本協議会会長などを務めた。平成13(2001)年3月に定年退職後、社団法人日本半導体ベンチャー協会常務理事・事務局長に就任。平成25(2013)年10月、同協会が発展的解消となり、(一社)日本電子デバイス産業協会が発足すると同時に監事を拝命し今日に至る。白井市では白井稲門会副会長、白井シニアライオンズクラブ会長などを務めた。本ブログには、平成6年5月23日~8月31日まで「【連載】半導体一筋60年」(平成6年5月23日~8月31日)を15回にわたって執筆し好評を博す。趣味は、音楽鑑賞(クラシックから演歌まで)、旅行(国内、海外)。好きな食べ物は、麺類(蕎麦、ラーメン、うどん、そうめん、パスタなど長いもの全般)とカツオのたたき(但しスーパーで売っているものは食べない)