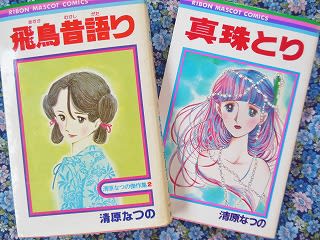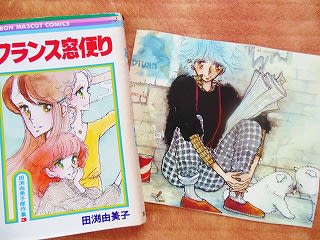
「フランス窓便り」田淵由美子(りぼん 1976年6~8月号)
すみません、写真がちょい小さすぎ。
右のイラストは「りぼんオリジナル」という雑誌の表紙でした。イラスト部分だけ切り取ったものを、あと何枚か持っているので、次回大きく出しますね。
で、田淵由美子さんです! 言わずと知れた「りぼん」の看板作家さん。なつかしい~!
とにかく絵柄が好きでした。かわいくて、あたたかみがあって、ハイセンス。
ちょっとアンティークな感じのファッションも、おしゃれですてきだった。
定規を使わずにペン入れするフリーハンドの手法で背景を描いてますが、それが効果的で、手作り感いっぱいでしたね。
お話のほうは、ほとんどが「自分に自信のない女の子」と「超イケメン男子」のラブストーリー。
性格のゆがんだ人間は皆無、まちがいなくみんな善人、まちがいなくハッピーエンド。
でもそこがよかった、というか、それがよかった。
安心して好きな絵柄にひたっていられました。
「このストーリーが好き!」というより、「田淵由美子ワールドが好き!」っていうのかな。
でもこれって、案外大変なことですよ。よほど画面に力がないとできないことですから。

「フランス窓便り」は、ひとつの家でくらしている3人の少女たちの連作短編でした。
安心の由美子ワールドでしたが、同時収録の「ローズ・ラベンダー・ポプリ」がさらに好きだったので、記念に写真を。
タイトルからして、あこがれでしたねー。ラベンダーとかポプリとかいう単語を知らない、女学生時代に読んだものだから(笑)。
あと、特筆すべきだと思うのは、キャラたちの年齢と舞台ですね。
ほとんどが大学生(たぶん早大生)で、大学のキャンパスとかもしょっちゅう出てくる。これが大変よかった。
高校じゃだめなんですよ。大学というのがポイント。
自分たち(女学生)が住んでいる場所とは少し離れた、少しおとなの世界。
かわいい絵柄にもかかわらず、そういうムードが、とくに男性キャラのほうにはっきり出ていてとても魅力的でした。
あたりまえですが、幼い絵柄のまま設定だけを大学生にしたって、魅力的でもなんでもありません。
おとなのムードを演出するに足る力が、作家にあったということです。
田淵さん自身は、「りぼん」時代のあとのほうでは、ハッピーエンドじゃない切ないストーリーに移行しようとした気配があります。
本当の意味でおとなっぽい、別のタイプの話も描きたくなったのかな、と思いながら読んでいましたが・・・。
出版社のニーズもあるし、それこそオトナの事情も大きい世界なんでしょうね。
つづきます


















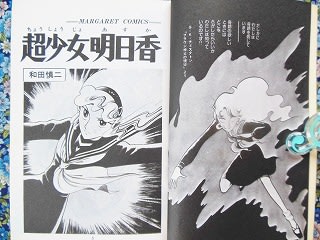



 こちらは、おまけ。
こちらは、おまけ。