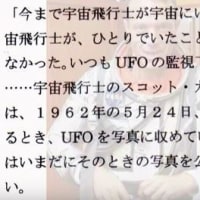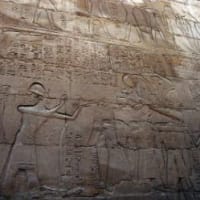Q.抗血小板薬を服用中・・・ 内出血が多いが、薬との関係は?
今年3月半ばに急性心筋梗塞で入院し、心臓の血管にステントを2か所入れる治療を受けました。今は元気になったのですが、血液をサラサラにする薬を飲んでいるので、歯医者は歯茎を切るような治療は控えるようにと言われています。最近、内出血が多く困っています。ぶつかったりした覚えがないのに、大きな青あざが腕などにあって、びっくりすることがあります。今も、腕に黒いアザが残っています。血管が切れやすくなっているのでしょうか。これは血液をサラサラにする薬と関係がありますか。(59歳女性)
A. 内出血は、薬、加齢、ビタミン不足などが原因か―南淵明宏 大和成和病院院長(神奈川県大和市)
大いに関係があります。前にもご相談いただいた、ステント治療の後、どうしても必要なプラビックスという薬剤による影響で出血が止まりにくい状況があるのだと想像されます。この薬によって、ステント治療による効果が永きにわたって続くために血液の持つ「出血を止める機能」を鈍磨させる必要があるのです。
なぜならステントはすばらしい医療器材ですが血管にとっては異物です。この部分を通過した血液がこのよそ者に驚いて、血管が破れて出血が起こった事態が起こったと勘違いして、血液を固めようと反応してしまいます。それを防止するための薬なのです。これを抗凝固療法と呼んでいます。
青あざが自然とできてしまうというのも、こういった抗凝固療法によるものと想像されます。血管が切れやすくなっているわけではありません。これは軽微な物理的損傷で誰でもいつでも毛細血管は切れてしまうのですが、その小さな出血をすぐに止血することができないせいで起こっているものです。
出血が止まる、という現象にはいくつかの要素が働いています。まずは血管の因子です。血管が脆いと出血もしやすいし出血を止めることもままなりません。でもこれは薬のせいではありません。加齢や栄養状態の不良化、ビタミンの不足、などによって血管の壁の構造が脆くなってしまうのです。
次に血液の因子です。血液の中に溶け込んでいる成分が、①量的に足りない②しっかり働かないーーことで、血が止まりにくくなります。プラビックスやワーファリン、バイアスピリンは出血を止める成分を②のように「しっかりと働かない」ようにする薬です。ご相談者の場合、血管の因子と薬の影響の両方で青あざができやすいと思われます。
さて、歯医者さんなど、心臓以外の問題で別の領域のお医者さんにかかる場合、こういった薬で抗凝固療法が行われている患者さんは敬遠されがちです。治療に出血が伴うと、その出血が自然に止血されない可能性があるからです。リスクのある、面倒な患者さんを扱いたくない気持ちを持つお医者さんがいるのは仕方がありません。
時に歯医者さんから「歯の治療をしたいので抗凝固療法の薬をしばらく止めていいですか?」とアホな質問をされます。こういった薬は心臓の働きを維持している薬です。そういう歯医者さんは歯の治療さえうまく行けば、治療台の上で患者さんの心臓が止まることがあっても平気なのでしょう。歯科医師の団体のホームページでも「心臓病治療中の抗凝固療法は中断してはならない」と注意が喚起されているのですが、こういった事情にも無頓着な歯科医もけっこういらっしゃるようです。
ご相談者様が心臓の治療を受ける病院や医師をしっかりと自分で吟味したように、歯の治療でもしっかりと歯科医を吟味して治療を受けるべきです。
(読売・医療相談室記事より)
◆これって大変なことですね! 歯科医師も知らないなんて。・・患者が賢くならなくては・・
◆医療機関案内
今年3月半ばに急性心筋梗塞で入院し、心臓の血管にステントを2か所入れる治療を受けました。今は元気になったのですが、血液をサラサラにする薬を飲んでいるので、歯医者は歯茎を切るような治療は控えるようにと言われています。最近、内出血が多く困っています。ぶつかったりした覚えがないのに、大きな青あざが腕などにあって、びっくりすることがあります。今も、腕に黒いアザが残っています。血管が切れやすくなっているのでしょうか。これは血液をサラサラにする薬と関係がありますか。(59歳女性)
A. 内出血は、薬、加齢、ビタミン不足などが原因か―南淵明宏 大和成和病院院長(神奈川県大和市)
大いに関係があります。前にもご相談いただいた、ステント治療の後、どうしても必要なプラビックスという薬剤による影響で出血が止まりにくい状況があるのだと想像されます。この薬によって、ステント治療による効果が永きにわたって続くために血液の持つ「出血を止める機能」を鈍磨させる必要があるのです。
なぜならステントはすばらしい医療器材ですが血管にとっては異物です。この部分を通過した血液がこのよそ者に驚いて、血管が破れて出血が起こった事態が起こったと勘違いして、血液を固めようと反応してしまいます。それを防止するための薬なのです。これを抗凝固療法と呼んでいます。
青あざが自然とできてしまうというのも、こういった抗凝固療法によるものと想像されます。血管が切れやすくなっているわけではありません。これは軽微な物理的損傷で誰でもいつでも毛細血管は切れてしまうのですが、その小さな出血をすぐに止血することができないせいで起こっているものです。
出血が止まる、という現象にはいくつかの要素が働いています。まずは血管の因子です。血管が脆いと出血もしやすいし出血を止めることもままなりません。でもこれは薬のせいではありません。加齢や栄養状態の不良化、ビタミンの不足、などによって血管の壁の構造が脆くなってしまうのです。
次に血液の因子です。血液の中に溶け込んでいる成分が、①量的に足りない②しっかり働かないーーことで、血が止まりにくくなります。プラビックスやワーファリン、バイアスピリンは出血を止める成分を②のように「しっかりと働かない」ようにする薬です。ご相談者の場合、血管の因子と薬の影響の両方で青あざができやすいと思われます。
さて、歯医者さんなど、心臓以外の問題で別の領域のお医者さんにかかる場合、こういった薬で抗凝固療法が行われている患者さんは敬遠されがちです。治療に出血が伴うと、その出血が自然に止血されない可能性があるからです。リスクのある、面倒な患者さんを扱いたくない気持ちを持つお医者さんがいるのは仕方がありません。
時に歯医者さんから「歯の治療をしたいので抗凝固療法の薬をしばらく止めていいですか?」とアホな質問をされます。こういった薬は心臓の働きを維持している薬です。そういう歯医者さんは歯の治療さえうまく行けば、治療台の上で患者さんの心臓が止まることがあっても平気なのでしょう。歯科医師の団体のホームページでも「心臓病治療中の抗凝固療法は中断してはならない」と注意が喚起されているのですが、こういった事情にも無頓着な歯科医もけっこういらっしゃるようです。
ご相談者様が心臓の治療を受ける病院や医師をしっかりと自分で吟味したように、歯の治療でもしっかりと歯科医を吟味して治療を受けるべきです。
(読売・医療相談室記事より)
◆これって大変なことですね! 歯科医師も知らないなんて。・・患者が賢くならなくては・・
◆医療機関案内