いつもランキングにご協力ありがとうございます。1日も1クリックお願いしま す。
 にほんブログ村
にほんブログ村
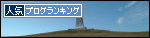 よろしければこちらもクリックお願いします
よろしければこちらもクリックお願いします
TEACCHプログラムで、重要なアセスメント視点してあげられるのが『芽ばえ反応』です。芽ばえ反応は、もう少しで本人が自立しそうな、達成しそうな部分です。
ゲーリー・メジボフ先生は「合格の方に向かっているもの」と表現されました。
分かりやすい状況や構造化を入れることで、気づき、自立に向かうようにするのが計画の方向性です。
自閉症教育・支援フレームワークでも、芽ばえ反応はアセスメントする重要な視点になります。しかしインフォーマルアセスメント※の中で、どのような状態を芽ばえ反応とするのかは、慣れるまで時間がかかります。
そこで、今回は「芽ばえ反応」になる視点を書き出した資料を用意しました。実践の中でご活用ください。
※インフォーマルアセスメントは、検査具をつかわない支援現場でのアセスメントになります。『フレームワークを活用した自閉症支援』では、これを推奨しています。
課題を見て芽ばえをどのように設定したか観てみます。

芽ばえ反応は2種類の分類です。まだ彼は5回に数回のミスがあります。
違いのはっきりした材料・指示を活用、プットインの指示で強く注目する設定になっています。それにより合格に近付けていきます。
視覚的明瞭化:プットインになっている。材料の色と課題の白色
視覚的整理統合:一体型で、材料がまとまっている
本日は以上です。読んでいただきありがとうございます。
【『フレームワークを活用した自閉症支援』のFacebookページができました】
【『フレームワークを活用した自閉症支援』を10倍活用する!(随時更新)】
【Amazonでの購入はこちら】
【スペース96での購入はこちらから】

















