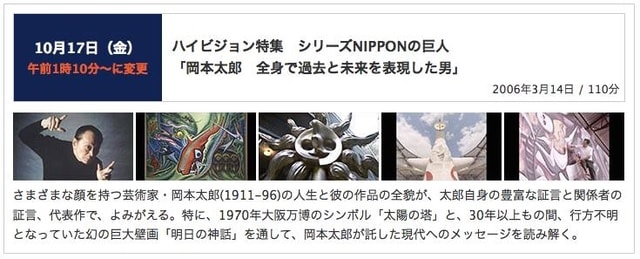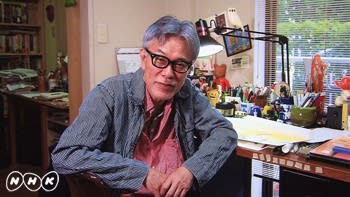寂聴文学塾第五回は「堕落論」で有名な坂口安吾です。
安吾は戦後間もなくの頃、太宰治、織田作之助とともに人気作家の1人でした。
初期は純文学作家、後年は何でも屋の文筆業。
悪く云えば大衆作家に成り下がり、良く言えば何でも書けた才能の持ち主。
家族を持ち、子どもも生まれて平和な家庭生活を望みましたが、ヒロポン中毒で入退院を繰り返し、やはり若くして亡くなりました。
当時の文学者の間にはヒロポンが蔓延していたようです。
それを使うと徹夜して書き続けても大丈夫、ということでした。
文筆業を含めて芸術家というのは脳の過覚醒状態をみな経験しているような気がします。
その時に素晴らしいアイディアが浮かぶので「神が降りてきた」なんて表現されます。
精神状態は躁うつ病の「燥」ですね。
つまり、躁うつ病(現在は双極性障害と呼ばれています)が芸術家の資質ではないかと感じることがあります。
それはさておき。
以前、TVで坂口安吾の「堕落論」特集を見たことがあります。
新鮮な驚きはなく、「なるほど」という以外の感想を持てませんでした。
私は安吾と考え方が似ているのかもしれません。
寂聴さんは戦後、北京から引き揚げてきてすぐに「堕落論」を読み、大きく影響を受けたそうです。
価値観が混沌としていてなにをしていいかわからない状況下、ええい堕落してやれと家を出て放浪生活を始めた若かりし頃。
のちに「安吾賞」という文学賞を受賞した寂聴さんは、受賞記念の挨拶で「私がこの賞をもらったのは、作品の内容ではなくて、生き方が安吾を地で行っていたからです」と話したそうです。
安吾は戦後間もなくの頃、太宰治、織田作之助とともに人気作家の1人でした。
初期は純文学作家、後年は何でも屋の文筆業。
悪く云えば大衆作家に成り下がり、良く言えば何でも書けた才能の持ち主。
家族を持ち、子どもも生まれて平和な家庭生活を望みましたが、ヒロポン中毒で入退院を繰り返し、やはり若くして亡くなりました。
当時の文学者の間にはヒロポンが蔓延していたようです。
それを使うと徹夜して書き続けても大丈夫、ということでした。
文筆業を含めて芸術家というのは脳の過覚醒状態をみな経験しているような気がします。
その時に素晴らしいアイディアが浮かぶので「神が降りてきた」なんて表現されます。
精神状態は躁うつ病の「燥」ですね。
つまり、躁うつ病(現在は双極性障害と呼ばれています)が芸術家の資質ではないかと感じることがあります。
それはさておき。
以前、TVで坂口安吾の「堕落論」特集を見たことがあります。
新鮮な驚きはなく、「なるほど」という以外の感想を持てませんでした。
私は安吾と考え方が似ているのかもしれません。
寂聴さんは戦後、北京から引き揚げてきてすぐに「堕落論」を読み、大きく影響を受けたそうです。
価値観が混沌としていてなにをしていいかわからない状況下、ええい堕落してやれと家を出て放浪生活を始めた若かりし頃。
のちに「安吾賞」という文学賞を受賞した寂聴さんは、受賞記念の挨拶で「私がこの賞をもらったのは、作品の内容ではなくて、生き方が安吾を地で行っていたからです」と話したそうです。