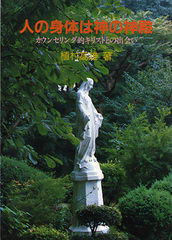<自死>を選ぶ人の生涯を想うと、とても哀しくなりますが、それ以上に自分の孤独を見る事を大半の人は避けています。これは当然の精神現象で孤独な自分を意識するほど惨めな事はありません。何故、孤独感が重要視されるかと言いますと哲学の世界では孤独感から実にすばらしい思想が誕生してきているからです。神との出会いも孤独感から生まれてくるのが大半なようです。親友がいない、愛してくれる人が居ない、と気付いた人はまずは神様が自分を愛してくれているというカトリツク神学を一度覗いてみませんか?人類の歴史そのものですから非常に面白いです。学問としてのこの思想は人類史上、一番重要な思想だと私は思っています。どんなに貧しい自分、汚れた自分、罪深い自分でも、神様が誰よりもそんな自分を愛してくださっていると信じる事が出来たら<自死>という事だけは避けられます。そればかりでなく生きていく希望と勇気と知恵が自然と湧いてくる不思議さを体験として五感と体感で理解出来ます。:<何を信じたらいいのか:385-5>:
いつもクリックして下さり有難うございます。感謝いたします。
 人気blogランキング
人気blogランキング
いつもクリックして下さり有難うございます。感謝いたします。
 人気blogランキング
人気blogランキング














 医者にしてもセラピストにしても患者さんの具体的な症状に触れたときに咄嗟にどんな概念、イメージがスーッと頭に浮かぶかで、その仕事の世界での優劣が決まります。イメージが湧かない人はどんどん職場を去る羽目になります。さてこの場合は<不安感><環境適応能力><解釈>の3つが優れた概念です。aさんはこの大震災の雰囲気の中で津波や家の喪失に遭遇したわけではありませんが放射能被害や風評に<不安感>を感じています。あるがままの現実をどう<解釈>しているか、といいますと自分をストレス曲線(不安感、怒り、身体症状、鬱、錯乱の5つ)へ追い込むような解釈をしていて幸福曲線(平安感、友好的感情、健康感、幸福感、統御感の5つ)へ押しやるような解釈はしていません。この傾向に気付いたaさんは環境にとにかく適応しようと努力開始をしましたら少し平安になつたそうです。このような流れが今は大事なのです。<何を信じたらいいのか:385-2>:
医者にしてもセラピストにしても患者さんの具体的な症状に触れたときに咄嗟にどんな概念、イメージがスーッと頭に浮かぶかで、その仕事の世界での優劣が決まります。イメージが湧かない人はどんどん職場を去る羽目になります。さてこの場合は<不安感><環境適応能力><解釈>の3つが優れた概念です。aさんはこの大震災の雰囲気の中で津波や家の喪失に遭遇したわけではありませんが放射能被害や風評に<不安感>を感じています。あるがままの現実をどう<解釈>しているか、といいますと自分をストレス曲線(不安感、怒り、身体症状、鬱、錯乱の5つ)へ追い込むような解釈をしていて幸福曲線(平安感、友好的感情、健康感、幸福感、統御感の5つ)へ押しやるような解釈はしていません。この傾向に気付いたaさんは環境にとにかく適応しようと努力開始をしましたら少し平安になつたそうです。このような流れが今は大事なのです。<何を信じたらいいのか:385-2>: