新説百物語巻三 7
7、あやしき焼物喰ひし事
ヘビをうまいうまいと食べたこと
さる大国の国守より、一年に一度づつ御領内の調査に役人たちを遣わす事があった。
その国の山家に三百軒ばかりの一村があった。
庄屋が代官とを兼任していて、治めており、富江の何某と言う者であった。
調査(御検分)の侍衆は、その所に滞留して一宿した。
山家の事であるので、ご馳走もなく、料理もおおかたは精進であって、焼物ばかりはさかなであった。
切れ目は鰤のようであって味も思いの外よかった。
その翌日、侍の一人がそのあたりをぶらぶらと歩いた。
すこし高みに小屋のあったのでのぞいて見れば、あるひは香のものような物などがあって、又おおきな桶に魚の切ったのを塩づけにして、五つ六つならべて置かれていた。
侍は、ゆうべのやきものはこの魚であろう、と思った。
「さあ、焼いて食べよう」としてて、四五人打ちよって、火であぶって食べると、言葉にならないほど美味しかった。
二切三切も食べたが、しばらくすると、体中があつくなり酒に酔った様にふらふらとして、足も立たず、身もなえて、正気のあるものは一人もなかった。
それを食べなかった侍の仲間たちは、これを見て大いに肝をつぶして、大騒ぎをした。
庄屋の富江はそれを聞き付けて、そこへ来た。
「もしかして、小屋の内に蓄えておいた桶の内のものをお食べになりませんでしたか?」と問うた。
侍たちは、これまでの様子を話したところ、何やら草の葉を持って来て、水で飲ませた。
しばらくして、みなみな、酔いが醒めもとのようになった。
「これは何でしょうか?。又昨晩は何の事もなく、今日はこのように酔ってしまったのでしょうか?」と問うた。
すると、庄屋はこう答えた。
「特別の物では、御座いません。ここは山奥でして海に遠く、殊の外さかなのは手に入りません。冬になった蟒(うわばみ)が食に飢えて弱った時をねらって、狩り取って小さk切り、塩漬けにして一年中の客に出しております。
この焼物を出す時は、同時に連銭草を浸し物にして付けております。
そうしないと、先のよううに酒に酔ったようになり、四五日も正気にもどらないのでございます。」と。
昨夜、この焼物をたべた者のうちで、なにとやら気味が悪く、吐いたりした者もあったそうである。
訳者注:連銭草は、カキドオシ。利尿、消炎作用がある。ヘビの肉は、通常、中毒(本文では、酔ったようになる、とあるが)を、起こさない。また、連銭草がヘビの毒に有効である、などの事は、古典に記述は見られない。














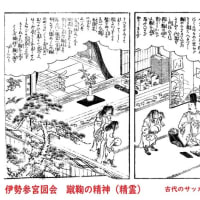




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます