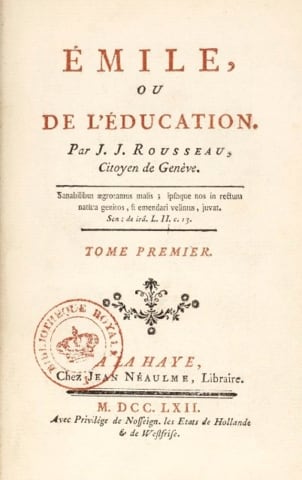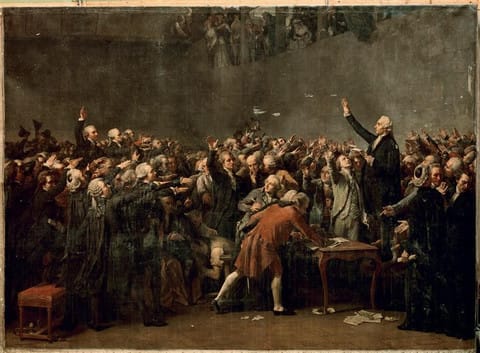白百合と菊Lys et Chrysanthèmeさんの、ビルコック(Billecocq)神父様による哲学の講話をご紹介します。
※この公教要理は、 白百合と菊Lys et Chrysanthèmeさんのご協力とご了承を得て、多くの皆様の利益のために書き起こしをアップしております
Billecocq神父に哲学の講話を聴きましょう
それから、最後に、15歳になってから、エミールにはいよいよ宗教を教わり始めるということです。ルソー論において、宗教教育の始まりは15歳からです。これについての文章は次の引用で始まります。
「私の生徒のよう少年時代を通じて、私が彼に宗教について何も語らないのを知って、どれほど多くの読者が驚きを感じることだろう。それを私は予想する。十五歳になっても彼は、自分が魂を持っているかどうか知らなかったが、十八歳になっても、まだそれを学ぶ時期ではあるまい。」
さすがに。エミールは自分自身しか見ていなく、自分中心主義になっているものの、霊魂とは何であるかに関して教えなくてはならないとね。
「真理を理解できる状態に置かれていない者にむかって真理を告げるようなことは控えよう。それは真理の代わりに誤謬に置かれていないことを与えようとすることだ。神にふさわしくない卑俗で幻想的な観念、冒涜的な観念をもつよりは神について何の観念も持たないでいる方がましだ。」(106頁)
次に、宗教に対する過激な攻撃文があります。有名な文章ですが、次回、見ておきたいと思っております。それは『サヴォアの助任司祭による信仰宣言』という部分です。要するに、神父を登場させて、エミールに宗教を教える設定です。
それによって、ルソーはエミールを社会的な生活に投げ込むのです。次回にご紹介することにします。時間を必要とするし、今回はもう時間をオーバーしています。
『サヴォアの助任司祭による信仰宣言』を見ることによって、ルソーの宗教生活というか、ルソーにとっての宗教はなんであるかをよく示しています。

それから、第五編になります。第五編においてソフィーと出会って、結婚します。出会ってから、まず恋愛して、そして、二年間ほどエミールが旅立ってソフィーと会っていないが、そのあと、いよいよ結婚するという流れです。そして、父です。そして、次は小説となって、『ジュリ または新エロイーズ』とつながります。最終的に、「身内だけで自立して生活している」というのが理想とされます。それによって、社会を避けるためであるといっています。
こういった理想こそは『ジュリ または新エロイーズ』著作の中心テーマです。思い出しましょう。二組の夫婦は同じ家に住んでいて自給自足のような状態で小説が終わります。
以上、ルソーの『エミール』を簡潔に要約する試みをしてみました。どうしても、多くの引用をご紹介することにしました。それは、ルソーが言っていることをよく示して、ルソーの思想とされているものが本当にルソーが思っていたことだと強調するためでした。
*********************************
結びとして、いくつかの点を指摘したいと思っております。
第一、理想主義ばっかりです。これは一目瞭然でしょう。
まず、生まれながら人間は善性であるという理想主義です。生まれながら善性の子供なんて合ったことはありません。それが現実です。
それから、エミールという生徒に関する理想主義です。エミールを完全に夢から生まれさせて一から作り上げるのです。綺麗な教育論かもしれませんが、そもそもこういった「エミール」は現実に存在しない生徒です。しかも、ルソーはどうしてもその生徒が独りぼっちとなり、唯一、一人しかない教師を許すだけと言います。教師でさえ、ルソーでさえ、あり得ない設定を作ります。教師はいつも生徒のそばにいられるかのように書いてありますが、それはルソーの夢想にすぎません。
一言でいうと、この教育論は、ルソーの失敗だらけの自分の人生に対する復讐のようなものだと言えましょう。
教師についての理想主義もあります。全く存在しない教師です。つまり、エミールといった存在しない生徒に、そう言った存在しない教師が付くという設定の教育論ですが、実際の世界では一体どうやって適用できるといえるでしょうか。ルソーはあり得ないほど、大げさに議論を展開します。それが本質的にルソーの教育論の真相だと認めざるを得ません。
ルソーによる過剰論です。そういった大げさな夢想はまたほかにあります。それは、教育の段階の仕切り方です。そもそも完全にあり得ない仕切り方です。
ルソーに言わせると、0歳から2歳まで、人間は体だけ。2歳から12歳まで感覚的な霊だけ。12歳から15歳までいよいよ理性の始まりが出始めて。そして、いよいよ15歳以降、道徳感がでてくると言っているわけです。
それはあり得ません。実際は、人間は最初から人間です。つまり、生まれた瞬間から、もう人は人です。つまり、体と霊魂を生まれた瞬間から持っているというのは真実なのです。言い換えると、子どもは生まれると体を持ち、五感で感覚を持ち、それから理性をも持っています。
潜在力として、少なくとも成長していく能力としてもうすでに知性がそなわっているのです。そういえば、7歳は分別の時代だとよくいわれていますね。平均だけですから、それより早く分別がついてくる子どももいますが、分別の年齢になると、子どもは本物の質問、深い質問を聞いてきます。

「なぜ?」と聞く子どもは紛れもなく理性があるということを具体的に示しています。動物はどうしても「なぜ?」と思うことはできません。「なぜ?」と問う子供は物事の理由、物事の目的を知りたいわけです。また、「何のためにある」ということを知りたいわけです。あるいは、子どもは「何ですか?」と聞くときに、ある物事の本性を知りたいわけです。それも理性があるということを表しています。
ルソーにとって、理性は大体12歳になってから出てくるといっています。というか、早くて12歳で、おそらくより遅く出てくるといっています。というのも、18歳になっても、霊魂があるということを知らなくてもよいと主張するぐらいですから。そういった主張を見てみるとね、どう見ても。
ちょっと大げさに言わせてもらうと、ルソー論は狂気です。なぜか狂気であるかというと、「非現実」的な理論ですから。この『エミール』は教育論でもなんでもなく、ある程度のフィクション、小説にすぎないだけではなく、しかも人間の心理を完全に読み間違っている小説です。
それはともかく、『エミール』の中心の目的は、「真理を否定するための攻撃文」だと思っています。ルソーは根本的に、真理を教えることを固く拒みます。
そして、子どもはたまたま自分の力で真理をみつけたとしても、あくまでも有用性のある真理でなければならないと言います。彼にとって目に見えないことに関する真理は論外です。彼にとって形而上学や宗教は教えてはいけないのです。宗教に関して、ルソー論における「教育論」においてどうなっているかを次回ご紹介しますが、なかなか大変です。
要するに、ルソーの教育論において、真理はダメです。ところが、それよりひどい話があります。真理どころか、何の知恵・ノウハウ・技術の継承も、ダメだとされています。教育論における「師傅」は教師でもなく、師匠でもなく、先生でもありません。つまり、何の継承も、何の権威もありません。ルソーの教育論は「自分を自分で教育する」という「セルフ教育」なのです。つまり、きわめて個人主義であり、また児童の権利を称賛する教育論です。本質的にそういったものです。
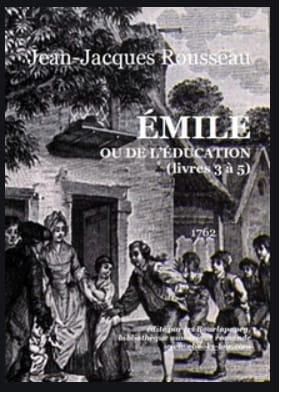
これから、ある考察を引用したいと思っております。その方は若手で、世間で意外と人気のあるかたです。私は彼の言動に関してすべてに同意しているわけではありませんが、François-Xavier Bellamyです。『不運の時代・継承すべしという緊急について』 という本を出しました。その中に、ルソーについて次のことを言っています。
「最初の二つの「論」において(第一回と第二回のときご紹介したルソーの論ですね)、現代普及した空気の原点がそこにあります。」確かに。
「しかしながら、『エミール』において、さらに一歩先です。完全になっているつもりの教育論で、実際の応用のための計画であるという位置づけで書かれています。そして、現代の公教育、非常に組織化された文部省によって実現された計画なのです。」
面白いでしょう。
「ルソーの教育論を読むと、現代、公教育の失敗だとよく評価されている多くの悪い結果は、ルソーの教育論でいうと実際にはかなりの成功であることに気づきます。現代の公教育は、完全に明白に紹介されたルソー教育論の成功なのです。一言でいうと、何の知恵・知識を継承することを固く絶対に拒む教育論の実現です。」
当たっていますね。言い換えると、現代の公教育は成功しています。なぜかというと、馬鹿な愚かな大人を養成しているからです。つまり、近代主義でいうと、愚かな人間を養成するのは失敗ではありません。わたしたちからみると、失敗に見えるかもしれませんが、近代主義的な教育論の筋でいうと本来ならば、とんでもない成功なのです。つまり、知恵・知識を継承しないという基本です。エミールは無知であるべきだからです。
彼はこう続けます。
「そういった教育は経験主義を基盤にしています。それはある種の自然主義です。」まさに当たっています。
また、エミールが自由であるかのように描写されていますが、実際に自由なんて何もありません。いや、それよりひどく、かなりの矛盾があります。というのも、エミールは結局、他人のまねをする、完全に順応主義になっています。その「師傅」についていくだけです。実際において、その「師傅」はエミールに対して暗に多くのことを禁じて、何もやらせていないのです。そして、案の定、エミールは社会人になったら、そういった教育ですから、順応主義にならざるを得ません。本当にひどいものです。
そういえば、『エミール』の最後には、エミールがソフィーと結婚しますが、なぜ結婚するかというと「師傅が望んだから」ということだけですよ!つまり、結婚する自由でさえありません。師傅は自由であることをエミールに信じ込ませていますが、実際において師傅の人形にすぎないのです。
最初にちょっと申し上げた通りです。自由に対する偽りの称賛です。自由であることを信じ込ませながら、実際、何も選べない、すべてにおいて誘導されているだけで、自由はないということです。まさに現代の民主主義における我々と一緒ですね。
また、その教育論のひどいところは、目的のない教育です。目的はありません。何を目指していることはありません。ルソーにいわせると、子どもは「生きるがいい」といっていますが、生きるだけでよいというような感じです。まさに現代、普及している雰囲気です。
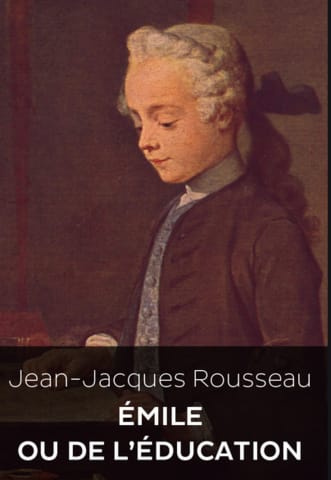
しかし、よく考えてみると、それほどひどいことはありません。理性のある被造物である人間が「どこへも向けられていない、何も狙っていない」のです。そんなことなんて非常に苦しいことです。ひどいです。「何のために生まれたか」という質問にルソーは「いや、何もない。何の理由のために生まれてきてはいない。生きるためだけ」と答えています。ひどいでしょう。理性のある人なら、それを聞くと絶望しかないでしょう。
つまり、永遠を思いはせる人、偉大なことを実現することが可能である人にとって、美しい立派なことをやり遂げることが可能な人に対して「いやいや、動物的に生きるだけでよいから」と言ったらどれほどひどいことでしょうか。「自分自身のために生きろ」ということで、子どもには目的を与えない教育です。目的を与えない教育です。
ルソーの教育論だと、「やる」だけでよいです。「何かのためにやる」ことはありません。目的がないから、方向づけられる行動はない、それは人間にとって悲惨なことです。何の目標・目的なしに生きるなんて悲惨で苦しいことです。なぜかというと、人間は、本性に刻印されている一つの特徴として、ある目的のために創られて、ある目的に方向づけられているのですから。目的を取り消して、目的を否定する教育なんて、子どもはそれを知らされないままになっているかもしれないが、それこそがルソー教育論の一番大きいな弊害です。
つまり、人間なら必ず「幸せ・幸福」を追求する気持ちは本性に刻印されています。が、そういった幸せに関して、ルソーは何も言わないのです。というのも、ルソーにとっての「幸福」は「今の状態だけの享楽」だけです。言い換えると、子どもは本性的に何か普遍的な、永遠なことを求めているものの、「今の瞬間」だけを享楽するがよいとしているのです。つまり、普遍的なことではなく、あくまでも偶然のもの、儚いもの、去っていくものだけがルソーの教育論の中心です。こういったような人生は本当に悲しいものです。ある意味で地獄のような人生です。
地獄の本質は永遠の苦しみである「劫罰」にあると言いますが、それは何と意味するでしょうか。地獄に落ちている霊魂は方向づけられている目的を自覚して、そしてその目的(天主)を渇望しているものの、いつまでその「渇望している善なる目的」を享受できないのが「劫罰」です。
その意味で、ルソーの『エミール』はこの世にいるうちから、地獄の準備のために働くかのような理論です。言い換えると、極端な個人主義ですから、自分自身中心で生きながら、同時にどうしても目的を持ちたい渇望もありながら、何の目的もないというこの世の地獄です。たとえてみると、呼吸したいのに、吸い込めないような状態です。つまり、肺臓は呼吸のためにある器官であることを実感しているから、肺臓を開けたいのですが、それでも吸い込めないような。

「目的への渇望」はそれと似ています。「目的(幸せ)への渇望」は人間の本性に刻印されています。どうしても幸せになりたいとみんな思うわけです。が、ルソーの教育論でいうと、「幸せはない」とされ、絶望しか残らないわけです。目的はない教育だからです。ですから、『エミール』は本物の地獄なのです。
最後、ルソーは「自然教育」を勧めますが、結局、自然に反する教育になります。
まず、ルソーは「自然」という言葉を定義していません。そして、家族を否定します。エミールには親も兄弟もいません。文化もありません。文化はゼロです。しかも文化をもたらしてはいけないと言います。エミールの理想像は結局、モーグリというキャラクターです。なんか、自然に投げ込んで、独りぼっちにさせて、自分自身ですべてやるようにならせるというような。
『エミール』は以上のようなものです。ルソーによる教育論。本物の理想主義です。そして、現代を見ると、ルソー教育論の凱旋的な成功です。というのも、最近の子供たちはエミールに似ているのが多いからです。しいていえば、最近の子供は「幸せ」ですが、馬鹿です。
次回、「サヴォアの助任司祭の信仰宣言」をご紹介します。ご清聴ありがとうございました。
~~
「エミールは何一つ、寓話さえも、暗記するようなことはしないだろう。ラ・フォンテーヌの寓話がどんなに素朴で魅力的だろうと、それさえも暗誦するようなことはしないだろう。歴史の言葉は歴史ではない、それ以上に寓話の言葉は寓話ではないからだ。」
※この公教要理は、 白百合と菊Lys et Chrysanthèmeさんのご協力とご了承を得て、多くの皆様の利益のために書き起こしをアップしております
Billecocq神父に哲学の講話を聴きましょう
それから、最後に、15歳になってから、エミールにはいよいよ宗教を教わり始めるということです。ルソー論において、宗教教育の始まりは15歳からです。これについての文章は次の引用で始まります。
「私の生徒のよう少年時代を通じて、私が彼に宗教について何も語らないのを知って、どれほど多くの読者が驚きを感じることだろう。それを私は予想する。十五歳になっても彼は、自分が魂を持っているかどうか知らなかったが、十八歳になっても、まだそれを学ぶ時期ではあるまい。」
さすがに。エミールは自分自身しか見ていなく、自分中心主義になっているものの、霊魂とは何であるかに関して教えなくてはならないとね。
「真理を理解できる状態に置かれていない者にむかって真理を告げるようなことは控えよう。それは真理の代わりに誤謬に置かれていないことを与えようとすることだ。神にふさわしくない卑俗で幻想的な観念、冒涜的な観念をもつよりは神について何の観念も持たないでいる方がましだ。」(106頁)
次に、宗教に対する過激な攻撃文があります。有名な文章ですが、次回、見ておきたいと思っております。それは『サヴォアの助任司祭による信仰宣言』という部分です。要するに、神父を登場させて、エミールに宗教を教える設定です。
それによって、ルソーはエミールを社会的な生活に投げ込むのです。次回にご紹介することにします。時間を必要とするし、今回はもう時間をオーバーしています。
『サヴォアの助任司祭による信仰宣言』を見ることによって、ルソーの宗教生活というか、ルソーにとっての宗教はなんであるかをよく示しています。

それから、第五編になります。第五編においてソフィーと出会って、結婚します。出会ってから、まず恋愛して、そして、二年間ほどエミールが旅立ってソフィーと会っていないが、そのあと、いよいよ結婚するという流れです。そして、父です。そして、次は小説となって、『ジュリ または新エロイーズ』とつながります。最終的に、「身内だけで自立して生活している」というのが理想とされます。それによって、社会を避けるためであるといっています。
こういった理想こそは『ジュリ または新エロイーズ』著作の中心テーマです。思い出しましょう。二組の夫婦は同じ家に住んでいて自給自足のような状態で小説が終わります。
以上、ルソーの『エミール』を簡潔に要約する試みをしてみました。どうしても、多くの引用をご紹介することにしました。それは、ルソーが言っていることをよく示して、ルソーの思想とされているものが本当にルソーが思っていたことだと強調するためでした。
*********************************
結びとして、いくつかの点を指摘したいと思っております。
第一、理想主義ばっかりです。これは一目瞭然でしょう。
まず、生まれながら人間は善性であるという理想主義です。生まれながら善性の子供なんて合ったことはありません。それが現実です。
それから、エミールという生徒に関する理想主義です。エミールを完全に夢から生まれさせて一から作り上げるのです。綺麗な教育論かもしれませんが、そもそもこういった「エミール」は現実に存在しない生徒です。しかも、ルソーはどうしてもその生徒が独りぼっちとなり、唯一、一人しかない教師を許すだけと言います。教師でさえ、ルソーでさえ、あり得ない設定を作ります。教師はいつも生徒のそばにいられるかのように書いてありますが、それはルソーの夢想にすぎません。
一言でいうと、この教育論は、ルソーの失敗だらけの自分の人生に対する復讐のようなものだと言えましょう。
教師についての理想主義もあります。全く存在しない教師です。つまり、エミールといった存在しない生徒に、そう言った存在しない教師が付くという設定の教育論ですが、実際の世界では一体どうやって適用できるといえるでしょうか。ルソーはあり得ないほど、大げさに議論を展開します。それが本質的にルソーの教育論の真相だと認めざるを得ません。
ルソーによる過剰論です。そういった大げさな夢想はまたほかにあります。それは、教育の段階の仕切り方です。そもそも完全にあり得ない仕切り方です。
ルソーに言わせると、0歳から2歳まで、人間は体だけ。2歳から12歳まで感覚的な霊だけ。12歳から15歳までいよいよ理性の始まりが出始めて。そして、いよいよ15歳以降、道徳感がでてくると言っているわけです。
それはあり得ません。実際は、人間は最初から人間です。つまり、生まれた瞬間から、もう人は人です。つまり、体と霊魂を生まれた瞬間から持っているというのは真実なのです。言い換えると、子どもは生まれると体を持ち、五感で感覚を持ち、それから理性をも持っています。
潜在力として、少なくとも成長していく能力としてもうすでに知性がそなわっているのです。そういえば、7歳は分別の時代だとよくいわれていますね。平均だけですから、それより早く分別がついてくる子どももいますが、分別の年齢になると、子どもは本物の質問、深い質問を聞いてきます。

「なぜ?」と聞く子どもは紛れもなく理性があるということを具体的に示しています。動物はどうしても「なぜ?」と思うことはできません。「なぜ?」と問う子供は物事の理由、物事の目的を知りたいわけです。また、「何のためにある」ということを知りたいわけです。あるいは、子どもは「何ですか?」と聞くときに、ある物事の本性を知りたいわけです。それも理性があるということを表しています。
ルソーにとって、理性は大体12歳になってから出てくるといっています。というか、早くて12歳で、おそらくより遅く出てくるといっています。というのも、18歳になっても、霊魂があるということを知らなくてもよいと主張するぐらいですから。そういった主張を見てみるとね、どう見ても。
ちょっと大げさに言わせてもらうと、ルソー論は狂気です。なぜか狂気であるかというと、「非現実」的な理論ですから。この『エミール』は教育論でもなんでもなく、ある程度のフィクション、小説にすぎないだけではなく、しかも人間の心理を完全に読み間違っている小説です。
それはともかく、『エミール』の中心の目的は、「真理を否定するための攻撃文」だと思っています。ルソーは根本的に、真理を教えることを固く拒みます。
そして、子どもはたまたま自分の力で真理をみつけたとしても、あくまでも有用性のある真理でなければならないと言います。彼にとって目に見えないことに関する真理は論外です。彼にとって形而上学や宗教は教えてはいけないのです。宗教に関して、ルソー論における「教育論」においてどうなっているかを次回ご紹介しますが、なかなか大変です。
要するに、ルソーの教育論において、真理はダメです。ところが、それよりひどい話があります。真理どころか、何の知恵・ノウハウ・技術の継承も、ダメだとされています。教育論における「師傅」は教師でもなく、師匠でもなく、先生でもありません。つまり、何の継承も、何の権威もありません。ルソーの教育論は「自分を自分で教育する」という「セルフ教育」なのです。つまり、きわめて個人主義であり、また児童の権利を称賛する教育論です。本質的にそういったものです。
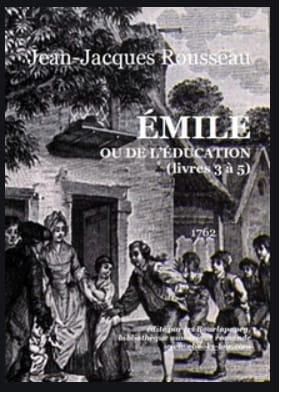
これから、ある考察を引用したいと思っております。その方は若手で、世間で意外と人気のあるかたです。私は彼の言動に関してすべてに同意しているわけではありませんが、François-Xavier Bellamyです。『不運の時代・継承すべしという緊急について』 という本を出しました。その中に、ルソーについて次のことを言っています。
「最初の二つの「論」において(第一回と第二回のときご紹介したルソーの論ですね)、現代普及した空気の原点がそこにあります。」確かに。
「しかしながら、『エミール』において、さらに一歩先です。完全になっているつもりの教育論で、実際の応用のための計画であるという位置づけで書かれています。そして、現代の公教育、非常に組織化された文部省によって実現された計画なのです。」
面白いでしょう。
「ルソーの教育論を読むと、現代、公教育の失敗だとよく評価されている多くの悪い結果は、ルソーの教育論でいうと実際にはかなりの成功であることに気づきます。現代の公教育は、完全に明白に紹介されたルソー教育論の成功なのです。一言でいうと、何の知恵・知識を継承することを固く絶対に拒む教育論の実現です。」
当たっていますね。言い換えると、現代の公教育は成功しています。なぜかというと、馬鹿な愚かな大人を養成しているからです。つまり、近代主義でいうと、愚かな人間を養成するのは失敗ではありません。わたしたちからみると、失敗に見えるかもしれませんが、近代主義的な教育論の筋でいうと本来ならば、とんでもない成功なのです。つまり、知恵・知識を継承しないという基本です。エミールは無知であるべきだからです。
彼はこう続けます。
「そういった教育は経験主義を基盤にしています。それはある種の自然主義です。」まさに当たっています。
また、エミールが自由であるかのように描写されていますが、実際に自由なんて何もありません。いや、それよりひどく、かなりの矛盾があります。というのも、エミールは結局、他人のまねをする、完全に順応主義になっています。その「師傅」についていくだけです。実際において、その「師傅」はエミールに対して暗に多くのことを禁じて、何もやらせていないのです。そして、案の定、エミールは社会人になったら、そういった教育ですから、順応主義にならざるを得ません。本当にひどいものです。
そういえば、『エミール』の最後には、エミールがソフィーと結婚しますが、なぜ結婚するかというと「師傅が望んだから」ということだけですよ!つまり、結婚する自由でさえありません。師傅は自由であることをエミールに信じ込ませていますが、実際において師傅の人形にすぎないのです。
最初にちょっと申し上げた通りです。自由に対する偽りの称賛です。自由であることを信じ込ませながら、実際、何も選べない、すべてにおいて誘導されているだけで、自由はないということです。まさに現代の民主主義における我々と一緒ですね。
また、その教育論のひどいところは、目的のない教育です。目的はありません。何を目指していることはありません。ルソーにいわせると、子どもは「生きるがいい」といっていますが、生きるだけでよいというような感じです。まさに現代、普及している雰囲気です。
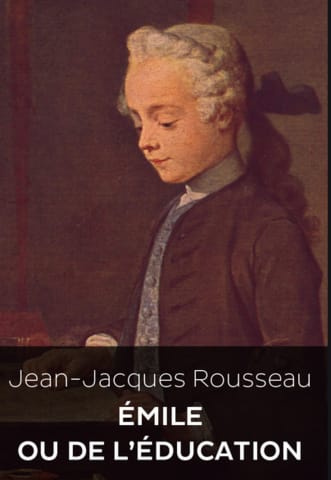
しかし、よく考えてみると、それほどひどいことはありません。理性のある被造物である人間が「どこへも向けられていない、何も狙っていない」のです。そんなことなんて非常に苦しいことです。ひどいです。「何のために生まれたか」という質問にルソーは「いや、何もない。何の理由のために生まれてきてはいない。生きるためだけ」と答えています。ひどいでしょう。理性のある人なら、それを聞くと絶望しかないでしょう。
つまり、永遠を思いはせる人、偉大なことを実現することが可能である人にとって、美しい立派なことをやり遂げることが可能な人に対して「いやいや、動物的に生きるだけでよいから」と言ったらどれほどひどいことでしょうか。「自分自身のために生きろ」ということで、子どもには目的を与えない教育です。目的を与えない教育です。
ルソーの教育論だと、「やる」だけでよいです。「何かのためにやる」ことはありません。目的がないから、方向づけられる行動はない、それは人間にとって悲惨なことです。何の目標・目的なしに生きるなんて悲惨で苦しいことです。なぜかというと、人間は、本性に刻印されている一つの特徴として、ある目的のために創られて、ある目的に方向づけられているのですから。目的を取り消して、目的を否定する教育なんて、子どもはそれを知らされないままになっているかもしれないが、それこそがルソー教育論の一番大きいな弊害です。
つまり、人間なら必ず「幸せ・幸福」を追求する気持ちは本性に刻印されています。が、そういった幸せに関して、ルソーは何も言わないのです。というのも、ルソーにとっての「幸福」は「今の状態だけの享楽」だけです。言い換えると、子どもは本性的に何か普遍的な、永遠なことを求めているものの、「今の瞬間」だけを享楽するがよいとしているのです。つまり、普遍的なことではなく、あくまでも偶然のもの、儚いもの、去っていくものだけがルソーの教育論の中心です。こういったような人生は本当に悲しいものです。ある意味で地獄のような人生です。
地獄の本質は永遠の苦しみである「劫罰」にあると言いますが、それは何と意味するでしょうか。地獄に落ちている霊魂は方向づけられている目的を自覚して、そしてその目的(天主)を渇望しているものの、いつまでその「渇望している善なる目的」を享受できないのが「劫罰」です。
その意味で、ルソーの『エミール』はこの世にいるうちから、地獄の準備のために働くかのような理論です。言い換えると、極端な個人主義ですから、自分自身中心で生きながら、同時にどうしても目的を持ちたい渇望もありながら、何の目的もないというこの世の地獄です。たとえてみると、呼吸したいのに、吸い込めないような状態です。つまり、肺臓は呼吸のためにある器官であることを実感しているから、肺臓を開けたいのですが、それでも吸い込めないような。

「目的への渇望」はそれと似ています。「目的(幸せ)への渇望」は人間の本性に刻印されています。どうしても幸せになりたいとみんな思うわけです。が、ルソーの教育論でいうと、「幸せはない」とされ、絶望しか残らないわけです。目的はない教育だからです。ですから、『エミール』は本物の地獄なのです。
最後、ルソーは「自然教育」を勧めますが、結局、自然に反する教育になります。
まず、ルソーは「自然」という言葉を定義していません。そして、家族を否定します。エミールには親も兄弟もいません。文化もありません。文化はゼロです。しかも文化をもたらしてはいけないと言います。エミールの理想像は結局、モーグリというキャラクターです。なんか、自然に投げ込んで、独りぼっちにさせて、自分自身ですべてやるようにならせるというような。
『エミール』は以上のようなものです。ルソーによる教育論。本物の理想主義です。そして、現代を見ると、ルソー教育論の凱旋的な成功です。というのも、最近の子供たちはエミールに似ているのが多いからです。しいていえば、最近の子供は「幸せ」ですが、馬鹿です。
次回、「サヴォアの助任司祭の信仰宣言」をご紹介します。ご清聴ありがとうございました。
~~
「エミールは何一つ、寓話さえも、暗記するようなことはしないだろう。ラ・フォンテーヌの寓話がどんなに素朴で魅力的だろうと、それさえも暗誦するようなことはしないだろう。歴史の言葉は歴史ではない、それ以上に寓話の言葉は寓話ではないからだ。」