中学受験で疲弊しないために、親子で楽しむ受験になるヒントを綴っていきたいと思います。
中学受験で子どもと普通に幸せになる方法
5年の壁を乗り越える工夫
3年生か、4年生ぐらいから塾を始め、今まではそんなに成績が悪くなかったのに、5年生になったらクラス分けで下がってしまった。
あるいは、子どもが勉強が大変で塾に行きたがらなくなっている。
宿題や課題が増えてこなせない。
このままでは「ついていけない」のではないか?
という気持ちになっておられるご家庭があるのではないかと思います。
でも、何に「ついていく?」のでしょうか。
テキスト? カリキュラム?
今はカリキュラムが昔に比べて半年近く早くなっています。
今までは6年生の1学期までですべてのカリキュラムが終了する運びになっていました。しかし、今は5年生の終わりで一通り終了する流れ。
その分演習量が増えているわけですが、しかし、私はそこまで急がなくても十分に間に合うだろうと思っています。
ただ、テキストやカリキュラムがそういうペースになっているから、それに間に合わせなければいけないと誰もが思いがちです。
でも、受験準備をしているのであって、組み分けテストの準備をしているわけではありません。
私は、5年生では算数と国語、がしっかりできればいい、ぐらいに思っています。
理科の計算は比が出てこないと、うまくいかない。そうすると5年生の理科は知識中心。社会はもとより知識中心ですから、結局は覚えることがメインになる。でも、5年で覚えても結局は6年でやり直すことになる。だったら、時間を上手に使った方が良いと私は思うのです。
例えば地理はどの塾でも早くやる。その後、歴史、公民ときて、6年生の夏休みに復習するには、すでに1年前の知識となっている。もちろん勉強しなくていい、というわけではありませんが、どこまで力を入れるか?ということは考えていいのではないでしょうか。
カリキュラムが一通り終わって、結局6年生の夏休みで復習し、6年生の秋に模擬試験があって演習を繰り返すようになれば、いいのです。
それにカリキュラムは早くなっても、子どもの学齢は上がっていないのです。
今は昔に比べて全員が飛び級状態。
だから、ペースを子どもに合うペースに変えれば良いのです。
塾の先生と相談して、やれる勉強に絞り込んでいけばいいのではないですか。それがうまくいかなければ、塾を変えてもいいし、メインとなるテキストを変えてもいい。
今は通信教育も、インターネットの動画教材もあるので、いくらでもペースを作りかえることができます。
視点を変えてみれば、5年の壁は乗り越えられます。
あわてないで、お子さんの様子をじっくり見ながら、よく話し合ってみてください。
==============================================================
田中貴.com通信を発刊しています。登録は以下のページからお願いします。
無料です。
田中貴.com通信ページ
==============================================================
今日の田中貴.com
運動会の練習
==============================================================
中学受験 算数オンライン塾
5月11日の問題
==============================================================


にほんブログ村
あるいは、子どもが勉強が大変で塾に行きたがらなくなっている。
宿題や課題が増えてこなせない。
このままでは「ついていけない」のではないか?
という気持ちになっておられるご家庭があるのではないかと思います。
でも、何に「ついていく?」のでしょうか。
テキスト? カリキュラム?
今はカリキュラムが昔に比べて半年近く早くなっています。
今までは6年生の1学期までですべてのカリキュラムが終了する運びになっていました。しかし、今は5年生の終わりで一通り終了する流れ。
その分演習量が増えているわけですが、しかし、私はそこまで急がなくても十分に間に合うだろうと思っています。
ただ、テキストやカリキュラムがそういうペースになっているから、それに間に合わせなければいけないと誰もが思いがちです。
でも、受験準備をしているのであって、組み分けテストの準備をしているわけではありません。
私は、5年生では算数と国語、がしっかりできればいい、ぐらいに思っています。
理科の計算は比が出てこないと、うまくいかない。そうすると5年生の理科は知識中心。社会はもとより知識中心ですから、結局は覚えることがメインになる。でも、5年で覚えても結局は6年でやり直すことになる。だったら、時間を上手に使った方が良いと私は思うのです。
例えば地理はどの塾でも早くやる。その後、歴史、公民ときて、6年生の夏休みに復習するには、すでに1年前の知識となっている。もちろん勉強しなくていい、というわけではありませんが、どこまで力を入れるか?ということは考えていいのではないでしょうか。
カリキュラムが一通り終わって、結局6年生の夏休みで復習し、6年生の秋に模擬試験があって演習を繰り返すようになれば、いいのです。
それにカリキュラムは早くなっても、子どもの学齢は上がっていないのです。
今は昔に比べて全員が飛び級状態。
だから、ペースを子どもに合うペースに変えれば良いのです。
塾の先生と相談して、やれる勉強に絞り込んでいけばいいのではないですか。それがうまくいかなければ、塾を変えてもいいし、メインとなるテキストを変えてもいい。
今は通信教育も、インターネットの動画教材もあるので、いくらでもペースを作りかえることができます。
視点を変えてみれば、5年の壁は乗り越えられます。
あわてないで、お子さんの様子をじっくり見ながら、よく話し合ってみてください。
==============================================================
田中貴.com通信を発刊しています。登録は以下のページからお願いします。
無料です。
田中貴.com通信ページ
==============================================================
今日の田中貴.com
運動会の練習
==============================================================
中学受験 算数オンライン塾
5月11日の問題
==============================================================

にほんブログ村
コメント ( 0 )
この3か月で6年生の保護者にやっていただきたいこと
夏休みまで、比較的のんびりする時期ではあるし、中学校のイベントや説明会もそれほど多い時期ではないので、親もついのんびりしがちです。
しかし、この時期6年生の保護者のみなさんにはやっていただきたいことが3つあります。
1 第一志望校を確認すること
2 第一志望校の出題傾向を調べること
3 夏休みから秋に向けての勉強のイメージをつくること
の3点です。
第一志望校は、もうこの時期決まっていて良いのではないかと思います。成績を見てから、と思われる方も多いし、そういう指導をする塾もありますが、第一志望校は子どもたちが「受験勉強をする」大事な動機です。これは早めに決まっていった方が良いと私は思います。
志望校をどう選ぶか(1)
志望校をどう選ぶか(2)
志望校をどう選ぶか(3)
志望校をどう選ぶか(4)
で、それが決まったら、今度は傾向を調べる、ということが必要です。
今年の過去問もそろそろ出そろってくるころですし、出題される傾向を調べる、ということで一覧にして見られると良いと思います。
親がまず志望校の学校別傾向を熟知する
ここまではすでにお話していたので、以前の記事を参考にしていただくとして、今日は3です。
夏休みの勉強や秋の勉強はどう進むのか、ご存じですか?
すでに上のお子さんの受験を経験されていれば、夏休みはこんな具合、秋はこうなって、というイメージがおありになると思いますが、最初のお子さんだとそうはいきません。
そのたびについ「バタバタ」してしまう。特に秋は模擬試験の成績が出てきて、いろいろな修正が必要になるわけですが、しかし、芯となる部分は本当はゆるがない方がいい。
第一志望はその典型だと思います。
で、細かな計画を立てる前の段階として、どんな勉強をしようか、とか、どんな体制にしようか、とかそういうイメージをもたれることが必要だと思うのです。
これは塾の先生と面談して聞いて見られても良いし、塾でも保護者会で説明してくれることもあるでしょう。もし可能なら昨年の合格者の方からお話を聞いてもいいかもしれない。
ただ、それを塾の言われるまま、あるいは経験者のいわれるままにやって良いわけではありません。
お子さんのことですから、そういうことを参考にしてどうするか?ということをイメージしていく。
例えば塾は秋に授業日数を増やします。一番少なくてたぶん4日。週5日、というところもありますし、毎日、という場合もあるかもしれません。
それが自分のお子さんに合うかどうか。体力が続くのか、という問題もあるでしょう。
あるいは学校別指導について、第一志望の学校別指導が見当たらない場合もありえるのです。
大方の塾は有名校の学校別指導については熱心で、いろいろな塾でやりますが、それ以外はだいたいグルーピングしてしまう。しかし例えば「大学付属校」のくくりになったとしても、学校によって出題傾向はやはり違うので、これをどうするかは考えておかないといけない。
しかし、9月になってどうするかとあわてて塾や個別指導を探すのだと後手に回ります。
そういうイメージを作るのは、今が一番良いのです。
例えば塾のお薦めの日は休みにして、家で過去問を解こうとか、知識の暗記をやろうとか。
そういうイメージを作っていくためには、情報も必要ですから、いろいろ話を聞いたりWEBで調べてみて、この夏からの受験準備をイメージしてください。
そして時間が近づいたら、今度は計画にしていきます。が、それまでにはまだ時間があります。だからしっかりイメージを作ってみてください。
==============================================================
田中貴.com通信を発刊しています。登録は以下のページからお願いします。
無料です。
次号は5月11日正午配信予定です。
田中貴.com通信ページ
==============================================================
今日の田中貴.com
第30回 勉強のスイッチをどう入れるか
==============================================================
今日の慶應義塾進学情報
つるかめ算なんですが・・・
==============================================================


にほんブログ村
しかし、この時期6年生の保護者のみなさんにはやっていただきたいことが3つあります。
1 第一志望校を確認すること
2 第一志望校の出題傾向を調べること
3 夏休みから秋に向けての勉強のイメージをつくること
の3点です。
第一志望校は、もうこの時期決まっていて良いのではないかと思います。成績を見てから、と思われる方も多いし、そういう指導をする塾もありますが、第一志望校は子どもたちが「受験勉強をする」大事な動機です。これは早めに決まっていった方が良いと私は思います。
志望校をどう選ぶか(1)
志望校をどう選ぶか(2)
志望校をどう選ぶか(3)
志望校をどう選ぶか(4)
で、それが決まったら、今度は傾向を調べる、ということが必要です。
今年の過去問もそろそろ出そろってくるころですし、出題される傾向を調べる、ということで一覧にして見られると良いと思います。
親がまず志望校の学校別傾向を熟知する
ここまではすでにお話していたので、以前の記事を参考にしていただくとして、今日は3です。
夏休みの勉強や秋の勉強はどう進むのか、ご存じですか?
すでに上のお子さんの受験を経験されていれば、夏休みはこんな具合、秋はこうなって、というイメージがおありになると思いますが、最初のお子さんだとそうはいきません。
そのたびについ「バタバタ」してしまう。特に秋は模擬試験の成績が出てきて、いろいろな修正が必要になるわけですが、しかし、芯となる部分は本当はゆるがない方がいい。
第一志望はその典型だと思います。
で、細かな計画を立てる前の段階として、どんな勉強をしようか、とか、どんな体制にしようか、とかそういうイメージをもたれることが必要だと思うのです。
これは塾の先生と面談して聞いて見られても良いし、塾でも保護者会で説明してくれることもあるでしょう。もし可能なら昨年の合格者の方からお話を聞いてもいいかもしれない。
ただ、それを塾の言われるまま、あるいは経験者のいわれるままにやって良いわけではありません。
お子さんのことですから、そういうことを参考にしてどうするか?ということをイメージしていく。
例えば塾は秋に授業日数を増やします。一番少なくてたぶん4日。週5日、というところもありますし、毎日、という場合もあるかもしれません。
それが自分のお子さんに合うかどうか。体力が続くのか、という問題もあるでしょう。
あるいは学校別指導について、第一志望の学校別指導が見当たらない場合もありえるのです。
大方の塾は有名校の学校別指導については熱心で、いろいろな塾でやりますが、それ以外はだいたいグルーピングしてしまう。しかし例えば「大学付属校」のくくりになったとしても、学校によって出題傾向はやはり違うので、これをどうするかは考えておかないといけない。
しかし、9月になってどうするかとあわてて塾や個別指導を探すのだと後手に回ります。
そういうイメージを作るのは、今が一番良いのです。
例えば塾のお薦めの日は休みにして、家で過去問を解こうとか、知識の暗記をやろうとか。
そういうイメージを作っていくためには、情報も必要ですから、いろいろ話を聞いたりWEBで調べてみて、この夏からの受験準備をイメージしてください。
そして時間が近づいたら、今度は計画にしていきます。が、それまでにはまだ時間があります。だからしっかりイメージを作ってみてください。
==============================================================
田中貴.com通信を発刊しています。登録は以下のページからお願いします。
無料です。
次号は5月11日正午配信予定です。
田中貴.com通信ページ
==============================================================
今日の田中貴.com
第30回 勉強のスイッチをどう入れるか
==============================================================
今日の慶應義塾進学情報
つるかめ算なんですが・・・
==============================================================

にほんブログ村
コメント ( 0 )
でも勉強しました。
まいにち目標ノートを見せてもらっていたときのことです。
「計画通り終わりました。」
「えらいねえ。で、できなかった問題はできたの?」
「いえ、わかりません。」
「それで、質問にきたっけ?」
「いいえ。」
「じゃ、どうするの?」
「でも、勉強しました。」
最後は論理になっておらず、
「私は計画通り勉強したんだ、何か文句ある?」
という感じでありました。
先日、こういう記事を書いたので、矛盾すると思われるかもしれませんが、
計画通り終わりゃあ、いいってものではありません。
結局、勉強はわかったのか、覚えたのかということが大事である。
勉強の質というか、中身がともなっていることが本来必要なわけです。だから、計画を作り、実行して、確認するときの最後の確認が
「ただ終わっている」
を確認するだけでは本当はいけない。
「で、わかったのか?」
「解けるようになったのか?」
が確認できていなければいけません。
これは女子に多いのだが、やはり、外からどう見えるかが気になる。だから、終わらないということは非常にいけないことだと思っています。
しかしながら、それでできるようになっているかどうかは、あまり気にしない。
したがって
「でも勉強しました。」
みたいな論理がまかり通ってくる場合があるものです。
気を付けて。
==============================================================
田中貴.com通信を発刊しています。登録は以下のページからお願いします。
無料です。
次号は5月11日正午配信予定です。
田中貴.com通信ページ
==============================================================
今日の田中貴.com
溶解度の問題
==============================================================
中学受験 算数オンライン塾
5月9日の問題
==============================================================

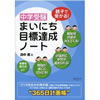
親子で受かる![中学受験]まいにち目標達成ノート

にほんブログ村
「計画通り終わりました。」
「えらいねえ。で、できなかった問題はできたの?」
「いえ、わかりません。」
「それで、質問にきたっけ?」
「いいえ。」
「じゃ、どうするの?」
「でも、勉強しました。」
最後は論理になっておらず、
「私は計画通り勉強したんだ、何か文句ある?」
という感じでありました。
先日、こういう記事を書いたので、矛盾すると思われるかもしれませんが、
計画通り終わりゃあ、いいってものではありません。
結局、勉強はわかったのか、覚えたのかということが大事である。
勉強の質というか、中身がともなっていることが本来必要なわけです。だから、計画を作り、実行して、確認するときの最後の確認が
「ただ終わっている」
を確認するだけでは本当はいけない。
「で、わかったのか?」
「解けるようになったのか?」
が確認できていなければいけません。
これは女子に多いのだが、やはり、外からどう見えるかが気になる。だから、終わらないということは非常にいけないことだと思っています。
しかしながら、それでできるようになっているかどうかは、あまり気にしない。
したがって
「でも勉強しました。」
みたいな論理がまかり通ってくる場合があるものです。
気を付けて。
==============================================================
田中貴.com通信を発刊しています。登録は以下のページからお願いします。
無料です。
次号は5月11日正午配信予定です。
田中貴.com通信ページ
==============================================================
今日の田中貴.com
溶解度の問題
==============================================================
中学受験 算数オンライン塾
5月9日の問題
==============================================================

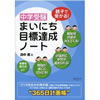
親子で受かる![中学受験]まいにち目標達成ノート
にほんブログ村
コメント ( 0 )
字がはみだす子
子どもの字と大人の字、というのがあります。
同じ人が書いた字でも、書いた時期によって違う。
例えば小学生のときの卒業文集。だいたいは手書きになっていることが多いので、そのときの子どもの字が残っていますが、それと同じ字を書いている大人は少ないでしょう。
どこかで子どもの字から大人の字に変わる。
これは、私が見ている限りではやはり中学生の時が多い。中学1年の後半から2年にかけて、字が変わる。
なぜ変わるのだろうか、というとやはり人からどう見えるか、が気になるということになるのでしょう。
つまり、「人からどう見えるか?」という意識が働くかどうかで、「字が汚い子」は「字がきれいな子」に変わるのです。
小学生の時は、字を習う、漢字を覚える。しかし、これは覚えるということに意識の中心が行きます。だから、どう見えるかまでは、意識が行かない。
形として覚えられるから、たとえばヘンとツクリのバランスが違っていても、まあ、同じ字だと認識できれば良い、ぐらいのレベルです。
しかし、字が人にどう見えるか?が意識されると、バランスにしても大きさにしても変わってくる。
この辺は明らかに女子の方が、意識が早い。
だから、ノートを見ていると、小学生から中学生の間は圧倒的に女子の字の方がきれいだし、大人の字に近づいている。(もちろん、女子には独特の丸文字があり、これを大人の字とするか、といえば議論は分かれるところかもしれませんが、まあ、これも「外からどう見えるか」という意味においては成長の後ということがいえるでしょう。)
で、問題なのは幼い男子ということになります。
まず、解答欄をはみ出す。
なぜはみ出すのか?「はみ出してはいけない」と思っていないからです。
「はみ出したら0点」
というと、直ります。当たり前ですが、意識の問題に過ぎないわけです。
最近は、塾でも学校でもこういうことに「うるさい先生」がいなくなった。
「書き直させる? それはいじめでしょう!」
なんて茶々が入るからかもしれないが、こういう基本的な姿勢はなるべく早くから、厳しくした方が、子どもに感謝されます。
例えば、子どもが勉強している姿勢。
今の子の姿勢は本当に悪い。昔はものさしを背中に突っ込まれたものだが、そんなことをする先生は今はいないでしょう。その分、姿勢が悪いと、きれいな字はかけるわけがないのです。
字が汚い子は、絶対に直ります。
本当に意識をしっかりそこに持たせ、厳しく指導することが大事です。これは低学年のときに早目に始めた方が効果が高い。
もちろん、6年生も本人が意識すれば、直ることですが。
==============================================================
田中貴.com通信を発刊しています。登録は以下のページからお願いします。
無料です。
田中貴.com通信ページ
==============================================================
今日の田中貴.com
記述式の算数
==============================================================
今日の慶應義塾進学情報
慶應義塾女子高校 2012年入試結果
==============================================================


にほんブログ村
同じ人が書いた字でも、書いた時期によって違う。
例えば小学生のときの卒業文集。だいたいは手書きになっていることが多いので、そのときの子どもの字が残っていますが、それと同じ字を書いている大人は少ないでしょう。
どこかで子どもの字から大人の字に変わる。
これは、私が見ている限りではやはり中学生の時が多い。中学1年の後半から2年にかけて、字が変わる。
なぜ変わるのだろうか、というとやはり人からどう見えるか、が気になるということになるのでしょう。
つまり、「人からどう見えるか?」という意識が働くかどうかで、「字が汚い子」は「字がきれいな子」に変わるのです。
小学生の時は、字を習う、漢字を覚える。しかし、これは覚えるということに意識の中心が行きます。だから、どう見えるかまでは、意識が行かない。
形として覚えられるから、たとえばヘンとツクリのバランスが違っていても、まあ、同じ字だと認識できれば良い、ぐらいのレベルです。
しかし、字が人にどう見えるか?が意識されると、バランスにしても大きさにしても変わってくる。
この辺は明らかに女子の方が、意識が早い。
だから、ノートを見ていると、小学生から中学生の間は圧倒的に女子の字の方がきれいだし、大人の字に近づいている。(もちろん、女子には独特の丸文字があり、これを大人の字とするか、といえば議論は分かれるところかもしれませんが、まあ、これも「外からどう見えるか」という意味においては成長の後ということがいえるでしょう。)
で、問題なのは幼い男子ということになります。
まず、解答欄をはみ出す。
なぜはみ出すのか?「はみ出してはいけない」と思っていないからです。
「はみ出したら0点」
というと、直ります。当たり前ですが、意識の問題に過ぎないわけです。
最近は、塾でも学校でもこういうことに「うるさい先生」がいなくなった。
「書き直させる? それはいじめでしょう!」
なんて茶々が入るからかもしれないが、こういう基本的な姿勢はなるべく早くから、厳しくした方が、子どもに感謝されます。
例えば、子どもが勉強している姿勢。
今の子の姿勢は本当に悪い。昔はものさしを背中に突っ込まれたものだが、そんなことをする先生は今はいないでしょう。その分、姿勢が悪いと、きれいな字はかけるわけがないのです。
字が汚い子は、絶対に直ります。
本当に意識をしっかりそこに持たせ、厳しく指導することが大事です。これは低学年のときに早目に始めた方が効果が高い。
もちろん、6年生も本人が意識すれば、直ることですが。
==============================================================
田中貴.com通信を発刊しています。登録は以下のページからお願いします。
無料です。
田中貴.com通信ページ
==============================================================
今日の田中貴.com
記述式の算数
==============================================================
今日の慶應義塾進学情報
慶應義塾女子高校 2012年入試結果
==============================================================

にほんブログ村
コメント ( 0 )
成績の上がり方
成績は右肩上がりにどんどん上がっていく、というようなイメージを持っておられる方が多いのではないかと思います。
下の図のようなイメージですね。
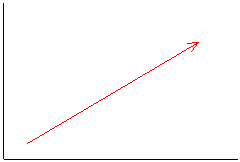
しかし、私がこれまで子どもたちを教えてきた感じで言えば、こんなイメージです。
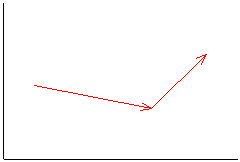
勉強を続けて、すぐできるということは、実際にはあまりない。
むしろ、混乱が始まります。
え、こうじゃなかったっけ。あれ、違うかな。
勉強したては、そう自信がすぐできるわけではない。だから、混乱する。したがって成績は下がるのです。
で、ここで「がっかり」しないことが大事。勉強したのに「できない」のは当然がっかりするし、親も不満に思う部分はあるのですが、これは成績が上がる前兆なのです。
それでもしっかり努力を続けていると、混乱がだんだん収束してくる。
これはこうだ、と確信を持てるようになる。そうすると、一気に成績が上がります。
「こんなに、成績が上がるなんて、まぐれね」
いや、いや、そんなことはない。しかし、続かないからそう思われてしまう可能性も少なくはないでしょう。次の試験でまた成績が下がったりしますから、そう見えても仕方がないが、これもまた新しいことを勉強しているから、混乱が生じて、定着していないから成績が下がる。
しかし、勉強が進んでいき、新しいことが少なくなるにつれて、どんどん停滞が短くなり、上昇場面が多くなるのです。
これは6年生の秋であることが多い。
だから6年生の秋に成績を上げる子は、合格しやすい。5,6月は低迷していても、秋に伸びれば一気に合格圏に行けます。
問題は、停滞期をどう判断するか。
つまり、これは勉強の仕方が悪くて停滞しているのか、それともしっかりした努力の上にある「必然性のある停滞」なのか。
しかし、子どもの様子を見ていればわかります。わかり始めると、勉強方法にも変化が出てくるというか、自分で工夫が始まる。そんなことを考えずに、ただ塾の宿題をやっている、ではなかなか停滞を脱しません。
その辺をこれから、お父さん、お母さんはじっくり見てあげてほしいと思います。
==============================================================
田中貴.com通信を発刊しています。登録は以下のページからお願いします。
無料です。
田中貴.com通信ページ
==============================================================
今日の田中貴.com
ペースを作る
==============================================================
中学受験 算数オンライン塾
5月7日の問題
==============================================================


にほんブログ村
下の図のようなイメージですね。
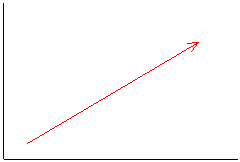
しかし、私がこれまで子どもたちを教えてきた感じで言えば、こんなイメージです。
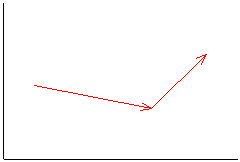
勉強を続けて、すぐできるということは、実際にはあまりない。
むしろ、混乱が始まります。
え、こうじゃなかったっけ。あれ、違うかな。
勉強したては、そう自信がすぐできるわけではない。だから、混乱する。したがって成績は下がるのです。
で、ここで「がっかり」しないことが大事。勉強したのに「できない」のは当然がっかりするし、親も不満に思う部分はあるのですが、これは成績が上がる前兆なのです。
それでもしっかり努力を続けていると、混乱がだんだん収束してくる。
これはこうだ、と確信を持てるようになる。そうすると、一気に成績が上がります。
「こんなに、成績が上がるなんて、まぐれね」
いや、いや、そんなことはない。しかし、続かないからそう思われてしまう可能性も少なくはないでしょう。次の試験でまた成績が下がったりしますから、そう見えても仕方がないが、これもまた新しいことを勉強しているから、混乱が生じて、定着していないから成績が下がる。
しかし、勉強が進んでいき、新しいことが少なくなるにつれて、どんどん停滞が短くなり、上昇場面が多くなるのです。
これは6年生の秋であることが多い。
だから6年生の秋に成績を上げる子は、合格しやすい。5,6月は低迷していても、秋に伸びれば一気に合格圏に行けます。
問題は、停滞期をどう判断するか。
つまり、これは勉強の仕方が悪くて停滞しているのか、それともしっかりした努力の上にある「必然性のある停滞」なのか。
しかし、子どもの様子を見ていればわかります。わかり始めると、勉強方法にも変化が出てくるというか、自分で工夫が始まる。そんなことを考えずに、ただ塾の宿題をやっている、ではなかなか停滞を脱しません。
その辺をこれから、お父さん、お母さんはじっくり見てあげてほしいと思います。
==============================================================
田中貴.com通信を発刊しています。登録は以下のページからお願いします。
無料です。
田中貴.com通信ページ
==============================================================
今日の田中貴.com
ペースを作る
==============================================================
中学受験 算数オンライン塾
5月7日の問題
==============================================================

にほんブログ村
コメント ( 0 )
中間テスト
5月の中盤から後半にかけて中間テストを行う中学校が多いでしょう。
最初にこれを受けたとき、まあ、面食らった記憶があります。
学校は午前中に限られるものの、毎時間テストである。
1時間目が英語、2時間目が理科、3時間目が数学1つ目、みたいな感じ。
ついでにいえば、家庭科も、音楽も試験がある。
音楽の試験って何?
そういう状態だから、最初からうまくいくわけはないし、それで良いと思います。いろいろ経験して、そのうち対策が生まれてくる。
この試験はこういう準備をしようとか。
だから中間テストはうまく利用して、次の期末に活かすのがよいのです。
試験というのは、なかなか最初からうまくいかないところがあるし、うまくいかない方が後から結果が良い傾向にあるのではないかと思います。
もちろん、うまくいかなくて、そのまま投げ出してしまえは、結果が良くなるはずはないですが、ただ、見直して、復習して、対策すれば、それなりに次の試験はうまくいくようになる。
これは受験勉強も同じです。
組み分けや模擬試験も、こんな問題が入試に出る、という経験を積むことが大事なのだから、見直して、復習して、対策することに意義があります。
どうしても合格可能性や偏差値、クラスに目が行くけれど、しかし、何も対策を考えないと、中間テストがズルズルで、そのまま期末も終わる、という中学生に通ずるところがある。
試験を受け、経験を積んで、次にどうするか、具体的に決めて、実行する。
この繰り返しが大事です。
そしてこの経験は、中学生になっても活きる。(少なくとも意識してもらえば。)
中間テストは失敗してもいいが、その後、取り返す方法を考えればよいわけです。
遊びほうけている新中学1年生を見て『ハラハラ、ドキドキ』しているお母さんが多いかもしれないが、まずは失敗させる、ことも大事なのです。
一番大事なのは、その後ですから。
==============================================================
田中貴.com通信を発刊しています。登録は以下のページからお願いします。
無料です。
田中貴.com通信ページ
==============================================================
今日の田中貴.com
「パパママ塾特別テスト」を作る
==============================================================
今日の慶應義塾進学情報
慶應湘南 学校説明会第一日程は5月13日日曜日です。
==============================================================


にほんブログ村
最初にこれを受けたとき、まあ、面食らった記憶があります。
学校は午前中に限られるものの、毎時間テストである。
1時間目が英語、2時間目が理科、3時間目が数学1つ目、みたいな感じ。
ついでにいえば、家庭科も、音楽も試験がある。
音楽の試験って何?
そういう状態だから、最初からうまくいくわけはないし、それで良いと思います。いろいろ経験して、そのうち対策が生まれてくる。
この試験はこういう準備をしようとか。
だから中間テストはうまく利用して、次の期末に活かすのがよいのです。
試験というのは、なかなか最初からうまくいかないところがあるし、うまくいかない方が後から結果が良い傾向にあるのではないかと思います。
もちろん、うまくいかなくて、そのまま投げ出してしまえは、結果が良くなるはずはないですが、ただ、見直して、復習して、対策すれば、それなりに次の試験はうまくいくようになる。
これは受験勉強も同じです。
組み分けや模擬試験も、こんな問題が入試に出る、という経験を積むことが大事なのだから、見直して、復習して、対策することに意義があります。
どうしても合格可能性や偏差値、クラスに目が行くけれど、しかし、何も対策を考えないと、中間テストがズルズルで、そのまま期末も終わる、という中学生に通ずるところがある。
試験を受け、経験を積んで、次にどうするか、具体的に決めて、実行する。
この繰り返しが大事です。
そしてこの経験は、中学生になっても活きる。(少なくとも意識してもらえば。)
中間テストは失敗してもいいが、その後、取り返す方法を考えればよいわけです。
遊びほうけている新中学1年生を見て『ハラハラ、ドキドキ』しているお母さんが多いかもしれないが、まずは失敗させる、ことも大事なのです。
一番大事なのは、その後ですから。
==============================================================
田中貴.com通信を発刊しています。登録は以下のページからお願いします。
無料です。
田中貴.com通信ページ
==============================================================
今日の田中貴.com
「パパママ塾特別テスト」を作る
==============================================================
今日の慶應義塾進学情報
慶應湘南 学校説明会第一日程は5月13日日曜日です。
==============================================================

にほんブログ村
コメント ( 0 )
合格可能性の判定
そろそろ第1回の模擬試験の結果が出てくると思います。
まあ、この時期ですから、それほど気にする問題でもないのですが、しかし、合格可能性という数値がでてきているところもあるでしょう。
合格可能性とはどういう計算をするのか。下のグラフはあるテストの開成中学の判定資料です。
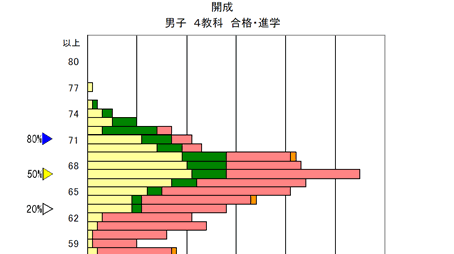
ここで縦軸にとられているのは、この時期の前年の同試験の偏差値。
黄色は合格して進学した生徒
緑は合格したが進学しなかった生徒
ピンクは不合格の生徒
の分布を表しています。この数値で見れば、全員が受かっていたのは73まで。
72から不合格者が出て、71で合格者は全体の80%になりました。
あとは同じ要領。
半分が合格している偏差値を合格可能性50%
5分の1が合格している偏差値を合格可能性20%
としているのです。
入試と模擬試験は違います。学校別でない限り、ひとつの試験でいろいろな学校の合格可能性を出すので、このような手法がとられるわけです。
うちの子は合格可能性が20%未満!
というのは、この偏差値より下だったということに過ぎません。
この試験のデータでは、ということなので、くれぐれも悲観されないように。
==============================================================
お知らせ
==============================================================
「中学受験、合格して失敗する子、不合格でも成功する子」e-pub版が無料でダウンロードできます。
DL-Marketへの登録が必要となりますが、お役に立てば幸いです。
ダウンロードサイト
==============================================================
田中貴.com通信を発刊しています。登録は以下のページからお願いします。
無料です。
田中貴.com通信ページ
==============================================================
今日の田中貴.com
潮干狩りの問題
==============================================================
中学受験 算数オンライン塾
5月5日の問題
==============================================================


にほんブログ村
まあ、この時期ですから、それほど気にする問題でもないのですが、しかし、合格可能性という数値がでてきているところもあるでしょう。
合格可能性とはどういう計算をするのか。下のグラフはあるテストの開成中学の判定資料です。
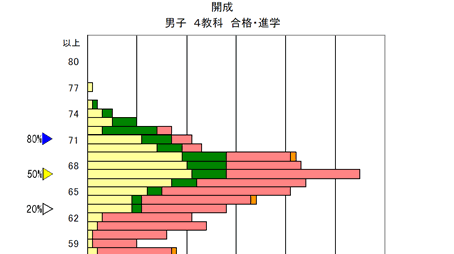
ここで縦軸にとられているのは、この時期の前年の同試験の偏差値。
黄色は合格して進学した生徒
緑は合格したが進学しなかった生徒
ピンクは不合格の生徒
の分布を表しています。この数値で見れば、全員が受かっていたのは73まで。
72から不合格者が出て、71で合格者は全体の80%になりました。
あとは同じ要領。
半分が合格している偏差値を合格可能性50%
5分の1が合格している偏差値を合格可能性20%
としているのです。
入試と模擬試験は違います。学校別でない限り、ひとつの試験でいろいろな学校の合格可能性を出すので、このような手法がとられるわけです。
うちの子は合格可能性が20%未満!
というのは、この偏差値より下だったということに過ぎません。
この試験のデータでは、ということなので、くれぐれも悲観されないように。
==============================================================
お知らせ
==============================================================
「中学受験、合格して失敗する子、不合格でも成功する子」e-pub版が無料でダウンロードできます。
DL-Marketへの登録が必要となりますが、お役に立てば幸いです。
ダウンロードサイト
==============================================================
田中貴.com通信を発刊しています。登録は以下のページからお願いします。
無料です。
田中貴.com通信ページ
==============================================================
今日の田中貴.com
潮干狩りの問題
==============================================================
中学受験 算数オンライン塾
5月5日の問題
==============================================================

にほんブログ村
コメント ( 0 )
勉強を楽しくやる工夫
例えば、分数と小数の計算問題があったとしましょう。
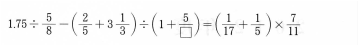
こんな感じのイメージの問題です。一目見て、あ、「面倒だ」と思うと思うのです。私は思います。少なくとも。
で、これが1枚のプリントに10題あるとします。
それを解く気になるか?
まあ、10人の子どもが10人「いやだなあ」と思うでしょう。たぶん。
で、これを訓練だ、練習だと強制する。強制しないとやらないから、なんですが、そうすると計算問題の練習をすること自体が楽しくなくなる。
元から楽しくないのです。それが強制され、かつたくさんあって、ついでに時間も制限されていたら。
「やる気はでない」でしょう。
でも計算力はつけないといけません。計算力をつけるためには、計算の練習をしないといけない。ここもその通り。
だとすると、あとは「楽しくやる工夫」をするしかないわけです。
ここで、たとえば競争するというゲームを考える。
最初にできた人10ポイント。ただし、その場で正解すると1問につき2ポイント。そうすると一番で全部できると問題が5問として20ポイント。
ポイントの大きい人から順位をつけて1位はジュースね。
とやると、少しはやる気になるわけです。1位がマグドナルド食べ放題、となるとこれまた違うかもしれない。
教室だったら、こんなことを私は考えます。で家だったら、結局たくさんやらせると、ひとつひとつのミスが出やすくなる。それに競う相手がいないので、自分との競争を考える。
つまり
「3題やって、答え合わせのときに、全部できていたら5ポイント!」
というシステムを作ります。そしてそのポイントが25ポイントになったら、「今週末は好きなテレビを見てよいチケット」が手に入る。
なんてことをきっと、考えるだろうと思います。
「勉強するのに、モノでつるんですか?」
という反論はあるかもしれないが、3年生、4年生ぐらいだとホントに喜んでやってくれるんです。だったら、それでいいではないかと私は思います。
歯を食いしばってやるイメージがある受験勉強ですが、私は楽しくやる工夫はいくらでもあると思うのです。
お父さん、お母さんのアイデア次第ではないでしょうか?
==============================================================
お知らせ
==============================================================
「中学受験、合格して失敗する子、不合格でも成功する子」e-pub版が無料でダウンロードできます。
DL-Marketへの登録が必要となりますが、お役に立てば幸いです。
ダウンロードサイト
==============================================================
田中貴.com通信を発刊しています。登録は以下のページからお願いします。
無料です。
田中貴.com通信ページ
==============================================================
今日の田中貴.com
第29回 効率化のカギ
==============================================================
今日の慶應義塾進学情報
身の回りの科学
==============================================================


にほんブログ村
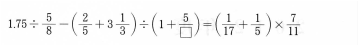
こんな感じのイメージの問題です。一目見て、あ、「面倒だ」と思うと思うのです。私は思います。少なくとも。
で、これが1枚のプリントに10題あるとします。
それを解く気になるか?
まあ、10人の子どもが10人「いやだなあ」と思うでしょう。たぶん。
で、これを訓練だ、練習だと強制する。強制しないとやらないから、なんですが、そうすると計算問題の練習をすること自体が楽しくなくなる。
元から楽しくないのです。それが強制され、かつたくさんあって、ついでに時間も制限されていたら。
「やる気はでない」でしょう。
でも計算力はつけないといけません。計算力をつけるためには、計算の練習をしないといけない。ここもその通り。
だとすると、あとは「楽しくやる工夫」をするしかないわけです。
ここで、たとえば競争するというゲームを考える。
最初にできた人10ポイント。ただし、その場で正解すると1問につき2ポイント。そうすると一番で全部できると問題が5問として20ポイント。
ポイントの大きい人から順位をつけて1位はジュースね。
とやると、少しはやる気になるわけです。1位がマグドナルド食べ放題、となるとこれまた違うかもしれない。
教室だったら、こんなことを私は考えます。で家だったら、結局たくさんやらせると、ひとつひとつのミスが出やすくなる。それに競う相手がいないので、自分との競争を考える。
つまり
「3題やって、答え合わせのときに、全部できていたら5ポイント!」
というシステムを作ります。そしてそのポイントが25ポイントになったら、「今週末は好きなテレビを見てよいチケット」が手に入る。
なんてことをきっと、考えるだろうと思います。
「勉強するのに、モノでつるんですか?」
という反論はあるかもしれないが、3年生、4年生ぐらいだとホントに喜んでやってくれるんです。だったら、それでいいではないかと私は思います。
歯を食いしばってやるイメージがある受験勉強ですが、私は楽しくやる工夫はいくらでもあると思うのです。
お父さん、お母さんのアイデア次第ではないでしょうか?
==============================================================
お知らせ
==============================================================
「中学受験、合格して失敗する子、不合格でも成功する子」e-pub版が無料でダウンロードできます。
DL-Marketへの登録が必要となりますが、お役に立てば幸いです。
ダウンロードサイト
==============================================================
田中貴.com通信を発刊しています。登録は以下のページからお願いします。
無料です。
田中貴.com通信ページ
==============================================================
今日の田中貴.com
第29回 効率化のカギ
==============================================================
今日の慶應義塾進学情報
身の回りの科学
==============================================================

 | 中学入試でる順算数計算900 (Obunsha study bear) |
| クリエーター情報なし | |
| 旺文社 |
にほんブログ村
コメント ( 0 )
中高一貫校のシラバス
シラバスというのは、授業予定とかカリキュラムという意味です。中学、高校で何を勉強するか、ということは指導要領で決まっているわけですが、その進め方はいろいろありえるわけで、それをどう進めるかを決めるのがシラバスです。
中高一貫校は、6年間の一貫教育ですから、その分どういう構成で授業を進めるか、ということが非常に重要になるわけですが、しかし、この決め方は大きく分けて2つあります。
ひとつは学校が全部決めてしまう。
これは最近の受験校では多いだろうと思います。こうなるとおおむね以下のようなプランになる。
中1から中2で中3までの指導要領を終える。
中3で高1 高1で高2、と1年ずつ前倒しすると、高2で高校の指導要領は全部終えることになりますから、高3は大学受験の演習を中心に進めることができる。これは6年一貫だからやりやすいことです。これが高校だけだとすると、3年のカリキュラムを2年で終えるのは難しい。しかし6年の過程を5年で終えることはそれほど大変ではない。
以前ゆとり教育で中学のカリキュラムが一気に縮小されたことがあって、それで中学がある意味スカスカになったので、ここを圧縮する方式が考えられたわけです。
もうひとつは、教員に任せる。
土台指導要領があるわけだから、その意味ではガイドラインが決まっているので、先生の進め方で決める。もちろん教科の会議などで決める場合もあるでしょうが、基本的には先生任せにする。大学方式といえるかもしれません。
この違いは、ある意味学校の風土とか、スクールカラーによるところが大きいのではないかと思います。自由に生徒を扱う学校は先生も自由に扱う、という面があります。だから、先生に任せる。ところが、先生は大学受験ばかりを考えるわけではありません。
教科を好きになるにはどうするか?
学問に興味を持つにはどうするか?
ということを考えながら、授業を進める。結果として、たとえば日本史が奈良時代だけになってしまう、ということが起きるわけです。
ところが、大学受験で奈良時代だけでる大学はありません。だから通史はもう一度自分でやり直さなければならない。
これが無駄だ、と考える保護者が増えているそうです。
大学受験に向けて、塾のように授業をやってほしい。
塾にもクレームが多いが、実は最近私学にもクレームは多いんだそうです。
何のために学費を払ってるんだ、とまあ、こんなことになっているらしいのですが。
最近は、管理型が人気なのもこの流れに沿っている、ということなのでしょうが、しかし、教員が中心にシラバスを決めている学校は、やはりそれなりに自由な風土やスクールカラーがあるせいか、子どもたちものびのびしているところがあり、最終的には
「勉強は自分でやるものだ」
という感覚で受験に向かっていくことになります。
何も全部が全部お膳立てをしなくとも、子どもは向かうべきところに向かっていく、ということではないかと思うのですが。
==============================================================
お知らせ
==============================================================
「中学受験、合格して失敗する子、不合格でも成功する子」e-pub版が無料でダウンロードできます。
DL-Marketへの登録が必要となりますが、お役に立てば幸いです。
ダウンロードサイト
==============================================================
田中貴.com通信を発刊しています。登録は以下のページからお願いします。
無料です。
田中貴.com通信ページ
==============================================================
今日の田中貴.com
違いを知る
==============================================================
中学受験 算数オンライン塾
5月3日の問題
==============================================================


にほんブログ村
中高一貫校は、6年間の一貫教育ですから、その分どういう構成で授業を進めるか、ということが非常に重要になるわけですが、しかし、この決め方は大きく分けて2つあります。
ひとつは学校が全部決めてしまう。
これは最近の受験校では多いだろうと思います。こうなるとおおむね以下のようなプランになる。
中1から中2で中3までの指導要領を終える。
中3で高1 高1で高2、と1年ずつ前倒しすると、高2で高校の指導要領は全部終えることになりますから、高3は大学受験の演習を中心に進めることができる。これは6年一貫だからやりやすいことです。これが高校だけだとすると、3年のカリキュラムを2年で終えるのは難しい。しかし6年の過程を5年で終えることはそれほど大変ではない。
以前ゆとり教育で中学のカリキュラムが一気に縮小されたことがあって、それで中学がある意味スカスカになったので、ここを圧縮する方式が考えられたわけです。
もうひとつは、教員に任せる。
土台指導要領があるわけだから、その意味ではガイドラインが決まっているので、先生の進め方で決める。もちろん教科の会議などで決める場合もあるでしょうが、基本的には先生任せにする。大学方式といえるかもしれません。
この違いは、ある意味学校の風土とか、スクールカラーによるところが大きいのではないかと思います。自由に生徒を扱う学校は先生も自由に扱う、という面があります。だから、先生に任せる。ところが、先生は大学受験ばかりを考えるわけではありません。
教科を好きになるにはどうするか?
学問に興味を持つにはどうするか?
ということを考えながら、授業を進める。結果として、たとえば日本史が奈良時代だけになってしまう、ということが起きるわけです。
ところが、大学受験で奈良時代だけでる大学はありません。だから通史はもう一度自分でやり直さなければならない。
これが無駄だ、と考える保護者が増えているそうです。
大学受験に向けて、塾のように授業をやってほしい。
塾にもクレームが多いが、実は最近私学にもクレームは多いんだそうです。
何のために学費を払ってるんだ、とまあ、こんなことになっているらしいのですが。
最近は、管理型が人気なのもこの流れに沿っている、ということなのでしょうが、しかし、教員が中心にシラバスを決めている学校は、やはりそれなりに自由な風土やスクールカラーがあるせいか、子どもたちものびのびしているところがあり、最終的には
「勉強は自分でやるものだ」
という感覚で受験に向かっていくことになります。
何も全部が全部お膳立てをしなくとも、子どもは向かうべきところに向かっていく、ということではないかと思うのですが。
==============================================================
お知らせ
==============================================================
「中学受験、合格して失敗する子、不合格でも成功する子」e-pub版が無料でダウンロードできます。
DL-Marketへの登録が必要となりますが、お役に立てば幸いです。
ダウンロードサイト
==============================================================
田中貴.com通信を発刊しています。登録は以下のページからお願いします。
無料です。
田中貴.com通信ページ
==============================================================
今日の田中貴.com
違いを知る
==============================================================
中学受験 算数オンライン塾
5月3日の問題
==============================================================

にほんブログ村
コメント ( 0 )
組み分けテストを総括する
そろそろ組み分けテストや月例テストの結果がまた出てくる時期でしょう。
で、点数や偏差値は気になるが、それはまあ、おいておいて。
大事なことは、問題の復習です。できなかった問題はやり直す。
どうして、できなかったのか。
解き方が思いつかなかった、という場合はあるでしょう。これは、これで仕方がない。しかし、今回勉強したことで、新たに解き方を覚えたのならそれは前進ですから、これでよし。
問題はミス。
「解けたはず」の問題が「点数がとれていなかった」のは一番、もったいないわけです。
で、その原因を考えてみる。その次に今度はそれを解決する方法を考える。
そして各教科ごとに3つの注意点を決めましょう。総括です。
これを手帳でも、ノートでも書き残しておくことが大事です。なんなら子どもの携帯電話にメールで残しておいてもいいかもしれない。
これは3つでなければいけない。
次にやろうと思っても、これ以上には注意が及びにくい。だからいろいろあるかもしれないが、3つにしておきましょう。
その3つを次の組み分けテストで、注意する。
だいたい大きなテストは1か月に1回ですから、前回のことを忘れてしまいがちなのです。
だから同じ間違いを繰り返しやすい。
今回のテストではここだけは注意しよう、と決めるために、ノートに残し、試験の前日に確認する。
偏差値やクラスを気にするよりも、こちらを重視してください。
いくら組み分けが良くても、入試でできなければ、まったく甲斐がないのですから。
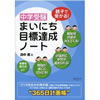
親子で受かる![中学受験]まいにち目標達成ノート
==============================================================
お知らせ
==============================================================
「中学受験、合格して失敗する子、不合格でも成功する子」e-pub版が無料でダウンロードできます。
DL-Marketへの登録が必要となりますが、お役に立てば幸いです。
ダウンロードサイト
==============================================================
田中貴.com通信を発刊しています。登録は以下のページからお願いします。
無料です。
田中貴.com通信ページ
==============================================================
今日の田中貴.com
公立中学選択制
==============================================================
今日の慶應義塾進学情報
反射の問題
==============================================================


にほんブログ村
で、点数や偏差値は気になるが、それはまあ、おいておいて。
大事なことは、問題の復習です。できなかった問題はやり直す。
どうして、できなかったのか。
解き方が思いつかなかった、という場合はあるでしょう。これは、これで仕方がない。しかし、今回勉強したことで、新たに解き方を覚えたのならそれは前進ですから、これでよし。
問題はミス。
「解けたはず」の問題が「点数がとれていなかった」のは一番、もったいないわけです。
で、その原因を考えてみる。その次に今度はそれを解決する方法を考える。
そして各教科ごとに3つの注意点を決めましょう。総括です。
これを手帳でも、ノートでも書き残しておくことが大事です。なんなら子どもの携帯電話にメールで残しておいてもいいかもしれない。
これは3つでなければいけない。
次にやろうと思っても、これ以上には注意が及びにくい。だからいろいろあるかもしれないが、3つにしておきましょう。
その3つを次の組み分けテストで、注意する。
だいたい大きなテストは1か月に1回ですから、前回のことを忘れてしまいがちなのです。
だから同じ間違いを繰り返しやすい。
今回のテストではここだけは注意しよう、と決めるために、ノートに残し、試験の前日に確認する。
偏差値やクラスを気にするよりも、こちらを重視してください。
いくら組み分けが良くても、入試でできなければ、まったく甲斐がないのですから。
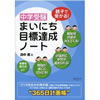
親子で受かる![中学受験]まいにち目標達成ノート
==============================================================
お知らせ
==============================================================
「中学受験、合格して失敗する子、不合格でも成功する子」e-pub版が無料でダウンロードできます。
DL-Marketへの登録が必要となりますが、お役に立てば幸いです。
ダウンロードサイト
==============================================================
田中貴.com通信を発刊しています。登録は以下のページからお願いします。
無料です。
田中貴.com通信ページ
==============================================================
今日の田中貴.com
公立中学選択制
==============================================================
今日の慶應義塾進学情報
反射の問題
==============================================================

にほんブログ村
コメント ( 0 )
| « 前ページ | 次ページ » |





