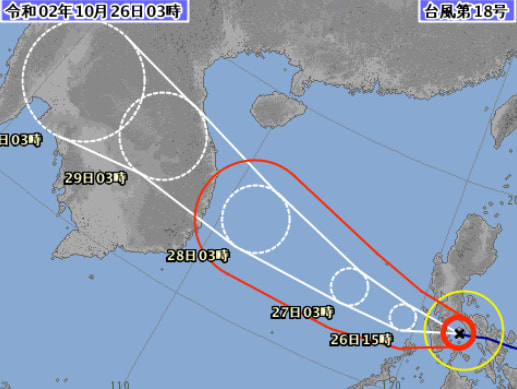政府が特定の国の製品不買運動を推進できるのは
-
-
- その国の強権で訴えられる心配がない
- 訴えられても証拠を残さなければ安心
- 訴訟に備えるため不買運動には慎重
前近代的な国や地域ほど上にあり、下に行くほど法治国家に近く、法治国家に近ければ不買運動よりも有効な手段がほかにあるのでしょう。
欠陥はあるけれども法治主義が望ましいのはそのせいで、これが分かっていないのが中国~朝鮮半島。
中国~韓国という擬似民主国家・非法治国家は「1.~2.」の段階にあり、「注意深く相手に訴えられないよう工夫」しています。
この「注意深く相手に訴えられないよう工夫」しているのが、実は「法の力」を大切にしていることの例証であり、時と場合によってこれらを使い分けるのが、だましあい国家の得意とするところです。
これらの国では「法はへ理屈であり、自分たちの結論が一番正しい」と考え、従っていまだ「共通なのは法だけ」という考えに至っておりません。
法律無視のこれらの国が「自分たちの考えが一番正しい」とするのは、こういった見方があるからで、これを「うぬぼれ」と称しています。
法治国家が一番いいとも限らず、本当は法を超えた何かの力があるほうが望ましいともいえますが、それは一時期の聖人に限られ99%あり得ず夢物語。
価値観がことなる国・地域では「共通なのは法だけ」なのですね。
まとめると「法の解釈力と国の成り立ちに関係している」と言えます。
さらに言えば
不買運動の背景として、「法治国家は製品を作っている」というのがあります。
国として最低限の誇りとして輸入制限の道筋は
-
-
- 不買運動(効果があるかどうかは別)
- 関税を上げる(率により効果あり)
- 輸入禁止(完全に効果がある)
が普通で、様子をみて次の段階へと進みます。
トルコ大統領、フランス製品不買を国民に呼び掛け:afp 2020年10月26日 22:30
トルコに限らず
全体主義国が多いアラブ諸国・イスラム諸国では、領土や方針によって対立すると、多くは朝令暮改の法律で「不買運動を展開」することがあります。
「不買運動」ならマシなほうで、より深刻な対立になるかも知れず、その時、普段の「大国」との付き合いが重要で、その深さに応じて「大国」の介入の度合いが異なります。
もちろんどちらに非があるかは分かりません。
しかし多くは
「法律依拠に徹し始めた」キリスト教国(表面的な宗教依存から脱した)」と、依然として「全体主義的な」イスラム教国の争いが多いようです。宗教対立と言われるだけあり、それぞれに利点・長所と欠点・短所があるのでしょう。
空爆による難民排出、その難民の受け入れ許容と、受け入れ拒否の現実は、これらで説明することができます。
全体主義的な国の傾向で、領土拡張が多く見られますが
それは「製品による侵略」という不買運動のきっかけが原因かも知れません。宗教による侵略・政治経済権力による侵略、そしてそれらを不買運動で阻止しようとする動きが見られます。
中世~近世では、
-
-
- まず派遣側から、信仰の自由を表に、ある国へ「宗教」から侵入し
- やがて一定の数の信者を集めると、当該国から抵抗があり
- 信者を救うとして「軍隊の派遣」をして
- 結局のっとりが成功しました。
- いわば「宗教が侵略の先発隊」だったのです。
今では宗教が表に出ることは影をひそめ、経済的侵略にとってかわりましたが、未完成な国際政策と、イスラム教の未熟な国際政策が、ぶつかりあっているのが現状でしょうか。
先にトルコのエルドアンは
マクロン氏は「精神検査を」(afp 2020年10月25日)
と述べたようです。
さてさて、皆様はどう思われますか。