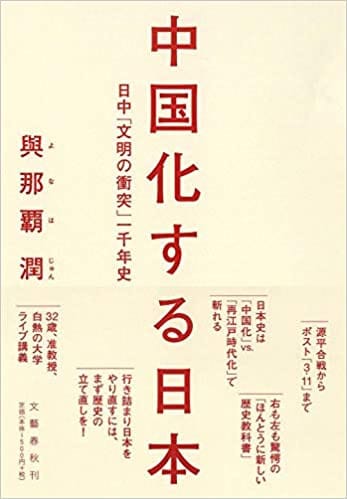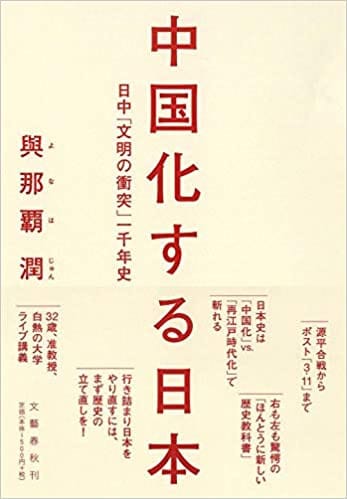
『中国化する日本』だなんて、その辺に溢れている「煽り」本らしい雰囲気のネーミングだが、これはけっしてそのたぐいではない。たまたま、私は著者の名前と本の概要を知っていたのだが、そうでなければ本屋でこのタイトルを見ただけではたぶん手を出さなかっただろう。
雑誌『atプラス』11号に大塚英志と著者の「中国化する日本/近代化できない日本」というタイトルの対談が掲載されていたので、本屋で探したのである。
現代の日本人のありようを、宮台真司は「田吾作」と言い、大塚英志は「土人」と呼ぶ[1]。「未完の近代を生きている私たち」という私の最近の実感にぴったりと嵌った彼らの言説は、与那覇潤のこの著書によって歴史学的根拠、背景を与えられているように思う。
この本は真摯な歴史の本であり、文字通り、大学における歴史講義を書籍化したものである。
本書によれば、日本の近世(前期近世と後期近世=近代)を読み解くキーワードは、「中国(郡県制)化」と「再江戸時代(封建制)化」と「ブロン」である。そして、国家はそのシステムとシステムに馴染まされ、そしてシステムを支える国民の心性とからなっている。したがって、システムの導入は、国家の変革にそのまま直結するわけではない、という機微もまたキーである。いやむしろ、国家システムと国民心性の乖離が、「ブロン」を結果してしまう、ということが歴史の日本的特徴なのかもしれない。
星新一の造語だという「ブロン」とは、メロンのような大きな(かつ美味な)果実がブドウの実のように無数に稔る理想の果物に与えられた名辞だが、実際に得られたのは、ブドウのように小さな実がメロンのようにほんのわずかに稔る植物だった、という由来による。
内藤湖南の言説に端を発する歴史観によれば、世界で始めて近世化したのは中国の「宋」である(p. 30~)。
宋は「貴族制度を全廃して皇帝独裁政治を始めた」つまり「経済や社会を徹底的に自由化する代わりに、政治の秩序は一極支配によって維持するしくみ」を作った。「科挙」によって選抜されたエリート役人が全国に派遣されて地方政治を行い(郡県制)、税は物納から貨幣によって納めるようになる。
すなわち冷戦後、主権国家どうしの勢力均衡に立脚した国際政治のパワーバランス(その最後の事例が米ソの均衡)が崩れ、米国一国の世界覇権へと一気に傾いたように、宋朝の中国でもいくつかの名門貴族が相互に掣肘しあう関係が終わり、皇帝一人のお膝元への全面的な権力集中が起きる。かつての社会主義国よろしく貴族の荘園に閉じ込められていた一般庶民も解放されて中国(≒世界)のどこでいかなる商売に従事してもよろしくなる――ただし、皇帝(≒アメリカ)のご機嫌さえ損ねなければ。
これが、宋朝時代の中国大陸で生じた巨大な変化なのです。ポスト冷戦の「歴史の終わった」世界などというのは、それを全地球大に引きき伸ばして拡大したものに過ぎません。
……
こうして宋朝時代の中国では、世界で最初に(皇帝以外の)身分制や世襲制が撤廃された結果、移動の自由・営業の自由・職業選択の自由が、広く江湖に行きわたることになります。科挙という形で、官吏すなわち支配者層へとなり上がる門戸も開放される。科挙は男性であればおおむね誰でも受験できましたので、(男女間の差別を別にすれば)「自由」と「機会の平等」はほとんど達成されたとすらいえるでしょう。
……え、「結果の平等」はどうなるのかって?
もちろん、そんなものは保障されません。機会は平等にしたわけですから、あとは自由競争あるのみです。商才を発揮してひと山当てた人、試験勉強に没頭して頑張りぬいた人にのみ莫大な報償を約束し、それができないナマケモノは徹底的に社会の底辺に叩き落とすことによって無能な貴族連中による既得権益の独占が排除され、あまねく全員が成功に向けて努力せざるを得ないインセンティヴが生み出されるのです。
また、自由といっても与えられるのは経済活動についての自由だけで、政治的な自由は(科挙への挑戦権を除
けば)極めて強く制限されます。貴族を排除して皇帝が全権力を握った以上、その批判は御法度、彼に逆らう「自由」などというものは存在しません。……ほら、自分の商売は好き勝手し放題だけど、「党」の批判は絶対厳禁、のいまの中国と同じでしょう?
――つくづく、ひどい世界ですね。でも、ここでちょっと振り返ってみてください。先ほどまで見てきた「冷戦後の世界」と比べて、そこまでひどいでしょうか?
低賃金の新興国に市場を奪われても、お前の努力不足が原因だ、だったらもっと賃金を切り下げて働け、それができなければ自己責任だといわれる今日の社会。アメリカのご機嫌を損ねられないばっかりに、基地提供でも戦争協力でも唯々諾々と従うよりほかはない極東の某「先進国」の現状を鑑みるとき、「中国は遅れた社会だ」なんて口が裂けてもいえません。むしろ「中国こそわれわれの先輩だ」というべきでしよう。 (p. 33-5)
皇帝と科挙官僚による権力独占のための機制として働いたのが「理想主義的な理念に基づく統治行為の正統化」である。その政治体制に関する理念は、朱子学によって強化される。後の満州族であった清朝の雍正帝は、「主流派である漢民族の人々が掲げてきた理念が全世界に通用する普遍的なものであるからこそ、それを正しく身につけた人物であれば、天子の座についてもよろしいのであって、「夷狄」が皇帝になることは中華帝国の恥辱ではなく、むしろ進歩を示すことなのだと、アピール」 (p. 70) することができたのである。
この理念による説得(そして権力奪取)は、現代アメリカにもそのまま当てはまる。「バラク・オバマ氏の演説の巧みさが、「差別されてきた黒人である自分でも大統領になれた事実こそが、アメリカというこの国の輝かしい伝統であり希望の証」という形で、放っておけば自分と対立しそうな(たとえば保守派の白人層のような)人々をも彼らが奉じる建国の理念に訴えることで味方に取り込んでいく点にある」 (p. 69) とされる。
この、相手の信じている理念の普遍性をまず認め、だったら他所から来たわれわれにも資格があるでしょうという形で権力の正統性を作り出すやり方が、宋朝で科挙制度と朱子学イデオロギーが生まれて以降の、かの国の王権のエッセンスです。言い方を変えると、世界中どこの誰にでもユーザーになってもらえるような極めて汎用性の高いシステムとして、近世中国の社会制度は設計され、そのことを中国の人々は「ナショナル・プライド」にしてきたと見ることもできます(「日本でしか使えない」ことを自慢する「親方日の丸」方式とはえらい違いですね)。 (p. 70)
「宋からは多くを学びそこねた国」としての日本も、律令制の再編を進めるが、科挙制度の導入ができずに世襲制の官職・統治システムを強化するだけであった。中国で「近世」が始まったころ、日本は院政の成立によってかろうじて「中世」に達したのであった。「院政」とは、天皇、荘園貴族を中心とするシステムでは貨幣経済を導入できないため、その身分システムから離脱した上皇による革新であった、という。
かくして、対中貿易を通じて宋銭をどんどん日本国内に流入させ、農業と物々交換に立脚した古代経済を一新し、かつ荘園制に立脚した既存の貴族から実権を奪い取っていく。この、科挙以外の貨幣経済の部分で、宋朝中国のしくみを日本に導入しようとした革新勢力が、後白河法皇と平清盛の強力タッグ、西日本中心の平氏政権であったということになります(小島毅『義経の東アジア』)。
ところが、こういう市場競争中心の「グローバリズム」に反動が伴うのは今も昔も同じで、猛反発したのが荘園経済のアガリで食っていた貴族や寺社の既得権益勢力(権門)と、国際競争に適した主要産品がなく、没落必至の関東地方の坂東武者たちでした(東日本でも東北は、金を輸出できるので競争力が強い)。
この守旧派貴族と田舎侍の二大保守勢力が手を組んで、平家一門を瀬戸内海に叩き落とし、難癖をつけて奥州藤原氏も攻め滅ぼし、平氏政権下では使用が公認されかけていた中国銭をふたたび禁止して物々交換に戻し、平家に押収されていた荘園公領を元の持ち主に返す代わりに、自分たちも「地頭」を送り込んで農作物のピンハネに一枚噛ませてもらう――かように荘園制に依拠する詣権門に雇われた、よくいってボディーガード、悪くいえば利権屋ヤクザ集団が源氏であり(こういう見方を「権門体制論」といいます)、彼らの築いた「反グローバル化政権」こそが鎌倉幕府だったわけです。
世を「武士の時代」といってはいけない第二の理由がここにあります。同じく「武士」とされるなかでも、隣国宋朝の制度を導入することで、古代日本とは異なる本当に新しいことをやろうと試みた平家(ファースト・サムライ)は、実は敗北してしまっていた。
むしろ、従来型の農業中心の荘園制社会を維持しょうとした守旧派勢力である源氏(ワースト•サムライ?)の方が勝ってしまって始まったのが、日本の中世だったのです…… (p. 45-6)
さて、日本の中世はいつ始まったのか。これも内藤湖南によって、応仁の乱以降とされる。「室町時代までの日本中世は「いくつかの中国化政権の樹立を通じて、日本でも宋朝と同様の中国的な社会が作られる可能性があった時代」、戦国時代以降の日本近世は「中国的な社会とは180度正反対の、日本独自の近世社会のしくみが定着した時代」として」(p. 75)考えられる、という。
身分制の解体という中国型の近世モデルに対して、強固な身分制を基礎とする「封建制」が日本の中世のシステムとして江戸時代を通じて長く続いた理由は、「イエ」と「イネ」だという。急速に普及した水田耕作は、大地主の粗放な荘園経営を破綻させ、家族中心の小規模農業をもたらした。その農民は身分制によって土地に固定されるが、それはまた「排他的に占有できる職業や土地があって、アガリを世襲することも認められているから、欲を張らずそれさえ愚直に維持していさえすれば子孫代々そこそこは食べていける家職や家産が、ようやっと貴族と武士だけではなく百姓にも与えられた」(p. 87)ことを意味する。
中国型の近世(郡県制)と日本型近世(封建制)がもたらす文化はまったく正反対、裏返しの関係になる。著者は、その反対称性を次のようにまとめる。
〔中国近世文化の特徴〕
A 権威と権力の一致……貴族のような政治的中間層と、彼らが依拠する荘園=村落共同体(中間集団)が打破された結果、皇帝が名目上の権威者に留まらず、政治的実権をも掌握する。
B 政治と道徳の一体化……その皇帝が王権を儒教思想=普遍主義的なイデオロギーによって正統化したため、政治的な「正しさ」と道徳的な「正しさ」が同一視されるようになる。
C 地位の一貫性の上昇……さらに、皇帝が行う科挙=「徳の高さ」と一体化した「能力」を問う試験で官僚が選抜されるため、「政治的に偉い人は、当然頭もよく、さらに人間的にも立派」(逆もまた真なり)というタテマエが成立する。
D 市場べースの秩序の流動化……貨幣の農村普及などの政策により、自給自足的な農村共同体をモデルとした秩序が解体に向かい、むしろ商工業者が地縁に関係なく利益を求めて動きまわる、ノマド(遊牧民)的な世界が出現する。
E 人間関係のネットワ—ク化……その結果、科挙合格者を探す上でも、商売上有利な情報を得るためにも便利なので、同じ場所で居住する者どうしの「近く深い」コミュニティよりも、宗族(父系血縁)に代表される「広く浅い」個人的なコネクションが優先される。 (p. 48-9)
〔日本近世文化の特徴〕
A’ 権威と権力の分離……多くの歴史上の政権で、権威者=天皇と、政治上の権力保有者(たとえば将軍)は別の人物であり、また現在の政党や企業などでも、名目上のトップはおおむね「箔付け」のための「お飾り」で、運営の実権は組織内の複数の有力者に分掌されている。
B’ 政治と道徳の弁別……政治とはその複数の有力者のあいだでの利益分配だと見なされ、利害調整のコーディネートが為政者の主たる任務となるので、統治体制の外部にまで訴えかけるような高邁な政治理念や、抽象的なイデオロギーの出番はあまりない。
C’ 地位の一貫性の低下……たとえ「能力」があるからといってそれ以外の資産(権力や富)が得られるとは限らず、むしろそのような欲求を表明することは忌避される。たとえば、知識人が政治に及ぼす影響力は、前近代(儒者)から近現代(帝大教授、岩波文化人)に至るまで一貫して低く、それを(ご本人たち以外)誰も問題視しない。
D’ 農村モデルの秩序の静態化……前近代には世襲の農業世帯が支える「地域社会」の結束力がきわめて高く、今日に至っても、規制緩和や自由競争による社会の流動化を「地方の疲弊」として批判する声が絶えない。
E’ 人間関係のコミュニティ化……ある時点で同じ「イエ」に所属していることが、他地域に残してきた実家や親戚(中国でいう宗族)への帰属意識より優先され、同様にある会社(たとえばトヨタ)の「社員」であるという意識が、他社における同業者(エンジニア、デザイナー、セールスマン……)とのつながりよりも優越する。(p. 49-50)
後期近世=近代は、当然ながら明治以降ということになるが、その実体は1000年以上前の宋代への中国化に過ぎない、ということを次のように例証している。
……明治維新とは「新体制の建設」というよりも「旧体制の自壊」に過ぎないのです。
その旧体制たる日本近世の本質とはなにかといえば、もともと中世の段階まではさまざまな面で昂進していたはずの「中国化」の芽を根こそぎつみとって、日本が宋朝以降の近世中国と同様の社会へと変化する流れを押しとどめていた「反・中国化体制」ですね。
それを自分で内側から吹き飛ばしてしまつたわけですから、当然ながら明治初期の日本社会は南北朝期以来久々の、「中国化」一辺倒の時代を迎えることとなります。 (p. 126)
将軍や幕府といった二重権力状態を排除して、明治天皇ご足下の太政官に政治システムを一本化したわけですから、ようやっと(後醍醐天皇や足利義満もめざした)「宋朝以降の中国皇帝のように権力が一元化された王権」が確立されたことになります。
さらに、1890年にはいわゆる教育勅語を発布、儒教道徳の色彩が濃い徳目を「之ヲ中外ニ施シテ悖ラス、朕爾臣民ト倶ニ拳々服膺シテ咸其徳ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ」(この教えはわが国のみならず全世界に通用する普遍的な教えなのでありますからこそ、私は臣下のみなさんと一緒にこれを実践してゆくのであります:意訳)と宣言します。政治権力の集中性プラス普遍的な道徳イデオロギーに基づく正統性、まさしく素晴らしい中華王権の誕生です。 (p. 127)
1894年からはじまる高等文官任用試験(現在の国家公務員I種試験)のルーツのひとつは、科挙にあるといわれています。今日の公務員について、「実際の仕事とは何の関係もない、やたらと範囲の広い教養科目ばかりが出題されて、ガリ勉丸暗記型の受験秀才ばかりが合格する。こんな連中がキャリアだなんだといって、本当の実務を担うノン•キャリアよりも上位にふんぞり返っているから、日本の官僚はダメなんだ……」式の批判を耳にしたことのない人は、いまやいないでしょう。
そう、かような理不尽な試験採用も、もとが「科挙」なんだと思えば当たり前。 (p. 128)
え、福沢先生は「天は人の上に人を造らず人の下に人を造らず」で人間平等を説いた素晴らしい思想家じゃなかったのかって? ――もちろん、全然違います。
その文章の直後に「今広く此人間世界を見渡すに…其有様雲と泥との相違あるに似たるは何ぞや。其次第甚だ明なり…賢人と愚人との別は学ぶと学ばざるとに由て出来るものなり」(今の世の中、勝ち組はみんな勉強したから成功してるんだ。勉強しないでダラけたやつが負け犬に落ちぶれているだけだ:意訳)と述べているように、福沢が強調した平等はあくまで「機会の平等」であって「結果の平等」ではないというのが、今日の明治思想史の見解です(坂本多加雄『市場・道徳・秩序』)。
要するに、検定教科書で『学問のすすめ』が引用されているのは、「勉強しないようなバカは自己責任だから将来貧乏になってもグダグダいうんじやねえぞ」と政府に言われているのと同じだと思わなければいけないのです。それを教師も生徒も一緒になって「江戸時代までは身分差別がありました。しかし明治になって平等になりました」などとお花畑な会話の素材にしているのだから、なるほど日本の教育は平和ボケしているのでしょう。 (p. 128-9)
明治以降の日本は、明治維新によって導入された「中国型近世システム」と、日本固有の近世システムであった封建制を懐旧する「再江戸時代化」勢力の争いとして記述される。じっさい、それに基づいて、本著の大部は明治から現代までのほとんどの事象の解明に充てられている。
たとえば、労使紛争は百姓一揆である、つまり高度な産業社会は「工業化した封建制」なのだ。あるいは、「脳味噌が江戸時代のまま」に「壮大な勘違い」によって遂行された「あの戦争」。「より徹底した再江戸時代化」を断行した田中角栄。「党内の派閥」「世襲の地縁」「地元の利権」とういう封建制そのものの選挙で、国会議員はけちな地方大名。封建制としての中選挙区制度と郡県制としての小選挙区制度。自虐史観と他人を罵る本人たちの自虐史観。とにかく、右も左もばっさりの小気味のよい事例が盛りだくさんである。
そして最後に、朱子学によって強化された宋の国家理念と同じく、日本国憲法九条は日本国家の優れた政治理念である、理想である、と著者は考える。
よく考えてみてください。だって、現実の皇帝が朱子学道徳の体現者にして世界一の完璧な人格者だなんて、ありえると思いますか? あるわけないでしょうが。そんなことは百も承知です。それでも理想としては掲げておいて、あるときは国政を正す道具に、またあるときはナショナル・プライドにする。
また、なにせ世界に通用する教えですから、よそから入ってきた奴らに「取られて分け前が減る」とは考えない。むしろ、われわれの正しさが彼らをも惹きつけたのだ、という自身の普遍性の証と考えて、ますます全世界大で流通するような、大言壮語に磨きをかける。
……かようなあたりが、中国化する世界をゆるゆると生き抜く方法ではないでしようか。
この辺の間合いになれていないのが、やはり日本人です。だから改憲問題がヒステリックになる。「九条を変えなかったら、中国が攻めてきても何ひとつ防衛ができない!」と叫ぶ右派がいれは「九条がある以上、今すぐ安保も自衛隊も廃止!」と騒ぐ左派もいる。バカバカしいことこの上ありません。 (p. 288-9)
前文に国際社会についての話があるのは変だ? 書いたのがアメリカ人だから気に入らない? そんなこと、どうだっていいじゃありませんか。だって人類普遍の教えなんだから、どこの国に向けて誰が書こうと正しいものは正しい。儒教社会の近世中国にあなたが生きていたら、孔子の出自は何民族か、なんて気にしますか? 満洲族に朱子学を「盗られた」だなんて思ってどうします? もちろんその理想は全然実現には遠いわけですが、そんなのはまだ夷狄どもがまつろわぬゆえと考えて、泰然自若としておればよいのです。
そしてここに、中国化する世界、および隣国としての中国と日本がつきあう際のヒントもあるように思います。せっかく、儒教並みに現実離れしているけれども妙に高邁でスケールの大きな憲法を持っているのだから、この際それを「ジャパニズム」の核にすればいい。独立宣言やゲティスバーグの演説が「アメリカニズム」のコアにあるのと同じです。
要はその理念を使って、中国やアメリカと自国の文明の普遍性を競いあえばいいわけです。 (p. 289-90)
自身アメリカ人であるP・ス夕ロビン氏は、中国が経済や軍事でアメリカを追い抜くことは可能、また西洋型の民主主義とは異なる「賢明な専制支配」が、今後は社会発展のモデルになることすらありうる、とあっさり認めた上で、かような中国にとって真の覇権を築く上での最大のネックは、アメリカニズムに相当する普遍理念がないことだと指摘しています(『アメリカ帝国の衰亡』)。もちろん、共産化にともなって儒教を捨て、その共産主義も改革・開放で事実上放棄して軍拡とお金儲けに狂奔しているからですね。
だとすれば、その分をたまたま日本に残っている「中国的」な理念で補ってあげるのが、本当の日中友好であり、また「中国化」する世界で日本のめざすべき進路ではないか。「憲法九条はアメリカの押しつけか」とかいう議論をぐだぐだやっているヒマがあったら、「いかにして憲法九条を中国に押しつけるか」を考えるのが、真の意味での憲法改正ではないか、と私は思います。
わが国の憲法の理念からして、こういうことはよろしくない。お宅もかつては儒教の国だったはずですが、その普遍主義は、道徳精神はどうしましたか。今や中華はわが国の方に移ったという理解でよろしいか――こういう競争の結果、たとえば東アジア共同体のビジョンはやはり中国ではなく日本の憲法をべースに、というシナリオがありえないものでしょうか。 (p. 291)
国家理念、国家理想を実現性とか現実性によってその価値をはかるのではなく、じつにその理念性、理想性そのものによってその実効的有用性を見るのである。そしてそれは宋時代から連綿と続いてきたもので、とりわけて目新しい考えではない。歴史を見通せる才能はそう語るのである。
[1] 大塚英志、宮台真司『愚民社会』(太田出版、2011年)。