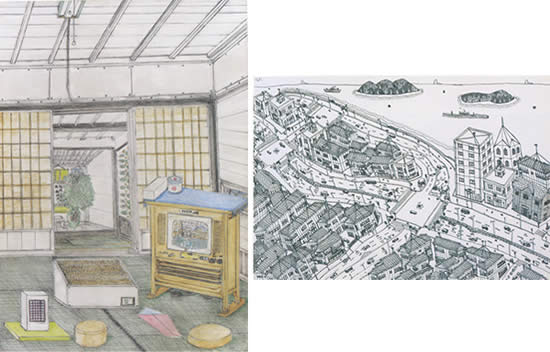森達也の『A3』がオウム事件後の社会を描きつつ批判しているとすれば、この『愚民社会』は、「3・11」後の社会批判である。とはいっても、3・11後に変わった社会を批判しているわけではない。むしろ、3・11にもかかわらず変わらない「愚民」である私たちの社会を批判しているのである。
本書は、3つの対談から構成されているが、第一章「すべての動員に抗して――立ち止まって自分の頭で考えるための『災害下の思考』」だけが3・11後になされているので、ここではその章だけに限って触れてみたい。
宮台真司は「私たち」を「田吾作」と呼び、大塚英志は「土人」と呼ぶ。それは、私たちが「未完の近代」または「前近代」を生きているにすぎないことを前提としている。しかし、深い洞察を秘めた該博な知識を有する二人の俊秀が、雄弁に語り合うことをまとめるのは至難の業である。
ここでは、これからも続く「震災後社会」を生きる私たちに棘のように刺さってくるであろう(と私が考える)話題を拾い上げるにとどめる。
対談は、いきなり震災直後の天皇の「おことば」から始まる。
宮台 三月一六日、震災のわずか五日後に天皇のビデオによる「おことば」が流れました。天皇が不特定多数の日本国民に対し、マスメディアを通じて自らメッセージを伝えたことは、一九四五年八月一五日の昭和天皇による玉音放送以来、六六年ぶりだったこともあって、一部では「平成の玉音放送」と表現されたりもしました。
僕の考えをいえば、天皇の「おことば」が"田吾作による天皇利用"であるのは至極当たり前です。田吾作というのは、真理や知識が意味を持たず、従ってどこにも大ボスがいないにもかかわらず、空気に縛られる存在のことです。昨今の原子力ムラ的なコミュニケーションが典型です。 (p. 28)
大塚 ……さらにもう一つ指摘しておきたいのは、国難みたいなものに対して天皇の気持ちに国民が心をシンクロさせる、そして、その天皇との心の一体感こそが日本人なんだと思い込むような古典的フレームの存在ですね。ぼくは、ラフカディオ・ハーンのエッセイを思い出さざるを得ない。明治時代に口シア皇太子ニコライを津田三蔵が襲って大騒ぎになった(大津事件)際に、天皇の心中を察して国中がシーンと静寂としている、その姿にハーンは感動したんだけど、冷静に考えれば、強国ロシアの皇太子に手を出してしまって、「まずくないか、おい」つて、国民全体がひいていただけだと思う。それを天皇の心にシンクロしている日本人という、いわば外国人が語った日本人論みたいなものが語られ、日本人の自己像として反復され近代天皇制がつくられていったのだということを改めて実感しました。ハーンの目には、日本人は言葉は悪いけど「土人」に見えたはずです。そこに感動したんですけど、感動された日本人の方が、「そうか、日本人ってそうなのか」と思っちゃった。明治以降、外国人の語る日本人論が日本人像の原型になっているケースが極めて多いですよね。
……
だから、問題は「日本人の自己像」がどう錯誤的につくられてきたのかという問題とも関わってくるのですが、ハーンの誤解が今や日本人の自己像になっている。そういう「日本」にぼくは違和しかない。
……
ぼくが今懐かしく思うのは、昭和天皇が亡くなったときに皇居の前に集まった人たちを見て、浅田彰が「土人」だといったことです。あのときは、さすがに浅田彰はいいすぎだろうとぼくは思ったんだけれど、それは正しかつたと思います。
……
だから震災以降、いろいろなことに対してああ、「土人」なんだ、この国の住人は、そう思うとすべてが氷解する。宮台さんは「田吾作」というけど、やさしすぎる。「土人」なんです、この国は。「天皇」の言説で歴史を区分し得るっていうのも「土人」ですね。「改元」でチャラになってまたやり直すって、つまり「歴史」という近代的な時間軸がつくれないってことでしよう。「時間はただ循環するだけでリセットを繰り返す」というのは思考回路が近代以前にあるってことでしかない。むろん、「土人」というのはあからさまな差別用語ですが、ここでは「日本人」たちが「近代」を忌避し、思考停止の中で生きている状態をそれこそ差別的に指します。 (p. 31-33)
そして、「近代」とは何か、という議論に進む。宮台は「エリート主義」を標榜してきたが、震災後にはいっそうその必要性を痛感し、近代主義的な行動規範を主張する。
宮台 つまり先に紹介した「〈任せて文句を垂れる作法〉から〈引き受けて考える作法> へ」云々は憲法前文に表明されているのです。ところが憲法施行直後に文部省が配布したあたらしい憲法のはなし』を読むと、民主主義とは多数派政治であり、多数の意見は滅多に間違わないなどと書いてあります。憲法前文に表明された精神から一〇〇歩以上後退しているのです。
多数派政治よりも大切な民主主義の本質は、参加・自治・少数者尊重・科学的態度です。つまり、(1)「〈任せて文句を垂れる社会〉から〈引き受けて考える社会〉へ」、(2)「〈空気に縛られる社会〉から〈知識を尊重する社会〉へ」、(3)「〈行政に従って褒美を貰う社会から〈善いことをすると儲かる社会〉へ」です。これらを欠いた多数決はクソも同然。
大塚さんはこうした民主主義に不可欠な 〈心の習慣〉を定着させようとしておられる。僕もそれを唱導しているほどで、それは必要な営みだと思います。 (p. 36-7)
宮台 ヨーロッパでは、一九八六年のチェルノブイリ原発事故で、エネルギーと食の危険が同時に意識されて、従来の〈食の共同体自治〉を目指すスローフードが、〈エネルギー共同体自治〉を目指す自然エネルギー運動につながります。フクシマ以降の日本的脱原発運動は巨大電力会社に電源取替えを要求するだけで、スローフードの取違えをリピートしています。
市場であれ国家であれ巨大システムに依存するのは危ないとする〈食の共同体自治〉と〈エネルギーの共同体自治〉の運動が、日本では巨大システムに食材取替えや電源取替えを要求する運動にすり替わります。ヨーロッパでは、デンマークのサムソ島が典型ですが、共同体の空洞化が始まった場所を、自然エネルギーを通じて再生しようとさえしています。 (p. 102-3)
大塚 今、震災で地域の存続が問題になっていますが、ムラ的な共同体は近代の明治期あたりで解体し始めて、昭和初頭の世界恐慌のときにほぼ崩壊しているわけです。地域の「互助システム」を使って共同体単位で日本を復興しょうとするのは世界恐慌時の政策です。農山漁村の経済更生運動、とかいうやつです。でも失敗した。とうに旧来のムラのシステムは崩壊していたからです。結局、何をやったかといえば郷土史や民話集をつくって「郷土愛」みたいなものを「あること」にして、ファシズムの下支えとしての郷土をつくった。だから厳しい言い方をすれば被災地の復興が進まないという責任の一つには「あなたたち、復興し得るような社会システムやモチベーシヨンを本当は持っていないんでしょう?」ということでしょう。 (p. 115)
大塚 本当になんとかしたいのだったら、東北だけはリアルなカタストロフィが今回あったわけで、それは、彼らだけは「近代」をやり直すチャンスがあるということです。たぶん、やらないで、中央の政治家に助成の陳情して、おしまいだと思いますが。
宮台 暴言で失脚した復興担当大臣の松本龍は実はそういったんですよ。正しいのです。
大塚 お前ら少しは自分の頭で考えろよって、ね。ぼくも彼は正しいなと思いましたよ。震災後の政治家の発言で唯一、同意できた。神戸みたいに復興予算を使い切っても何も変わらないのか、歴史のスパイラルを東北だけは一段先に行けるのかやらせりゃよかった。 (p. 116-7)
大塚 さっきもいったけど明治時代、西洋からやって来た人問はずっとこのことをいい続けているわけです。その日本人像にあわせてきた結果が現在なんですね。パーシヴァル・ローウェルは日本人は進化論的に劣勢だから自我が発達していないといい切った人です。それを踏まえた上でラフカディオ・ハーンをはじめとする明治期の外国人たちの日本人論が成り立っていて、個人的な自我、「個我」と訳されますが、個我が発達していないから集団的なのだ、と、それが最終的には美徳なのだという具合に変わっていく。
ローウェルはつまり日本人は猿だ、土人だといつてるのにそれが自己肯定的な日本人像になっていく。どう勘違いすればそうなるのかと思いますけど、「動物化」もこの文脈で受け取るべき日本人論に過ぎない。外国人が語った日本人論によって日本文化が語られて、いわば、それが「近代」へのサボタージュの方便や根拠の一つになっている。 (p. 149)
大塚 宮台さんのおしやつていることはどんどん柳田の「公民の民俗学」に近づいていっています。自分のいる、今、この場所で、公共性や社会を形成していく責任を引き受け、それは具体的には自身の言葉で合理的に考えていくということです。「共同体エリート」とは柳田が『明治大正史 世相編』の中で「選手」という形容をしているあり方に重なります。
でもやはり問題はそこから先だということに戻ります。宮台さんが育てるとすればそうした理論的前衛ですよね。「誘導する」側です。でも、思想を具体化する設計された制度を動かす必要もある。さっきいった小さなリーダーの問題ですが、具体的にはそれを各々の行動の中で振る舞い、行動として、あるいは嚙み砕かれた言葉として使っていけるような人間たちをつくっていかなければいけないわけです。それは「土人の近代化」というプログラム抜きにはあり得ない。「草の根運動」は「草の根」が「バカ」ならアメリカのティーパーティーにしかなりません
もちろん、前衛やエリートが大衆が「動物」や「土人」でただ欲望と本能で動いていってもなんとかなる社会を設計できるっていうならすればいいし、WEBってツールは「土人」統治にはよく向いている気がします。でも、WEBで「土人」を統治する社会にぼくは関わりたくない。
柳田國男が考えていた理想というのは、エリート階級の構築ではなくて、共同体の中での上位グループの実践的教育による近代化の達成です。その人たちが、理論的抽象的概念ではなく、具体的な振る舞いであるとか、民俗学でいうと習慣ですよね。習慣そのものの修正とか再設計をたぶん柳田は野心していたんですよね。 (p. 158-9)
宮台 僕の思惑通り、世田谷区や目黒区のママたちは大挙して子供たちを疎開させました。リスクマネジメントの観点から当然の行動です。ママたちの多くは日頃から原発情報に注意してきたわけではないと思いますが、震災二週問後にメルトダウンの可能性を示唆した原子力安全保安院の係官を左遷した政府&東電連合軍のインチキにいち早く気づいてくれました。
政府と東電は嘘つきだから宮台ツイートを参照したほうが良いと口コミしてくれることで、大人数の子供たちの疎開を可能にしたママたちの振る舞いは、明らかに公共的です。批判にはあたりません。ただ、しばらくたって問題だと思ったのは、僕は疎開に際してヨソの子を連れて行きましたが、同じように振る舞った人がほとんどいなかったということです。
大塚 問題はそこですよね。
宮台 大塚さんのいうように、「子供のため」という場合、「え、自分の子供だけだったのか」という問題です。というのは、近隣にも子供がいて、お父さんやお母さんの都合で東京を離れられないケースはいくらでもある。「子供のため」というなら、そういう子たちを連れて行くべきです。でも、実際にはそういう動きがほとんどなかった。想定外でした。
この部分には大塚さんの批判があたります。「なぜヨソの子を連れて疎開しないのか」と朝日新聞の記事でも語りました。リスクマネジメントの観点から疎開は合理的だといってきましたが、自分の子だけを疎開させることは合理化できません。そこには母性の自然感情を偽装したエゴセントリズム(自己中心性)があり、それ自体がこの社会の空洞ぶりを顕わにします。
大塚 そうですよね。だから、そこに共同体自治の可能性の契機を見ることは、正直にいえばとてもできない。宮台さんが夢見たように、他の家の子供も疎開させるようなことはなかった。また、ツイッターとかを介しながらも、そのネットワークはたぶん経済的なクラスの中で、完結している。宮台さんのツイッターから持ってきた情報を地域全体の母親が共有するのではなくて、そもそも母親たちは同じような経済状態でカテゴライズされていますから、その同じ階級の中で広がっていく。「安全保障」は常に保障される対象を限定しますよね。貧乏な家の子供は対象外だし、そもそも住めない。
宮台 そうですね。
大塚 その時点でアウトでしょう。 (p. 127-8)
彼らの広範な話題の展開の中で、上のピックアップは議論を少し矮小化しているかも知れない。いや、じつはハウツー的な矮小化を意図的にやったのである。震災後の今を生きる私たち「愚民」は、近代論や近代社会システム論、はては近代政治論や民俗学の中で迷子になりそうな気がしたためである。小さくとも即応した方がいいのではないか、いや、それは「土人」の行いか。