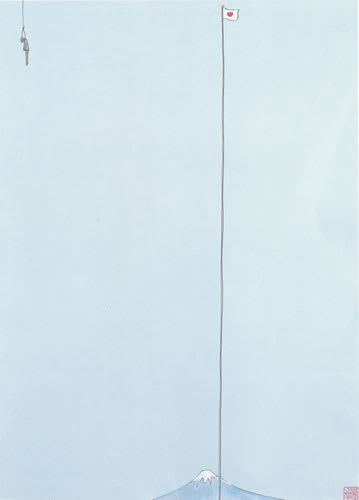円空仏を見る機会は比較的多い。以前にも国立博物館でかなりの数を見たような記憶がある。ただ、これまではいつも円空の全仕事のイメージが把握できるような見方をしたことがない。荒い鉈彫りで削り出された円空仏の不思議な魅力に、その場その場で感心していただけだった、そんな気がしている。
今回は、飛騨という限られた地域の作品群であるが、私としてはかなり見通しの良い展示となっていた。(文中、作品の番号は、図録『特別展 飛騨の円空――千光寺とその周辺の足跡』(読売新聞社、NHK,NHKプロモーション、2013)で付与されている作品番号で、引用には図録のページを示してある。)
「円空年表」 [p. 32] によれば、円空は1632(寛永9)年の生まれで、徳川治世で言えば4代家綱、5代綱吉の時代を生き、1695(元禄8)年に亡くなっている。晩年は、京都、大阪を中心とする元禄文化の隆盛期に相当している。尾形光琳、野々村仁清、本阿弥光悦などと円空が同じ時代を生きていたというのは、その作品の極端な対称性を考えれば不思議な感じがする。一方は趣味、芸術の領野で生き、一方は信仰の世界で生きたということからすれば残された作品の反対称性は当然と言えないこともないのだが。
年表には多くの作品の制作年代が記されているが、今回の出展作品45点中、制作年が記されているのは2点だけである。ただし、《如意輪観音菩薩座像》の作品解説に、「このような特色は、東北にある円空仏に通ずるもので、この像の制作時期がそれらと近い可能性がある」 [p. 132] とある。
「このような特色」とは、円空仏には珍しく、丁寧な鑿使いで平滑に仕上げている点である。円空が東北、北海道に行ったのは34,5歳の頃であるから、初期の作品の特徴と考えてよいのかもしれない。

左:《弁財天立像》 総高100.8cm、飛騨国分寺、針葉樹材(ヒノキか)製 (25)。
中:《如意輪観音菩薩座像》 総高74.8cm、東山白山神社 (26)。
右:《千手観音菩薩立像》 総高114.3cm、清峰寺、針葉樹材(ヒノキか)製 (33)。
私の勝手な推測だが、初期の作品に属すると思われるような丁寧な鑿使いの作品として、写真の3点を挙げてみた。丁寧に仕上げてあるというだけでなく、目尻が長く、柔和な表情をしている点にも共通性が見られる。誰が言ったのかすっかり忘れてしまったが、奈良の仏の表情が「アルカイック・スマイル」と表されていた(和辻哲郎の『古寺巡礼』のような気もするが、定かではない)と思うが、円空の仏たちの微少にもそのような魅力がある。
これらの作品は、おそらく日本古来からの仏像の伝統(仏師たちの伝統的な技術)に則って作られているように思える。若い時代、伝統的な仏像制作に携わるということは不思議なことではないだろう。後年の作品に見られる「自在さ」は、そうした基礎的な技法の習熟によってもたらされたと考えるのは自然である。

左:《両面宿儺座像》 総高86.8cm、千光寺、針葉樹材(アスナロか)製 (1)。
右:《金剛力士(仁王)立像 吽形》 総高226.0cm、千光寺、伝ハリギリ製 (2)。
仏師たちは職業として仏を制作する。円空は僧としての信仰の行いとして仏を彫る。それが、円空の仏たちの姿が、仏師たちの仏たちの姿から大きく離れていく理由であったろう。当然と言えば当然だが、円空仏は「信仰」概念でしか解き明かせないのではないか、と思う。
《金剛力士(仁王)立像 吽形》は、千光寺の立ち枯れの木に直接彫りつけたものだという。2mを越す威容に圧倒される作品である。この威容に、荒い鉈彫りはよく似合うのである。表現技法が表現内容に見事に適合している例だろう。
彫り方は荒いが表現は丁寧な《両面宿儺座像》も異様な作品である。「両面宿儺」とは日本書紀に登場する怪物で、浅見隆介は日本書紀を引用して次のように記している。
一つの体に二つの顔があり、互いに背を向けて頭の数は一つだが項がない。各有手足というのはその後に「四手」とあるので、顔一つにつきそれぞれ手足があるということである。ただし膝はあるが膕(ひかがみ、膝の裏の窪み)と踵とがないというから脚も顔と同様に背面に張り付いているということだろう。左右の腰に剣を佩き、四本の手で弓矢を使うという。この異形の怪物が天皇の命令に従わず、人々を苦しめたので武振熊を遣わして征伐したというのである。
おそらく五世紀ころの飛騨の豪族が大和朝廷に帰順しなかったことを反映した説話と考えられている。 [p. 28]
しかし、中央政権から見れば反逆の徒がその土地では英雄であるというのは良くある話である。飛騨の人々の信仰に寄りそっていく円空は、飛騨の英雄「両面宿儺」を信仰の対象として制作する。両面が並んでいる方が信仰心を持って見上げるのに都合がいいということもあったのだろう。手足も持ち物も日本書紀の記述とは大きく異なっている。

上:《三十三観音立像》 総高61.0~82.0cm、千光寺、針葉樹材(ヒノキか)製 (5)。
下:《如来座像》 総高 左から5.6、5.8、5.1cm、千光寺、針葉樹材(ヒノキか)製 (22)。
荒い彫りは、いっそう顕著になって、それは制作時間の短縮をもたらしただろう。円空は大量の仏を制作する。その一例が《三十三観音立像》である。「近隣の人々が病気になると借り出して回復を祈ったといい、戻らないこともあったという」 [p. 125] と解説にあり、そのような用途で作られる仏は、数が多く、できるだけ多くの人々に用いられることが大事であったろう。
また、《如来座像》のようなとても小さな仏も作られ、円空はこのような仏像を信者一人一人に授けていたらしいのである。
信者のためにたくさんの仏を作る必要があって荒い鉈彫りで制作時間の短縮をはかったのか、荒い鉈彫りの制作法の確立が多数の仏の制作を可能にしたのか、その辺の機制は分からないが、いずれせよ、「信仰」という契機がなければ起こりえないことであろう。

左二体:《護法神立像》 総高 左212.0cm、216.5cm、千光寺、針葉樹材(ヒノキあるいはスギか)製 (11)。
右二体:《金剛神立像》 総高 左216.6cm、220.3cm、飯山寺、針葉樹材(ヒノキあるいはスギか)製 (31)。
《護法神立像》と《金剛神立像》もきわめて特徴的な彫刻である。縦割りにした材の割れ跡がそのまま見えるような極端な粗彫りの身体も特徴であるが、西洋におけるマニエリスムの絵画や彫刻に見られるような異様に長い躯が目を引くのである。
二日前にエル・グレコの絵を観る機会があったのだが、グレコの描くキリスト教(カソリック)の聖人たちも異様な長躯で描かれている。それには、教会に掲げられる聖人像は崇敬の対象として信者が見上げることになるのだが、そのときにちょうど適切な長さの躯として見えるように工夫されている、という理由によるのだそうである。
円空の《護法神立像》や《金剛神立像》も信仰の対象として信者が見上げるのだろう。円空もまた、エル・グレコと同じように考えたのではないか。信者が崇敬の念を持って見上げる絵と彫刻、「信仰」を芸術に優先させた東洋と西洋の二人は同じような表象を結果するようになる。楽しい想像ではある。
ちなみに、エル・グレコは円空が生まれるわずか18年前に亡くなっている。

《賓頭盧尊者座像》 総高47.4cm、千光寺、針葉樹材(ヒノキか)製 (3)。
《賓頭盧(びんずる)尊者座像》は、作風にことさら特徴があるわけではないが、なぜか心引かれた作品である。まず「賓頭盧」という名前がいい。もともとはビンドラ・バラダージャという釈迦の弟子で、十六羅漢の一人だとされる人物である。それに、円空自身の像とも言われている、ということも興味深いのである。
また、「頭やからだにつやがあるのは人が撫でたからと思われ、撫で仏とも呼ばれる賓頭盧と見るべき」 [p. 125] という解説がある。
それを、「人々が親愛を込めて撫でていた円空さん」と勝手に解釈し直してしまうと、私の興味と興奮は極に達するようなのだ。