今回も、セブンイレブンの会長、鈴木敏文について書いていきたいと思います。
彼の経歴は1956年 中央大学経済学部卒業、東京出版販売(現トーハン)に入社[5]。から始まっているといっても過言ではありません。
略歴
株式会社セブン&アイ・ホールディングスの有価証券報告書[1]、セブン-イレブン・ジャパンの「沿革」を元に構成[2]。
長野県埴科郡坂城町出身[3]。
1952年 長野県小県蚕業高等学校(現在の長野県上田東高等学校)卒業[4]。
1956年 中央大学経済学部卒業、東京出版販売(現トーハン)に入社[5]。
1963年9月 株式会社イトーヨーカ堂入社。
1971年9月 株式会社イトーヨーカ堂取締役。
1973年11月 セブン-イレブンを展開する米サウスランド社と提携し株式会社ヨークセブン(のちの株式会社セブン-イレブン・ジャパン)を設立、専務取締役に就任。
1974年5月 セブン-イレブン1号店を東京都江東区に出店。
1975年6月 福島県郡山市でセブン-イレブンの24時間営業を開始。
コンビニ脳を量産する、衝動性をくすぐる商売)コンビニを使わなくなれば幸せになる理由
を参考にしてください。
このトーハンという業界が何をしているかというと出版取次という仕事です。
出版取次とは普通にサラリーマンをしていては縁のない世界ですね。
詳しく見ていきましょう。
・・・・・・・・・・・(出版流通の危機を読み解く① 取次という仕組み―日本は出版天国でした〈文化通信コラム第2回〉社会 2018/3/21)
いま出版業界で最大の課題は、戦後日本の出版業界を成長させる原動力であった流通網が維持できなくなりつつあることです。それは、出版流通を担ってきた「取次」の日本特有のあり方が、デジタル化の影響を受けて危機的状況に陥っていることに起因します。その「取次」はどのようなものなのか、そしてなぜ危機的な状況に陥っているのかを、数回にわたって書いてみたいと思います。
出版に興味をお持ちの方なら出版業界に「取次」と呼ばれる会社が存在することはご存じでしょう。要は書籍や雑誌を出版社から仕入れ、書店に卸している問屋の機能を果たしている会社です。日本出版販売(日販)とトーハンが大手として知られています。
この「取次」は日本にしか存在しないと思われます。海外にも本の卸会社はあるのですが、雑誌と書籍を一緒に扱うところはありません。また、書店が書籍、雑誌を仕入れる場合、日本ほど取次経由で仕入れる比率が高いという国もほかにはないと思います。
そもそも「取次」は明治時代に雑誌を配送することでスタートしました。大正時代にその雑誌配送ルートに書籍を載せて運ぶようになったことが、いまの「取次」の形につながっているといわれています。
ちなみに、雑誌の流通に書籍を初めて載せたのは、講談社を創業した野間清治で、それは関東大震災直後に刊行してベストセラーになった『大正大震災大火災』という図録だったそうです。震災という非常時に、当時のベンチャー企業であった講談社を創業した野間清治が編み出した、まさにイノベーションによって生み出された仕組みだといえます。
そして、毎日のように書店などを回っている雑誌配送網に書籍を載せることで、本来であれば1冊ずつ運ばなければならない書籍を、他の国々に比べて大変安いコストで流通させることを可能にしました。日本の書籍が諸外国に比べて安いのは、これが最大の原因です。
しかも、「取次」は新しく出る書籍を自動的に割り振って書店に配送する「配本」ということを行っています。これも日本にしかみられないものです。日本以外の国では一般的に、出版社はこれから刊行する書籍の情報や見本版を、発売の半年、短くても3カ月前には書店などに届けて注文を取り、発売後に注文した書店に配送します。

しかし、「配本」は書店が注文していなくても、書店の立地や規模(売り場面積等)、過去の販売実績などに応じて新刊書籍を届けています。「配本」を使えば、出版社は発売前に書店から注文を集めたりする必要がないのです。ですから、日本の出版社は他の国と比べて営業担当者の数が少ないなど、営業活動にかかる費用も安いのです。
<※いわゆる手発注でなく、自動発注システムですね>
第二次世界大戦後、日本の出版産業は「取次」があったおかげで、書籍、雑誌、マンガ、文庫など次々に大衆向けの安価な出版物を全国に流通させ、アメリカに次いで世界第2位の市場規模に成長することができました。当時、日本ほど出版をしやすい国はなかったでしょう。他の国(社会主義、共産主義の国は別ですが)の出版社からみれば、まさに「出版天国」
出版流通の危機を読み解く② なぜ書店が減っている?―雑誌で食べてきた街の本屋さん〈文化通信コラム第3回〉
ビジネス 2018/4/11
この頃、新聞やテレビで、書店が減っていると報道されることがあります。全国で書店がない自治体がいくつあるとか、人々に愛された小規模な書店が閉店したといったニュースです。では、書店はどのぐらい減っているのでしょうか。そして、なぜ減っているのでしょうか。
全国の書店数としてよく引用されるのが、アルメディアという調査会社の統計と、一般社団法人日本出版インフラセンター(JPO)という業界団体が発表している数字です。
このうちアルメディアは、30年以上前から『ブックストア全ガイド』という書店名簿を発行してきた会社で、書店数のデータを90年代から集計しているのはこの会社だけです。一方、JPOが書店数の集計を始めたのは、出版社が共同で運営していた「共有書店マスタ」という書店データベスの運営を開始した2009年以降です。
両者が発表する数字には違いがありますが、文化通信社では以前からアルメディアのデータを元に年に1回、全国の書店数統計をまとめてきたため、継続的な統計を行うため、アルメディアのデータを使い続けています。
アルメディアの調査によると、昨年5月時点での書店数は1万2526店。ただ、この中には営業所や本部といった売場のないところも含まれており、売場面積がわかる店舗は1万1202店。さらに、この中には少しだけ雑誌を扱っていたり、ほとんど開店休業状態の店も入っています。
図書カードを発行する日本図書普及によると、カードリーダーの設置店舗数は9080店(2017年3月末時点)ですから、それなりに書籍を揃えている書店は1万店を下回っているとみられます。アルメディアの統計をさかのぼると、いまから20年ほど前の書店数は2万3000店以上でしたので、この間に半数以下になったわけです。
それでも、日本には書店が多いのです。例えば超大国アメリカには、正確な統計はありませんが、独立系書店が2311店(2016年の書店団体会員数)、最大手書店のバーンズ&ノーブルが約650店など、おそらく全体でも5000店にみたないと思われます(書籍販売で書店以外のチャンネルも大きいのですが)。
また、欧米で比較的独立系書店が多いドイツでも、書店数は国内で3000店、オーストリアとスイス、ベルギーなどのドイツ語圏を合わせても5000店と言われています。それに比べると、減ったとはいえ日本には書店が多いのです。
欧米と比べて日本に書店が多い理由は、前回のコラムでも書いたように、日本では書店が書籍と雑誌の両方を扱ってきたからです。欧米の書店は基本的に書籍を販売する店です。欧米の雑誌は読者による定期購読が多く、書店に雑誌が置いてあったとしても、ビジネスとしては小さいのです。
日本の書店、特に中小書店は、雑誌の販売で利益を得てきました。ですから、日本には小規模な雑誌・書籍小売店が多かったのです。その雑誌市場が縮小したため、小規模な、いわゆる街の本屋さんが激減しているのです。
・・・・・・・(転載ここまで)
要するに、雑誌を配本するルートをローコストで作ったため、全国に雑誌が普及した、安く配布でき、ユーザーも書店で購読できるため、売れ数が上がり、利益の中心となったということですね。
その流通網を作ったのが、講談社の野間清治という野間一族の一人で、その流通ルートのことを出版取次という表現をするようです。
欧米では、「書籍」と「雑誌」の流通網が別々であり、雑誌は読者が定期購読するスタイルであるため、なかなか普及しない=売上げが立たないため、雑誌に対して庶民のアクセスが少ないため、ビジネスとしては小さいと説明があります。
日本は各種娯楽雑誌を安価で流通させることにより、小さな町の書店が販売網となって、利益が生み出されるシステムが確立されていたといえます。
しかし、ネットや電子書籍の時代になり、雑誌自体が市場が縮小してきて、こういった従来の古いスキームが通用しなくなり、その煽りを受けて、町の小さな書店が倒産していっているようです。
そこで、雑誌を売ってあげていたのが、コンビニという業態で、セブンイレブンの鈴木会長は出版取次業界に強い発言権を持っていました。
既存の書店では雑誌売上げ数が上げられないのを、セブンイレブンなどコンビニが中心となって雑誌売上げに貢献していたのです。
しかし、その戦略は2009年頃までしか通用しなくなります。
・・・・・・・・・・・(客引きの役目を終えつつあるコンビニの雑誌たち)

↑ コンビニ外際にずらりと並ぶ雑誌群。しかしその立ち位置も少しずつ…
コンビニでは雑誌が売れなくなりつつある
コンビニでは欠かせない商材の一つ、雑誌。コンビニで少年・少女、青年向け定期発刊誌を購入した経験がある人は多いはず。また、コンビニに足を運ぶ際、外から立ち読み客が見えることで、ある種の安心感を覚える人もいるだろう。コンビニ側にとって雑誌は、来客動機の高い商材としてだけでなく、店舗に繁盛している状況を演出させる効果も持つ、重要な存在だった。
しかしコンビニでは雑誌が売れなくなりつつある。雑誌全体の不調も一因だが、それ以上の下落スピードでコンビニでのセールスは落ち込んでいる。
 ↑ コンビニの店舗数とコンビニにおける出版物売上高
↑ コンビニの店舗数とコンビニにおける出版物売上高
原因は複数考えられる。思い当たるものを列挙すると、
・雑誌そのものの娯楽における立ち位置の低下
・外出時における暇つぶしの対象の立場をモバイル端末に奪われた
・コンビニで販売される機会が多い雑誌(専門誌)の不調
・コンビニでしか買えない雑誌の類の減少
・コンビニで販売されるタイプの雑誌における、付加価値や情報そのものの陳腐化
・成人向け雑誌の販売スペース縮小、取扱の中止
・インターネット通販の普及に伴う、コンビニでの雑誌購入の必然性の低下
などが挙げられる。雑誌そのもののコンビニでの販売はコンビニの生誕と同時に始まったものであるが、時代の流れについていけなくなった感はある。
最初に足を運ぶが、特に無くても困らない
コンビニにおける雑誌の立ち位置の低迷は、コンビニ利用者に対する調査結果からも明らか。コンビニに来店をして最初に足を運ぶ場所としては上位にあるが、「コンビニから無くなったら困るもの」では順位は低め。食品やスイーツなどはともかく、チケット・コンビニ端末よりも下位層にある始末(以下2グラフはマルハニチロホールディングス調べ)。


さらにコンビニを利用する、選択する際のポイントとしても、「本・雑誌の充実」という項目はほとんど回答者が居ない(以下グラフはリサーチバンク調べ)。

コンビニ利用者にとって、本や雑誌は別に充実していなくてもかまわない、本や雑誌がコンビニにとって、十分な集客アイテムには成りえない現状を再認識できる。
「立ち読み効果」が逆効果と認識されるように
コンビニに雑誌が置かれる理由の一つは、利用客が立ち読みをすることで、店内に客がいることを店外からも知らしめ、呼び水的な効果を期待する面にあった。しかし最近ではその効用は他のアイテム、例えば淹れたてコーヒーやイートインコーナー、数々のエンタメアイテム(キャラクター系くじ)に十八番を奪われつつある。
さらにマナーの低下もあり、他の利用客に迷惑をかけるとの理由から、少年・青年雑誌そのものを雑誌コーナーから取り払い、レジで直接販売するというコンビニも登場するようになった(少年・青年雑誌の無いコンビニ雑誌コーナー)。
携帯電話、特にスマートフォンの浸透に伴う雑誌そのものの娯楽性の相対的低下(通勤・通学電車内で利用客が何をしているかを見れば一目瞭然である)も一因だが、コンビニにとって雑誌がかつてのような「客寄せアイテム」としての価値を見出しにくくなっている、そして実際に売れ行きも低迷している事実は否定しようがない。
コンビニから雑誌コーナーが無くなることはさすがにないだろう。しかし、今後さらにその規模を縮小する、ウェイトが小さくなることは避けられまい。一方で雑誌業界サイドから見れば、小規模書店が相次ぎ閉店する中、コンビニは重要な販売ルートの一つであるだけに、由々しき事態であることは言うまでもない。
・・・・・・・(転載ここまで)
つまり、スマホ、ネットの普及により、雑誌が衰退していき、その雑誌のおかげで大躍進してきたセブンイレブンは苦境に立たされているということになります。
潰れていく中小書店を尻目に、コンビニは出版取次でぼろ儲けしていたのにも関わらず落ち目になっているといえるでしょう。
では、廃れつつある、日本の出版業界事情について見ていきましょう。
日本の出版流通の際立った特徴は、日本出版販売(日販)とトーハンという2大取次(出版業界では卸売業、問屋)が君臨していることである。この2社の売り上げがいかに突出しているかは、取次上位7社の直近の年商を見てみれば一目瞭然だ。
[1)日本出版販売(日販)6327億円、2)トーハン5748億円、3)大阪屋1282億円、4)栗田出版販売503億円、5)太洋社419億円、6)日教販379億円、7)中央社244億円]
出版社上位4社の年商は『新文化』の決算記事によると、講談社1350億円、小学館1275億円、9月に新しい決算が出る集英社が1376億円、角川グループホールディングスが映像事業339億円を含んで1416億円。
書店上位5社の年商は「日経MJ」によると、紀伊國屋書店1198億円、丸善958億円、有隣堂546億円、文教堂グループホールディングス512億円、ジュンク堂書店421億円。
これらを比較してみると、「出版社→取次(卸売)→書店」といった出版流通のメインストリームにおいて、日販、トーハンの占める位置付けがいかに巨大かが分かるだろう。日販、トーハンの規模は取次3位の大阪屋の4.5~5倍であり、4位の栗田出版販売以下とは10倍以上の開きがある。まさに流通寡占である。
また、4大出版社の規模や書店トップの紀伊國屋書店の規模は、大阪屋とほぼ拮抗(きっこう)しており、日販、トーハンに比べれば本当に小さな会社である。出版社と書店はいわば中小企業の集合体であって、寡占とは真逆の群雄割拠になっているのだ。
つまり、川上と川下の企業数が多く、川中が寡占化された、砂時計のような特異な構造を出版業界は有している。他業界にはほとんど見られない構造だ。
日本型出版流通の大きな特徴は、このように日販とトーハンの流通寡占であり、出版社は全国の書店やコンビニに書籍・雑誌を流すために2社に依存しているということ。また、中小企業の集合体である書店各社も、2社のうちどちらかとでも取引できれば、数多ある出版社の本を一挙に集めることができるのだ。日本における出版流通で取次経路の売り上げが占める割合は約7割であり圧倒的である。
『書籍再販と流通寡占』(アルメディア)の著者・木下修杏林大学客員教授は、日販、トーハン2社の取次におけるシェアは、近年ますます高まっているという。「公正取引委員会の累積集中度調査によれば、2006 年の書籍・雑誌取次業のCR3(上位3社の累積集中度)は84.0%、HHI(ハーフィンダール・ハーシュマン指数:公正取引委員会では1800以上で市場構造が高度に寡占的)は3303でした。1993年のCR3が73.1%、 HHIが2304であり、13年間で前者が10.9ポイント、後者が約1000ポイント増加しています。日販、トーハンの2社の市場占拠率は75%を超えています」とのことだ。
●戦中の国策独占会社、日配を起源とする
2大取次のルーツは1941年、戦時統制の一環として作られた日本出版配給株式会社(日配)にある。太平洋戦争に突入していく当時の政府は、出版流通統制のために、240社ほどあった取次を解散させ、日配1社に集約させた。
戦後GHQは財閥解体を目的とする、過度経済力集中排除法を施行。日配も閉鎖機関令(1947年3月)によって閉鎖機関に指定され、清算処理を命じられて、活動停止を余儀なくされた。しかし、日配がなくなれば出版物が流通しない。急遽(きゅうきょ)、日販やトーハン、大阪屋などが誕生した。
<※ GHQと組んで、意図的に情報工作するために、出版取次業界を統合したのでしょう!>
日配は書籍と雑誌の両方を扱う巨大な「総合取次」であった。このような出版取次業態は世界にない。総合取次の起源は関東大震災後の大正末期に、当時の雑誌 4大取次の東京堂、北隆館、東海堂、大東館が、書籍も積極的に扱い出したことにある。その頃すでに流通寡占は始まっていたのである。
「欧州も米国も、書籍と雑誌は別の業界。取次は別々であり、流通チャネルも異なっています。海外の書店は、書籍を売る専門店です。雑誌は主にニューズスタンド、キヨスク、スーパー、コンビニ、通信販売で売っているのです。ところが日本は取次も書店も、雑誌と書籍の両方を扱っています。日本の出版流通は、世界的に見れば奇妙な独特な発展を遂げているのです」と、木下教授は指摘した。
●欧米に比肩する書籍流通システムを構築
「日本の雑誌流通は世界一」という評価がある。大手総合取次は雑誌の流通・販売に力を入れてきたからだ。
<※ 国策的に雑誌を通して洗脳工作、文化的堕落、退廃を進めてきたということです>
一方、書籍流通は注文品の流通改善がなかなか進まなかった。欧州や米国では情報化の進行を背景にして、1980年代末~1990年代にかけて大型書籍流通センターが建設され、書籍の注文品流通の合理化・効率化が急速に進んだ。
一方、日本はそれが大きく遅れた。しかし、2000年代に入ると情報武装型の大型書籍流通センター建設に見られるように、書籍の注文品流通システムが整備されつつあると、木下氏は評価している。世界最大のネット書店・アマゾンの上陸という黒船のインパクトがあったにせよ、取次が書籍の注文品流通システム作りに巨額の投資をし、真剣に流通改善に取り組み始めたのは大きな変化だ。トーハンの桶川SCMセンター、日販の王子流通センター、大阪屋の茨木と新座の流通センターなどがそれである。
<※ 娯楽、堕落目的の雑誌流通に胡坐をかいていた業界が、米国Amazonの進出によって、書籍部門を奪われた形となります>
●日販はTSUTAYA、トーハンはGEOと提携
出版科学研究所の調べによると、1998年に1兆5315億円あった雑誌総販売金額は、2008年には1兆1299億円にまで落ち込んでいる。つまり雑誌の市場規模は最近約10年で25%近くも減少しているのだ。
書籍も同様に1998年の1兆100億円から、2008年には8878億円に落ち込んでいるものの、12%程度の減少で、雑誌に比べれば減少幅は小さいと言える。
出版業界は高度成長期、不況知らずの2ケタ成長が続いていた。1976年に雑誌の売り上げが書籍を抜いて以後、「雑高書低」が基調であった。しかしバブル崩壊以降、出版業界は長期的な売上不振に陥っている。
このような状況下でさまざまな変化が見られる。日販は「TSUTAYA」のカルチュア・コンビニエンス・クラブ、トーハンは「GEO」のゲオ、大阪屋と日販はアマゾンと関係を結んでいる。アマゾンは現在、日販との関係を深める傾向にあるのも興味深い。
<※CCCカルチャーコンビニエンスクラブはイルミナティの団体ですね!>
「TSUTAYA」「GEO」のような総合ソフトショップ、アマゾンのようなネット通販といった、新しい小売業態と取次とのタッグが出版再編の軸になる可能性もある。
●書店を系列化して、配本でコントロール
新しく書店を開く際、今日のように読者のニーズが多様化する状況に対応しようとすれば、バラエティに富んだ品揃えを確保するため、大手取次と交渉せざるを得ず、日販やトーハンの系列書店としてスタートすることになる。取次1社と独占契約を結び、一種のフランチャイズ加盟店のようになってしまうのだ。
書店は日販やトーハンに配本をコントロールされるだけではない。困ったことに中小零細書店や実績のない書店には、一番欲しいベストセラー本がなかなか配本されないといった事態が発生している。
ベストセラー本は、販売力のある大型書店、チェーン書店への配本が優先される。小さな書店はベストセラー本を一生懸命売ろうとしても調達が難しく、注文しても後回しにされ、希望する数を調達できず、店頭品切れ状態の期間が長くなって、常に販売機会の損失に苦しむことになってしまうのだ。
それだけではない。書店には見計らい配本によって、欲しくもない本も箱詰めにされて一緒に送られてくる。
書店に並んでいる本は再販商品であり、古書と異なり定価で売ることが決められている。書店は売れ残った本を値引き処分したり、売れに売れて品薄になった本を高値で売ることができない。とはいえ、新刊書のほとんどが、一度買っても返品自由な委託販売制のもとにある。ならば書店は気楽な立場かというと、そんなことはない。
取次は月々の代金回収機能を持っている。中小書店は月に2回の支払いを義務付けられている。一方で大書店は月1回の支払いだ。書店の決済は返品相殺方式なので、いずれの書店も、売れなかった本をできるだけ早く返品して、支払額を少なくしたいといった心理が働く。そこで中小書店からの信じられないほどの大量返品が発生してしまうのだ。
「新刊本の返品率は大変高い。不適正な配本、不確実な配本、非確実な押込型新刊マーケティング、非適正な新刊広告、書店の決済が送品即請求、返品自由などいくつもの原因が重なって、推計部数返品率は60~70%になるでしょう」と木下教授。書籍返品率は40%前後と言われるが、これは注文品や買切品も含めた平均値。新刊本の返品は半数をはるかに超え、極端な場合は一度も陳列されずに、出版社に返されていく。
委託販売制のメリットとしては新刊本をスピーディに全国津々浦々まで配本することや、ヒットする本やベストセラーが出やすい土壌を作れるといった効果がある。一方、問題点としては、出版社・取次の見計らい押し込み送本による大量返品の発生、書店の返品相殺方式・早期決済制と早期返品の発生などがある。
●老舗出版社の急場の資金づくりに寄与
「2大取次を中心とした巨大な日本の出版流通経済システムという枠組を補強するサブシステムとして、委託販売制、固定正味制、帳合制、再販制度などが機能しているのです。委託販売を止めて書籍を買取制にする論議がありますが、出版社たちが持っている既得権を放棄してまで、本気でそれをやろうとしているとは思えません」(木下教授)
実は、取次と老舗大手・中堅出版社200社超の間には、新刊委託部数分に対して、翌月にその何割かのお金が自動的に支払われる取り決めがある。比率は出版社によって個別に決まっていて、10割のケースから4割のケースまでさまざまだ。新刊委託で送品した本が売れようが売れまいが、新刊本を押し込めさえすれば急場のお金が作れるから、委託販売を止められないのだ。
<※ 取次側が新刊を押し売りできるシステムがあるようです。雑誌売れ行き好調だった頃は良かったのでしょう>
しかし、新しく取次と取引を始めた新規の出版社には一切そのような特典はなく、新刊委託本の代金は半年後に清算される。取次は、書店に対する配本と集金に関しては大手を優遇し中小には厳しい傾向があるが、出版社に対しては老舗と新参に分けて老舗の有力出版社を優遇しているのである。
「再販制度は日本だけではなく多くの国にあります。ただ、欧州の書籍再販国は、再販拘束期間18カ月とか24カ月というように明確な期間を決めて、それを過ぎたら自動的にオープン価格に移行する制度を取っています」(木下教授)
せめて欧州のように、弾力的に再販制度を運用すれば、出版社にとっても書店にとっても、ビジネスチャンスが広がって良いのではないだろうか。
●流通は刷新されたが、出版社が対応しきれない
1冊の本が売れると、取次のマージンは8%、書店のマージンは22~23%、残りは著者の印税や制作費がかかるものの全て出版社の取り分である。
つまり、出版社は本がヒットすれば、みるみるうちにもうかる仕組みになっている。
「私はもう“出版不況”という言葉は使わないほうがいいと思います。好況があるから不況もあるのですが、日本の出版物売上高はずっと落ちる一方ですよね。出版不況という言葉は業界人の思考停止・努力不足をごまかすための無責任な都合のいいキーワードにもなっているのです。なぜ日本だけが長期的に停滞・下降しているのか、真剣にその原因究明をすべきです。
そして、その原因を取次寡占、書店大量閉鎖などに求めるのはおかしいです。日本の出版流通システムは改善されつつあり、しかも大型店が増えているため、書店の売場面積は広がってきているのですから。
むしろ、大事な問題の1つは作り手側にあります。これだけ取次に優遇されていながら、良い企画、売れる本が作れない。良い著者を発掘できないこと、すなわち編集者の企画力の陳腐化、出版社のマーケティング力不足がまず厳しく問われるべきです」と、木下教授は出版社に手厳しい。
米国の 2007年の書籍売上高は前年より3.2%増。ドイツは3.4%増。フランスは5%増。雑誌を含まない書籍の統計ではあるが、少なくとも欧州、米国の出版業界は、日本のように落ちっぱなしのイメージはなく、不況もあれば好況もあり、むしろ近況では持ち直しているようだ。「インターネット、携帯電話が普及したから本が売れない」というのは、国際的視野から見れば嘘である。
日本の場合、出版の主役はずっと雑誌であった。
しかし平成になって、大手取次が大きな資本を投下して書籍流通システムを改善していったのは、時代を読んだ英断だったのではないだろうか。あとは出版社のコンテンツ作り、書店の売場作りがついてくるかどうかだろう。
●出版流通のリーダーとして2大取次の役割は大きい
以上、取次がどういうもので、どういった商慣行が行われているか見てきたが、出版不況の原因につながりそうな疑問点を整理してみよう。
1.日販やトーハンの過度の寡占で、ほかの取次の商売が阻害されていないかどうかは検討の余地がある。
2.日販やトーハンは中小零細書店を系列化しておいて、ベストセラー本を満足に送らなかったり、月に2回の支払いを求めたりと、売れる環境を整えていないのにお金の取り立てが厳しすぎるのではないか。書店マージンも22~23%では回転率の悪い現状では、中小零細書店はもうからなさすぎではないか。せめて 30%にはならないものか。
3.日販やトーハンと老舗出版社との間に、新刊委託部数分に対して、翌月にその何割かのお金が自動的に支払われる取り決めがあるにせよ、新しい出版社にはそのメリットがないのだから、買取制を進めればどうか。新規参入の買取制の出版社が増えれば、委託販売制のもとでの異常に高い返品率の改善につながるのではないか。
4.雑誌販売のみを視野に入れたと思しき、再販制度の硬直的運用によって、書店は売れ残った書籍を値引き販売して売りさばく自由を失っている。欧州方式で、定価販売の期間を限定して、後は書店が価格を自由に決められるようにしてはどうか。
5.流通システムがいくら最新でも、流すコンテンツや活用の仕方が悪ければ有効に機能しない。日販、トーハンは出版流通のリーダーとして、出版社、書店も巻き込んだ、売れる本作りの開発拠点にならないものか期待したい。出版社や書店を支配するというのではなく、シンクタンク機能を持てないだろうか。
出版不況の要因は複雑であり、取次のみに原因を求めるべきでない。出版社の企画や売り場が面白くないこともあるだろう。消費者・読者の変化もある。
しかし取次、特にシェアを寡占している日販とトーハンが、大手書店と老舗出版社を優遇して、零細書店と新興出版に冷たいのなら、新しく書店や出版を始めようとする人がいなくなり、硬直化した業界の衰退は必定だろう。
・・・・・・・・・・・・(転載ここまで)
出版社のコンテンツがネットに負けたということですね。
出版社の多くは、支配層側で、どうにかして、雑誌が低迷し始めたため、書籍で取り返す作戦を立て、芸能人やお笑い芸人に数々の賞を授与して話題づくりをしています。
・・・・・・(セカオワSaori 直木賞受賞ならず—芸能人が小説を書くということ。青島幸男から押切もえまで
明日1月16日、第158回直木賞が発表されます。その候補作のひとつに挙がって、大きな話題になっているのが、SEKAI NO OWARIのSaoriこと藤崎彩織さんの『ふたご』(文藝春秋)。藤崎さんにとって初の小説で、直木賞の候補に挙がったことも話題になっています。(現時点でこの作品は未読です)
今回は、いわゆる芸能人が小説を書くこと、文学賞の候補に挙がったり受賞したり、世間で話題を振りまいたり…昨年、川口則弘さんが上梓された『芸能人と文学賞』(KKベストセラーズ)を読んで、考えたことを書きました。
湊かなえ、激怒する
2016年5月、『ユートピア』(集英社)で山本周五郎賞を受賞したベストセラー作家・湊かなえさんは、そのとき「怒って」いました。
文芸の外の人が2作目なのに上手に書けているという、イロモノ扱いのままで審査された作品と僅差だった。そのような結果が動力になる小説家がいるのでしょうか。怒りや悔しさは力に変えることができるけれど、なんだそりゃ、とあきれる思いを力に変えることは、私にはできません。(中略)
今現在、そして、5年先、10年先、この海での航海を牽引することができる才能と実力を備えた船たちを、この海で勝負するのだという覚悟をもった船たちを、二番煎じの愚作に巻き込むのは、どうか今年限りにしてください。
―湊かなえ「山本周五郎賞受賞記念エッセイ」『小説新潮』2016年7月号
選考会で最終まで争った2作の候補作のうち、もう一作が、モデルでタレントの押切もえさんの『永遠とは違う一日』(新潮社)。選考委員の石田衣良、角田光代、佐々木譲、白石一文、唯川恵(敬称略)が、押切さんの候補作に相応の評価を与え、選考は最終まで拮抗したようです。
明示はされていませんが、「二番煎じの愚作」とは、2015年の又吉直樹さん『火花』の芥川賞受賞、大ヒットに継ぐものとして、「小説執筆を本業としない芸能人の小説を文学賞の候補作に挙げてきたこと」を指すのは明らかでしょう。
「小説家以外」の直木賞受賞者(1980年代以降)
「小説家以外」の、直木賞受賞者を挙げてみようとしながら、マルチな肩書きで活躍される方たちもいて、「文芸の外の人」とか「小説家以外」と区分するのが実はとても難しい。1980年上半期を見ても、脚本家として十分な実績のあった向田邦子さんは「小説家以外」と言えるのかと。
文字を紡ぐ職業で実績のある方たちも多数含めていますが、あえて挙げています。ご了承ください。
第83回 1980年上半期
向田邦子(脚本家)
「花の名前」「かわうそ」「犬小屋」
第85回 1981年上半期
青島幸男(放送作家、俳優)
『人間万事塞翁が丙午』
第86回 1981年下半期
つかこうへい(劇作家)
『蒲田行進曲』
第93回 1985年上半期
山口洋子(作詞家、クラブ経営者)
「演歌の虫」「老梅」
第94回 1985年下半期
林真理子(エッセイスト、コピーライター)
「最終便に間に合えば」「京都まで」
第99回 1988年上半期
景山民夫(放送作家)
『遠い海から来たCOO』
第122回 1999年下半期
なかにし礼(作詞家)
『長崎ぶらぶら節』
といったところでしょうか。受賞には至らなかったけど候補者になった、本業が「小説家以外」の方たちは、作詞家の阿久悠さんなどをはじめ、かなりの数になるのではないかと。
町田康さん、辻仁成さんなど、芥川賞にも「小説家以外」だった受賞者の方たちというのは、少なからずいて「小説家以外」で小説を書くというケースは、珍しくないことがわかります。
異業種から参入してくる「小説家」
以前、以下の記事で書いた内容と重複するのですが…
[書評] 林真理子 × 見城徹『過剰な二人』/ 大衆作家として生きるということ [Ted]
村上春樹さんは、エッセイ集『職業としての小説家』で、こう語っています。
小説の世界に異業種から新人が文壇に名乗りを上げてきても、すでに小説を本業として身を立てている作家たちは新人たちにはきわめて寛容である、と。
文壇をプロレスの「リング」に喩え、「リング」に上がってくるのは自由、ただそのリングの上で戦い、長く残ることができるのは極めて少人数であること、そして、ベテランの作家たちはそれをよく知っているからこそ、異業種から参入してくる新人には優しく接するのだと。
芸能人が文学賞を賑わす「功」
新進・中堅作家によるエンターテインメント作品の単行本のなかから、最も優秀な作品に贈られる賞
―公益財団法人 日本文学振興会 公式サイト
創設者の菊池寛が、時代の大衆文学とその担い手を顕彰するという目的としているなら、話題になった、今回の人気バンドのメンバーの処女作の直木賞候補も決しておかしいものではないでしょう。
近年は、中堅作家やベテラン作家の功労賞的な意味合いが強くなったこの賞も、創設当初はおそらく「新人賞」的な位置付けだったはず。
いわゆる芸能人やタレントの方たちの作品も、相応の質が伴うなら偏見なしで受け入れられるべきでしょう。一部の人にしか覗けない特殊な世界の経験に基づいて、独自の小説世界を紡ぐこともできるかもしれない。そして、その著者の知名度により、出版の側では商業的な成功も見込める。小説を読む読者層も増えるかもしれない。
だけど、少し懸念も
ただ、彼ら彼女らが一時的な話題となるだけで、1作や2作発表してその後が続かないとなると、本当にサイクルの短いインスタントな「小説家」が雨後の筍のように降って湧くだけということになる。まあ、それはそれで、文学史の中のひとつの現象としてありなのかもしれませんが。
最後にひとつ懸念するのは、冒頭で湊かなえさんが言うように、絶大な知名度を有している芸能人の「小説家」を目の前にして、本業として文学を志す多くの新進作家たち、文壇というこの海で勝負するのだという覚悟をもった船たちの、その気概が削がれてしまうのではないか、ということ。それだけは、少し気になるところです。
何はともあれ、明日1月16日に発表される結果。今回は文学にそれほど関心のない人たちも注目しているのではないでしょうか。受賞が誰であれ、結果が気になるところではあります。[Ted]
・・・・・・・・・(転載ここまで)
本流の作家が傍流のタレント作家に淘汰されていく。
致し方ないかもしれませんね。
日本の文学は、「不倫、小児性愛、同性愛、麻薬、ドラッグ、絶望、自殺」といったテーマばかりで、堕落しきっています。
雑誌や書籍も打開するポイントがみつけられそうにありません。
続いては2006年のネットの記事ですが、「1円廃棄」というシステムについてです。
関係ないかもしれませんが、どうやってコンビニ業界がFCオーナーからむしりとっているのか?
この悪魔的なFCシステムについて知れば知るほど、「コンビニは利用してはいけない」と思います。
昨年11月、福島県いわき市の「ファミリーマートいわき久之浜町店」の店長(当時)、斎藤泰慎(やすのり)さん(36)は、緊張した面持ちで店内事務所のパソコンに向かった。
画面には仕入れた商品の売価が並ぶ。斎藤さんは十数分後に「販売期限」が迫り、廃棄処分寸前となった弁当やおにぎりなど約20品目を選んでキーボードを操作した。
売価を「1円」や「5円」に書き換えていったのだ。斎藤さんはすぐにそれらの商品をかき集め、すべて売価で購入した。そして、その日を境に斎藤さんは来る日も来る日も、この操作を繰り返したという。
俗に「1円廃棄」と呼ばれるこの手法。数年前、コンビニ会計への痛烈な反対の意思表示として、別の大手チェーンで複数のオーナーが始めた方法だ。極端な値引きにみえる。だが、公正取引委員会は「お客さんに売っているわけではない。周辺地域の店との公正な競争を阻害しないので、独占禁止法上の不当廉売にはあたらない」との見解を示している。
◇
なぜこれが本部の鼻を明かすことになるのか-。それは、斎藤さんらが反発する「コンビニ会計」の仕組みを逆手にとっているからだ。コンビニ会計-それは「いくら廃棄が出ても、店だけが不利益を負う」会計システムを言う。
公取委によると、加盟店から本部に支払われるロイヤルティー(指導料)は一般的に、「売上総利益」に一定のロイヤルティー率をかけて計算される。この「売上総利益」が一般の企業会計とコンビニ会計では概念が異なるのだ。
一般企業の場合、売上総利益とは「売上高-売上原価」のことを指す(1)。しかしコンビニでは、売上総利益は「売上高-(売上原価-廃棄ロスや棚卸ロスの原価)」(2)となる。廃棄ロスは売れ残った商品、棚卸ロスとは万引などで減った商品のこと。大半のコンビニチェーンがこの方式を採用している。
単純化してみよう。原価70円のおにぎりを10個仕入れ、100円で7個売れたとする。廃棄は3個、ロイヤルティー率を50%として計算した式が表だ。すると(1)と(2)では、ロイヤルティーの金額が変わることがわかる。
(2)の場合、本部に105円、店に105円の利益が入るが、店は廃棄した商品の原価210円分も負担しなければならない。このため、店側は「105円-210円」で、105円の損になる計算だ。
では、廃棄する3個を1円にした場合はどうなるか。すると、売上高は「700円+3円(1円×3個)」で703円。このため、売上総利益は「703円-700円」で3円。本部へのロイヤルティーは1・5円ですみ、廃棄分の原価負担もしなくていい。これが、斎藤さんらのおこなう「1円廃棄」のからくりとなっている。
<※ 以下解説
全部売れた場合
売上¥1000-原価¥700=粗利¥300
本部に¥150上納
オーナー¥150利益
7個売れた場合
700-490=210
本部105
オーナー105-210(破棄分)=▲105
1円売りにした場合
703ー700=3
本部1.5
オーナー1.5
破棄分も考慮した計算
700-490=210-210(破棄分)=0
本部0
オーナー0
しかし、本部は売れ残りの買い戻しをしないので、
オーナーへの売上700円分あるので損は無し。基本的に奴隷制度 解説ここまで>
◇
1円廃棄をファミリーマート本部は認めていない。斎藤さんに対し、1月に送った「警告書」の中で、「売価変更は商品販売のためなされたものとはいえず」「適正な会計処理を定めたFC(=フランチャイズ)契約の重大な違反に該当する」と指摘、やめるように指導した。
これに対し、斎藤さんは「法的にも、契約的にも、売価変更行為(値決め行為)は、一事業主たる当方に最終権限がある」と反論。その結果、契約解除を通告され、商品配送などがストップされた。
斎藤さんは2月、同様に1円廃棄をおこなった元店長らと福島県内に新しいコンビニチェーン「フレスコ」を設立、現在、郡山市内で3号店の店長を務めている。
「問題は、いろいろなチェーンで書類や口頭による“廃棄のノルマ”があること。食品を捨てることに我慢ができない」と斎藤さん。これに対し、本部側はこう反論している。
「店の棚をいっぱいにしておかないと、(消費者が逃げて)売り逃しが出る。(廃棄は)店舗のためでもある」
◇
日本フランチャイズチェーン協会によると、コンビニチェーンは今年2月末現在で13社4万1493店にのぼる。伸びは鈍化しているとはいえ、依然増加傾向にある。その繁栄の影で起きている、コンビニ会計をめぐる攻防。実態を追った。
¥100(原価¥70)の物を10個仕入れ ロイヤルティ(50%)
・・・・・・・・(転載ここまで)
お分かりでしょうか?
要するに廃棄が出れば出るほど、オーナーは苦しくなる、借金し始めるシステムなのです。
ロスゼロなんて小売業界ではありえないのですが、それを逆手にとってオーナーを搾取するシステムです。
もう少し詳しく見てみましょう。
・・・・・・・・・・・(加盟店に弁当を廃棄させて儲けるセブン-イレブンのえげつない経営術 2014年10月25日 20時30分 LITERA(リテラ))
国内約1万7000店を超えるコンビニエンスストア業界最大手のセブン-イレブン・ジャパン(以下、セブン)。その経営術が、セブンのマンガコーナーでも売っている『まんがでわかるセブン‐イレブンの16歳からの経営学』(まんが・迫ミサキ 監修・セブン‐イレブン・ジャパン/宝島社)にまとめられている。
同書によると、約40年たゆまず成長を続けるセブンの強さの秘密が「顧客志向の商品開発力」と「発注」だという。
「顧客志向の商品開発力」とはたとえば、2013年1月に登場して1年で4億5000万杯以上売れるという大ヒットしたセブンカフェだ。セブンカフェは「開発担当者が『自分が毎日飲みたいコーヒー』の質を追求して生まれた」ものだという。
また、「発注」とは「店舗で売る商品を本部の情報ネットワークを介してメーカーや取引先に注文すること(略)顧客が欲しい商品をいかに発注するかで売上げは大きく変わってしまうからだ」(同書より)
ここまではまあ、どの小売業にも共通する話だ。しかし、セブンイレブン商法が特徴的なのは、売れ残った商品の廃棄で生じる損失(廃棄ロス)よりも、商品の発注が少なすぎて売上げを逃すロス(機会ロス)を避けることを重視している点だ。
「多くの場合、経営者は、廃棄ロスばかりを気にかけてしまいがち。だから廃棄ロスがゼロとなる『完売』だと万々歳となるお店は多い。だが、セブン‐イレブンの考え方は違う。完売は顧客にとって、その商品を買えないことを意味する。顧客は別の店に商品を探しに行くか、購入を諦めるしかない。(略)このような売り手の満足は、顧客にとっては不満足だと考える必要があるわけだ。セブン‐イレブンが目指すのは廃棄ロスではなく機会ロスの最小化である」(同書より)
つまり、売れ残ってでもいいから、品物を売り切れ状態にするな、というのである。
びっくりするような経営哲学だが、たしかにこのやり方がセブン本部を成長させたというのは事実だ。しかし、それは同書に書かれている「機会ロスの最小化」が客を呼び込んでいるというようなきれいな話ではない。実は、この経営哲学の裏には、加盟店を食い物にし、本部だけを太らせていくコンビニ独特の会計学、フランチャイズシステムを利用した詐欺まがいのカラクリがあるのだ。
そのカラクリとは、商品の「廃棄ロス」分のロイヤリティも加盟店側が支払うという、えげつない取り決めのことだ。
一般的な会計では「廃棄ロス」は「売上原価」に含むために粗利が減り、粗利に一定のチャージをかけた本部に払うロイヤリティは少なくなる。売れ残って廃棄すると、当然、仕入れ金額は払わなければならないが、そのぶんのロイヤリティは払わなくてすむ。
しかし、コンビニ業界では「廃棄ロス」を営業費用(販売費)に含めることになっており、売れ残って廃棄された商品の分も本部にロイヤリティを支払わなければならないのだ。
だから、本部は「機会ロス」を最小限にするため、などというお題目で、加盟店にどんどん商品を発注させる。発注させれば、売れ残ろうが廃棄されようが、本部に入ってくる金は増えていく。
しかし、一方の加盟店は「廃棄ロス」を出せば出すほど、大きな出費になる。『非情な社長が「儲ける」会社をつくる 日本的経営は死んだ!』(有森隆/さくら舎)ではその金額を推計している。
「公正取引委員会が二〇〇九年に実施した調査では、廃棄額は一店舗あたり年平均五三〇万円に達していた。一二年一〇月末現在、国内店舗は一万四六六二店ある。つまり、一日で二億円強、一年では七七〇億円超の商品が廃棄される計算だ。膨大な金額である。これだけのものが捨てられても、セブン-イレブン本部は何の痛痒も感じない。賞味期限切れで廃棄された商品についても、加盟店がロイヤリティを支払う取り決めになっている」
会計の専門家の間でも、このマイナスからプラスを生む「ロスチャージ会計」には疑問が呈されている。たとえば、2005年6月、「エコノミスト」(7月5日号/毎日新聞社)では、税理士資格も持つ、北野弘久日本大学名誉教授(当時・故人)が「セブン‐イレブン会計マジックを糾す」という論文を執筆し、セブンイレブン方式では各店舗の経営が「赤字」になってしまうことを指摘している。
また、北野名誉教授は「私は、希代の詐欺集団であった豊田商事の被害者弁護団長をつとめたが、コンビニの優良企業といわれるセブン‐イレブンの詐術は、豊田商事以上であるという感を深くしている」と論評しようとしたが、印刷直前に掲載情報を入手したセブン幹部による毎日新聞社への猛抗議で、その記述は削除されている。
この廃棄ロス問題は、マイナスからプラスを生む「ロスチャージ会計」として2000年代に一部加盟店により裁判で争われた。最高裁まで争われたものの、2007年、契約時に加盟店側の合意があることなどから、加盟店の主張は認められず、セブン側の勝訴となっている。
現在はこうしたトラブルもあってか、「廃棄商品の原価の15パーセント、年間100億円分を本部が負担する」という妥協案を打ち出しているが、その基本構造は変わっていない。セブン本部は営業利益は2127億円(2014年2月期 決算補足資料)と絶好調だが、これは加盟店の犠牲のうえに生み出されたものではないのか。
セブンは『まんがでわかる~』の第二弾として、『セブン ‐イレブン本部の弁当を捨てさせて儲ける方法』というタイトルの本でも出したらどうだろう。
(小石川シンイチ)
・・・・・・・・・・(転載ここまで)
相当悪質ですね。
あれこれと脱線してしまいましたが、セブンイレブンのような悪質な企業集合体は早々になくなってもらったほうが日本のためだと思います。
今回記事を書くために調べていて、これだけ悪質なシステムを構築した企業はなかなか無いと思います。
雑感ですが、FC契約でセブンイレブンだけはやめといたほうがいいとわかりました。











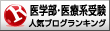

















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます