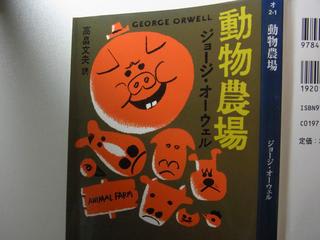The chair she sat in, like a burnished throne,
Glowed on the marble, where the glass
Held up by standards wrought with fruited vines
From which a golden Cupidon peeped out
(Another hid his eyes behind his wing)
Doubled the flames of sevenbranched candelabra
Reflecting light upon the table as
The glitter of her jewels rose to meet it,
From satin cases poured in rich profusion.
In vials of ivory and coloured glass
Unstoppered, lurked her strange synthetic perfumes,
Unguent, powdered, or liquid-troubled, confused
And drowned the sense in odours; stirred by the air
That freshened from the window, these ascended
In fattening the prolonged candle-flames,
Flung their smoke into the laquearia,
Stirring the pattern on the cofferd ceiling.
Huge sea-wood fed with copper
Burned green and orange, framed by the coloured stone,
In which sad light a carved dolphin swam.
Above the antique mantel was displayed
As though a window gave upon the sylvan scene
The change of Philomel, by the barbarous king
So rudely forced; yet there the nightingale
Filled all the desert with inviolable voice
And still she cried, and still the world pursues,
‘ Jug Jug ’to dirty ears.
And other withered stumps of time
Were told upon the walls; staring forms
Leaned out, leaning, hushing the room enclosed.
Footsteps shuffled on the stair.
Under the firelight, under the brush, her hair
Spread out in fiery points
Glowed into words, then would be savagely still.
‘My nerves are bad to-night. Yes, bad. Stay with me.
‘Speak to me. Why do you never speak. Speak.
‘What are you thinking of? What thinking? What?
‘I never know what you are thinking. Think.’
I think we are in rats' alley
Where the dead men lost their bones.
‘What is that noise?
The wind under the door.
‘What is that noise now? What is the wind doing?'
Nothing again nothing.
‘Do
‘You know nothing? Do you see nothing? Do you remember
‘Nothing?
I remember
Those are pearls that were his eyes.
‘Are you alive, or not? Is there nothing in your head?
But
O O O O that Shakespeherian Rag―
It's so elegant
So intelligent
‘What shall I do now? What shall I do?'
‘I shall rush out as I am, and walk the street
‘With my hair down, so. What shall we do tomorrow?
‘What shall we ever do?
The hot water at ten.
And if it rains, a closed car at four.
And we shall play a game of chess,
Pressing lidless eyes and waiting for a knock upon the door.
When Lil's husband got demobbed, I said―
I didn't mince my words, I said to her myself,
HURRY UP PLEASE ITS TIME
Now Albert's coming back, make yourself a bit smart.
He'll want to know what you done with that money he gave you
To get yourself some teeth. He did, I was there.
You have them all out, Lil, and get a nice set,
He said, I swear, I can't bear to look at you.
And no more can't I, I said, and think of poor Albert,
He's been in the army four years, he wants a good time,
And if you don't give it him, there's others will, I said.
Oh is there, she said. Something o' that, I said.
Then I'll know who to thank, she said, and give me a straight look.
HURRY UP PLEASE ITS TIME
If you don't like it you can get on with it, I said.
Otheres can pick and choose if you can't.
But if Albert makes off, it won't be for lack of telling.
You ought to be ashamed, I said, to look so antique.
(And her only thirty-one.)
I can't help it, she said, pulling a long face,
It's them pills I took, to bring it off, she said.
(She's had five already, and nearly died of young George.)
The chemist said it would be all right, but I've never been the same.
You are a proper fool, I said.
Well, if Albert won't leave you alone, there it is, I said,
What you get married for if you don't want children?
HURRY UP PLEASE ITS TIME
Well, that Sunday Albert was home, they had a hot gammom,
And they asked me in to dinner, to get the beauty of it hot―
HURRY UP PLEASE ITS TIME
HURRY UP PLEASE ITS TIME
Goonight Bill. Goonight Lou. Goonight May. Goonight.
Ta ta. Goonight, Goonight
Good night, ladies, good night, sweet ladies, good night,
good night.
※ 『きことわ』との直接の関連はありませんが、「チェス」からの連想です。
“「逗子市は地図でみるとイルカのかたちをしています」と百花(ももか)が読み上げた一文に永遠子は驚いた。永遠子が小学生のころは、「逗子市は地図でみると大きな魚のかたちをしています」と教わっていた。永遠子にはそれがダンクルオステウスといった古代魚のすがたにみえていた。娘の代では、イルカのかたちをしているというふれこみにかわっている。しかし、あらためてプリントアウトされた地図のかたちをイルカだと思ってみれば、たしかにそのようにもみえるのだった。百花は「ダンクルオステウスってなに?」「油壺(あぶらつぼ)マリンパークにはいる?」といくつもの質問を永遠子にむける。”
『きことわ』 朝吹真理子
“居間からひろがる一面の庭、柳に美男葛(びなんかずら)、百日紅(さるすべり)、名を知らない丈高の草木がきりなく葉擦れし、敷石の青苔(あおごけ)が石目をくくむ。はやばやと葉を落とした裸木のあるところは光線がじかに落ち、土がひかりを吸う。庭の奥はひときわ野放図に枝枝がかさなってゆく。うすみどりに照るところもあれば、青く翳る(かげる)ところもある。貴子ははじめてこの庭の秋のすがたを知った。草陰のさらに向こうからタイワンリスが鳴く。かつてひとなれした狐狸(こり)がバーベキューをしているとごそごそあらわれいでたことが年代の失われた記憶として思い起こされた。バーベキューの埋み火に松毬(まつぼっくり)をいれると形を持したまま炭化すること、午睡からめざめると草木を透して永遠子の髪と畳に流れていた暮れ方のひかり、明け方、緻密につむぎだされた蜘蛛の巣の露に濡れたのを惚ける(ほうける)ようにしてみあげたこと、一瞬一刻ごとに深まるノシランの実の藍(あい)の重さ。そのときどきの季節の推移にそったように、照り、曇り、あるいは雨や雪が垂直に落下して音が撥ねる(はねる)。時間のむこうから過去というのが、いまが流れるようによぎる。ふたたびその記憶を呼び起こそうとしても、つねになにかが変わっていた。同じように思い起こすことはできなかった。いつのことかと、記憶の周囲をみようとするが、外は存在しないとでもいうように周縁はすべてたたれている。かたちがうすうすと消えてゆくというよりは、不断にはじまり不断に途切れる。それがかさなりつづいていた。映画の回想シーンのような溶明溶暗はとられなかった。”
『同上』
“映画という機械は人間と同じでまぶたを持っているんです。それは、シャッターというものなんですが、そのまぶたが、何と一秒間に二十四回の速さでまばたきをし続けているんです。映画というのはこんな長いフィルムで、一秒間に二十四枚の絵がカタカタカタと通り過ぎていくんですね。お昌ちゃんがふっと振り向くのに一秒かかるとすると、それは二十四枚の寸断された瞬間の絵の連なりになっているんです。それが連続して送り出されると、たとえば列車に乗っていて近くの線路際の小石など見ていると、流れて線になってしまう。あんなふうに映画の画面も流れてしまうのです。けれども、車窓でさっと素早く視線を振ると、瞬間、小石の形が残像のようにまぶたの裏に焼きついて残りますよね。映画のひとコマはちょうどそれと同じで、そのまぶた代わりになるのがシャッターで、覆いかくされた、二十四分の一秒の闇なのです。つまりシャッターというものは人間のまぶたと同じでレンズの前をふさいじゃうわけですね。しかも本当はスクリーンに絵が映っている時間よりも、スクリーンが闇になっている時間のほうが長いんです。 (中略)
だから映画は本当は目の前に映し出されたものを見ているんじゃなくて、見たと信じ、目を閉じて、まぶたの裏に残っているものを見ているんですね。”
『ワンス・アポン・ア・タイム・イン尾道』 大林宣彦 (1987.8.15発行)