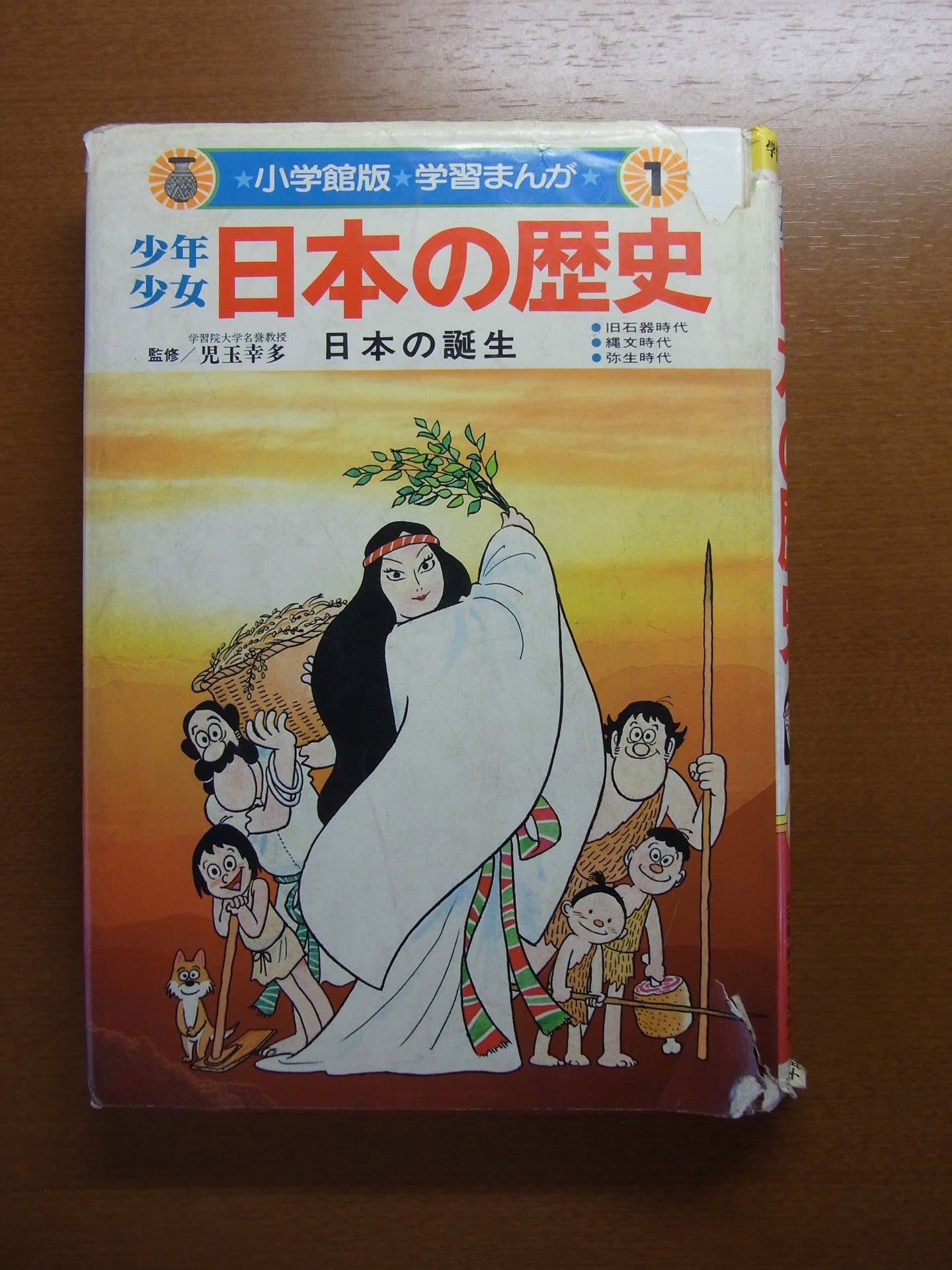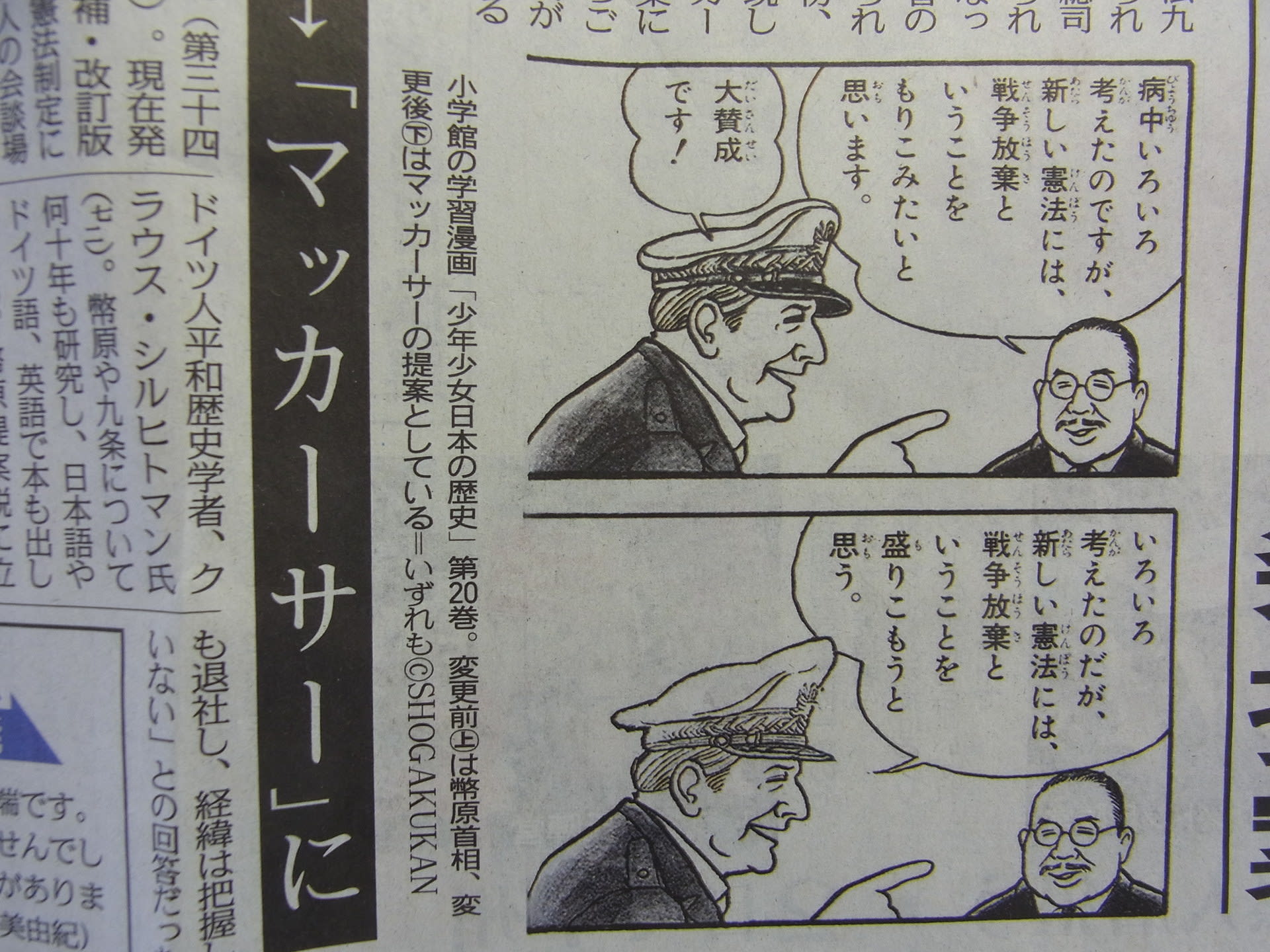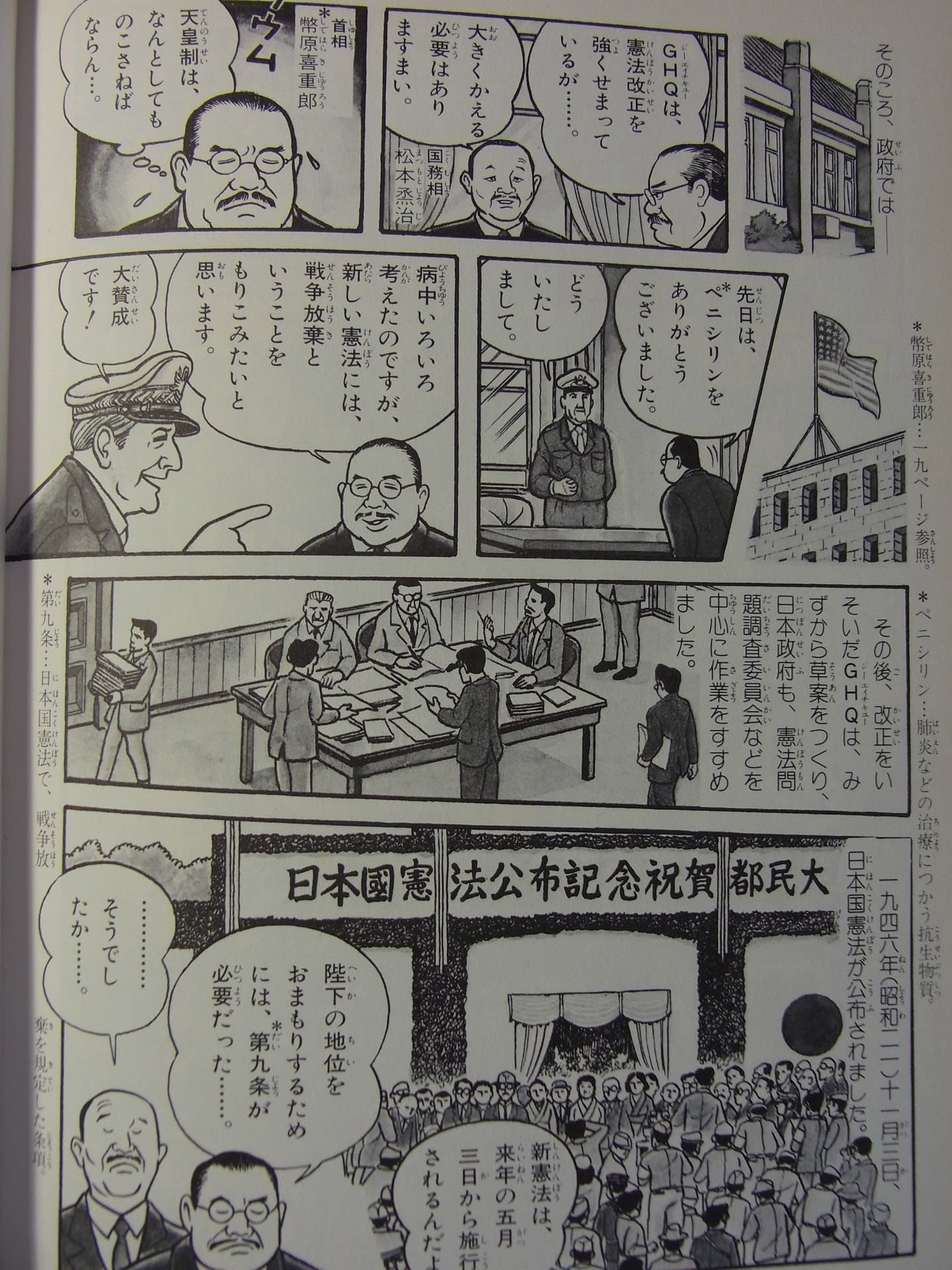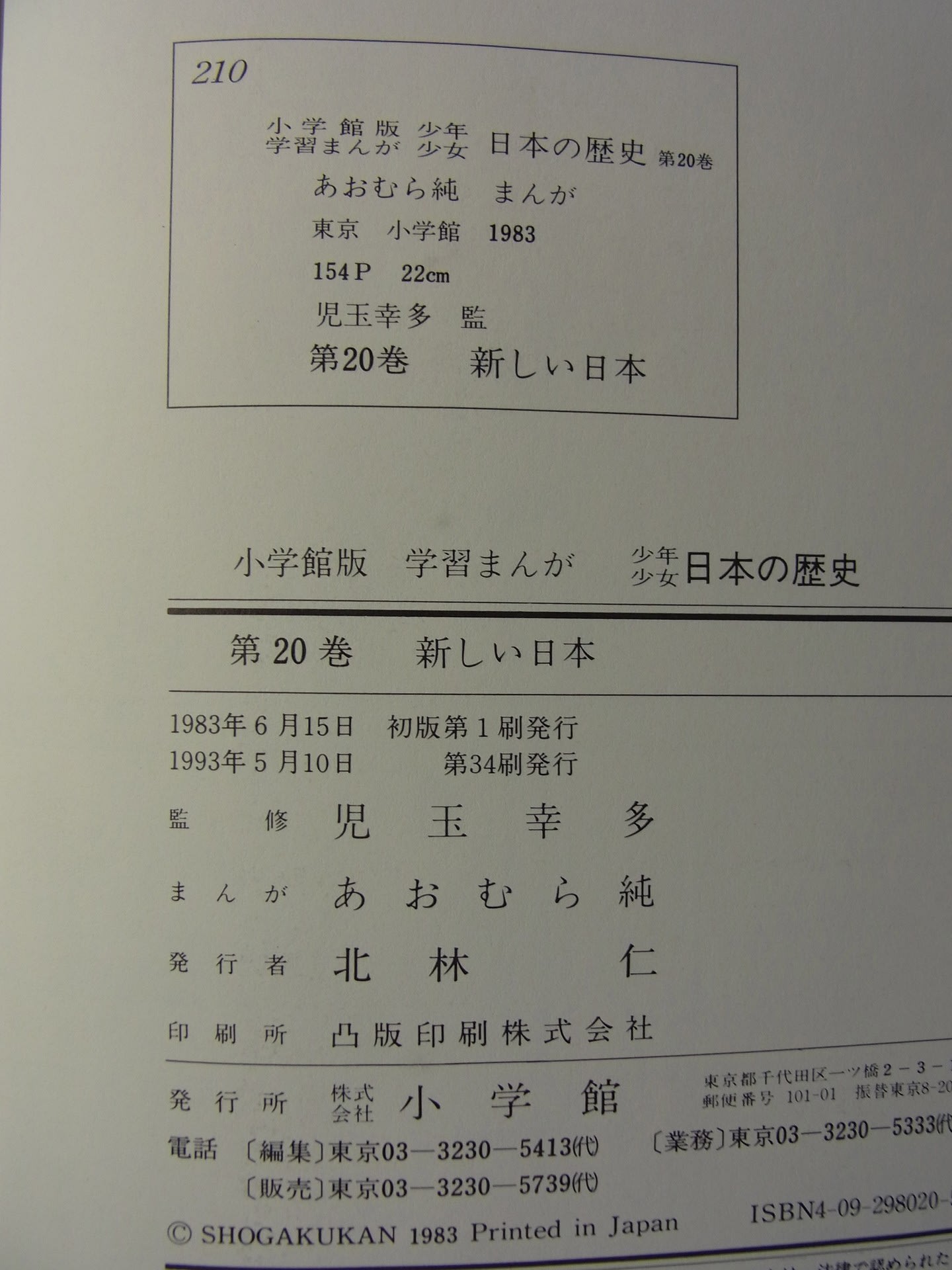『家族はつらいよ』の続篇として現在、山田洋次監督の新作『家族はつらいよ2』が制作されている。私はここしばらくツイッターを休んでいたので、その情報を全く知らなかった。しかし撮影ももう、終了しているようだ。
※ 『家族はつらいよ ニュース』
前作の『家族はつらいよ』は、近くの劇場の「フィルム撮影デジタル上映版」を観たが、「フィルム上映版」へは行けなかった。
※ 当ブログ記事,『家族はつらいよ』(2016.3.23)
だから一回しか観ていない印象であるけれど、一番強く感じたのは、「渥美清」という喜劇俳優の存在の、とてつもない大きさとその空白だった。しかし「それをいっちゃあおしめえよ」である(笑)。俳優たちの演技は勿論すばらしかったし、次の作品でも、“笑って笑ってシャツのボタンがちぎれてしまうような、そんな映画” を観ることができたなら、どんなに幸せなことだろう。
【2016.12.9 追記】
予告篇が出た。
^Ⅲ^)
「夢路」 『山田洋次作品集8』 (初出: 昭和52年1月~6月『東京新聞』「放射線」)
数年前に定年でやめてしまったが、照明技師にSさんという人がいた。中学を出るとすぐに撮影所に入り、長い間照明ひと筋に生きぬいた古き良き時代の活動屋だったが、彼がよくつかう言葉に「ユメジ」というのがあった。はじめのころはなんのことかわからなかったが、やがてそれが「イメエジ」であることを私は発見した。つまり「監督のユメジどおりにはいかないな」とか、「あの監督のユメジはよくわかるんだが」とかいったつかいかたをするのである。そして彼が「ユメジ」というときは、決して英語の「イメエジ」の発音を間違えているのではなく、あきらかに「ユメジ」つまり「夢路」というレッキとした日本語としてとらえているところがとてもおかしかった。イメージ→夢路という翻訳の妙を、私たち若い助監督は笑いながら感心したものである。
今私といっしょに仕事をしている大道具のKさんは定年まぢかである。なかなかの芸人で宴席にはなくてはならない人なのだが、このタイプの人の例にもれず、とても気持ちが優しく、まるで女性のような気づかいを見せる人である。この人は、撮影のある日には必ず三十分前にステージに入り、セットの畳を掃き、床にぞうきんをあて、スタッフが入ってくるころにはちりひとつ落ちていないほどきれいにしておいてくれる。監督である私も、たいがい三十分前にスタジオに入り、セットの畳にあぐらをかいてたばこをくゆらしながらその日いちにちのプランをあれこれ考える習慣がある。そんな私の傍らで、Kさんはいつも静かに、物音をたてないように気づかいながら掃除をしているのである。いつだったか、私が「Kさん、いつも掃除をしてくれてありがとう、おかげでとっても気持ちがいいな」と声をかけたら、Kさんは恥ずかしそうに笑いながらこう答えた。
「畳がよごれたりしてるとよ、役者が服のよごれを気にしていい芝居ができねえからよ」
映画とはすばらしい芸術なんだ、と私が思うのはそういう時である。大勢の裏方たちがそのむさくるしい風采とはうらはらに、こまやかに気をくばり、優しい思いやりを抱きながら監督の「夢路」を追うのが映画という芸術なのだ。
①“The Cider House Rules”(1999)
②『文鳥』 夏目漱石 (青空文庫)
http://www.aozora.gr.jp/cards/000148/files/753_42587.html
【2017.5.28 追記】
『Scener ur ett äktenskap』(1973)
『八月の狂詩曲』(1991)
※ 『家族はつらいよ ニュース』
前作の『家族はつらいよ』は、近くの劇場の「フィルム撮影デジタル上映版」を観たが、「フィルム上映版」へは行けなかった。
※ 当ブログ記事,『家族はつらいよ』(2016.3.23)
だから一回しか観ていない印象であるけれど、一番強く感じたのは、「渥美清」という喜劇俳優の存在の、とてつもない大きさとその空白だった。しかし「それをいっちゃあおしめえよ」である(笑)。俳優たちの演技は勿論すばらしかったし、次の作品でも、“笑って笑ってシャツのボタンがちぎれてしまうような、そんな映画” を観ることができたなら、どんなに幸せなことだろう。
【2016.12.9 追記】
予告篇が出た。
^Ⅲ^)
「夢路」 『山田洋次作品集8』 (初出: 昭和52年1月~6月『東京新聞』「放射線」)
数年前に定年でやめてしまったが、照明技師にSさんという人がいた。中学を出るとすぐに撮影所に入り、長い間照明ひと筋に生きぬいた古き良き時代の活動屋だったが、彼がよくつかう言葉に「ユメジ」というのがあった。はじめのころはなんのことかわからなかったが、やがてそれが「イメエジ」であることを私は発見した。つまり「監督のユメジどおりにはいかないな」とか、「あの監督のユメジはよくわかるんだが」とかいったつかいかたをするのである。そして彼が「ユメジ」というときは、決して英語の「イメエジ」の発音を間違えているのではなく、あきらかに「ユメジ」つまり「夢路」というレッキとした日本語としてとらえているところがとてもおかしかった。イメージ→夢路という翻訳の妙を、私たち若い助監督は笑いながら感心したものである。
今私といっしょに仕事をしている大道具のKさんは定年まぢかである。なかなかの芸人で宴席にはなくてはならない人なのだが、このタイプの人の例にもれず、とても気持ちが優しく、まるで女性のような気づかいを見せる人である。この人は、撮影のある日には必ず三十分前にステージに入り、セットの畳を掃き、床にぞうきんをあて、スタッフが入ってくるころにはちりひとつ落ちていないほどきれいにしておいてくれる。監督である私も、たいがい三十分前にスタジオに入り、セットの畳にあぐらをかいてたばこをくゆらしながらその日いちにちのプランをあれこれ考える習慣がある。そんな私の傍らで、Kさんはいつも静かに、物音をたてないように気づかいながら掃除をしているのである。いつだったか、私が「Kさん、いつも掃除をしてくれてありがとう、おかげでとっても気持ちがいいな」と声をかけたら、Kさんは恥ずかしそうに笑いながらこう答えた。
「畳がよごれたりしてるとよ、役者が服のよごれを気にしていい芝居ができねえからよ」
映画とはすばらしい芸術なんだ、と私が思うのはそういう時である。大勢の裏方たちがそのむさくるしい風采とはうらはらに、こまやかに気をくばり、優しい思いやりを抱きながら監督の「夢路」を追うのが映画という芸術なのだ。
①“The Cider House Rules”(1999)
②『文鳥』 夏目漱石 (青空文庫)
http://www.aozora.gr.jp/cards/000148/files/753_42587.html
【2017.5.28 追記】
『Scener ur ett äktenskap』(1973)
『八月の狂詩曲』(1991)