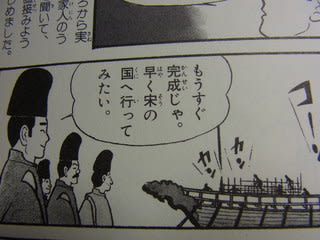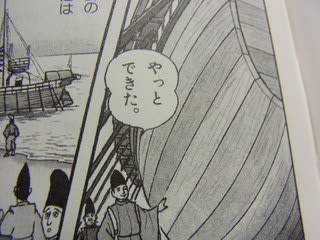※ 三浦半島へ「吟行」に行ってきた(笑)。



『日本の歴史 第13巻』
しかし、新聞や、氷川きよしの番組へ投稿できるような、「能句(よきく)」は得られなかった(笑)。
やはり、“ひとつひとつ階(きざはし)をのぼらずして、いかでか高き所に至るべき。”(鬼貫) ということだろう。
『万葉集 巻第四』(続き)
間(あひだ)なく恋ふれにかあらむ草まくら旅なる君が夢(いめ)にし見ゆる (621)
草まくら旅に久しくなりぬれば汝(な)をこそ思へな恋ひそ我妹(わぎも) (622)
道に逢ひて笑(ゑ)まししからに降る雪の消(け)なば消(け)ぬがに恋ふといふ我妹(わぎも) (624)
わが背子(せこ)がかく恋ふれこそぬばたまの夢(いめ)に見えつつ寝(い)ねらえずけれ (639)
はしけやし間近(まちか)き里を雲居(くもゐ)にや恋ひつつ居(を)らむ月も経(へ)なくに (640)
我妹子(わぎもこ)に恋ひて乱ればくるべきに掛けて搓(よ)らむと我(あ)が恋ひそめし (642)
ひさかたの天(あめ)の露霜(つゆしも)置きにけり家(いへ)なる人も待ち恋ひぬらむ (651)
相見ては月も経なくに恋ふと言はばをそろと我(あれ)を思ほさむかも (654)
我(あれ)のみそ君には恋ふるわが背子(せこ)が恋ふと言ふことは言(こと)のなぐさそ (656)
思へども験(しるし)もなしと知るものをなにかここだく我(あ)が恋ひわたる (658)
恋ひ恋ひて逢(あ)へる時だに愛(うつく)しき言(こと)尽(つ)くしてよ長くと思はば (661)
相見ぬは幾久(いくびさ)さにもあらなくにここだく我(あれ)は恋ひつつもあるか (666)
恋ひ恋ひて逢ひたるものを月(つき)しあれば夜(よ)はこもるらむしましはあり侍て (667)
倭文(しつ)たまき数にもあらぬ命(いのち)もてなにかここだく我(あ)が恋ひわたる (672)
をみなへし佐紀沢(さきさは)に生(お)ふる花(はな)かつみかつみても知らぬ恋もするかも (675)
春日山(かすがやま)朝(あさ)居(ゐ)る雲のおほほしく知らぬ人にも恋ふるものかも (677)
直(ただ)に逢ひて見てばのみこそたまきはる命に向かふ我(あ)が恋やまめ (678)
否(いな)と言はば強(し)ひめや我(わ)が背(せ)菅(すが)の根の思ひ乱れて恋ひつつもあらむ (679)
(巻第四は、まだ続く…)
【調査報告】
ら-ぶか〔羅鱶〕
ラブカ科のサメ。全長二メートルに達する。細長く、背びれの基底は長く、尾びれは槍の穂状。体は暗褐色。他のサメと違い、口が頭の先端にあることなどにより、原始的とされる。深海性で、生息地は日本では相模灘・駿河湾が知られる。 『広辞苑 第六版』



油壺しんととろりとして深ししんととろりと底から光り 北原白秋