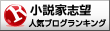一番初めにわたしのこころのスクリーンに
登場するのは、若き日の母の姿です。
わたしは五歳くらいだったでしょう。
母はわたしの目からは後ろ向き、お風呂で
使うくらいの高さの腰掛にすわって、何やら
ジャブジャブ音立ててやっています。
はいているのは、モンペでした。
わたしはほかのことに夢中。
母が何をやっているかなど、まったく興味
がありませんでした。
苗間の水口から流れ込んでくる水を、一心
に見つめていました。
いったい、何が目当てでそんなふうにして
いたのでしょうね。
「気をつけるんやで。苗間でおぼれるような
ことになったらあかんよ」
母のやさしい声が、ときどき、わたしの耳に
届きます。
「いたあ。石亀さんの赤ちゃんだ」
ひとつひとつつかんでは、バケツに入れてい
きました。
わたしの嬌声に、母がふりむいて、にこりと
笑いました。
母だけではありません。
親せきのおばさん連中もいっしょでした。
田植えも取り入れも、一族郎党、みなが寄り
集まっての作業でした。
彼女らはたくみに、両手で苗を引っこ抜いて
は、苗の束作り上げていました。
ちょうど、両手の親指と人さし指で、わっか
を作るくらいの数量です。
口にくわえた少し濡れたわらから、さっさと
二本抜き取るとすぐに、苗一束作ろうと、わら
をくるくると巻きます。
とてもすばやい動作です。
昭和二十八年の時分。
秋篠の川の水。
それはそれはきれいでした。
上流にある堰で、流れがふたつに分けられ
ていて、そのうちのひとつの流れが、堀をつ
たってくるのでした。
生き物が豊かでした。
ナマズやうなぎ、鮒に鯉。
きらきら光る小さな魚。
あれはきっとタナゴだったのでしょう。
シジミやカラス貝。
台湾どじょう。
ああそうそうモクズガニもいましたよ。
男の子にとって、川や堀っこはすばらしい
あそび場でした。
食管法が活きていた時代。
コメはすべて、荷車を牛に引かせて、農協
に運びました。
登場するのは、若き日の母の姿です。
わたしは五歳くらいだったでしょう。
母はわたしの目からは後ろ向き、お風呂で
使うくらいの高さの腰掛にすわって、何やら
ジャブジャブ音立ててやっています。
はいているのは、モンペでした。
わたしはほかのことに夢中。
母が何をやっているかなど、まったく興味
がありませんでした。
苗間の水口から流れ込んでくる水を、一心
に見つめていました。
いったい、何が目当てでそんなふうにして
いたのでしょうね。
「気をつけるんやで。苗間でおぼれるような
ことになったらあかんよ」
母のやさしい声が、ときどき、わたしの耳に
届きます。
「いたあ。石亀さんの赤ちゃんだ」
ひとつひとつつかんでは、バケツに入れてい
きました。
わたしの嬌声に、母がふりむいて、にこりと
笑いました。
母だけではありません。
親せきのおばさん連中もいっしょでした。
田植えも取り入れも、一族郎党、みなが寄り
集まっての作業でした。
彼女らはたくみに、両手で苗を引っこ抜いて
は、苗の束作り上げていました。
ちょうど、両手の親指と人さし指で、わっか
を作るくらいの数量です。
口にくわえた少し濡れたわらから、さっさと
二本抜き取るとすぐに、苗一束作ろうと、わら
をくるくると巻きます。
とてもすばやい動作です。
昭和二十八年の時分。
秋篠の川の水。
それはそれはきれいでした。
上流にある堰で、流れがふたつに分けられ
ていて、そのうちのひとつの流れが、堀をつ
たってくるのでした。
生き物が豊かでした。
ナマズやうなぎ、鮒に鯉。
きらきら光る小さな魚。
あれはきっとタナゴだったのでしょう。
シジミやカラス貝。
台湾どじょう。
ああそうそうモクズガニもいましたよ。
男の子にとって、川や堀っこはすばらしい
あそび場でした。
食管法が活きていた時代。
コメはすべて、荷車を牛に引かせて、農協
に運びました。