2025 1月29日 (水曜日) 晴
上毛新聞のコラム記事に目がいった。
随分前になるが父親が珍しく映画を見に行こうと言ったことがあった。
それは新田次郎の小説『八甲田山死の彷徨』の映画化であった。
ズーっと冷たい気がする凄い怖い映画であった。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
コラム記事は
▼日本海側を中心に住宅や農業施設が損壊するなど大雪の被害が報じられている。
記録的な積雪となった
青森県では10市町村で災害救助法が適用される事態となっている
▼1902年1月、八甲田山で発生したのが雪中行軍遭難事件である。
日露戦争を想定した演習中の青森歩兵第5連隊が猛吹雪の中で遭難し、
210人のうち199人が死亡した
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
▼この時、同じ山中で行軍していたのが、
旧境町出身の福島泰蔵大尉率いる弘前第31連隊だった。
同隊は38人全員が無事に生還。両者の明暗を分けたのは、
大尉の緻密で周到な研究と準備だったことが知られている
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
▼だが世界最大級の山岳遭難事件の陰に隠れ、
その成功に光が当たることはなかった。
大尉の死後、生家の福島家も陸軍の機密情報と考えて沈黙を守り続けた。
行軍が世に知られるようになったのは、
新田次郎の小説『八甲田山死の彷徨(ほうこう)』の題材となり、77年に映画化されてからだ。

◆会社の試験問題に二つの隊のあり方について記せ!と言うのがあったなあ~!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
▼現当主の福島国治さん(76)は13年前、
自宅の蔵で100年以上大切に保管してきた遺品の多くを自衛隊に寄贈した。
厳格できちょうめんだったと伝わる大伯父の遺影を見上げながら
「肩の荷が下りた思いだった」と振り返る
▼行軍から3年後、福島大尉が日露戦争の激戦地となった
黒溝台(こっこうだい)の会戦で戦死してから、きょうで120年となる。
吹雪の中の出来事について多くを語らぬまま、38歳の早過ぎる死だった。
=========================
◆新田次郎氏は小説以上に良い映画が出来たと言ったとか・・どこかで読んだ!
メモ: 新田次郎氏

1912(明治45)年、長野県上諏訪生れ。
無線電信講習所(現在の電気通信大学)を卒業後、
中央気象台に就職し、富士山測候所勤務等を経験する。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1956(昭和31)年『強力伝』で直木賞を受賞。 『縦走路』『孤高の人』『八甲田山死の彷徨』など山岳小説の分野を拓く。
次いで歴史小説にも力を注ぎ、
1974年『武田信玄』等で吉川英治文学賞を受ける。
1980年、心筋梗塞で急逝。没後、
その遺志により新田次郎文学賞が設けられた。

実際の出来事を下敷きに、我欲・偏執等人間の本質を深く掘り下げた
ドラマチックな作風で時代を超えて読み継がれている。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

◆御子息の藤原正彦氏
作家・新田次郎の未完の絶筆を、息子の藤原正彦
(数学者、エッセイスト、お茶の水女子大名誉教授)が
32年の歳月を経て書き継ぎ、完成させた作品である。
ポルトガルの軍人、外交官で、晩年を徳島で過ごしたヴェンセスラウ・モラエス(1854~1929年)の評伝小説だ。
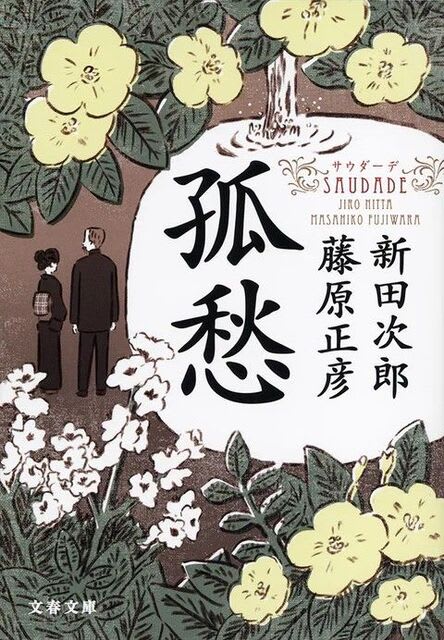
~~~~~~~~~~
◆藤原氏の本は非常に面白い。
風が出てきた。・・・こんな中、15時から青色パトロールだ。
近隣小学校の校区を青いパトライトをつけて巡回してまわる。
一時間ほどはかかる。

上毛新聞のコラム記事に目がいった。
随分前になるが父親が珍しく映画を見に行こうと言ったことがあった。
それは新田次郎の小説『八甲田山死の彷徨』の映画化であった。
ズーっと冷たい気がする凄い怖い映画であった。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
コラム記事は
▼日本海側を中心に住宅や農業施設が損壊するなど大雪の被害が報じられている。
記録的な積雪となった
青森県では10市町村で災害救助法が適用される事態となっている
▼1902年1月、八甲田山で発生したのが雪中行軍遭難事件である。
日露戦争を想定した演習中の青森歩兵第5連隊が猛吹雪の中で遭難し、
210人のうち199人が死亡した
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
▼この時、同じ山中で行軍していたのが、
旧境町出身の福島泰蔵大尉率いる弘前第31連隊だった。
同隊は38人全員が無事に生還。両者の明暗を分けたのは、
大尉の緻密で周到な研究と準備だったことが知られている
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
▼だが世界最大級の山岳遭難事件の陰に隠れ、
その成功に光が当たることはなかった。
大尉の死後、生家の福島家も陸軍の機密情報と考えて沈黙を守り続けた。
行軍が世に知られるようになったのは、
新田次郎の小説『八甲田山死の彷徨(ほうこう)』の題材となり、77年に映画化されてからだ。

◆会社の試験問題に二つの隊のあり方について記せ!と言うのがあったなあ~!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
▼現当主の福島国治さん(76)は13年前、
自宅の蔵で100年以上大切に保管してきた遺品の多くを自衛隊に寄贈した。
厳格できちょうめんだったと伝わる大伯父の遺影を見上げながら
「肩の荷が下りた思いだった」と振り返る
▼行軍から3年後、福島大尉が日露戦争の激戦地となった
黒溝台(こっこうだい)の会戦で戦死してから、きょうで120年となる。
吹雪の中の出来事について多くを語らぬまま、38歳の早過ぎる死だった。
=========================
◆新田次郎氏は小説以上に良い映画が出来たと言ったとか・・どこかで読んだ!
メモ: 新田次郎氏

1912(明治45)年、長野県上諏訪生れ。
無線電信講習所(現在の電気通信大学)を卒業後、
中央気象台に就職し、富士山測候所勤務等を経験する。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1956(昭和31)年『強力伝』で直木賞を受賞。 『縦走路』『孤高の人』『八甲田山死の彷徨』など山岳小説の分野を拓く。
次いで歴史小説にも力を注ぎ、
1974年『武田信玄』等で吉川英治文学賞を受ける。
1980年、心筋梗塞で急逝。没後、
その遺志により新田次郎文学賞が設けられた。

実際の出来事を下敷きに、我欲・偏執等人間の本質を深く掘り下げた
ドラマチックな作風で時代を超えて読み継がれている。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

◆御子息の藤原正彦氏
作家・新田次郎の未完の絶筆を、息子の藤原正彦
(数学者、エッセイスト、お茶の水女子大名誉教授)が
32年の歳月を経て書き継ぎ、完成させた作品である。
ポルトガルの軍人、外交官で、晩年を徳島で過ごしたヴェンセスラウ・モラエス(1854~1929年)の評伝小説だ。
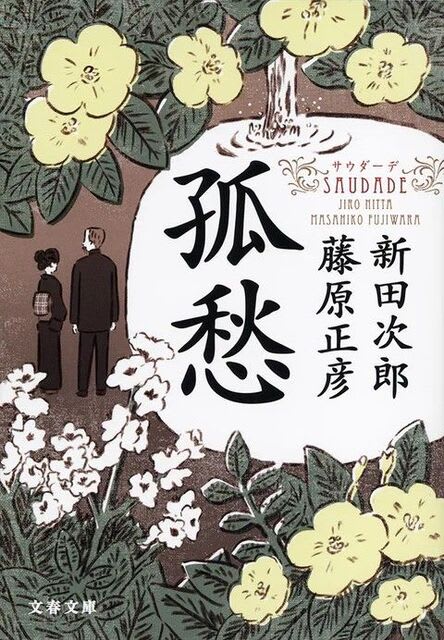
~~~~~~~~~~
◆藤原氏の本は非常に面白い。
風が出てきた。・・・こんな中、15時から青色パトロールだ。
近隣小学校の校区を青いパトライトをつけて巡回してまわる。
一時間ほどはかかる。

























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます