1.秋でもないのに/本田路津子 1970年9月
本田路津子の歌は好きだったなあ。
この歌もよかったが「風がはこぶもの」が好きだった。
それから「郊外電車で」もよかった。
どうしても森山良子とかぶってしまうところがあってかわいそうに思っていた。
キレイな高音ゆえになのか、それとも彼女のイメージなのか「清純」な歌しか歌えないような雰囲気もあって、いまひとつ幅がなくて、とも思っていた。
2.春だったね/吉田拓郎 1972年7月
アルバム「元気です」の最初の曲である。
このアルバムはとっても注目されていたものだった、と思う。「結婚しようよ」が大ヒットして、さあ続いて吉田拓郎はどうなるのか?という期待と、うまくいくのかという興味とが混ざっていた、そんな社会の雰囲気であったように思う。
これまでの吉田拓郎の歌は「私小説風で若干野暮ったい」というカンジではあった。つまり、僕らの気持ちを代弁しているようではあるが、それは僕らには魅力ではあるが、僕らでない人にとってはどうなんだろう?「結婚しようよ」だけの一発屋で終わるのではないだろうか?という不安みたいなものがあった。
しかし「元気です」はそれをすっかり消し去ってしまった。
この「春だったね」は、洗練されたサウンド、のように感じたし、なんといっても「春」のほこりっぽい乾いた情景が感じ取れた。
ほかの曲も含めて、これまで以上のスケールの大きさが感じられたのであった。
「春だったね」はその後もいろいろ編曲されて発表されているが、どうしても「元気です」のアレンジが忘れられない。
2006年のつま恋のコンサートで
「そいじゃ 皆さんの 好きな曲を やってあげるね」
といって、この歌のイントロがはじまったときには、鳥肌がたった。
拓郎の歌ではある種「別格」の存在なのである。
3.ロマンス/GARO 1973年8月
甘い歌を甘く歌われると、なんだか恥ずかしくなったりするのである。
GARO自身も、この路線はあまり好んでいなかった、ということも聞くが、一生懸命やってはいるものの、どこか乗り切っていない雰囲気があって、あまり好んで聴いた歌ではなかった。
4.ありがとう/小坂忠 1971年10月
小坂忠という人がいる、ということは知っていたが、歌は聴いたことがなかった。
この歌もはじめて聴いたと思うのであるが、なんだか聴いたことがあるような気もするし・・・
細野晴臣の作詞・作曲だそうで、そういうカンジは十分にある。
5.ポスターカラー/古井戸 1972年9月
古井戸とかRCサクセションの歌は、当時の自分とは「かけ離れている」というような気がして、敬して遠ざける、というような存在であった。
描かれている世界がよく理解できなかったのである。
自分の周りにはない世界だったような気がする。
6.花・太陽・雨/PYG 1971年4月
PYGは「スーパーバンド」という位置づけであったが、なんだかとっても高いところに位置するようであって「共感度」がいまひとつだったような気がする。
ちょうど今の巨人(ジャイアンツ)のように、グループサウンズのなかから4番バッターをピックアップしてきたようで、そんざいそのものが「おそれいったか」というようでいて、歌詞もサウンドもなんだか難しかった。
「ブログ村」というところにこのブログを登録しています。読書日記を探しているかた、下のバナーをクリックするとリンクされていますので、どうぞご覧ください。またクリックしてもらうと私の人気度が上がるということにもなります。そのへんもご考慮いただき、ひとつよろしくお願いします。

本田路津子の歌は好きだったなあ。
この歌もよかったが「風がはこぶもの」が好きだった。
それから「郊外電車で」もよかった。
どうしても森山良子とかぶってしまうところがあってかわいそうに思っていた。
キレイな高音ゆえになのか、それとも彼女のイメージなのか「清純」な歌しか歌えないような雰囲気もあって、いまひとつ幅がなくて、とも思っていた。
2.春だったね/吉田拓郎 1972年7月
アルバム「元気です」の最初の曲である。
このアルバムはとっても注目されていたものだった、と思う。「結婚しようよ」が大ヒットして、さあ続いて吉田拓郎はどうなるのか?という期待と、うまくいくのかという興味とが混ざっていた、そんな社会の雰囲気であったように思う。
これまでの吉田拓郎の歌は「私小説風で若干野暮ったい」というカンジではあった。つまり、僕らの気持ちを代弁しているようではあるが、それは僕らには魅力ではあるが、僕らでない人にとってはどうなんだろう?「結婚しようよ」だけの一発屋で終わるのではないだろうか?という不安みたいなものがあった。
しかし「元気です」はそれをすっかり消し去ってしまった。
この「春だったね」は、洗練されたサウンド、のように感じたし、なんといっても「春」のほこりっぽい乾いた情景が感じ取れた。
ほかの曲も含めて、これまで以上のスケールの大きさが感じられたのであった。
「春だったね」はその後もいろいろ編曲されて発表されているが、どうしても「元気です」のアレンジが忘れられない。
2006年のつま恋のコンサートで
「そいじゃ 皆さんの 好きな曲を やってあげるね」
といって、この歌のイントロがはじまったときには、鳥肌がたった。
拓郎の歌ではある種「別格」の存在なのである。
3.ロマンス/GARO 1973年8月
甘い歌を甘く歌われると、なんだか恥ずかしくなったりするのである。
GARO自身も、この路線はあまり好んでいなかった、ということも聞くが、一生懸命やってはいるものの、どこか乗り切っていない雰囲気があって、あまり好んで聴いた歌ではなかった。
4.ありがとう/小坂忠 1971年10月
小坂忠という人がいる、ということは知っていたが、歌は聴いたことがなかった。
この歌もはじめて聴いたと思うのであるが、なんだか聴いたことがあるような気もするし・・・
細野晴臣の作詞・作曲だそうで、そういうカンジは十分にある。
5.ポスターカラー/古井戸 1972年9月
古井戸とかRCサクセションの歌は、当時の自分とは「かけ離れている」というような気がして、敬して遠ざける、というような存在であった。
描かれている世界がよく理解できなかったのである。
自分の周りにはない世界だったような気がする。
6.花・太陽・雨/PYG 1971年4月
PYGは「スーパーバンド」という位置づけであったが、なんだかとっても高いところに位置するようであって「共感度」がいまひとつだったような気がする。
ちょうど今の巨人(ジャイアンツ)のように、グループサウンズのなかから4番バッターをピックアップしてきたようで、そんざいそのものが「おそれいったか」というようでいて、歌詞もサウンドもなんだか難しかった。
「ブログ村」というところにこのブログを登録しています。読書日記を探しているかた、下のバナーをクリックするとリンクされていますので、どうぞご覧ください。またクリックしてもらうと私の人気度が上がるということにもなります。そのへんもご考慮いただき、ひとつよろしくお願いします。











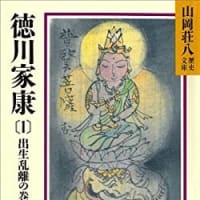
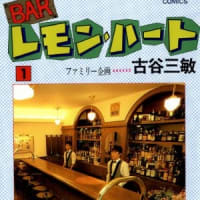
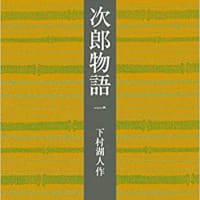
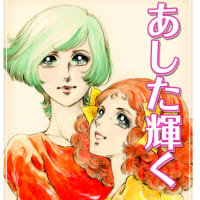
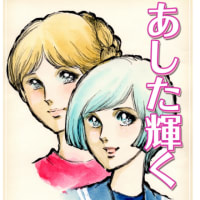
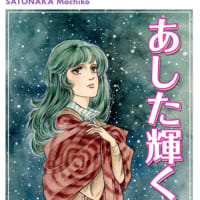
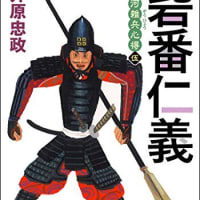
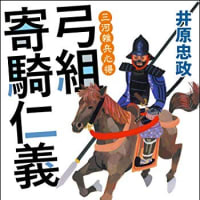
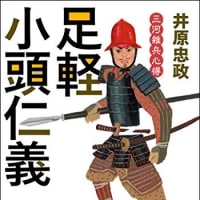
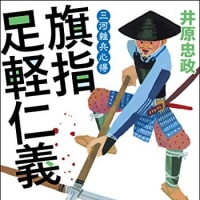





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます