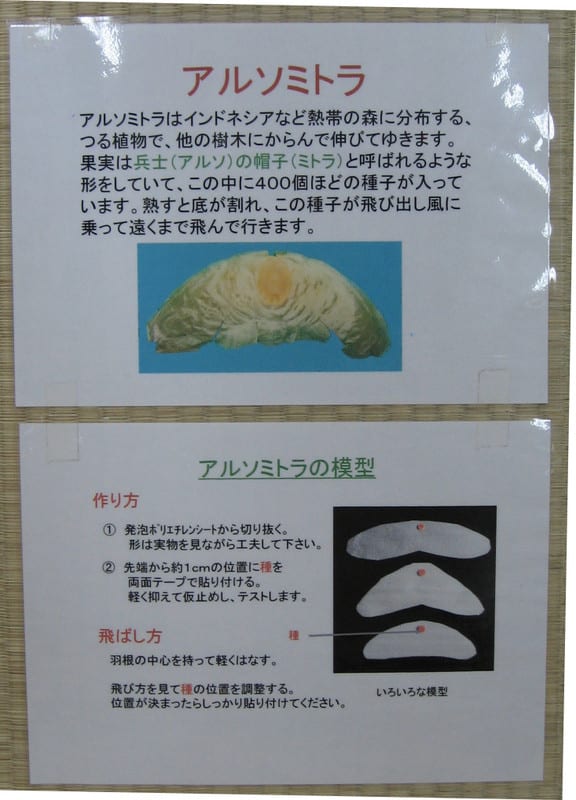2011年10月1日(土)~3日(月)の三日間に亘って、西東京市の南町地区会館まつりが開催された。
通常、会館を利用して活動しているグループや個人、地域にある柳沢小学校の児童が、手芸品や工作品、書道、絵画、短歌(短冊)、写真、いけばな、夏休みの自由研究、旅行記などを持ち寄って展示したり、舞踊・カラオケ・民謡・詩吟・シャンソンなどの発表をしたり、活動<ヨガ・茶道・着付け教室・謡曲など>の公開を行うイベントなどに参加ができる。今年も、留学生をはじめ多数の来場者があって大変賑わっていた。
地区会館は、西東京市(旧田無市)における地域のコミュニティセンターである。市内11か所あり、それぞれの地域の住民による自主運営(指定者管理制度による)で行っている。その中でも、南町地区会館の活動は非常に活発である。設立してから25年あまりの間に、地域の住民の長年のボランティアが実り、単なる施設の貸し出しにとどまらず、「文化部」「文庫部(ぞうさん文庫)」「広報部」の3本柱の元に計画的な活動が行われている。
一番古い歴史を持つ「文庫部=ぞうさん文庫」は、南町地区会館が設立される以前より、地域の子どもたちのお母さんたちが、子どもたちのために洋治・児童向け図書を集めて貸し出しを行っている。また、年間に”夏休み工作教室”、”クリスマスお楽しみ会”、”七夕飾り”のほか、毎月1回【お話しおばさん】による読み聞かせも行われている。今では、児童図書にとどまらず大人向けの新刊書などの貸し出しも行っている。活動は、毎週金曜日午後3時~5時と限られているが、子どもの数が少なくなっている昨今、年々、活動に参加したり、本を借りに来る子供の数は減ってきているのは寂しい気がする。
次に始まったのが、「文化部=会館まつり」前述のように、地域住民の学習・懇親・情報交換の場になっている。
「広報部=会館だより」(毎月15日発行)では、もともと、会館運営の情報を発信するだけであったが、2000年より、折角のB4判の誌面を有効に活用し、地区会館内の運営だけにとどまらず、地域活動の情報発信の場にしようということから、両面を使って多くの日常的な内容の発信も行っている。南町1・2・3丁目、向台町1丁目、柳沢5・6丁目の一部に市報と共に5000戸あまりに配布されている。地域の青少年育成会「あしたば」や、子どもや高齢者の交流活動をするボランティアグループ「ふれあいの会」などの活動紹介などや、地域内の柳沢小学校、田無工業高校などにおける外部向けの活動、および、「振り込め詐欺」や「交通安全」、選挙啓発の情報なども掲載している。
私も、広報部に地域ボランティアとして所属していて、毎月、取材や写真撮影と原稿作成をさせていただいている。会館まつりには、ポスターや案内チラシ[プログラム]の作成もお手伝いさせていただいています。