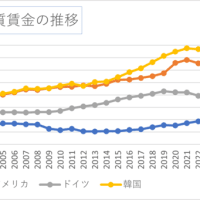今回も、私と取引の有った会社の話しです。 経営方針によっては、会社が長続きしたり、あっという間に破綻するケースも有ります。チョットした工夫が、会社を良くする場合も有ります。
【先端技術を追求した会社】
ガラ携→スマホへと急激に技術が進歩しました。それらに欠かせない部品を開発/製造していた会社の話しです。 その会社から製造ラインに組み込む高価な部品を、年に二三回発注して頂きました。毎回、新しい工夫を要求するので、私は、その都度打合せに行きました。対応してくれる方は、何時も同じ課長さんだったので、お互いに何でも話せる関係になりました。彼は、給与の話もしました。私の2倍以上の高給でした。
工場は立ち入り禁止で、現場社員の様子は分かりませんでしたが、スタッフ達は生き生きと働いている様に見受けられました。 然し、私は「この会社は長続きしない」と思いました。
私の”持論”では、『ある技術が急激に進歩する時期がありますが、→停滞する様になり、→飽和状態が続き、・・・→周辺技術が進んで、→その技術がまた進歩し始めます。』 会社が永続する為には、開発は重要ですが、安く製造する努力はもっと重要なのです。 特に・この会社が手掛けていた巨大なマーケットが有る場合はそうです。 中国の企業が、この会社の製品を真似て、安価な製品を売り始めました。この会社は、更に難しい製品を開発して上市するのですが、暫くすると、ほぼ同機能の製品を中国企業が安価に売り始めるのです。・・・→現在、この会社は存在していません。
(学生諸君へのアドバイス) ベンチャー企業への就職を考えられている方は、「将来、市場が拡大すると予想される分野の企業では、競合企業に対抗する事を加味した経営をしているか?」と言う視点でも、企業を選択すべきです。
(私の心配) キーエンス社は1974年の創業以来、難しい/優れた製品を開発し続けて、超優良企業になっていますが、機器の製造は全て製造委託しています。換言すると、工場を持たない会社なのです。シュレッダーの明光商会も、製造委託の会社でした。シュレッダーの技術革新は直ぐに飽和したので、明光商会の創業者・故高木禮二氏の採用した営業戦略は、『製造を委託する会社を3社程に限定して、技術と製造は委託会社に任せ/競争させ→安価に作らせて、明光商会は新規参入会社を叩いて国内市場を独占し、価格低下を招かない体制にする』ことでした。数社からシュレッダーが販売されましたが、殆どはOEM(相手先ブランド名製造)で、明光商会が協力会社に作らせた物でした。 キーエンス社は、斬新なアイデアが少なくなった時の事も、そろそろ考えるべきだと思います。
【制御設計を四直三交代へ】
ある田舎のメーカーに受け取り検査に出張しました。 試運転で少し問題が発生したので、徹夜する事になってしまったのですが、夜中の12時過ぎに外に出てタバコを吸っていたら、二十歳代の女性が目の前を通り過ぎたのです。
この会社では、現地据付や納入品の点検/修理に、男性の機械組立工と男性の制御設計者をペアーで派遣していました。 現地での作業は、顧客が働かない夜間や休日に行う事が多く、制御プログラムの修正を机/椅子の無い現場で、床に座って行うケースが多かった様です。
インターネットが普及して、結構大容量の制御プログラムもメールに添付して送れる様になりました。 制御設計担当者を24時間、最低一人は会社にいる様にして、現地には機械組立工を一人派遣する体制にしてみたのだそうです。 プログラマーが良好な環境で、落ち着いて仕事が出来るので、ミスが減る等、効果大だったそうです。
それで、制御設計部隊を四直三交代にして、女性も平等に扱うことにしたのです。 予想に反して、女性達は夜勤に抵抗せず、寧ろ男女平等にしたことを歓迎したそうです。
近年、「女性の活躍出来る社会へ!」とか、「働き方改革」が叫ばれていますが、成功した例は沢山有ります。 与野党の政治家や会社の経営者は、女性が男性と同様に働いたら、国家にも会社にも大きなメリットが有る事を認識して、足を使って勉強し、工夫する事が肝要です。 全てのケースに適応出来る妙案は有りません。 それぞれのケースで工夫する必要が有ります。
【工場の中央にNCプログラマー室を設けた例】
軽合金の素材も手掛けている某大手企業の重役が、「素材で売るのでは無く、部品に加工して、付加価値を付けて売る」事にしました。 第一段階として機械加工を委託する協力会社を育てる事にした様です。 小さな町工場を経営していた、従順で真面目なだけが取り得の社長に大金を融資して新工場を建設させ、工作機械等の設備は破格の条件で貸与しました。 然し、全ての営業権は大手企業が握りました。
一見良さそうな戦略ですが、私は「この会社は長続き出来ない」と思いました。予想の通り現在は存在していません。 大手企業の営業マンは会議が多く、報告書の作成などで多忙で、販売活動に割ける時間は少ししか有りません。 彼らの給与は高く、もろもろの経費が沢山発生するのです。 (経費の例 :兆円単位の売り上げの有る企業では経理処理用のプログラムが必要です、一件受注すると経理処理の為の番号を取って、大形コンピューターに登録(インプット)します。この時点で一万円以上の経費が発生します。)
私が打合せの為に出張した頃は、工場建屋は真新しく、工作機械は全てNCで、購入して数年しか経っていませんでした。当時は受注量も多く、四直三交代でフル稼働に近い状態でした。 殆どの社員が二十歳代で、生き生きと仕事をしていました。毎日、掃除をする様で、東京ディズニーランドの様にゴミは落ちていませんでした。
私が一番感心したのは、工場のほぼ真ん中に十畳ほどのガラス張りのNCプログラマー室を設けていた事です。 若い女性が三人ほど働いていました。 プログラムに問題が発生すると、彼女達がその機械まで行って、状況を確認して直ぐに修正していました。
(余談 :自惚れ!) 「いずれ大手企業は手を引くと思われるが、私に会社を任せてもらえたら十分維持/発展させられる会社だ」と思いました。
【私の精密機械加工の大先生】
1984年頃に、私は超精密機械加工が必要な機械を開発していました。 八方手を尽くして業者を探していたのですが、 なんと! 私の家から歩いて行ける所に、日本有数の素晴らしい会社が有ったのです。
戦後、東京工業大学の機械工学科を卒業された、五十歳代の方が三代目の社長になっておられました。社長の超精密機械加工への情熱には敬服しました。 最初に訪問した時、社長の机の上に、ほぼ完成した機械式ジャイロスコープを置いていました。 ジッと見てたら動かしてくれました。私の目では正常に動く様に見えましたが、少し修正加工が必要だと社長は言われました。 (機械式ジャイロスコープには高度な加工技術が必要です。)
現在では、カメラは全てオートフォーカス(自動焦点)ですが、1984年当時はまだ普及していませんでした。ミノルタがオートフォーカス・カメラの名機『アルファ(α)-7000』を開発中で、主要部品の試作を、この会社(M社)に依頼していました。ミノルタは1985年にα-7000を発売し、私は直ぐに買いました。社長(M社長)に、「何故、量産に参加しなかったのですか?」と聞くと、「ミノルタの生産計画に対応する為には、新工場の建設が必要だが、私の後継者がこれ以上大きな会社を経営出来ると思えないので辞退した」と言われました。
M社長から最初に紹介して頂いたのは、機械検査技能士の特級か1級の資格を持った検査員(N氏)でした。 N氏の横で、「N君が合格だと言ったら、間違いは有りません」と大きな声で言われました。私が製作依頼する時、どの寸法をチェックするか決めておくと、N氏が測定した数値を記入した検査成績書を添付して納入してくれました。 一年程してM社は、まだ高価だった三次元測定機を購入し、N氏が操作していました。
M社は、スイスやドイツ製の超高価な精密工作機械を十台ほど所有していて、それらを『マザーマシン』と呼んでいました。 社長が全幅の信頼を寄せている社員に一台ずつ与えていました。 彼らは超硬(タングステン・カーバイド)のバイト(切削の刃物)を自分で製作して、それぞれが、鍵付きの収納ケースに保管し、社長でも勝手にバイトを見てはいけないルールになっていました。
私の依頼した部品の加工の一部に、『マザーマシン』が必要な個所が有りました。それぞれのマザーマシには月単位の工程表が作成されていて、月の始めには、その月の工程表には”空き日”が無い状態でした。 M社は、マザーマシを担当しているベテラン社員には、余程の事が無い限り残業を強いない事を社訓の様にしていました。 (タイムカードを見なくても、各工作機械の工程表で社員の会社への貢献度がチェック出来ると、私は思いました。)
当時、私は精密機械の知識が乏しかったのですが、M社長が何回も何回も、私を機械の前に連れて行って説明してくれました。 日本製の工作機械も多数所有していたので、同じ機能の輸入機械と国産機械の違いなども詳しく教えて頂きました。 (M社長の知識と経験の深さには、敬服しました。)
(余談) 私はコーヒーが大好きなんで、コーヒーカップの収集も初めていました。 M社長は、美味しいコーヒーを出してくれる様になり、ヨーロッパ製の飾り棚を買って高価なカップも買われました。 M社は私の家から近かったので、M社が土曜日出勤の時は、時々電話が掛かってきて、散歩がてらコーヒーを頂きに行きました。私の土産は、超電導や原動機などの技術の話しでした。 精密加工には幾何学の計算が必要なんですが、定年後には幾何学の顧問になる約束でしたが、残念ながら私がリタイアする前に亡くなられてしまいました!
【富士フイルムの尊敬すべき技術者】
(余談 ①) 大正時代に大日本セルロイドと言うセルロイドの会社が出来ました。 セルロイド以外にも事業を展開して、戦後、社名を「ダイセル」に変更しました。(日本とロイドを省略し、大を”ダイ”にした分けです。) 昭和初期に写真フィルム部門を独立させて『富士フイルム』を設立しました。 富士フイルムがアメリカのゼロックス社と合弁企業を設立したのが『富士ゼロックス』です。
ダイセルは私達の身近な製品をほとんど製造していませんが、自動車のエアーバックに入っているインフレーター(火薬を燃焼させてガスを発生させる装置)では日本一で、日本たばこ社が製造するタバコのフィルターは全てダイセルが作っています。
富士フイルムは、生みの親のダイセルの血を引いているのか?斜陽の本業(写真フィルム)からの事業転換が見事でした。 (現在では、写真用のフィルムの貢献度は数%まで低下しています。)
(余談 ②) 写真のフィルムは結構厚いですが、薄いフィルムを何枚か積層している様です。 富士フイルムは薄いフィルムを製造する技術があり、その技術を応用してPCやTVの液晶ディスプレイの表面に貼る偏光層保護フィルムに進出し、現在この分野では世界一になっています。
当時、私は均熱ロールを手掛けていました。富士フイルムは他社製の均熱ロールを多数所有されていて、その修理と難しい改造の仕事を沢山頂きました。難しい仕事の大半は、F氏から頂きました。 F氏は表面に硬質クロムメッキを施したロールをピカピカに磨き上げる技術開発に情熱を注がれていました。 私がお付き合いを始めた時は、既に世界最高と言っても過言でないノウハウを確立されていました。 (均熱ロールの詳細はhttp://www.hidec-kyoto.jp/heat_roll/shr.htmlを参照願います。)
F氏から修理するロールが着くと、→私の会社で分解して、ロールに仕込まれたヒートパイプを殺します、→ロールだけメッキ会社に送り、メッキ補修して、→研磨会社に送り、→私の会社に帰って来ました。 ヒートパイプを生かして、ロールを組立、ロール表面に傷が無いか目の良い社員が目視検査をしました。 F氏が許容していた表面粗さは、市販されていた面粗度計の精度を超えていたので、目視検査しか出来なかったのです。
F氏の技術のポイントは二つ有って、①クロムメッキのレシピを業者と決めていた事(F氏から、「今回は〇×番のレシピで」と指示が有り、私は、その番号を書いたタグ(札)を付けてメッキ業者に送りました。 ②研磨職人を育てた事(G社に二人、H社に一人、合計三人はF氏が認定した職人でした。 更に、別の社で一人を育てていました。) 卓越した職人には、誰でも成れるわけでは有りません。 日本を代表する様な職人に育てる為には、F氏がやった様に沢山の職人に会って、人物を見極めて、じっくりと時間を掛けて支援し続ける必要が有ります。
F氏が地道に仕事を続けられたのは、富士フイルムの技術を大切にする社風によると、私は思いました。F氏の作ったロールを使用しているラインは極秘扱いでしたので、見るチャンスは有りませんでしたが、富士フイルムにとって重要な製品を製造しているのだと思いました。
(余談 :F氏) 私がお付き合いしていた時は、F氏は定年まじかでしたが、最後まで情熱は尽きませんでした。 ハンサムでスラットされていて、趣味の良い服と高価そうなブーツを履いておられたのですが、何故か独身でした。 趣味はスキューバダイビングで、インドネシアのある村に、毎年、一二回出掛けられていました。
【先端技術を追求した会社】
ガラ携→スマホへと急激に技術が進歩しました。それらに欠かせない部品を開発/製造していた会社の話しです。 その会社から製造ラインに組み込む高価な部品を、年に二三回発注して頂きました。毎回、新しい工夫を要求するので、私は、その都度打合せに行きました。対応してくれる方は、何時も同じ課長さんだったので、お互いに何でも話せる関係になりました。彼は、給与の話もしました。私の2倍以上の高給でした。
工場は立ち入り禁止で、現場社員の様子は分かりませんでしたが、スタッフ達は生き生きと働いている様に見受けられました。 然し、私は「この会社は長続きしない」と思いました。
私の”持論”では、『ある技術が急激に進歩する時期がありますが、→停滞する様になり、→飽和状態が続き、・・・→周辺技術が進んで、→その技術がまた進歩し始めます。』 会社が永続する為には、開発は重要ですが、安く製造する努力はもっと重要なのです。 特に・この会社が手掛けていた巨大なマーケットが有る場合はそうです。 中国の企業が、この会社の製品を真似て、安価な製品を売り始めました。この会社は、更に難しい製品を開発して上市するのですが、暫くすると、ほぼ同機能の製品を中国企業が安価に売り始めるのです。・・・→現在、この会社は存在していません。
(学生諸君へのアドバイス) ベンチャー企業への就職を考えられている方は、「将来、市場が拡大すると予想される分野の企業では、競合企業に対抗する事を加味した経営をしているか?」と言う視点でも、企業を選択すべきです。
(私の心配) キーエンス社は1974年の創業以来、難しい/優れた製品を開発し続けて、超優良企業になっていますが、機器の製造は全て製造委託しています。換言すると、工場を持たない会社なのです。シュレッダーの明光商会も、製造委託の会社でした。シュレッダーの技術革新は直ぐに飽和したので、明光商会の創業者・故高木禮二氏の採用した営業戦略は、『製造を委託する会社を3社程に限定して、技術と製造は委託会社に任せ/競争させ→安価に作らせて、明光商会は新規参入会社を叩いて国内市場を独占し、価格低下を招かない体制にする』ことでした。数社からシュレッダーが販売されましたが、殆どはOEM(相手先ブランド名製造)で、明光商会が協力会社に作らせた物でした。 キーエンス社は、斬新なアイデアが少なくなった時の事も、そろそろ考えるべきだと思います。
【制御設計を四直三交代へ】
ある田舎のメーカーに受け取り検査に出張しました。 試運転で少し問題が発生したので、徹夜する事になってしまったのですが、夜中の12時過ぎに外に出てタバコを吸っていたら、二十歳代の女性が目の前を通り過ぎたのです。
この会社では、現地据付や納入品の点検/修理に、男性の機械組立工と男性の制御設計者をペアーで派遣していました。 現地での作業は、顧客が働かない夜間や休日に行う事が多く、制御プログラムの修正を机/椅子の無い現場で、床に座って行うケースが多かった様です。
インターネットが普及して、結構大容量の制御プログラムもメールに添付して送れる様になりました。 制御設計担当者を24時間、最低一人は会社にいる様にして、現地には機械組立工を一人派遣する体制にしてみたのだそうです。 プログラマーが良好な環境で、落ち着いて仕事が出来るので、ミスが減る等、効果大だったそうです。
それで、制御設計部隊を四直三交代にして、女性も平等に扱うことにしたのです。 予想に反して、女性達は夜勤に抵抗せず、寧ろ男女平等にしたことを歓迎したそうです。
近年、「女性の活躍出来る社会へ!」とか、「働き方改革」が叫ばれていますが、成功した例は沢山有ります。 与野党の政治家や会社の経営者は、女性が男性と同様に働いたら、国家にも会社にも大きなメリットが有る事を認識して、足を使って勉強し、工夫する事が肝要です。 全てのケースに適応出来る妙案は有りません。 それぞれのケースで工夫する必要が有ります。
【工場の中央にNCプログラマー室を設けた例】
軽合金の素材も手掛けている某大手企業の重役が、「素材で売るのでは無く、部品に加工して、付加価値を付けて売る」事にしました。 第一段階として機械加工を委託する協力会社を育てる事にした様です。 小さな町工場を経営していた、従順で真面目なだけが取り得の社長に大金を融資して新工場を建設させ、工作機械等の設備は破格の条件で貸与しました。 然し、全ての営業権は大手企業が握りました。
一見良さそうな戦略ですが、私は「この会社は長続き出来ない」と思いました。予想の通り現在は存在していません。 大手企業の営業マンは会議が多く、報告書の作成などで多忙で、販売活動に割ける時間は少ししか有りません。 彼らの給与は高く、もろもろの経費が沢山発生するのです。 (経費の例 :兆円単位の売り上げの有る企業では経理処理用のプログラムが必要です、一件受注すると経理処理の為の番号を取って、大形コンピューターに登録(インプット)します。この時点で一万円以上の経費が発生します。)
私が打合せの為に出張した頃は、工場建屋は真新しく、工作機械は全てNCで、購入して数年しか経っていませんでした。当時は受注量も多く、四直三交代でフル稼働に近い状態でした。 殆どの社員が二十歳代で、生き生きと仕事をしていました。毎日、掃除をする様で、東京ディズニーランドの様にゴミは落ちていませんでした。
私が一番感心したのは、工場のほぼ真ん中に十畳ほどのガラス張りのNCプログラマー室を設けていた事です。 若い女性が三人ほど働いていました。 プログラムに問題が発生すると、彼女達がその機械まで行って、状況を確認して直ぐに修正していました。
(余談 :自惚れ!) 「いずれ大手企業は手を引くと思われるが、私に会社を任せてもらえたら十分維持/発展させられる会社だ」と思いました。
【私の精密機械加工の大先生】
1984年頃に、私は超精密機械加工が必要な機械を開発していました。 八方手を尽くして業者を探していたのですが、 なんと! 私の家から歩いて行ける所に、日本有数の素晴らしい会社が有ったのです。
戦後、東京工業大学の機械工学科を卒業された、五十歳代の方が三代目の社長になっておられました。社長の超精密機械加工への情熱には敬服しました。 最初に訪問した時、社長の机の上に、ほぼ完成した機械式ジャイロスコープを置いていました。 ジッと見てたら動かしてくれました。私の目では正常に動く様に見えましたが、少し修正加工が必要だと社長は言われました。 (機械式ジャイロスコープには高度な加工技術が必要です。)
現在では、カメラは全てオートフォーカス(自動焦点)ですが、1984年当時はまだ普及していませんでした。ミノルタがオートフォーカス・カメラの名機『アルファ(α)-7000』を開発中で、主要部品の試作を、この会社(M社)に依頼していました。ミノルタは1985年にα-7000を発売し、私は直ぐに買いました。社長(M社長)に、「何故、量産に参加しなかったのですか?」と聞くと、「ミノルタの生産計画に対応する為には、新工場の建設が必要だが、私の後継者がこれ以上大きな会社を経営出来ると思えないので辞退した」と言われました。
M社長から最初に紹介して頂いたのは、機械検査技能士の特級か1級の資格を持った検査員(N氏)でした。 N氏の横で、「N君が合格だと言ったら、間違いは有りません」と大きな声で言われました。私が製作依頼する時、どの寸法をチェックするか決めておくと、N氏が測定した数値を記入した検査成績書を添付して納入してくれました。 一年程してM社は、まだ高価だった三次元測定機を購入し、N氏が操作していました。
M社は、スイスやドイツ製の超高価な精密工作機械を十台ほど所有していて、それらを『マザーマシン』と呼んでいました。 社長が全幅の信頼を寄せている社員に一台ずつ与えていました。 彼らは超硬(タングステン・カーバイド)のバイト(切削の刃物)を自分で製作して、それぞれが、鍵付きの収納ケースに保管し、社長でも勝手にバイトを見てはいけないルールになっていました。
私の依頼した部品の加工の一部に、『マザーマシン』が必要な個所が有りました。それぞれのマザーマシには月単位の工程表が作成されていて、月の始めには、その月の工程表には”空き日”が無い状態でした。 M社は、マザーマシを担当しているベテラン社員には、余程の事が無い限り残業を強いない事を社訓の様にしていました。 (タイムカードを見なくても、各工作機械の工程表で社員の会社への貢献度がチェック出来ると、私は思いました。)
当時、私は精密機械の知識が乏しかったのですが、M社長が何回も何回も、私を機械の前に連れて行って説明してくれました。 日本製の工作機械も多数所有していたので、同じ機能の輸入機械と国産機械の違いなども詳しく教えて頂きました。 (M社長の知識と経験の深さには、敬服しました。)
(余談) 私はコーヒーが大好きなんで、コーヒーカップの収集も初めていました。 M社長は、美味しいコーヒーを出してくれる様になり、ヨーロッパ製の飾り棚を買って高価なカップも買われました。 M社は私の家から近かったので、M社が土曜日出勤の時は、時々電話が掛かってきて、散歩がてらコーヒーを頂きに行きました。私の土産は、超電導や原動機などの技術の話しでした。 精密加工には幾何学の計算が必要なんですが、定年後には幾何学の顧問になる約束でしたが、残念ながら私がリタイアする前に亡くなられてしまいました!
【富士フイルムの尊敬すべき技術者】
(余談 ①) 大正時代に大日本セルロイドと言うセルロイドの会社が出来ました。 セルロイド以外にも事業を展開して、戦後、社名を「ダイセル」に変更しました。(日本とロイドを省略し、大を”ダイ”にした分けです。) 昭和初期に写真フィルム部門を独立させて『富士フイルム』を設立しました。 富士フイルムがアメリカのゼロックス社と合弁企業を設立したのが『富士ゼロックス』です。
ダイセルは私達の身近な製品をほとんど製造していませんが、自動車のエアーバックに入っているインフレーター(火薬を燃焼させてガスを発生させる装置)では日本一で、日本たばこ社が製造するタバコのフィルターは全てダイセルが作っています。
富士フイルムは、生みの親のダイセルの血を引いているのか?斜陽の本業(写真フィルム)からの事業転換が見事でした。 (現在では、写真用のフィルムの貢献度は数%まで低下しています。)
(余談 ②) 写真のフィルムは結構厚いですが、薄いフィルムを何枚か積層している様です。 富士フイルムは薄いフィルムを製造する技術があり、その技術を応用してPCやTVの液晶ディスプレイの表面に貼る偏光層保護フィルムに進出し、現在この分野では世界一になっています。
当時、私は均熱ロールを手掛けていました。富士フイルムは他社製の均熱ロールを多数所有されていて、その修理と難しい改造の仕事を沢山頂きました。難しい仕事の大半は、F氏から頂きました。 F氏は表面に硬質クロムメッキを施したロールをピカピカに磨き上げる技術開発に情熱を注がれていました。 私がお付き合いを始めた時は、既に世界最高と言っても過言でないノウハウを確立されていました。 (均熱ロールの詳細はhttp://www.hidec-kyoto.jp/heat_roll/shr.htmlを参照願います。)
F氏から修理するロールが着くと、→私の会社で分解して、ロールに仕込まれたヒートパイプを殺します、→ロールだけメッキ会社に送り、メッキ補修して、→研磨会社に送り、→私の会社に帰って来ました。 ヒートパイプを生かして、ロールを組立、ロール表面に傷が無いか目の良い社員が目視検査をしました。 F氏が許容していた表面粗さは、市販されていた面粗度計の精度を超えていたので、目視検査しか出来なかったのです。
F氏の技術のポイントは二つ有って、①クロムメッキのレシピを業者と決めていた事(F氏から、「今回は〇×番のレシピで」と指示が有り、私は、その番号を書いたタグ(札)を付けてメッキ業者に送りました。 ②研磨職人を育てた事(G社に二人、H社に一人、合計三人はF氏が認定した職人でした。 更に、別の社で一人を育てていました。) 卓越した職人には、誰でも成れるわけでは有りません。 日本を代表する様な職人に育てる為には、F氏がやった様に沢山の職人に会って、人物を見極めて、じっくりと時間を掛けて支援し続ける必要が有ります。
F氏が地道に仕事を続けられたのは、富士フイルムの技術を大切にする社風によると、私は思いました。F氏の作ったロールを使用しているラインは極秘扱いでしたので、見るチャンスは有りませんでしたが、富士フイルムにとって重要な製品を製造しているのだと思いました。
(余談 :F氏) 私がお付き合いしていた時は、F氏は定年まじかでしたが、最後まで情熱は尽きませんでした。 ハンサムでスラットされていて、趣味の良い服と高価そうなブーツを履いておられたのですが、何故か独身でした。 趣味はスキューバダイビングで、インドネシアのある村に、毎年、一二回出掛けられていました。