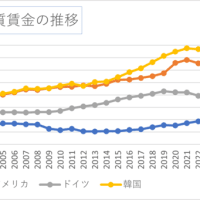今回も、チョットした事で、社員が楽しく/生き生きと仕事が出来ると言う例を書きます。 政治家や大きな組織の力を借りなければ出来ない、会社の改革については、もう少し考えを纏めてて、後日、公表したいと考えています。
【放任社長の例 :1】
私の小学校以来の友達(S君)の話しです。 S君は幼い頃から、かなりいい加減な性格です。 高校卒業後、色々有りましたが、1980年頃に地方都市で奥さんと二人で、フェンス工事や花壇作りを主とした工務店を始め、 そして直ぐに、人を雇える様になりました。 最初の頃に雇った方が、非常に優秀で会社は安定した経営になり、少しずつ成長し始めました。 (会社名に創業者の氏名を入れたがりますが、S君はカタカナの近代的な名称にしたのも良かったと思います。)
S君は高校時代に将棋が強くなり、会社が少し順調になって来ると、徹夜で将棋を楽しみ、会社には余り出勤しなくなりました。 奥さんと、社員で会社を運営していると言っても過言では無い様に見えました。 S君の出した素晴らしい提案は、「会社の経営をガラス張りにし、利益を三等分して、①会社の内部留保と設備投資、②S君の取り分、③社員への第3番目のボーナス(特別ボーナス)にする」ことでした。
特別ボーナスは、社員一人一人の業績を加味して決めました。かなりの差をもうけた様ですが、誰が幾ら貰ったか分かる様にしたのです。 日本には種々の資格試験が有りますが、受験費用を会社負担にしたので、沢山資格保有者が出来、会社の業績は益々上がりました。→→2019年現在、社員数は60名ほどになっています。
(余談) S君は年老いたので、数年前から会社を息子に譲る事を考え始めました。 今年・電話で、「僕は会社の為に何もしてこなかった。死ぬまでに役に立ちたいので、新しい事業を2年前から始めた」と言うのです。 私は、「①優秀な社員を自由に働かせた。②(前述の)素晴らしい提案をした。両方とも普通の人では出来ない事だったから、十分会社に貢献した」と言いましたが、新しい事業は続けると言い張ります。私は、「多分失敗する」と心配しています。
【放任社長の例 :2】
家庭電気製品も作っている大手重電気会社(M社)の、小さな協力会社の話しです。パートの女性が10名弱いました。 彼女達がこの会社を支えていると言っても過言では無い状態でした。 社長は高齢で口煩い人でしたが、彼女達が担当している仕事には興味が無く、任せ切りでした。
M社の数工場から、小さな種々雑多な部品が定期的に多量に注文されていましたが、各部品の担当の女性が受け付けて、必要な材料を手配し→プレス会社に発送し→彼女が簡単な加工をし→メッキ工場に発送し→彼女が検査して納品するのです。素材の在庫管理、外注費用の管理、納期管理を全て彼女達がやりました。納期が間に合いそうに無い時は、その部品の担当の女性が夜中の12時頃まで自主的に残業していました。
昼食の時間や、仕事が終わってからは楽しそうに雑談していましたが、女性社員が勤務時間中に無駄話をしているのを見た事が有りませんでした。会社から出る生ゴミなどは、町内のゴミ置き場に出していましたが、女性達が早く出勤してゴミ置き場周辺の草引きをしたり、仕事が終わった後にゴミ置き場の掃除をするのです。工場内の掃除や草引きは、夕方、タイムカードを押した後に皆で自主的にしていました。
最低賃金より10%~20%高く、残業代もキチット支払っていましたので、パート社員の定着率は非常に高かったです。
(余談 ①) 裕福な家庭の奥さんが何人かいました。その一人に、60歳後半の寡黙な方(Bさん)がおられ、皆に一目置かれていました。 この会社では、時々大きな機械を製造するのですが、そんな時はパートの女性達も参加していました。 部長と課長の指示で作業が始まるのですが、組立時に問題が発生すると、Bさんがテキパキと指示を出すのです。
(余談 ②) 積層絶縁板をCD(コンパクトディスク)状に加工して欲しかったのですが、正社員に頼んだら商品として出せる物は出来ませんでした。 別の仕事を担当していたパートの女性が、「社長に内緒にしてくれるのなら、私がやります」と言ってくれ、慣れた手つきで機械を操作して、申し分ない物を作ってくれました。 彼女は、機械加工の小さな会社の奥さんだったのです。
【民家の様な建物】
これは、私が長くお付き合いして頂いた機械系の設計事務所の話しです。 田園地帯の一角に沢山・木を植えて、その中に大きな民家の様な二階建ての建物を建てて事務所にしていました。内装も少し金の掛かった民家風でした。社長に、「民家を買って事務所にしたのか?」と聞くと、「社員は一日、部屋の中で図面を描くので、明るくて落ち着く雰囲気にしたかったので、家内と相談して設計した」と言われました。
この会社は、まだ高価だったキャド(CAD)をいち早く導入しました。当時は、IBMのキャダム(CADAM)が主流で、一式1,000万円ほどしたと思います。 その後、パソコン(PC)で動かせる廉価版のCADの時代になりました。 この会社は、大手企業数社と取引していたのですが、各社が導入したCADが違うので、数種類のCADで仕事をしていました。 (私は、数社に出向したので、3種類のCADで仕事をしました。)
(余談) 残念ながら、社長が二代目に代わられて、事務所は建て替えられ殺風景な外観になっています。その周辺の田圃は工場と住宅になっています。昔の様に社員が生き生きと働いている様には思えません!
【溶接と農業】
この話も、田園地帯に有った会社の話しです。 私が出向していた会社に、納品の途中に雑談をしに来る、小さな溶接の会社の社長がいました。 私は溶接で苦労した時が有ったので、仕上がった物を見たら溶接工の腕の良し悪しがだいたい分かりました。 何時も、社長がトラックに積んだ品物を見せてくれたのですが、非常に複雑な形状で、肉厚の違った部材を見事に溶接していました。
社長は大手の重機械メーカで溶接技術を磨いて、お弟さんと二人で独立した様です。 大形のプリンターを購入し、顧客からのメールに添付された図面を即アウトプットして、見積書をメールで返し、金額が了承されたら製作する分けです。納品は、自前のトラックで社長がしていました。 A1(新聞を広げたサイズ)の印刷が出来るプリンターでした。
私が雑談していた頃は、三人雇って五人の会社になっていました。 五人に共通するのは、広い田圃を相続した米農家だった事です。 農繁期の時は会社は休みにして農作業する分けですが、大形の機械を使用するると、春の田植え、秋の収穫もそれぞれ一週間程で終わってしまいます。 米作と会社は、殆ど問題無く兼業出来る様でした。 米農家の多いい地域では、参考になると思います。
【農業機械のメーカー】
農業機械メーカーを数社訪問しました。その中で、最も旨く経営していた会社を紹介します。 農業機械にも色々有りますが、比較的小形の機械を得意としていた会社(T社)の話しです。 一般には余り知られていませんが、中堅の農業機械メーカーは東北地方に結構沢山有ります。
各社で、ほぼ共通していたのは、(価格競争が激しいので、)残業無し(定時操業)の運営をしていた事です。 T社には、設計/経理/営業などの社員にサービス残業(ただ働き)をさせる習慣は全く有りませんでした。「残業したら割増賃金を支払う必要が有るので、熾烈な価格競争に勝てない」と言っていました。 T社の製品が、T1、T2、・・・TNまで有ったとします。今日、T3を40台組み立てる計画です。前日までに40台分の部品を全て揃えて置き、数量だけで無く、欠陥の無い事を確認していました。今日、組立現場に必要な作業者の人数を正確に出しておきます。現場社員では不足する場合は、設計を含めた事務所の社員を動員していました。
私は設計担当者と打合せしましたが、「月単位で生産計画が立てられるので、自分が組み立てに参加する日を加味して、設計の日程計画を立てるので支障は無い」と言っていました。「たまに現場で身体を使った仕事をする方が、楽しい」とも言っていました。 私は、「自分が設計した機械を組立たら、こんなに設計変更したら、もっと組み立て安くなると言ったアイディアが湧く」とも思いました。
多くの農業機械は赤一色の塗装をしていますが、機械を大きく見せる為だそうです。 中堅の農業機械メーカーでも、本格的な自動塗装装置を所有しています。 エンドレスのハンガー付きワイヤーが組立工場内を走る様になっていました。 組立の順番に部品をハンガーにぶら下げると、自動塗装装置の中で塗装/乾燥した部品が組立ラインに運ばれます。その日の製造計画で、ワイヤーの走る速度が決められていました。
完成した機械は、とんでもなく大きな倉庫に保管され、注文を受けた後に全国に出荷していました。洋服には夏服、冬服、合服が有りますが、農業機械も季節によって売れる機械が違います。倉庫にも限界が有りますから、T社では年間を通して工場が稼働する様に工夫していました。 例えば、私が最初に訪問した時、数年前にまでは秋に売れる機械が少なかったので、社員達で知恵を絞って秋売れる機械を開発したのです。非常に単純な機械でしたが、確かに農家の作業を効率化出来ると思いました。ヒット商品になっていました。
T社では、殆どの部品を協力会社に依頼していましたが、溶接の必要な部品は自社で作っていました。南向きの窓側にブースを幾つか設けて、溶接の光が組立工の目に入らない工夫をしていました。 溶接場所は3K(きつい、危険、きたない)が一般的ですが、結構清潔で明るかったです。
【傲慢な社長】
これは典型的な反面教師の例です。 昔は、○○重工と言う会社には超大型の工作機械が沢山有りました、私の会社にも有りました。 関西では1985年頃までに超大型の工作機械は殆ど廃棄されて、重工会社はK鉄工所に依頼する様になっていました。 私の勤めていた会社もK鉄工所で加工して貰っていましたが、「経営状態が悪化して来たので、工場サーベイ(調査)をして欲しい」と資材部署から何回も言われていたのですが、断っていました。 (私は、超大型の工作機械についての知識と経験が全く無かったのです。)
ある日、別の加工会社に出張しようとしていたら、H部長が、「僕も出掛ける所だから、車で送る」と言うのです。 暫くドライブして、「途中寄る所がある」と言い出し、着いた所がK鉄工所でした。 私と、ほぼ同年代の社長と名刺交換をしたのですが、開口一番「僕は、東京大学の機械工学科の出身だ!」と言い出したので、面喰ってしまいました。 社長は、「東大卒業後、大手企業に就職していたのだが、2年程前に先代の社長が急死したので、仕方なしに社長になった」と初対面の私に言うのです。
一応工場見学はしました。 古い超大型機ですから、数値制御(NC)機能付きの工作機械は1台も見当たりませんでした。 「職人さんの腕が頼りですが、この社長では職人は辞めてしまうから、多分数年以内に倒産すると思います」とH部長に言いました。 本当に私の予想通りになりました。 こんな社長に代わったら、社員は出来るだけ早く転職するのが、最良です。
【東京近辺と職人さん】
2005年頃の話です。大手製紙会社から、全ての製紙ラインに組み込まれている、一見単純そうな装置のメーカーを調査して欲しいとの依頼が有りました。 その数年前から、その装置を製造していたメーカーが、次々と撤退してしまったのです。私が知っていたほぼ全ての製紙関係の方に電話したら、「昔、関東の小さな会社(Z社)で作った」と言う方がいました。電話したら、「転業した」と断られたのですが、強引に説得に行きました。
古かったですが広い工場で、老人達が数名働いていました。社長だけが40歳代で、「職人さん達が働ける内は、無理してでも、会社を維持したい」と言われました。「貴社、一社しか作れないのだから、若い人を雇うべきでは」と言うと、「会社を継いだ後、何回も求人を出したが、一週間以上勤めた人がいない。もう諦めた!」と言われました。 東京に電車で一時間程で行ける所では、職人の求人は無理なんです。
社長が職人の頭(かしら)を呼んで、私が持ち込んだ案件を受けるか?相談してくれ、了解を得ました。但し、大幅な計画変更が必要だと指摘されました。 彼らの指摘を加味した、シミュレーションプログラムを作ってみたら、顧客の計画では駄目な事が分かりました。 顧客に報告に行くと、「君の会社経由で発注する。改造が必要になったら費用は出すから、当社の案で作れ」と言われました。
納入前に、私は旨く行かなかった時の改造案を検討しました。 試運転すると、Z社の職人が予想した通りの結果になってしまいました。 顧客も改造案を考えられていて、事前に改造に必要な部品/資材を購入されていました。顧客案を試して見ましたが、駄目でした。 私の改造案は、金と時間が掛かりましたが、何とか旨く行きました。
(余談) 東京近辺には、Z社以外でも優れた技術を持った会社を知っていましたが、店仕舞いした所が多いいです。大阪には、今でも、若い人達が優れた職人さんと一緒に働く中小企業が沢山有ります。関西では東大阪市が特に有名です。 「国の発展には製造業が極めて重要だ!」と言うのが私の持論です。 若者達が中小の製造業で働きたくなる様に、官民挙げての取り組みが必要だと思います。
【放任社長の例 :1】
私の小学校以来の友達(S君)の話しです。 S君は幼い頃から、かなりいい加減な性格です。 高校卒業後、色々有りましたが、1980年頃に地方都市で奥さんと二人で、フェンス工事や花壇作りを主とした工務店を始め、 そして直ぐに、人を雇える様になりました。 最初の頃に雇った方が、非常に優秀で会社は安定した経営になり、少しずつ成長し始めました。 (会社名に創業者の氏名を入れたがりますが、S君はカタカナの近代的な名称にしたのも良かったと思います。)
S君は高校時代に将棋が強くなり、会社が少し順調になって来ると、徹夜で将棋を楽しみ、会社には余り出勤しなくなりました。 奥さんと、社員で会社を運営していると言っても過言では無い様に見えました。 S君の出した素晴らしい提案は、「会社の経営をガラス張りにし、利益を三等分して、①会社の内部留保と設備投資、②S君の取り分、③社員への第3番目のボーナス(特別ボーナス)にする」ことでした。
特別ボーナスは、社員一人一人の業績を加味して決めました。かなりの差をもうけた様ですが、誰が幾ら貰ったか分かる様にしたのです。 日本には種々の資格試験が有りますが、受験費用を会社負担にしたので、沢山資格保有者が出来、会社の業績は益々上がりました。→→2019年現在、社員数は60名ほどになっています。
(余談) S君は年老いたので、数年前から会社を息子に譲る事を考え始めました。 今年・電話で、「僕は会社の為に何もしてこなかった。死ぬまでに役に立ちたいので、新しい事業を2年前から始めた」と言うのです。 私は、「①優秀な社員を自由に働かせた。②(前述の)素晴らしい提案をした。両方とも普通の人では出来ない事だったから、十分会社に貢献した」と言いましたが、新しい事業は続けると言い張ります。私は、「多分失敗する」と心配しています。
【放任社長の例 :2】
家庭電気製品も作っている大手重電気会社(M社)の、小さな協力会社の話しです。パートの女性が10名弱いました。 彼女達がこの会社を支えていると言っても過言では無い状態でした。 社長は高齢で口煩い人でしたが、彼女達が担当している仕事には興味が無く、任せ切りでした。
M社の数工場から、小さな種々雑多な部品が定期的に多量に注文されていましたが、各部品の担当の女性が受け付けて、必要な材料を手配し→プレス会社に発送し→彼女が簡単な加工をし→メッキ工場に発送し→彼女が検査して納品するのです。素材の在庫管理、外注費用の管理、納期管理を全て彼女達がやりました。納期が間に合いそうに無い時は、その部品の担当の女性が夜中の12時頃まで自主的に残業していました。
昼食の時間や、仕事が終わってからは楽しそうに雑談していましたが、女性社員が勤務時間中に無駄話をしているのを見た事が有りませんでした。会社から出る生ゴミなどは、町内のゴミ置き場に出していましたが、女性達が早く出勤してゴミ置き場周辺の草引きをしたり、仕事が終わった後にゴミ置き場の掃除をするのです。工場内の掃除や草引きは、夕方、タイムカードを押した後に皆で自主的にしていました。
最低賃金より10%~20%高く、残業代もキチット支払っていましたので、パート社員の定着率は非常に高かったです。
(余談 ①) 裕福な家庭の奥さんが何人かいました。その一人に、60歳後半の寡黙な方(Bさん)がおられ、皆に一目置かれていました。 この会社では、時々大きな機械を製造するのですが、そんな時はパートの女性達も参加していました。 部長と課長の指示で作業が始まるのですが、組立時に問題が発生すると、Bさんがテキパキと指示を出すのです。
(余談 ②) 積層絶縁板をCD(コンパクトディスク)状に加工して欲しかったのですが、正社員に頼んだら商品として出せる物は出来ませんでした。 別の仕事を担当していたパートの女性が、「社長に内緒にしてくれるのなら、私がやります」と言ってくれ、慣れた手つきで機械を操作して、申し分ない物を作ってくれました。 彼女は、機械加工の小さな会社の奥さんだったのです。
【民家の様な建物】
これは、私が長くお付き合いして頂いた機械系の設計事務所の話しです。 田園地帯の一角に沢山・木を植えて、その中に大きな民家の様な二階建ての建物を建てて事務所にしていました。内装も少し金の掛かった民家風でした。社長に、「民家を買って事務所にしたのか?」と聞くと、「社員は一日、部屋の中で図面を描くので、明るくて落ち着く雰囲気にしたかったので、家内と相談して設計した」と言われました。
この会社は、まだ高価だったキャド(CAD)をいち早く導入しました。当時は、IBMのキャダム(CADAM)が主流で、一式1,000万円ほどしたと思います。 その後、パソコン(PC)で動かせる廉価版のCADの時代になりました。 この会社は、大手企業数社と取引していたのですが、各社が導入したCADが違うので、数種類のCADで仕事をしていました。 (私は、数社に出向したので、3種類のCADで仕事をしました。)
(余談) 残念ながら、社長が二代目に代わられて、事務所は建て替えられ殺風景な外観になっています。その周辺の田圃は工場と住宅になっています。昔の様に社員が生き生きと働いている様には思えません!
【溶接と農業】
この話も、田園地帯に有った会社の話しです。 私が出向していた会社に、納品の途中に雑談をしに来る、小さな溶接の会社の社長がいました。 私は溶接で苦労した時が有ったので、仕上がった物を見たら溶接工の腕の良し悪しがだいたい分かりました。 何時も、社長がトラックに積んだ品物を見せてくれたのですが、非常に複雑な形状で、肉厚の違った部材を見事に溶接していました。
社長は大手の重機械メーカで溶接技術を磨いて、お弟さんと二人で独立した様です。 大形のプリンターを購入し、顧客からのメールに添付された図面を即アウトプットして、見積書をメールで返し、金額が了承されたら製作する分けです。納品は、自前のトラックで社長がしていました。 A1(新聞を広げたサイズ)の印刷が出来るプリンターでした。
私が雑談していた頃は、三人雇って五人の会社になっていました。 五人に共通するのは、広い田圃を相続した米農家だった事です。 農繁期の時は会社は休みにして農作業する分けですが、大形の機械を使用するると、春の田植え、秋の収穫もそれぞれ一週間程で終わってしまいます。 米作と会社は、殆ど問題無く兼業出来る様でした。 米農家の多いい地域では、参考になると思います。
【農業機械のメーカー】
農業機械メーカーを数社訪問しました。その中で、最も旨く経営していた会社を紹介します。 農業機械にも色々有りますが、比較的小形の機械を得意としていた会社(T社)の話しです。 一般には余り知られていませんが、中堅の農業機械メーカーは東北地方に結構沢山有ります。
各社で、ほぼ共通していたのは、(価格競争が激しいので、)残業無し(定時操業)の運営をしていた事です。 T社には、設計/経理/営業などの社員にサービス残業(ただ働き)をさせる習慣は全く有りませんでした。「残業したら割増賃金を支払う必要が有るので、熾烈な価格競争に勝てない」と言っていました。 T社の製品が、T1、T2、・・・TNまで有ったとします。今日、T3を40台組み立てる計画です。前日までに40台分の部品を全て揃えて置き、数量だけで無く、欠陥の無い事を確認していました。今日、組立現場に必要な作業者の人数を正確に出しておきます。現場社員では不足する場合は、設計を含めた事務所の社員を動員していました。
私は設計担当者と打合せしましたが、「月単位で生産計画が立てられるので、自分が組み立てに参加する日を加味して、設計の日程計画を立てるので支障は無い」と言っていました。「たまに現場で身体を使った仕事をする方が、楽しい」とも言っていました。 私は、「自分が設計した機械を組立たら、こんなに設計変更したら、もっと組み立て安くなると言ったアイディアが湧く」とも思いました。
多くの農業機械は赤一色の塗装をしていますが、機械を大きく見せる為だそうです。 中堅の農業機械メーカーでも、本格的な自動塗装装置を所有しています。 エンドレスのハンガー付きワイヤーが組立工場内を走る様になっていました。 組立の順番に部品をハンガーにぶら下げると、自動塗装装置の中で塗装/乾燥した部品が組立ラインに運ばれます。その日の製造計画で、ワイヤーの走る速度が決められていました。
完成した機械は、とんでもなく大きな倉庫に保管され、注文を受けた後に全国に出荷していました。洋服には夏服、冬服、合服が有りますが、農業機械も季節によって売れる機械が違います。倉庫にも限界が有りますから、T社では年間を通して工場が稼働する様に工夫していました。 例えば、私が最初に訪問した時、数年前にまでは秋に売れる機械が少なかったので、社員達で知恵を絞って秋売れる機械を開発したのです。非常に単純な機械でしたが、確かに農家の作業を効率化出来ると思いました。ヒット商品になっていました。
T社では、殆どの部品を協力会社に依頼していましたが、溶接の必要な部品は自社で作っていました。南向きの窓側にブースを幾つか設けて、溶接の光が組立工の目に入らない工夫をしていました。 溶接場所は3K(きつい、危険、きたない)が一般的ですが、結構清潔で明るかったです。
【傲慢な社長】
これは典型的な反面教師の例です。 昔は、○○重工と言う会社には超大型の工作機械が沢山有りました、私の会社にも有りました。 関西では1985年頃までに超大型の工作機械は殆ど廃棄されて、重工会社はK鉄工所に依頼する様になっていました。 私の勤めていた会社もK鉄工所で加工して貰っていましたが、「経営状態が悪化して来たので、工場サーベイ(調査)をして欲しい」と資材部署から何回も言われていたのですが、断っていました。 (私は、超大型の工作機械についての知識と経験が全く無かったのです。)
ある日、別の加工会社に出張しようとしていたら、H部長が、「僕も出掛ける所だから、車で送る」と言うのです。 暫くドライブして、「途中寄る所がある」と言い出し、着いた所がK鉄工所でした。 私と、ほぼ同年代の社長と名刺交換をしたのですが、開口一番「僕は、東京大学の機械工学科の出身だ!」と言い出したので、面喰ってしまいました。 社長は、「東大卒業後、大手企業に就職していたのだが、2年程前に先代の社長が急死したので、仕方なしに社長になった」と初対面の私に言うのです。
一応工場見学はしました。 古い超大型機ですから、数値制御(NC)機能付きの工作機械は1台も見当たりませんでした。 「職人さんの腕が頼りですが、この社長では職人は辞めてしまうから、多分数年以内に倒産すると思います」とH部長に言いました。 本当に私の予想通りになりました。 こんな社長に代わったら、社員は出来るだけ早く転職するのが、最良です。
【東京近辺と職人さん】
2005年頃の話です。大手製紙会社から、全ての製紙ラインに組み込まれている、一見単純そうな装置のメーカーを調査して欲しいとの依頼が有りました。 その数年前から、その装置を製造していたメーカーが、次々と撤退してしまったのです。私が知っていたほぼ全ての製紙関係の方に電話したら、「昔、関東の小さな会社(Z社)で作った」と言う方がいました。電話したら、「転業した」と断られたのですが、強引に説得に行きました。
古かったですが広い工場で、老人達が数名働いていました。社長だけが40歳代で、「職人さん達が働ける内は、無理してでも、会社を維持したい」と言われました。「貴社、一社しか作れないのだから、若い人を雇うべきでは」と言うと、「会社を継いだ後、何回も求人を出したが、一週間以上勤めた人がいない。もう諦めた!」と言われました。 東京に電車で一時間程で行ける所では、職人の求人は無理なんです。
社長が職人の頭(かしら)を呼んで、私が持ち込んだ案件を受けるか?相談してくれ、了解を得ました。但し、大幅な計画変更が必要だと指摘されました。 彼らの指摘を加味した、シミュレーションプログラムを作ってみたら、顧客の計画では駄目な事が分かりました。 顧客に報告に行くと、「君の会社経由で発注する。改造が必要になったら費用は出すから、当社の案で作れ」と言われました。
納入前に、私は旨く行かなかった時の改造案を検討しました。 試運転すると、Z社の職人が予想した通りの結果になってしまいました。 顧客も改造案を考えられていて、事前に改造に必要な部品/資材を購入されていました。顧客案を試して見ましたが、駄目でした。 私の改造案は、金と時間が掛かりましたが、何とか旨く行きました。
(余談) 東京近辺には、Z社以外でも優れた技術を持った会社を知っていましたが、店仕舞いした所が多いいです。大阪には、今でも、若い人達が優れた職人さんと一緒に働く中小企業が沢山有ります。関西では東大阪市が特に有名です。 「国の発展には製造業が極めて重要だ!」と言うのが私の持論です。 若者達が中小の製造業で働きたくなる様に、官民挙げての取り組みが必要だと思います。