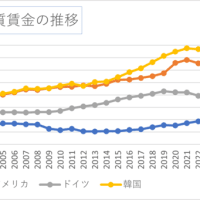【はじめに】
新型コロナが猛威を振るう様になって、「日本には今!、判断力/決断力/行動力/指導力の有る優秀な政治家が必要だ!」と思うようになりました。 民主主義国では議員を選挙で選びますが、「選挙は、優秀な人間を選別する篩の役割は出来ない」のだと気付きました。
民主主義がドンナニして発展してきたのか? 現在の民主主義では問題/課題が解決出来ない事が多々有るから、ドンナニ変えて行けば良いのか?・・・色々考える様になりました。
昔、読んだマックス・ヴェーバーの『職業としての政治』を、「民主主義の進歩と言う視点で読み返して見よう」と思い付きました。 ヴェーバーの与えてくれたヒントを基に、私の独断による「民主主義の進歩の歴史」を数回に分けて投稿します。次回は日本について書く予定です。
第1章 :ヴェーバーの『職業としての政治』を読み返して!
【職業としての政治】
ドイツ人で、政治学/経済学/社会学の分野で活躍したマックス・ヴェーバーをご存知ですか? ヴェーバーは、1864年に生まれ、亡くなったのは1920年です。 沢山の著作を残し、その多くが翻訳されて、今でも日本で読まれています。 私は、大学の教養部で細谷昂(ほそや たかし)先生のマックス・ヴェーバーに関する講義を受けました。
細谷先生の話は難解で、内容を殆ど覚えていませんが、先生が時々言及された『職業としての政治』の翻訳本が、1980年に岩波文庫として出版されたので、直ぐに買って読んでみました。 (今も出版していて、税込みで704円で、本文は120ページ程ですから、是非読んで見て下さい。)
第一次世界大戦(1914年~18年)でドイツは敗戦国になりましたが、終戦の2カ月後(1919年)にミュンヘンで学生相手に行った講演の内容を纏め、『職業としての政治』と言うタイトルで出版しました。
章(見出し)が無く、小説の様に書かれているので、一回読んだだけでは「分かった様で、分からない」本です。
【ヴェーバーが勉強出来た範囲は】
ヨーロッパ諸国の一部では中世に議会が誕生しました。初期の頃の議員は貴族や聖職者などで、無給でした。庶民が議員になると、有給制度になりました。ヴェーバーの言う『職業としての政治家(職業政治家)』の誕生です。 ヴェーバーは、政治家には『情熱』、『責任感』、『判断力』の三つの資質が必要であると言っています。
ヴェーバー後の100年で工業技術は目覚ましく進歩し、核兵器が誕生し『戦争抑止』と言う考え方が広がりました。一党独裁国家の中国が『世界の工場』と呼ばれるまでに発展し、近年は覇権主義政策をを露骨に進める様になっています。 現在の日本の政治家に必要な資質は、ヴェーバーの三つの資質では不足だと考えています。『工業/科学の知識』、『世界情勢についての見識』・・・などなど。 これから政治家を目指す若者達へ!『Boys be ambitious!』
『職業としての政治』には、第一次世界大戦までの統治体制(王政 皇帝 封建制、共和制、立憲君主制などなど)、貴族→有給の官僚による政治、有給の国会議員の誕生、派閥→政党の誕生、政党の組織化/拡大→政党の役員や職員の台頭、既得権団体の誕生/ロビー活動・・・など、現在に通じる内容が書かれています。
『職業としての政治』が出版された1年ほど前に、共産・ソビエトが誕生しました。初期の施策についてほんの少し触れていますが、「共産主義国家がドンナ統治をするのか?」ヴェーバーは知る事無く亡くなりました。 そして、イスラム教のアラビアの石油産出諸国が発展したのも、ヴェーバーが去った後です。
ヴェーバー歿後・100年が経過しました。先進国では民主主義化は進みましたが、多くの国では独裁政治/専制政治/一党独裁政治が行われています。 そして、民主主義政治の問題点や限界も顕著になって来ました。一党独裁政治の中国と経済戦争する為に、自由主義/民主主義の後退が必要かも知れません。
★ 紀元前509年~紀元前27年 :共和制のローマ
★ 1775年~83年 :アメリカ独立戦争
★ 1789年 :アメリカ・初代大統領=ジョージ・ワシントン就任
★ 1789年~95年 :フランス革命
★ 1861年~65年 :アメリカ南北戦争
★ 1864年 :マックス・ヴェーバー誕生 (プロイセン王国)
★ 1868年=明治元年
★ 1914年 :第一次世界大戦勃発
★ 1917年 :ロシア革命
★ 1918年 :第一次世界大戦が終戦
★ 1918年 :ドイツはドイツ帝国→ドイツ革命→ヴァイマル共和国になる。
★ 1919年1月28日 :ヴェーバー『職業としての政治』講演
★ 1920年 :ヴェーバー没 (ドイツ)
第2章 :私の考え方
ヴェーバーが生きていた時代に、国の主人は民衆で有るという『民主主義国家』はフランス、イギリスそしてアメリカだけだったと思います。ヴェーバー没後100年経ちます。 現在では、先進国の多くは民主主義国家になりました。然し、中国は未だに民主主義国家では無く、逆に・民主主義を否定している様に思えます。
民主主義の進捗状況を表す尺度の一つが、身分、貧富の差、男女の区別で選挙権を制限しない『普通選挙』を採用しているか?どうかだと考えます。今でも、国会議員の国民投票を実施していない国があります。女性の選挙権を認めていない国もあります。
選挙制度には小選挙区制、中選挙区制、大選挙区制、比例代表制と、それらを組み合わせた制度(例:小選挙区比例代表並立制)が有ります。 一方、民主主義国家とは、「国会で少数意見/思想の政党にも議席を与え、発言させる。最後には多数決で決める制度を採用している国」の事だと思います。 小選挙区制では少数派は議席を得るのが難しく、大選挙区制や比例代表制では政党が乱立して何も決められなくなってしまいます。 ヴェーバーは選挙制度については殆ど言及していませんが、(ヴァイマル共和国で採用されたと思われる)『比例選挙法』の問題点を予想しています。
民主主義は進化して、現在は『自由』と『平等』が含まれます。『博愛』も含まれるかも知れません。然し、イスラム教の信者で、神の教えを最優先する人達にとっては、民主主義思想をそのままでは受け入れられません。マホメットの時代は、「女性は男性に仕える存在」だったのです。 男は5人まで妻を娶っても良いが、女性が複数の男性を愛する事は許されないのです。
共産主義国家では選挙が出来ません。「共産党は民衆の政党で有るが、他の思想の政党は民衆の敵である。選挙をして民衆の敵(ブルジョア)に政権を渡す必要は無い」と主張している様です。レーニンは政権を取って直ぐに国会議員選挙を実施しましたが、ブルジョア政党に敗れてしまいました。レーニンは、直ちに国会を閉鎖して、以来・ソビエトでは選挙は行われませんでした。共産党員の為の国家になって行ったのです。
第3章 :ドイツの民主化
【中世のドイツ】
ドイツ語を公用語としている国は、①ドイツ、②オーストリア、③リヒテンシュタイン、④スイス、⑤ルクセンブルグ、⑥ベルギーの6っか国です。④~⑥の国はフランス語なども公用語です。 (フランツ・カフカはチェコスロバキア出身の作家で、ドイツ語を使用していますが、チェコスロバキアはスロバキア語の国でした。)
幕末までの日本の歴史に、外国の影響は少ないですが、陸続きのヨーロッパ諸国の場合は真逆です。『日本』と言う国号は701年に制定された大宝律令から採用されたと言われています。『ドイチェス・ライヒ』と言う国号は19世紀の後半からです。 中世のドイツは神聖ローマ帝国に含まれ、1701年からはプロイセン王国が統治しました。
962年に、ドイツ王兼イタリア王のオツトー1世が皇帝になりました。 彼が統治し始めた国が、後に神聖ローマ帝国と呼ばれる様になったのです。 名前に『ローマ』が入っていますが、ドイツ人が支配する帝国でした。 神聖ローマ帝国は領土を拡大し→縮小して、1806年に滅亡しました。 ウイキペディア『神聖ローマ帝国』で検索すると、962年~1806年の領土の変遷が動画(?)で見れます。
一方、現在のスイスにドイツ系の貴族・ハプスブルク家が有りました。政略結婚を繰り返して領土を拡大していきました。神聖ローマ帝国の王は諸侯が相談して決める事になっていました。 1272年に、王が絶大な権力を握らない様に、当時はまだ弱小の諸侯だったハプスブルク家のルドルフ1世を選びました。ルドルフ1世はハプスブルク家を大諸侯の一つにしました。 然し、神聖ローマ帝国の皇帝の世襲は、当時は認めていませんでした。(1549年にハプスブルク家出身者が、神聖ローマ皇帝位を世襲する事になりました。)
中世ヨーロッパは『封建制』でした。然し、徳川時代の封建制とは大きな違いが有ります。①女性でも王や貴族の相続権が有りました。A王国とB王国の相続権を有する男女が結婚して子供が出来ると、子供はA王国とB王国の王になるのです。 ②A王国の貴族(日本の藩主)がB王国の貴族の相続権を持つ女性と結婚すると、子供はA王国とB王国の貴族を兼務する事になります。③政略結婚を繰り返して領土を拡張し、王と同等か以上になった貴族が、王の相続権を持つ女性と結婚して、遂に『王』になる事が出来ました。 その典型例がハプスブルク家です。
16世紀になって、ハプスブルク家の版図は拡大しました。1519年にハプスブルク家のスペイン王だったカルロス1世が、ドイツに出向いて神聖ローマ帝国の皇帝・カール5世になりました。ハプスブルク家は、フランスを挟んで広大な地域を統治する事になりましたが、カール5世は直ぐにスペインに帰ってしまいました。
【宗教改革】
カトリック教会では昔から、犯した罪を神に許してもらうために、反省/善行をするだけで無く、教会にお金を寄進する習慣が有りました。教会は免罪符(贖宥状)を与えました。 私は、「仏教の戒名の制度に似ている」と思います。
神聖ローマ帝国は、十字軍に参加しない信徒に、免罪符を売りつけました。その後、免罪符を販売して教会が金を集める様になりました。教皇レオ10世が(現在もバチカンに有る)サン・ピエトロ大聖堂の建設費を集める為に、大々的に免罪符を販売しました。それに反対して起こったのがルターの『宗教改革』です。 ドイツにプロテスタント(新教)が誕生し、信徒を増やしていきました。
1618年~48年にカトリックとプロテスタント間で戦争(三十年戦争)が起こりました。多くの国が参戦し、覇権が目的になり、宗教の為の戦争では無くなりました。戦争中にペスト(黒死病)等の感染症が蔓延して、人口が激減して、ヨーロッパ諸国は大変革しました。カトリックとプロテスタントが共存する様になったのです。
【農奴解放】
中世のヨーロッパ諸国は農奴制でした。農奴達が1524年に農奴解放を求めて立ち上がりましたが、直ぐに鎮圧されてしまいました。ドイツで農奴解放が行われたのは1807年の『十月革命』によってですが、不完全なものでした。1848年の『三月革命で』で完了しました。 1850年に、「最高56年の分割払い」を条件に、それまで耕していた農地を農民に与える事になりました。
【ナポレオン戦争後のドイツ】
プロイセン王国は、1806年にナポレオンと戦争を始めましたが、敗れて領土の一部を割譲し、多額の賠償金を支払って1807年に和睦しました。 プロイセン王国は、そのまま存続して民主主義化は進みませんでした。
1871年にプロイセン王が皇帝になり、ドイツ帝国になりました。工業化が進み、現在のドイツの工業の礎(いしづえ)が確立した時代です。農林漁業の国が工業/商業の国に急激に変貌したのです。(経済は発展しましたが、民主主義化は進みませんでした。)
【第一次世界大戦の賠償金】
そして、ドイツ帝国は第一次世界大戦(1914年~18年)を始め、敗戦国になり→大統領制のヴァイマル共和国になりました。戦勝国から莫大な賠償金・1320億金マルク(=純金47,256トン)を30年間の分割払いをする様に要求されました。 (現在の日本円では200兆円ほどになるそうです。)
ドイツは共和国になりましたが、民主主義の経験が皆無に近い状態で、「戦争で荒廃した国家の再建と莫大な賠償金の支払いの為に、国民は希望が持てなかったのでは?」と想像します。 戦後15年でヒトラー政権が誕生して、覇権主義国家に戻ってしまいました。
【ヒトラー】
1933年にヒトラーがヴァイマル共和国の首相に任命され、彼は直ぐに大統領と議会の権限を停止させたので、ヴァイマル共和国は実質的に消滅しました。
1939年にドイツはポーランドに侵攻し、その後・直ぐにソビエトもポーランドに侵攻しました。 イギリスとフランスがドイツに宣戦布告して、第二次世界大戦が始まりました。(何故か?、ソビエトに対しては宣戦布告しませんでした。)
【敗戦後のドイツ】
若い頃に読んだ本には、「第一次世界大戦の反省から、第二次世界大戦後の補償額は少なかった」と書かれていましたが、実際は莫大な補償が要求された様です。但し、東西ドイツに分割したので、どちらの国に要求するか?と言う問題が有りました。1990年の再統一後に要求されたケースも有る様です。
占領下の西ドイツで1949年に、ドイツ連邦共和国基本法(憲法)が制定され、一部は改正されましたが、東西ドイツの再統一後も存続しています。 日本国憲法の第9条の様な、戦争を放棄すると言う条項は有りません。
【ホロコーストの反省】
ナチスがユダヤ人を多量に虐殺した『ホロコースト』の惨状を知らない人は、殆どいないと思われます。 ユダヤ人の犠牲者の数は正確には把握されていませんが、500万人~600万人と言われています。
敗戦後に覇権主義を否定して、民主主義思想が広がったのは「ホロコーストに対して国民が強く反省したからではないか」と思います。(日本は民主主義的な憲法をGHQに押し付けられたからです。)
【再軍備】
第二次世界大戦後、東西ドイツは国境警備隊や沿岸警備隊などを除いて、軍隊は廃止させられました。 米ソ対立(冷戦)の為に、西ドイツは1955年に再軍備が認められて、NATOに加盟しています。
冷戦時代にアメリカは、ヨーロッパ諸国に多量の核爆弾を持ち込んだと言われています。その後、多くは持ち帰りましたが、ドイツ国内に10発~20発を残し、両国の共有(核シェアリング)となっています。 歴代のドイツ政府は、アメリカと核爆弾の撤去について粘り強く交渉して来ました。まだ、実現していません。
【メルケル首相】
2005年にアンゲラ・メルケル(51歳)が首相に選ばれました。 わたくしは、「戦後の民主化の象徴的な出来事だ!」と思いました。 彼女が生まれて直ぐに、牧師だった両親が西ドイツから東ドイツに移住したので、東ドイツで育ちました。彼女は頭脳明晰で、大学では理論物理学を専攻しました。
ベルリンの壁が崩壊した1989年、メルケルは35歳でした。そして直ぐに政治家になろうと決心した様です。そして16年後にドイツの最初の女性首相になったのです。
彼女は二回結婚しています。23歳・学生時代に『メルケル』氏と結婚し、離婚しました。1998年に現在の夫と再婚しましたが、『夫婦別姓』を選択したので、今でも最初の夫の姓『メルケル』を名のっているのです。(日本には女性首相は誕生していないし、夫婦別姓は許されていません!)
★ 神聖ローマ帝国 : 962年~1806年・・・十字軍遠征
★ ハプスブルク家 :現在のスイス領内に発祥したドイツ系(アルザス系)の貴族。
★ 宗教改革 :マルティン・ルター
★ ドイツ農民戦争 :1524年・・・農奴制の廃止を要求
★ 三十年戦争 :1618年~48年プロテスタントとカトリックとの対立
★ プロイセン王国 :1701年~1871年→→ドイツ帝国
★ ナポレオン戦争 :1803年~15年
★ 十月革命 :1807年→→農奴解放
★ ドイツ連邦(ドイツ同盟) :1815年~66年・・・連邦議会・・・オーストリアを中心にした国
★ ドイツ帝国 :1871年~1918年
★ 第一次世界大戦 :1914年~18年
◎◎◎ 1919年1月『職業としての政治』講演された ◎◎◎
★ ヴェーバー :1919年・・・ドイツ革命(1918年)によってドイツ帝国が廃止された。
★ ヴァイマル共和国 :1919年~33年・・・憲法
★ 普通選挙 :1919年・・・世界初
★ 大統領制 :1919年
★ ヒトラー首相 :1933年 ・・・ヒンデンブルク大統領が任命した。
★ 全権委任法 :1933年・・・議会と大統領の権限は完全に形骸化した。
★ ヴァイマル共和国の廃止 :1934年
★ ポーランド侵攻 :1939年→→第二次世界大戦
★ ヒトラー自殺 :1945年→→ドイツ敗戦
★ ドイツ連邦共和国(西ドイツ) :1949年~
★ 西ドイツの憲法 :1949年
★ ドイツ再統一 :1990年
新型コロナが猛威を振るう様になって、「日本には今!、判断力/決断力/行動力/指導力の有る優秀な政治家が必要だ!」と思うようになりました。 民主主義国では議員を選挙で選びますが、「選挙は、優秀な人間を選別する篩の役割は出来ない」のだと気付きました。
民主主義がドンナニして発展してきたのか? 現在の民主主義では問題/課題が解決出来ない事が多々有るから、ドンナニ変えて行けば良いのか?・・・色々考える様になりました。
昔、読んだマックス・ヴェーバーの『職業としての政治』を、「民主主義の進歩と言う視点で読み返して見よう」と思い付きました。 ヴェーバーの与えてくれたヒントを基に、私の独断による「民主主義の進歩の歴史」を数回に分けて投稿します。次回は日本について書く予定です。
第1章 :ヴェーバーの『職業としての政治』を読み返して!
【職業としての政治】
ドイツ人で、政治学/経済学/社会学の分野で活躍したマックス・ヴェーバーをご存知ですか? ヴェーバーは、1864年に生まれ、亡くなったのは1920年です。 沢山の著作を残し、その多くが翻訳されて、今でも日本で読まれています。 私は、大学の教養部で細谷昂(ほそや たかし)先生のマックス・ヴェーバーに関する講義を受けました。
細谷先生の話は難解で、内容を殆ど覚えていませんが、先生が時々言及された『職業としての政治』の翻訳本が、1980年に岩波文庫として出版されたので、直ぐに買って読んでみました。 (今も出版していて、税込みで704円で、本文は120ページ程ですから、是非読んで見て下さい。)
第一次世界大戦(1914年~18年)でドイツは敗戦国になりましたが、終戦の2カ月後(1919年)にミュンヘンで学生相手に行った講演の内容を纏め、『職業としての政治』と言うタイトルで出版しました。
章(見出し)が無く、小説の様に書かれているので、一回読んだだけでは「分かった様で、分からない」本です。
【ヴェーバーが勉強出来た範囲は】
ヨーロッパ諸国の一部では中世に議会が誕生しました。初期の頃の議員は貴族や聖職者などで、無給でした。庶民が議員になると、有給制度になりました。ヴェーバーの言う『職業としての政治家(職業政治家)』の誕生です。 ヴェーバーは、政治家には『情熱』、『責任感』、『判断力』の三つの資質が必要であると言っています。
ヴェーバー後の100年で工業技術は目覚ましく進歩し、核兵器が誕生し『戦争抑止』と言う考え方が広がりました。一党独裁国家の中国が『世界の工場』と呼ばれるまでに発展し、近年は覇権主義政策をを露骨に進める様になっています。 現在の日本の政治家に必要な資質は、ヴェーバーの三つの資質では不足だと考えています。『工業/科学の知識』、『世界情勢についての見識』・・・などなど。 これから政治家を目指す若者達へ!『Boys be ambitious!』
『職業としての政治』には、第一次世界大戦までの統治体制(王政 皇帝 封建制、共和制、立憲君主制などなど)、貴族→有給の官僚による政治、有給の国会議員の誕生、派閥→政党の誕生、政党の組織化/拡大→政党の役員や職員の台頭、既得権団体の誕生/ロビー活動・・・など、現在に通じる内容が書かれています。
『職業としての政治』が出版された1年ほど前に、共産・ソビエトが誕生しました。初期の施策についてほんの少し触れていますが、「共産主義国家がドンナ統治をするのか?」ヴェーバーは知る事無く亡くなりました。 そして、イスラム教のアラビアの石油産出諸国が発展したのも、ヴェーバーが去った後です。
ヴェーバー歿後・100年が経過しました。先進国では民主主義化は進みましたが、多くの国では独裁政治/専制政治/一党独裁政治が行われています。 そして、民主主義政治の問題点や限界も顕著になって来ました。一党独裁政治の中国と経済戦争する為に、自由主義/民主主義の後退が必要かも知れません。
★ 紀元前509年~紀元前27年 :共和制のローマ
★ 1775年~83年 :アメリカ独立戦争
★ 1789年 :アメリカ・初代大統領=ジョージ・ワシントン就任
★ 1789年~95年 :フランス革命
★ 1861年~65年 :アメリカ南北戦争
★ 1864年 :マックス・ヴェーバー誕生 (プロイセン王国)
★ 1868年=明治元年
★ 1914年 :第一次世界大戦勃発
★ 1917年 :ロシア革命
★ 1918年 :第一次世界大戦が終戦
★ 1918年 :ドイツはドイツ帝国→ドイツ革命→ヴァイマル共和国になる。
★ 1919年1月28日 :ヴェーバー『職業としての政治』講演
★ 1920年 :ヴェーバー没 (ドイツ)
第2章 :私の考え方
ヴェーバーが生きていた時代に、国の主人は民衆で有るという『民主主義国家』はフランス、イギリスそしてアメリカだけだったと思います。ヴェーバー没後100年経ちます。 現在では、先進国の多くは民主主義国家になりました。然し、中国は未だに民主主義国家では無く、逆に・民主主義を否定している様に思えます。
民主主義の進捗状況を表す尺度の一つが、身分、貧富の差、男女の区別で選挙権を制限しない『普通選挙』を採用しているか?どうかだと考えます。今でも、国会議員の国民投票を実施していない国があります。女性の選挙権を認めていない国もあります。
選挙制度には小選挙区制、中選挙区制、大選挙区制、比例代表制と、それらを組み合わせた制度(例:小選挙区比例代表並立制)が有ります。 一方、民主主義国家とは、「国会で少数意見/思想の政党にも議席を与え、発言させる。最後には多数決で決める制度を採用している国」の事だと思います。 小選挙区制では少数派は議席を得るのが難しく、大選挙区制や比例代表制では政党が乱立して何も決められなくなってしまいます。 ヴェーバーは選挙制度については殆ど言及していませんが、(ヴァイマル共和国で採用されたと思われる)『比例選挙法』の問題点を予想しています。
民主主義は進化して、現在は『自由』と『平等』が含まれます。『博愛』も含まれるかも知れません。然し、イスラム教の信者で、神の教えを最優先する人達にとっては、民主主義思想をそのままでは受け入れられません。マホメットの時代は、「女性は男性に仕える存在」だったのです。 男は5人まで妻を娶っても良いが、女性が複数の男性を愛する事は許されないのです。
共産主義国家では選挙が出来ません。「共産党は民衆の政党で有るが、他の思想の政党は民衆の敵である。選挙をして民衆の敵(ブルジョア)に政権を渡す必要は無い」と主張している様です。レーニンは政権を取って直ぐに国会議員選挙を実施しましたが、ブルジョア政党に敗れてしまいました。レーニンは、直ちに国会を閉鎖して、以来・ソビエトでは選挙は行われませんでした。共産党員の為の国家になって行ったのです。
第3章 :ドイツの民主化
【中世のドイツ】
ドイツ語を公用語としている国は、①ドイツ、②オーストリア、③リヒテンシュタイン、④スイス、⑤ルクセンブルグ、⑥ベルギーの6っか国です。④~⑥の国はフランス語なども公用語です。 (フランツ・カフカはチェコスロバキア出身の作家で、ドイツ語を使用していますが、チェコスロバキアはスロバキア語の国でした。)
幕末までの日本の歴史に、外国の影響は少ないですが、陸続きのヨーロッパ諸国の場合は真逆です。『日本』と言う国号は701年に制定された大宝律令から採用されたと言われています。『ドイチェス・ライヒ』と言う国号は19世紀の後半からです。 中世のドイツは神聖ローマ帝国に含まれ、1701年からはプロイセン王国が統治しました。
962年に、ドイツ王兼イタリア王のオツトー1世が皇帝になりました。 彼が統治し始めた国が、後に神聖ローマ帝国と呼ばれる様になったのです。 名前に『ローマ』が入っていますが、ドイツ人が支配する帝国でした。 神聖ローマ帝国は領土を拡大し→縮小して、1806年に滅亡しました。 ウイキペディア『神聖ローマ帝国』で検索すると、962年~1806年の領土の変遷が動画(?)で見れます。
一方、現在のスイスにドイツ系の貴族・ハプスブルク家が有りました。政略結婚を繰り返して領土を拡大していきました。神聖ローマ帝国の王は諸侯が相談して決める事になっていました。 1272年に、王が絶大な権力を握らない様に、当時はまだ弱小の諸侯だったハプスブルク家のルドルフ1世を選びました。ルドルフ1世はハプスブルク家を大諸侯の一つにしました。 然し、神聖ローマ帝国の皇帝の世襲は、当時は認めていませんでした。(1549年にハプスブルク家出身者が、神聖ローマ皇帝位を世襲する事になりました。)
中世ヨーロッパは『封建制』でした。然し、徳川時代の封建制とは大きな違いが有ります。①女性でも王や貴族の相続権が有りました。A王国とB王国の相続権を有する男女が結婚して子供が出来ると、子供はA王国とB王国の王になるのです。 ②A王国の貴族(日本の藩主)がB王国の貴族の相続権を持つ女性と結婚すると、子供はA王国とB王国の貴族を兼務する事になります。③政略結婚を繰り返して領土を拡張し、王と同等か以上になった貴族が、王の相続権を持つ女性と結婚して、遂に『王』になる事が出来ました。 その典型例がハプスブルク家です。
16世紀になって、ハプスブルク家の版図は拡大しました。1519年にハプスブルク家のスペイン王だったカルロス1世が、ドイツに出向いて神聖ローマ帝国の皇帝・カール5世になりました。ハプスブルク家は、フランスを挟んで広大な地域を統治する事になりましたが、カール5世は直ぐにスペインに帰ってしまいました。
【宗教改革】
カトリック教会では昔から、犯した罪を神に許してもらうために、反省/善行をするだけで無く、教会にお金を寄進する習慣が有りました。教会は免罪符(贖宥状)を与えました。 私は、「仏教の戒名の制度に似ている」と思います。
神聖ローマ帝国は、十字軍に参加しない信徒に、免罪符を売りつけました。その後、免罪符を販売して教会が金を集める様になりました。教皇レオ10世が(現在もバチカンに有る)サン・ピエトロ大聖堂の建設費を集める為に、大々的に免罪符を販売しました。それに反対して起こったのがルターの『宗教改革』です。 ドイツにプロテスタント(新教)が誕生し、信徒を増やしていきました。
1618年~48年にカトリックとプロテスタント間で戦争(三十年戦争)が起こりました。多くの国が参戦し、覇権が目的になり、宗教の為の戦争では無くなりました。戦争中にペスト(黒死病)等の感染症が蔓延して、人口が激減して、ヨーロッパ諸国は大変革しました。カトリックとプロテスタントが共存する様になったのです。
【農奴解放】
中世のヨーロッパ諸国は農奴制でした。農奴達が1524年に農奴解放を求めて立ち上がりましたが、直ぐに鎮圧されてしまいました。ドイツで農奴解放が行われたのは1807年の『十月革命』によってですが、不完全なものでした。1848年の『三月革命で』で完了しました。 1850年に、「最高56年の分割払い」を条件に、それまで耕していた農地を農民に与える事になりました。
【ナポレオン戦争後のドイツ】
プロイセン王国は、1806年にナポレオンと戦争を始めましたが、敗れて領土の一部を割譲し、多額の賠償金を支払って1807年に和睦しました。 プロイセン王国は、そのまま存続して民主主義化は進みませんでした。
1871年にプロイセン王が皇帝になり、ドイツ帝国になりました。工業化が進み、現在のドイツの工業の礎(いしづえ)が確立した時代です。農林漁業の国が工業/商業の国に急激に変貌したのです。(経済は発展しましたが、民主主義化は進みませんでした。)
【第一次世界大戦の賠償金】
そして、ドイツ帝国は第一次世界大戦(1914年~18年)を始め、敗戦国になり→大統領制のヴァイマル共和国になりました。戦勝国から莫大な賠償金・1320億金マルク(=純金47,256トン)を30年間の分割払いをする様に要求されました。 (現在の日本円では200兆円ほどになるそうです。)
ドイツは共和国になりましたが、民主主義の経験が皆無に近い状態で、「戦争で荒廃した国家の再建と莫大な賠償金の支払いの為に、国民は希望が持てなかったのでは?」と想像します。 戦後15年でヒトラー政権が誕生して、覇権主義国家に戻ってしまいました。
【ヒトラー】
1933年にヒトラーがヴァイマル共和国の首相に任命され、彼は直ぐに大統領と議会の権限を停止させたので、ヴァイマル共和国は実質的に消滅しました。
1939年にドイツはポーランドに侵攻し、その後・直ぐにソビエトもポーランドに侵攻しました。 イギリスとフランスがドイツに宣戦布告して、第二次世界大戦が始まりました。(何故か?、ソビエトに対しては宣戦布告しませんでした。)
【敗戦後のドイツ】
若い頃に読んだ本には、「第一次世界大戦の反省から、第二次世界大戦後の補償額は少なかった」と書かれていましたが、実際は莫大な補償が要求された様です。但し、東西ドイツに分割したので、どちらの国に要求するか?と言う問題が有りました。1990年の再統一後に要求されたケースも有る様です。
占領下の西ドイツで1949年に、ドイツ連邦共和国基本法(憲法)が制定され、一部は改正されましたが、東西ドイツの再統一後も存続しています。 日本国憲法の第9条の様な、戦争を放棄すると言う条項は有りません。
【ホロコーストの反省】
ナチスがユダヤ人を多量に虐殺した『ホロコースト』の惨状を知らない人は、殆どいないと思われます。 ユダヤ人の犠牲者の数は正確には把握されていませんが、500万人~600万人と言われています。
敗戦後に覇権主義を否定して、民主主義思想が広がったのは「ホロコーストに対して国民が強く反省したからではないか」と思います。(日本は民主主義的な憲法をGHQに押し付けられたからです。)
【再軍備】
第二次世界大戦後、東西ドイツは国境警備隊や沿岸警備隊などを除いて、軍隊は廃止させられました。 米ソ対立(冷戦)の為に、西ドイツは1955年に再軍備が認められて、NATOに加盟しています。
冷戦時代にアメリカは、ヨーロッパ諸国に多量の核爆弾を持ち込んだと言われています。その後、多くは持ち帰りましたが、ドイツ国内に10発~20発を残し、両国の共有(核シェアリング)となっています。 歴代のドイツ政府は、アメリカと核爆弾の撤去について粘り強く交渉して来ました。まだ、実現していません。
【メルケル首相】
2005年にアンゲラ・メルケル(51歳)が首相に選ばれました。 わたくしは、「戦後の民主化の象徴的な出来事だ!」と思いました。 彼女が生まれて直ぐに、牧師だった両親が西ドイツから東ドイツに移住したので、東ドイツで育ちました。彼女は頭脳明晰で、大学では理論物理学を専攻しました。
ベルリンの壁が崩壊した1989年、メルケルは35歳でした。そして直ぐに政治家になろうと決心した様です。そして16年後にドイツの最初の女性首相になったのです。
彼女は二回結婚しています。23歳・学生時代に『メルケル』氏と結婚し、離婚しました。1998年に現在の夫と再婚しましたが、『夫婦別姓』を選択したので、今でも最初の夫の姓『メルケル』を名のっているのです。(日本には女性首相は誕生していないし、夫婦別姓は許されていません!)
★ 神聖ローマ帝国 : 962年~1806年・・・十字軍遠征
★ ハプスブルク家 :現在のスイス領内に発祥したドイツ系(アルザス系)の貴族。
★ 宗教改革 :マルティン・ルター
★ ドイツ農民戦争 :1524年・・・農奴制の廃止を要求
★ 三十年戦争 :1618年~48年プロテスタントとカトリックとの対立
★ プロイセン王国 :1701年~1871年→→ドイツ帝国
★ ナポレオン戦争 :1803年~15年
★ 十月革命 :1807年→→農奴解放
★ ドイツ連邦(ドイツ同盟) :1815年~66年・・・連邦議会・・・オーストリアを中心にした国
★ ドイツ帝国 :1871年~1918年
★ 第一次世界大戦 :1914年~18年
◎◎◎ 1919年1月『職業としての政治』講演された ◎◎◎
★ ヴェーバー :1919年・・・ドイツ革命(1918年)によってドイツ帝国が廃止された。
★ ヴァイマル共和国 :1919年~33年・・・憲法
★ 普通選挙 :1919年・・・世界初
★ 大統領制 :1919年
★ ヒトラー首相 :1933年 ・・・ヒンデンブルク大統領が任命した。
★ 全権委任法 :1933年・・・議会と大統領の権限は完全に形骸化した。
★ ヴァイマル共和国の廃止 :1934年
★ ポーランド侵攻 :1939年→→第二次世界大戦
★ ヒトラー自殺 :1945年→→ドイツ敗戦
★ ドイツ連邦共和国(西ドイツ) :1949年~
★ 西ドイツの憲法 :1949年
★ ドイツ再統一 :1990年