
昨夜は結局3時過ぎに寝床につきました。
7時には起床し、まだ出来ていなかった、弔辞の文章をパソコンで書き始めました。9時半には家を出なければならないので、急ぎます。昨日のうちにネットで弔辞の文例集を探して、一通り内容は考えていましたが、いざ書き始めると、祖母との思い出がめまぐるしく頭の中をかけめぐり、なかなか纏めることができません。時間も押し迫っていたので、頭に浮かんだことを自然に書き綴っていきました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
弔辞もなんとか間に合い、葬儀場に向いました。
午前11時、葬場祭(告別式)が始まりました。昨日、猛烈に足が痺れた教訓から、今日は胡坐(あぐら)で臨みました。昨日の通夜・遷霊祭(神式ではこちらの方がより重要らしい)よりは短く、開始から30分ほどで玉串奉献となりました。まず父が、次に母が奉献しました。そして私と弟の番ですが、この奉献の際に私が弔辞を読む段取りになっていました。
玉串を持って祭壇の前に進み、まず玉串を奉献しました。
一度拝礼して、いよいよ読み始めます。
「謹んで、祖母、堤節子の霊前に申し上げます。
以下、祖母のことを、生前に呼びかける際に用いておりました、バーバと呼ばせていただきます。
バーバ、今日、こんなにも早くにお別れを告げる日が来ようとは、思いもよりませんでした。突然の逝去に、とても驚きました。早朝の父からの電話によって、それを知ったのですが、かなうことならば、孫として最後の瞬間に立ち会いたかったところ、私が遠隔の地に住んでいるために、それがかなわず、まことに残念でなりません。
思えばバーバとは、本当に色んなところに行きましたね。幼いころには、よく二人で熊本に墓参りに行きましたし、大きくなってからは、北海道や沖縄も旅しましたね。
特に思い出深いのは、五年前に行った北海道旅行です。宗谷岬、釧路の市場、霧に包まれた摩周の湖畔、網走では流氷に触れ、美瑛では遥かなかなたまで連なる大地に、一緒に感動しましたね。その瞬間の一つ一つが、今となっては素晴しい思い出です。あの旅は、自ら計画を立てたために、あれもこれもと欲張ってしまい、結構過密な行程でしたが、そんな中でも、バーバは初めての北の大地で、元気を貰えたと、喜んでいました。また、いつかはあの広大な畑の真ん中に住んで、毎日趣味の絵を描きながら暮らしてみたいとも言っていました。齢八十を越えてなおも、夢を持っていたバーバ、私が大人になったら、是非それをかなえてあげたいと思っていました。
私が旅好きで、絵や写真が趣味なのも、バーバの影響なのでしょうか。私が知っているのは、晩年の七十歳以降のことですが、保険の仕事を続けながらも、様々な趣味、絵画、茶道、華道、郷土文化の研究などをする姿は、実に生き生きとしていて、格好良く見えました。また、バーバが語る昔話は、どんな教科書よりも興味深いものでした。特に大正時代の幼稚園の頃から、昭和前期、戦前から戦中に至る内容は、実体験に基づくもので、なんど聞いても飽きませんでした。是非それらの話を、記録に残したいと思っていたのですが、最近ではそれが難しい状態になってしまい、ついにはかなわぬこととなり、残念です。
ただ、バーバは、八十六年の人生を十分に楽しんだことと思います。もちろんこれまでに多くの苦労をしてきたでしょうが、その分多くの楽しみ・喜びも味わったことでしょう。バーバは明るいことや賑やかなことが好きでしたね。だから、今日、私はバーバの旅立ちを明るく見送りたいとおもいます。
長い間お世話になりました。そして、いってらっしゃい、バーバ。
孫、堤 元佐、Y(弟)」
弔辞を読んでいる間も、それぞれの思い出が私の頭の中を巡りつづけていました。
読み終えると、弔辞の紙を玉串の奉献台に置き、席に戻りました。何人かの人が、すすり泣く声が聞こえてきました。隣に座る母も目に涙を溜めています。父も同様で、私も目頭が熱い状態が続いていました。
その後、参列者全員の玉串奉献が終わり、葬場祭は恙無く終わりました。
そして、いよいよ出棺のときがやってきました。事前に、祖母の愛用品(草履、時刻表、飛行機の機内誌など)を入れた棺に、参列者が花を挿していきます。そして、棺の蓋を再び閉じると、私を含む親族の男たちで棺を運び始めました。葬儀場が建物(普段は別の用途で使われている)の4階にあり、エレベータが使えないため、階段で降ろします。棺はかなり重く、一階一階、慎重に降ろしていきました。1階に着くと、すでに玄関に霊柩車が付けられており、そのまま車の寝台に棺を運び入れました。霊柩車の助手席には喪主である父が乗りこみ、その後ろ、棺の横の席に私が座りました。さらに、弟が反対側の余ったスペースに無理やり入り込んで、珍しい(?)5人乗りで葬儀場を後にしました。
十五分ほどで、市の火葬場に到着しました。すぐさま、マイクロバスに乗ってきた他の親族と一緒に窯の前に棺を運びます。
火葬に先立ち、祭事を執り行い、最後の拝顔を済ませ、祖母の棺は窯の中へと入っていきました。
・・・・・・
一旦、葬儀場に帰り、葬後祭をつとめたのち、直会(なおらい)となりました。親族一同が揃って食事することもなかなかないことなので、話が弾みました。会話の中で、びっくりすることがありました。親戚に、貝類の収集を本格的にされている方がいるのですが、その人と話したところ、琉球大学のとある教授と知り合いで、時折メールでの連絡もしているとのこと。詳しく聞いてみると、その教授とは、なんと私が昨年のゼミでお世話になった山口教授(今年退官されました)だったのです。山口教授は、貝類の研究をされていたので、もしやとは思いましたが、こんな近くに繋がりがあったとは!それからその親戚の方と話が盛り上がりました。
しばしの休息だった直会が終わると、一同再び火葬場へ、お骨の取り出しに向いました。
火葬場に着くと、すでに祖母のお骨は窯の外に出されていました。早速、二人一組で長い箸を使って骨壷に骨を入れていきます。足から順に、頭まで順番に入れ、最後に頭骨の上に喉仏を乗せ、蓋を閉めました。それを火葬場の職員の方が布で包み、お骨の取り出しは終わりました。あっというまのことでした。予想以上に祖母の骨は軽く、関節がすり潰れたような箇所もあり、火葬場の職員の方も言っておられましたが、生前は相当にきつかったであろうことが窺い知れました。
その後、親族一同は解散し、家族で祖母の霊爾とお骨、遺影を家に持ち帰り、急作りの祭壇に安置しました。これから五十日祭(仏教の四十九日)が終わるまでは、喪に伏すことになります。
こうして、滞りなく、ひとまず祖母の葬儀は終わりました。
正直なところ、まだ祖母が亡くなったという実感はありません。まだ、祖母が入院していた病院に行けば会えそうな気さえします。しかし、実家の元々祖母が使っていた部屋で、祖母の遺影を眺めると、それが現実であることを改めて思い知らされるのです。これから、徐々に実感が伴ってくるのだと思います。
今日はとにかく疲れました。
7時には起床し、まだ出来ていなかった、弔辞の文章をパソコンで書き始めました。9時半には家を出なければならないので、急ぎます。昨日のうちにネットで弔辞の文例集を探して、一通り内容は考えていましたが、いざ書き始めると、祖母との思い出がめまぐるしく頭の中をかけめぐり、なかなか纏めることができません。時間も押し迫っていたので、頭に浮かんだことを自然に書き綴っていきました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
弔辞もなんとか間に合い、葬儀場に向いました。
午前11時、葬場祭(告別式)が始まりました。昨日、猛烈に足が痺れた教訓から、今日は胡坐(あぐら)で臨みました。昨日の通夜・遷霊祭(神式ではこちらの方がより重要らしい)よりは短く、開始から30分ほどで玉串奉献となりました。まず父が、次に母が奉献しました。そして私と弟の番ですが、この奉献の際に私が弔辞を読む段取りになっていました。
玉串を持って祭壇の前に進み、まず玉串を奉献しました。
一度拝礼して、いよいよ読み始めます。
「謹んで、祖母、堤節子の霊前に申し上げます。
以下、祖母のことを、生前に呼びかける際に用いておりました、バーバと呼ばせていただきます。
バーバ、今日、こんなにも早くにお別れを告げる日が来ようとは、思いもよりませんでした。突然の逝去に、とても驚きました。早朝の父からの電話によって、それを知ったのですが、かなうことならば、孫として最後の瞬間に立ち会いたかったところ、私が遠隔の地に住んでいるために、それがかなわず、まことに残念でなりません。
思えばバーバとは、本当に色んなところに行きましたね。幼いころには、よく二人で熊本に墓参りに行きましたし、大きくなってからは、北海道や沖縄も旅しましたね。
特に思い出深いのは、五年前に行った北海道旅行です。宗谷岬、釧路の市場、霧に包まれた摩周の湖畔、網走では流氷に触れ、美瑛では遥かなかなたまで連なる大地に、一緒に感動しましたね。その瞬間の一つ一つが、今となっては素晴しい思い出です。あの旅は、自ら計画を立てたために、あれもこれもと欲張ってしまい、結構過密な行程でしたが、そんな中でも、バーバは初めての北の大地で、元気を貰えたと、喜んでいました。また、いつかはあの広大な畑の真ん中に住んで、毎日趣味の絵を描きながら暮らしてみたいとも言っていました。齢八十を越えてなおも、夢を持っていたバーバ、私が大人になったら、是非それをかなえてあげたいと思っていました。
私が旅好きで、絵や写真が趣味なのも、バーバの影響なのでしょうか。私が知っているのは、晩年の七十歳以降のことですが、保険の仕事を続けながらも、様々な趣味、絵画、茶道、華道、郷土文化の研究などをする姿は、実に生き生きとしていて、格好良く見えました。また、バーバが語る昔話は、どんな教科書よりも興味深いものでした。特に大正時代の幼稚園の頃から、昭和前期、戦前から戦中に至る内容は、実体験に基づくもので、なんど聞いても飽きませんでした。是非それらの話を、記録に残したいと思っていたのですが、最近ではそれが難しい状態になってしまい、ついにはかなわぬこととなり、残念です。
ただ、バーバは、八十六年の人生を十分に楽しんだことと思います。もちろんこれまでに多くの苦労をしてきたでしょうが、その分多くの楽しみ・喜びも味わったことでしょう。バーバは明るいことや賑やかなことが好きでしたね。だから、今日、私はバーバの旅立ちを明るく見送りたいとおもいます。
長い間お世話になりました。そして、いってらっしゃい、バーバ。
孫、堤 元佐、Y(弟)」
弔辞を読んでいる間も、それぞれの思い出が私の頭の中を巡りつづけていました。
読み終えると、弔辞の紙を玉串の奉献台に置き、席に戻りました。何人かの人が、すすり泣く声が聞こえてきました。隣に座る母も目に涙を溜めています。父も同様で、私も目頭が熱い状態が続いていました。
その後、参列者全員の玉串奉献が終わり、葬場祭は恙無く終わりました。
そして、いよいよ出棺のときがやってきました。事前に、祖母の愛用品(草履、時刻表、飛行機の機内誌など)を入れた棺に、参列者が花を挿していきます。そして、棺の蓋を再び閉じると、私を含む親族の男たちで棺を運び始めました。葬儀場が建物(普段は別の用途で使われている)の4階にあり、エレベータが使えないため、階段で降ろします。棺はかなり重く、一階一階、慎重に降ろしていきました。1階に着くと、すでに玄関に霊柩車が付けられており、そのまま車の寝台に棺を運び入れました。霊柩車の助手席には喪主である父が乗りこみ、その後ろ、棺の横の席に私が座りました。さらに、弟が反対側の余ったスペースに無理やり入り込んで、珍しい(?)5人乗りで葬儀場を後にしました。
十五分ほどで、市の火葬場に到着しました。すぐさま、マイクロバスに乗ってきた他の親族と一緒に窯の前に棺を運びます。
火葬に先立ち、祭事を執り行い、最後の拝顔を済ませ、祖母の棺は窯の中へと入っていきました。
・・・・・・
一旦、葬儀場に帰り、葬後祭をつとめたのち、直会(なおらい)となりました。親族一同が揃って食事することもなかなかないことなので、話が弾みました。会話の中で、びっくりすることがありました。親戚に、貝類の収集を本格的にされている方がいるのですが、その人と話したところ、琉球大学のとある教授と知り合いで、時折メールでの連絡もしているとのこと。詳しく聞いてみると、その教授とは、なんと私が昨年のゼミでお世話になった山口教授(今年退官されました)だったのです。山口教授は、貝類の研究をされていたので、もしやとは思いましたが、こんな近くに繋がりがあったとは!それからその親戚の方と話が盛り上がりました。
しばしの休息だった直会が終わると、一同再び火葬場へ、お骨の取り出しに向いました。
火葬場に着くと、すでに祖母のお骨は窯の外に出されていました。早速、二人一組で長い箸を使って骨壷に骨を入れていきます。足から順に、頭まで順番に入れ、最後に頭骨の上に喉仏を乗せ、蓋を閉めました。それを火葬場の職員の方が布で包み、お骨の取り出しは終わりました。あっというまのことでした。予想以上に祖母の骨は軽く、関節がすり潰れたような箇所もあり、火葬場の職員の方も言っておられましたが、生前は相当にきつかったであろうことが窺い知れました。
その後、親族一同は解散し、家族で祖母の霊爾とお骨、遺影を家に持ち帰り、急作りの祭壇に安置しました。これから五十日祭(仏教の四十九日)が終わるまでは、喪に伏すことになります。
こうして、滞りなく、ひとまず祖母の葬儀は終わりました。
正直なところ、まだ祖母が亡くなったという実感はありません。まだ、祖母が入院していた病院に行けば会えそうな気さえします。しかし、実家の元々祖母が使っていた部屋で、祖母の遺影を眺めると、それが現実であることを改めて思い知らされるのです。これから、徐々に実感が伴ってくるのだと思います。
今日はとにかく疲れました。












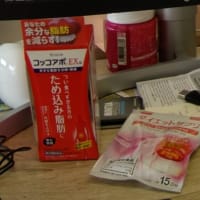


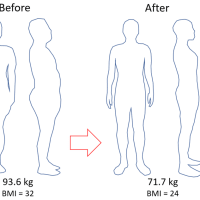




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます