皆様こんばんは。m(_ _)m
札幌へ戻ってからちょうど1週間が経ちました。
春休み中の記事の補完を優先しているので、新記事の投稿を行っていませんでしたが、あまりにしなさ過ぎると、ご心配になられる向きもあるかと思いますので、週末に当たってのまとめを書かせていただきます。
5日月曜日、研究室公式スケジュール再開日は、ちゃんと朝から登校しました。
この日は掃除当番に当たっていたので、まずは研究室の掃除をしました。春休み中は掃除が疎かになっていたようで、結構ゴミが溜まっていて、運ぶのが大変でした。
また、この日は席替えがありました。私のデスクのある部屋では、左隣と右隣の席の先輩が3月で卒業されたので、空席となっていました。新4年生の机(研究テーマが決まるまでの仮席)決めが行われていたので、それに乗じて私の席を左隣に移動しました。
私の新しい席は窓際で、ブラインドを開ければなかなかグッドな眺望を独り占めでき、実は以前から狙っていた席なのです。ここは地上7階で北西側に面していますから、農学部農場(かのポプラ並木含む)や手稲山、天気が良いときは小樽方面まで望めます。きっとこれからは毎日四季の移ろいを楽しめることでしょう。
この日から7日水曜日までは、新学期の書類配布や提出などの手続きが多かったので、それを中心に動きました。
8日木曜日には、新年度最初の実験を行いました。抗菌タンパク質の溶菌活性の実験で、3月に4日連続で行った実験の続きでした。この前のときは、サンプル数が多く、菌も自分で培養しなければならなかったので凄まじく忙しかったのですが、今回はサンプルは8つで、菌も凍結乾燥のものを利用、実験自体もかなり自動化されたメソッドを用いたので比較的楽でした。(タンパク質の濃度調節などはより慎重に行いましたが)
実験終了後の先生との打ち合わせで、ひょんなことからこの研究を他の研究室との共同研究にすることになり、早速その研究室の教授とも打ち合わせ。その際に初めてよその研究室を訪ねましたが、そちらの方が以前私がいた研究室に似た雰囲気でした。
9日は実験データ整理と実験安全講習会&新入生歓迎会でした。今年度、我が研究室にはよその大学から2人の修士1年生が配属されました。同じ境遇の仲間が増えて喜ばしいことです。
歓迎会の席でも、彼らとは色々と話せました。
そしてこの週末は、フジテレビの「我が家の歴史」やNHKの「大仏開眼」で楽しみました。どちらもなかなか面白い内容でしたが、特に「大仏開眼」は、平城宮や大仏殿の創建当初の再現CGが多く使われていたり、天皇の即位の礼や落慶法要の際の臣官の服装が美しく再現されていて、とても気に入りました。藤原仲麻呂(何故か一発で変換できる)が織田信長風に描かれていたのも斬新でしたね。一部分だけ録画したのですが、何度も見直してしまいました。
大仏と言えば、東大寺の七重塔が復原に向かって動き出したそうですね。先日、複数の新聞に記事が掲載されていました。まずは近々復原のための発掘調査を行うそうですが、東大寺の七重塔といえば、高さ100mにも及ぶという巨大なものです。奈良市の現在の建築物は最高でも30m程度に高さが抑えられており、興福寺五重塔と東大寺大仏殿が高さおよそ50mのところ、七重塔が復原されれば一気に抜きん出ることになります。(避雷針とかどうするのだろう・・)何十年後に完成するか分かりませんが、かなり面白い風景が見られることになりますね。

東大寺大仏殿にある、創建当初の東大寺の伽藍の復元模型。大仏殿も現在よりさらに巨大な建物でした。復原が計画されているのは、写真右の七重塔です。
札幌へ戻ってからちょうど1週間が経ちました。
春休み中の記事の補完を優先しているので、新記事の投稿を行っていませんでしたが、あまりにしなさ過ぎると、ご心配になられる向きもあるかと思いますので、週末に当たってのまとめを書かせていただきます。
5日月曜日、研究室公式スケジュール再開日は、ちゃんと朝から登校しました。
この日は掃除当番に当たっていたので、まずは研究室の掃除をしました。春休み中は掃除が疎かになっていたようで、結構ゴミが溜まっていて、運ぶのが大変でした。
また、この日は席替えがありました。私のデスクのある部屋では、左隣と右隣の席の先輩が3月で卒業されたので、空席となっていました。新4年生の机(研究テーマが決まるまでの仮席)決めが行われていたので、それに乗じて私の席を左隣に移動しました。
私の新しい席は窓際で、ブラインドを開ければなかなかグッドな眺望を独り占めでき、実は以前から狙っていた席なのです。ここは地上7階で北西側に面していますから、農学部農場(かのポプラ並木含む)や手稲山、天気が良いときは小樽方面まで望めます。きっとこれからは毎日四季の移ろいを楽しめることでしょう。
この日から7日水曜日までは、新学期の書類配布や提出などの手続きが多かったので、それを中心に動きました。
8日木曜日には、新年度最初の実験を行いました。抗菌タンパク質の溶菌活性の実験で、3月に4日連続で行った実験の続きでした。この前のときは、サンプル数が多く、菌も自分で培養しなければならなかったので凄まじく忙しかったのですが、今回はサンプルは8つで、菌も凍結乾燥のものを利用、実験自体もかなり自動化されたメソッドを用いたので比較的楽でした。(タンパク質の濃度調節などはより慎重に行いましたが)
実験終了後の先生との打ち合わせで、ひょんなことからこの研究を他の研究室との共同研究にすることになり、早速その研究室の教授とも打ち合わせ。その際に初めてよその研究室を訪ねましたが、そちらの方が以前私がいた研究室に似た雰囲気でした。
9日は実験データ整理と実験安全講習会&新入生歓迎会でした。今年度、我が研究室にはよその大学から2人の修士1年生が配属されました。同じ境遇の仲間が増えて喜ばしいことです。
歓迎会の席でも、彼らとは色々と話せました。
そしてこの週末は、フジテレビの「我が家の歴史」やNHKの「大仏開眼」で楽しみました。どちらもなかなか面白い内容でしたが、特に「大仏開眼」は、平城宮や大仏殿の創建当初の再現CGが多く使われていたり、天皇の即位の礼や落慶法要の際の臣官の服装が美しく再現されていて、とても気に入りました。藤原仲麻呂(何故か一発で変換できる)が織田信長風に描かれていたのも斬新でしたね。一部分だけ録画したのですが、何度も見直してしまいました。
大仏と言えば、東大寺の七重塔が復原に向かって動き出したそうですね。先日、複数の新聞に記事が掲載されていました。まずは近々復原のための発掘調査を行うそうですが、東大寺の七重塔といえば、高さ100mにも及ぶという巨大なものです。奈良市の現在の建築物は最高でも30m程度に高さが抑えられており、興福寺五重塔と東大寺大仏殿が高さおよそ50mのところ、七重塔が復原されれば一気に抜きん出ることになります。(避雷針とかどうするのだろう・・)何十年後に完成するか分かりませんが、かなり面白い風景が見られることになりますね。

東大寺大仏殿にある、創建当初の東大寺の伽藍の復元模型。大仏殿も現在よりさらに巨大な建物でした。復原が計画されているのは、写真右の七重塔です。












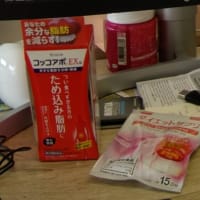


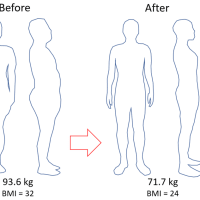




6~8月あたりに気をつけないと。
現代建築とは、全然違った技法で修復するのかな?
東大寺南大門などにも、よく見たら避雷針が設置されていますね。
薬師寺や室生寺の修復などで、三重塔・五重塔の復原の技法は培われているはずですから、やはり当時の技法を用いて木造で復原するのでしょう。
それにしても、1300年も前にこんな巨大な建築物を造れたことに驚きますね。