日経新聞、朝日新聞、読売新聞がそれぞれ政府の基礎的財政収支の黒字化目標の試算が甘いと批判する社説を書いた。コロナ禍の現在では財政出動は必要だが、基礎的財政収支の黒字化のために歳入を増やし、歳出を減らさなければならないと書く。
だが基礎的財政収支の黒字化目標がそもそも間違いなのだ。国債償還費を除いた歳出を税収で賄わなければならないという発想が間違っている。インフレさえ起こさなければ国債を発行して何の問題もない。
歳入を増やすということはつまりは増税だ。消費税10%への増税で国民はどれだけ苦しんでいるか。他に社会保険料の引き上げなど負担増は多い。そうでなくとも増税は景気を冷やす。消費税増税を繰り返してきたが、景気が冷え込み税収は思ったほど増えていないのがこの30年ではなかったか。
歳出を減らすことも景気を冷やす。GDPは民間消費、民間投資、政府支出、純輸出で成り立つ。政府支出を減らせば当然GDPは減り景気は悪化する。そのことを理解せず歳出を減らし消費税増税の緊縮財政を強行したのが橋本龍太郎の莫迦総理だ。与謝野馨もマスコミには「政策通」と持ち上げられていたが、経済も財政も何も理解しておらず官房副長官として経済を破綻させた。
それ以降小渕恵三が積極財政で一時的に経済を持ち直したが、財務省の緊縮財政志向をはねのけることができず日本経済はずっと停滞している。
経済停滞から成長軌道に移すには減税か国債発行しかない。何度も繰り返し書いてきたが、それしかないのだ。消費税廃止ないし減税をするにしても歳出の規模は維持しなければ意味がないので廃止ないし減税して税収が減った分は国債発行で補わなければならない。
新聞は偉そうに政府の政策を批判するが、批判する思想が間違っているから滑稽でしかない。政治は妥協のアートだから計算上のそれだけでできるわけではない。だが新聞はそうした苦労を考えず正しさのみで批判する_わけではなく新聞の主張そのものが間違いなのだ。今必要なのは財政再建ではなく国債を大量に発行する積極財政だ。
日露戦争の講和への反対。対米戦争の煽り。共産圏の称賛。新自由主義への賛成。そして財政再建。日本の新聞は常に間違えてきた。新聞の主張通りにしたら大東亜戦争で破滅した。戦後も新聞がこぞって称賛した共産圏は破綻した。その後の新自由主義で経済はボロボロだ。財政再建の主張も経済を縮小する。
だが新聞の社説を批判することは無意味かもしれないとも思っている。国民は誰も読んでいないからだ。まず新聞を購読している世帯が全世帯の半分程度。日本新聞協会が公表した新聞購読世帯率は61%だが、これは押し紙と事業所による購読を含んでいる。それを加味すれば購読世帯は半分を切るだろう。とくに若者は読んでいない。まして社説など。
それでも「日本に財政再建が必要だ。」「基礎的財政収支の黒字化を成し遂げねばならない」と強固に思い込んでいる人達と緊縮財政で利益を得る人達以外には財政再建を主張する新聞社説を批判することで今必要なのは積極財政だと訴えることができるだろう。その意味では意味がある。
社説よりも財政再建を訴える署名記事やコラムを批判した方が効果的かもしれないが、私自身新聞はあまり読んでいないのだ。この3本の社説を読んだのも昨日のことで毎日社説を読んではいない。毎日だらだらネットを巡回してネタを探しているのだが、新聞サイトは産経新聞くらいしか読んでいない。異論を読むことの重要性はわかるのだが。
基礎的財政収支の黒字化目標がまず間違いなのだ。基礎的財政収支の黒字化は意味がないどころか経済を破綻させる。財政赤字は必要なのだ。社説を引用しておく。ひとつひとつ間違いを指摘しないので斜め読みで構わない。
~~引用ここから~~

政府が中長期の経済財政試算をまとめた。国と地方の基礎的財政収支(プライマリーバランス=PB)が、早ければ2029年度に黒字に転じるとみている。経済成長率などの前提が総じて甘く、信頼に足る試算とは言い難い。
コロナ禍に対応する経済対策などの影響で、PBの赤字は19年度の14.6兆円から、20年度には69.4兆円に膨らむ。その後に年度平均で名目3%超、実質2%超の成長率を維持できれば、29年度に0.3兆円の黒字となる。
この成長率は民間の想定を上回る。しかも昨年7月にまとめた前回の試算より財政が悪化したにもかかわらず、25年度以降のPBの値は同じである。厳しい現実を直視せず、甘い見通しで覆い隠したと批判されても仕方ない。
政府がより慎重に見積もったシナリオでは、29年度も10.3兆円の赤字となる。こちらの方がまだ実情に近いのではないか。
政府は25年度にPBを黒字化する目標をまだ撤回していない。今回の試算で7.3兆円、より慎重なシナリオでは12.6兆円の赤字が残るにもかかわらずである。今後の歳出改革などによって赤字を前倒しで解消できるというが、あまりにも現実離れしていると言わざるを得ない。
コロナの感染がここにきて急速に拡大し、政府は緊急事態宣言の再発動に追い込まれた。日本経済の低迷が長引き、追加の経済対策を迫られる可能性もある。
困窮している個人や企業を、いまはしっかりと支えるべきだ。そのために必要な国・地方の財政出動をためらう時ではない。
だが、政府には財政の窮状を正しく伝える責任もある。コロナ禍がいっこうに収まらず、先を見通すのが困難だとしても、地に足の着いた試算を示して国民や市場の理解を得るべきではないのか。
国・地方の長期債務残高はいまや1200兆円規模に膨らみ、国内総生産(GDP)のほぼ2倍に相当する。日本の財政悪化は主要国の中でもとりわけ深刻で、とても楽観できる状況ではない。
たとえ危機下でも財政に負荷をかけすぎれば、そのツケはいずれ返ってくる。目先の予算措置で規律や節度を守るだけでなく、いずれは本格的な歳入・歳出改革への取り組みも必要になろう。
政府が現実から遊離した試算や目標を掲げたままでは、次の一歩も踏み出せまい。
~~引用ここまで~~
~~引用ここから~~

政府が発行する国債の償還までの期間が急速に短くなっている。2019年度発行分の償還は平均9年後だったが、20年度は6年8カ月後、21年度も6年10カ月後となる計画だ。
短期の資金調達が増えるほど金融市場が混乱した際の影響を受けやすくなる。このため、財務省は期間が長い国債の発行比率を高めてきたが、コロナ禍で転換した。政府の借金急増で、リスクが高い長期国債への需要が限界に近づき、日本銀行が大量購入する短期国債に頼らざるを得なくなったからだ。
国債市場では超低金利が続いており、国債の発行が行き詰まるとは当面考えにくい。だが、日銀が実質的に政府の借金を引き受ける異例の政策は、いつまでも続けられないことを、政府は肝に銘じなければならない。
借金拡大を止めるには、政策経費を税収などでまかなえるかを示す基礎的財政収支を黒字にすることが欠かせない。
内閣府が先週公表した試算によると、今年度の国と地方の基礎的収支の赤字は69兆円。昨年1月の試算から54兆円も膨らんだ。25年度に黒字化する計画の達成は絶望的である。
政府が目標とする実質2%程度という高めの経済成長を続けたとしても、黒字になるのは29年度だ。第2次安倍政権下並みの実質1%程度ならば、試算の最終年度の30年度でも10兆円の赤字が残る。
政府は、歳出と歳入の両面を改革しなければ、黒字化できない現実を直視するべきだ。
菅首相は今国会の施政方針演説で「(人口減社会を迎えるなか)国民に負担をお願いする政策も必要になる。その必要性を国民に説明し、理解してもらわなければならない」と信条を述べた。財政再建ほど、この言葉の重みが問われる課題はない。
コロナ禍のいまは、国民の命や暮らしを守ることが急務で、財政出動を惜しむべき局面ではない。ただ、感染収束後には、財政の立て直しに正面から取り組む必要がある。先送りを防ぐには、感染や景気がどのような状況になれば作業を本格化するのか、一定の目安を設けるよう、あらかじめ議論しておくことが求められる。
きのう衆院で審議入りした今年度3次補正予算案は、緊急事態宣言を前提にしていない。このため観光や飲食などの需要喚起策「Go To」事業に1兆円超が計上されている。いま優先するべきは、逼迫(ひっぱく)する医療機関や収入が減った低所得者への支援であり、予算を早急に組み替えるべきだ。
現実とずれた不要不急の事業を行う余裕などないことを、まず政府は自覚する必要がある。
~~引用ここまで~~
~~引用ここから~~

高い経済成長に期待するだけでは、財政の持続可能性が揺らぐ。政府は新型コロナウイルスの感染拡大で一段と厳しくなった財政の現状を、直視せねばならない。
内閣府は、中長期の新たな財政試算をまとめた。国と地方の基礎的財政収支(PB)は2025年度に7・3兆円の赤字となり、黒字になるのは29年度になると予想している。いずれも、昨年7月時点の試算から変わっていない。
PBは、借金に頼らずに、政策に使う経費を税収などでどれだけ賄えているかを表す指標だ。
政府は、歳出改革に取り組めば、黒字化を3年程度前倒しできると説明し、コロナ禍の前から掲げている「25年度の黒字化」という目標は見直さなかった。
20年度は3度の補正予算で大量の国債を発行するため、PBの赤字額は69・4兆円と、昨年7月時点の予測よりさらに悪化した。黒字化は遠のいたはずなのに、目標を維持するのは理解に苦しむ。
赤字が残るとした試算ですら、高い経済成長率を前提にしたものだ。21年度に物価の影響を除いた実質成長率が4%に回復し、家計の実感に近い名目成長率は4・4%になると見込んでいる。
その後も20年代は、デジタルや環境分野への投資拡大で、3%を上回るバブル期以来の名目成長率が続くと想定した。あまりに楽観的だと言わざるを得ない。
財政再建には経済成長が重要であることに異論はないが、経済の実力を示す日本の潜在成長率は1%弱に低迷したままだ。
政府が、目標維持の根拠とする歳出改革も心もとない。22年からは団塊の世代が75歳以上の後期高齢者になり始め、社会保障費の増加ペースが加速する。
後期高齢者が払う医療費の自己負担割合を22年度中に引き上げるが、抜本改革にはほど遠い。
消費税率の再引き上げは、論議が封印されており、黒字化の道筋は全く見えてこない。
今後も感染症が収束せず、追加の経済対策が必要になる可能性がある。無論、困窮する家庭や企業の救済に万全を期すのは当然で、支出をためらうべきではない。
それでも政府としては、財政の危機的な状況にしっかりと向き合い、信頼性の高い試算を国民に示して、今後の改革への理解を求める責任があるのではないか。
日本の財政悪化はコロナ禍の前から先進国で突出している。甘い見通しを排し、財政健全化のシナリオを描き直してもらいたい。
~~引用ここまで~~
最新の新聞部数を引用して示す。戸別配達制度維持のため新聞各社は押し紙を急速に減らしているようだが、それでもまだ押し紙を含んだ部数なので実際の実売部数はさらに少ない。
「メディア黒書」は毎月必ず新聞部数を出してくれるわけではないのだが、私が知る限り全国紙の部数を毎月無料で出してくれるのはここしかない。それを毎回引用しておけば新聞部数の変化の記録になるので毎回引用しておけば良かった。これからは毎月新聞部数が出る限り記事にしようと思う。
~~引用ここから~~
http://www.kokusyo.jp/oshigami/16006/(メディア黒書)
読売、年間で約60万部の減部数、対前月差はコロナ禍の中でも約1万2500部の増加、2020年11月度のABC部数
2020年11月度のABC部数が明らかになった。それによると読売新聞は年間で約60万部の減部数、朝日新聞は約40万部の減部数となった。毎日新聞は、約26万部の減部数である。
全国の日刊紙の年間減部数は、約226万部である。東京新聞社が5社消えたに等しい。
新聞離れに歯止めはかかっていない。
減部数の原因は、新聞社が残紙(広義の「押し紙」)を減らした結果だと推測される。
折込広告の需要が高ければ残紙が多くても、販売店はある程度まで残紙による損害を相殺できるが、折込広告の受注が少なければ、残紙の損害を相殺できないので、新聞社は残紙を減らさざるを得ない。さもなければ新聞の戸別配達制度そのものが崩壊する。
ちなみに、紙媒体の読者と電子新聞の読者の分離は、ほぼ完了しているとみるのが妥当だ。
2020年11月度(最新)の部数は次の通りである。()内は前年同月差である。
朝日:4,892,411(−407,561)
毎日:2,045,652(−263,999)
読売:7,351,854(−602,272)
日経:2,048,943(−178,941)
産経:1,228,940(−122,302)
なお読売は年間では約60万部の減部数を招いたが、対前月差は約1万2500部の増加となっている。コロナ禍の中でも増加に転じた。
~~引用ここまで~~
~~引用ここから~~
http://www.kokusyo.jp/oshigami/16057/(メディア黒書)
日経新聞が200万部の大台を割る、2020年12月度のABC部数
2020年12月度のABC部数が明らかになった。12月度の特徴としては、日経新聞がはじめて200万部の大台を割ったことである。前回11月度の部数は2,048,943部で、今回12月度は1,993,132となった。年間で約24万部の減部数だった。
他社も部数減の傾向に歯止めはかからず、年間で読売が約60万部の部数減となり、朝日は約42万部の部数減となった。
朝日:4,865,826(-418,887)
毎日:2,032,278(-272,448)
読売:7,303,591(-597,545)
日経:1,993,132(-243,305)
産経:1,221,674(-126,384)
新聞各社は、残紙を整理しない限り販売網が維持できない状況に追い込まれている。しかし、未だに日本新聞協会は、「押し紙」の存在を認めていない。自分たちの非は絶対に認めない姿勢を貫いている。新聞人の資質そのものに問題がある。
「押し紙」政策の非を認めて、販売店に対して過剰請求した新聞代金を返済すべきだろう。また、広告主に対しては、折込広告(自治体の広報紙を含む)の過剰請求分を精算しなければならない。
~~引用ここまで~~
だが基礎的財政収支の黒字化目標がそもそも間違いなのだ。国債償還費を除いた歳出を税収で賄わなければならないという発想が間違っている。インフレさえ起こさなければ国債を発行して何の問題もない。
歳入を増やすということはつまりは増税だ。消費税10%への増税で国民はどれだけ苦しんでいるか。他に社会保険料の引き上げなど負担増は多い。そうでなくとも増税は景気を冷やす。消費税増税を繰り返してきたが、景気が冷え込み税収は思ったほど増えていないのがこの30年ではなかったか。
歳出を減らすことも景気を冷やす。GDPは民間消費、民間投資、政府支出、純輸出で成り立つ。政府支出を減らせば当然GDPは減り景気は悪化する。そのことを理解せず歳出を減らし消費税増税の緊縮財政を強行したのが橋本龍太郎の莫迦総理だ。与謝野馨もマスコミには「政策通」と持ち上げられていたが、経済も財政も何も理解しておらず官房副長官として経済を破綻させた。
それ以降小渕恵三が積極財政で一時的に経済を持ち直したが、財務省の緊縮財政志向をはねのけることができず日本経済はずっと停滞している。
経済停滞から成長軌道に移すには減税か国債発行しかない。何度も繰り返し書いてきたが、それしかないのだ。消費税廃止ないし減税をするにしても歳出の規模は維持しなければ意味がないので廃止ないし減税して税収が減った分は国債発行で補わなければならない。
新聞は偉そうに政府の政策を批判するが、批判する思想が間違っているから滑稽でしかない。政治は妥協のアートだから計算上のそれだけでできるわけではない。だが新聞はそうした苦労を考えず正しさのみで批判する_わけではなく新聞の主張そのものが間違いなのだ。今必要なのは財政再建ではなく国債を大量に発行する積極財政だ。
日露戦争の講和への反対。対米戦争の煽り。共産圏の称賛。新自由主義への賛成。そして財政再建。日本の新聞は常に間違えてきた。新聞の主張通りにしたら大東亜戦争で破滅した。戦後も新聞がこぞって称賛した共産圏は破綻した。その後の新自由主義で経済はボロボロだ。財政再建の主張も経済を縮小する。
だが新聞の社説を批判することは無意味かもしれないとも思っている。国民は誰も読んでいないからだ。まず新聞を購読している世帯が全世帯の半分程度。日本新聞協会が公表した新聞購読世帯率は61%だが、これは押し紙と事業所による購読を含んでいる。それを加味すれば購読世帯は半分を切るだろう。とくに若者は読んでいない。まして社説など。
それでも「日本に財政再建が必要だ。」「基礎的財政収支の黒字化を成し遂げねばならない」と強固に思い込んでいる人達と緊縮財政で利益を得る人達以外には財政再建を主張する新聞社説を批判することで今必要なのは積極財政だと訴えることができるだろう。その意味では意味がある。
社説よりも財政再建を訴える署名記事やコラムを批判した方が効果的かもしれないが、私自身新聞はあまり読んでいないのだ。この3本の社説を読んだのも昨日のことで毎日社説を読んではいない。毎日だらだらネットを巡回してネタを探しているのだが、新聞サイトは産経新聞くらいしか読んでいない。異論を読むことの重要性はわかるのだが。
基礎的財政収支の黒字化目標がまず間違いなのだ。基礎的財政収支の黒字化は意味がないどころか経済を破綻させる。財政赤字は必要なのだ。社説を引用しておく。ひとつひとつ間違いを指摘しないので斜め読みで構わない。
~~引用ここから~~

[社説]財政悪化の現実を直視できないのか
政府が中長期の経済財政試算をまとめた。国と地方の基礎的財政収支(プライマリーバランス=PB)が、早ければ2029年度に黒字に転じるとみている...
日本経済新聞 電子版
政府が中長期の経済財政試算をまとめた。国と地方の基礎的財政収支(プライマリーバランス=PB)が、早ければ2029年度に黒字に転じるとみている。経済成長率などの前提が総じて甘く、信頼に足る試算とは言い難い。
コロナ禍に対応する経済対策などの影響で、PBの赤字は19年度の14.6兆円から、20年度には69.4兆円に膨らむ。その後に年度平均で名目3%超、実質2%超の成長率を維持できれば、29年度に0.3兆円の黒字となる。
この成長率は民間の想定を上回る。しかも昨年7月にまとめた前回の試算より財政が悪化したにもかかわらず、25年度以降のPBの値は同じである。厳しい現実を直視せず、甘い見通しで覆い隠したと批判されても仕方ない。
政府がより慎重に見積もったシナリオでは、29年度も10.3兆円の赤字となる。こちらの方がまだ実情に近いのではないか。
政府は25年度にPBを黒字化する目標をまだ撤回していない。今回の試算で7.3兆円、より慎重なシナリオでは12.6兆円の赤字が残るにもかかわらずである。今後の歳出改革などによって赤字を前倒しで解消できるというが、あまりにも現実離れしていると言わざるを得ない。
コロナの感染がここにきて急速に拡大し、政府は緊急事態宣言の再発動に追い込まれた。日本経済の低迷が長引き、追加の経済対策を迫られる可能性もある。
困窮している個人や企業を、いまはしっかりと支えるべきだ。そのために必要な国・地方の財政出動をためらう時ではない。
だが、政府には財政の窮状を正しく伝える責任もある。コロナ禍がいっこうに収まらず、先を見通すのが困難だとしても、地に足の着いた試算を示して国民や市場の理解を得るべきではないのか。
国・地方の長期債務残高はいまや1200兆円規模に膨らみ、国内総生産(GDP)のほぼ2倍に相当する。日本の財政悪化は主要国の中でもとりわけ深刻で、とても楽観できる状況ではない。
たとえ危機下でも財政に負荷をかけすぎれば、そのツケはいずれ返ってくる。目先の予算措置で規律や節度を守るだけでなく、いずれは本格的な歳入・歳出改革への取り組みも必要になろう。
政府が現実から遊離した試算や目標を掲げたままでは、次の一歩も踏み出せまい。
~~引用ここまで~~
~~引用ここから~~

(社説)財政の悪化 健全化めざすためには:朝日新聞デジタル
政府が発行する国債の償還までの期間が急速に短くなっている。2019年度発行分の償還は平均9年後だったが、20年度は6年8カ月後、21年度も...
朝日新聞デジタル
政府が発行する国債の償還までの期間が急速に短くなっている。2019年度発行分の償還は平均9年後だったが、20年度は6年8カ月後、21年度も6年10カ月後となる計画だ。
短期の資金調達が増えるほど金融市場が混乱した際の影響を受けやすくなる。このため、財務省は期間が長い国債の発行比率を高めてきたが、コロナ禍で転換した。政府の借金急増で、リスクが高い長期国債への需要が限界に近づき、日本銀行が大量購入する短期国債に頼らざるを得なくなったからだ。
国債市場では超低金利が続いており、国債の発行が行き詰まるとは当面考えにくい。だが、日銀が実質的に政府の借金を引き受ける異例の政策は、いつまでも続けられないことを、政府は肝に銘じなければならない。
借金拡大を止めるには、政策経費を税収などでまかなえるかを示す基礎的財政収支を黒字にすることが欠かせない。
内閣府が先週公表した試算によると、今年度の国と地方の基礎的収支の赤字は69兆円。昨年1月の試算から54兆円も膨らんだ。25年度に黒字化する計画の達成は絶望的である。
政府が目標とする実質2%程度という高めの経済成長を続けたとしても、黒字になるのは29年度だ。第2次安倍政権下並みの実質1%程度ならば、試算の最終年度の30年度でも10兆円の赤字が残る。
政府は、歳出と歳入の両面を改革しなければ、黒字化できない現実を直視するべきだ。
菅首相は今国会の施政方針演説で「(人口減社会を迎えるなか)国民に負担をお願いする政策も必要になる。その必要性を国民に説明し、理解してもらわなければならない」と信条を述べた。財政再建ほど、この言葉の重みが問われる課題はない。
コロナ禍のいまは、国民の命や暮らしを守ることが急務で、財政出動を惜しむべき局面ではない。ただ、感染収束後には、財政の立て直しに正面から取り組む必要がある。先送りを防ぐには、感染や景気がどのような状況になれば作業を本格化するのか、一定の目安を設けるよう、あらかじめ議論しておくことが求められる。
きのう衆院で審議入りした今年度3次補正予算案は、緊急事態宣言を前提にしていない。このため観光や飲食などの需要喚起策「Go To」事業に1兆円超が計上されている。いま優先するべきは、逼迫(ひっぱく)する医療機関や収入が減った低所得者への支援であり、予算を早急に組み替えるべきだ。
現実とずれた不要不急の事業を行う余裕などないことを、まず政府は自覚する必要がある。
~~引用ここまで~~
~~引用ここから~~

政府の財政試算 甘い見通しでは信頼が揺らぐ : 社説
高い経済成長に期待するだけでは、財政の持続可能性が揺らぐ。政府は新型コロナウイルスの感染拡大で一段と厳しくなった財政の現状を、直視せねばなら...
読売新聞オンライン
高い経済成長に期待するだけでは、財政の持続可能性が揺らぐ。政府は新型コロナウイルスの感染拡大で一段と厳しくなった財政の現状を、直視せねばならない。
内閣府は、中長期の新たな財政試算をまとめた。国と地方の基礎的財政収支(PB)は2025年度に7・3兆円の赤字となり、黒字になるのは29年度になると予想している。いずれも、昨年7月時点の試算から変わっていない。
PBは、借金に頼らずに、政策に使う経費を税収などでどれだけ賄えているかを表す指標だ。
政府は、歳出改革に取り組めば、黒字化を3年程度前倒しできると説明し、コロナ禍の前から掲げている「25年度の黒字化」という目標は見直さなかった。
20年度は3度の補正予算で大量の国債を発行するため、PBの赤字額は69・4兆円と、昨年7月時点の予測よりさらに悪化した。黒字化は遠のいたはずなのに、目標を維持するのは理解に苦しむ。
赤字が残るとした試算ですら、高い経済成長率を前提にしたものだ。21年度に物価の影響を除いた実質成長率が4%に回復し、家計の実感に近い名目成長率は4・4%になると見込んでいる。
その後も20年代は、デジタルや環境分野への投資拡大で、3%を上回るバブル期以来の名目成長率が続くと想定した。あまりに楽観的だと言わざるを得ない。
財政再建には経済成長が重要であることに異論はないが、経済の実力を示す日本の潜在成長率は1%弱に低迷したままだ。
政府が、目標維持の根拠とする歳出改革も心もとない。22年からは団塊の世代が75歳以上の後期高齢者になり始め、社会保障費の増加ペースが加速する。
後期高齢者が払う医療費の自己負担割合を22年度中に引き上げるが、抜本改革にはほど遠い。
消費税率の再引き上げは、論議が封印されており、黒字化の道筋は全く見えてこない。
今後も感染症が収束せず、追加の経済対策が必要になる可能性がある。無論、困窮する家庭や企業の救済に万全を期すのは当然で、支出をためらうべきではない。
それでも政府としては、財政の危機的な状況にしっかりと向き合い、信頼性の高い試算を国民に示して、今後の改革への理解を求める責任があるのではないか。
日本の財政悪化はコロナ禍の前から先進国で突出している。甘い見通しを排し、財政健全化のシナリオを描き直してもらいたい。
~~引用ここまで~~
最新の新聞部数を引用して示す。戸別配達制度維持のため新聞各社は押し紙を急速に減らしているようだが、それでもまだ押し紙を含んだ部数なので実際の実売部数はさらに少ない。
「メディア黒書」は毎月必ず新聞部数を出してくれるわけではないのだが、私が知る限り全国紙の部数を毎月無料で出してくれるのはここしかない。それを毎回引用しておけば新聞部数の変化の記録になるので毎回引用しておけば良かった。これからは毎月新聞部数が出る限り記事にしようと思う。
~~引用ここから~~
http://www.kokusyo.jp/oshigami/16006/(メディア黒書)
読売、年間で約60万部の減部数、対前月差はコロナ禍の中でも約1万2500部の増加、2020年11月度のABC部数
2020年11月度のABC部数が明らかになった。それによると読売新聞は年間で約60万部の減部数、朝日新聞は約40万部の減部数となった。毎日新聞は、約26万部の減部数である。
全国の日刊紙の年間減部数は、約226万部である。東京新聞社が5社消えたに等しい。
新聞離れに歯止めはかかっていない。
減部数の原因は、新聞社が残紙(広義の「押し紙」)を減らした結果だと推測される。
折込広告の需要が高ければ残紙が多くても、販売店はある程度まで残紙による損害を相殺できるが、折込広告の受注が少なければ、残紙の損害を相殺できないので、新聞社は残紙を減らさざるを得ない。さもなければ新聞の戸別配達制度そのものが崩壊する。
ちなみに、紙媒体の読者と電子新聞の読者の分離は、ほぼ完了しているとみるのが妥当だ。
2020年11月度(最新)の部数は次の通りである。()内は前年同月差である。
朝日:4,892,411(−407,561)
毎日:2,045,652(−263,999)
読売:7,351,854(−602,272)
日経:2,048,943(−178,941)
産経:1,228,940(−122,302)
なお読売は年間では約60万部の減部数を招いたが、対前月差は約1万2500部の増加となっている。コロナ禍の中でも増加に転じた。
~~引用ここまで~~
~~引用ここから~~
http://www.kokusyo.jp/oshigami/16057/(メディア黒書)
日経新聞が200万部の大台を割る、2020年12月度のABC部数
2020年12月度のABC部数が明らかになった。12月度の特徴としては、日経新聞がはじめて200万部の大台を割ったことである。前回11月度の部数は2,048,943部で、今回12月度は1,993,132となった。年間で約24万部の減部数だった。
他社も部数減の傾向に歯止めはかからず、年間で読売が約60万部の部数減となり、朝日は約42万部の部数減となった。
朝日:4,865,826(-418,887)
毎日:2,032,278(-272,448)
読売:7,303,591(-597,545)
日経:1,993,132(-243,305)
産経:1,221,674(-126,384)
新聞各社は、残紙を整理しない限り販売網が維持できない状況に追い込まれている。しかし、未だに日本新聞協会は、「押し紙」の存在を認めていない。自分たちの非は絶対に認めない姿勢を貫いている。新聞人の資質そのものに問題がある。
「押し紙」政策の非を認めて、販売店に対して過剰請求した新聞代金を返済すべきだろう。また、広告主に対しては、折込広告(自治体の広報紙を含む)の過剰請求分を精算しなければならない。
~~引用ここまで~~












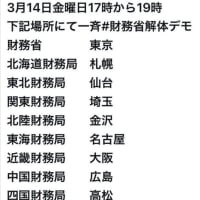

















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます