私は自身を保守派と評価しているが、欧米で言うところの極右やポピュリストに近いかもしれない。国家観や歴史観では保守派の中でも右の部類だろうが、経済的には左派なのだ。
大企業や富裕層から税を多く取り、大衆に再分配すべきだと考えている。そのような思想は極右ないしポピュリストと評されるからだ。
大企業や富裕層の代弁者であるマスコミにレッテルを貼られる存在でもある。彼らには都合が悪いのだ。
だから投票する際自分の思想に近い政党がなくて投票先にはいつも悩む。「古き良き自民党」がもう少し安全保障政策に積極的になった存在が私の理想だ。
今の自民党はグローバリスト政党に変貌してしまい、財界や外資、富裕層の利益しか代表していない。それでいて米国や支那には媚びている。腐りきってしまったのだ。
だから中曽根康弘死去で書いたように、国鉄分割民営化には反対で英国労働党の公約のように、鉄道、郵便、水道、エネルギー産業(電気、ガス、原子力他)を国有化すべきだと考えている。
英国の水道はサッチャーに民営化されたがろくなことがない。だが、日本の水道はだいぶ民間委託が進んでいるとはいえまだ「公営」だ。「国有化」して「国営日本水道公社」を設立する必要はない。民営化を止めれば良いのだ。小さな自治体は水道を広域化する必要はあるかもしれない。
~~引用ここから~~
宮城県、水道運営民間委託で条例案 全国初、22年度導入へ 2019年11月25日(時事通信)
宮城県の村井嘉浩知事は25日、上下水道事業の運営権を民間に委ねる全国初の「コンセッション方式」の導入に向けた条例改正案を、同日開会の11月県議会に提出した。閉会日の12月17日に採決される予定。
上水道へのコンセッション方式導入は、10月施行の改正水道法に基づき可能となった。県は、人口減少や施設老朽化で水道事業の収益が悪化することを踏まえ、上水道、工業用水道、下水道の3事業を官民連携で一体的に運営する「みやぎ型管理運営方式」を打ち出し、2022年度の導入を目指している。
実現すれば3事業について、今後20年間の総事業費の約7%に相当する247億円を削減できるという。条例改正案では、水道事業の運営権を受託する民間事業者の選定手続きや業務の範囲などに関する項目を盛り込んだ。
~~引用ここまで~~
宮城県の水道が民営化されようとしている。村井嘉浩宮城県知事が筋金入りの新自由主義者だからだ。前任の浅野史郎といい宮城県は知事に恵まれない。県民自らが選んだせいではあるが、地方選挙は実質選択肢がないのだ。
宮城県議会が「水道民営化」条例を否決すると良いのだが。宮城県議会、与野党問わず宮城県議に働き掛けたい。
中曽根康弘の業績とされる「国鉄分割民営化」だが、実質は地方切り捨てだった。北海道は不採算路線の廃止が相次いで酷いことになっている。

当時の「国鉄分割民営化」反対派の理屈だ。裏取りはしていないが、不採算路線の廃止で北海道全土にあった路線が、ほとんど次のように減ってしまったそうだ。

第44回衆議院議員総選挙(ウィキペディア)を参照して欲しいが、平成17年のいわゆる「郵政選挙」手では自民党が大勝したが、北海道の12の小選挙区のうち4選挙区でしか勝てなかった。
あの自民党に大変な追い風が吹いているなかでだ。北海道民は中曽根康弘の「国鉄分割民営化」をはじめとして自民党による北海道切り捨てに反発していたことがわかる。
しかしせっかく政権交代した民主党も「コンクリートから人へ」と称してさらに公共事業を減らしてしまった。北海道民は自民党の方がまだマシだと考えるようになってしまった。
平成21年の第45回衆議院議員総選挙(ウィキペディア)。いわゆる「政権交代」選挙では民主党が北海道の12の小選挙区のうち10の小選挙区で勝利している。中川昭一が比例でも落選してしまい、失意のうちに死んでしまったのは日本に取って損失だった。中川昭一が生きていれば安倍晋三の再登板はなく、中川昭一が内閣総理大臣になっていたのではあるまいか。
平成24年の第46回衆議院議員総選挙(ウィキペディア)。いわゆる「政権再交代」選挙では12ある小選挙区のうち11の小選挙区で自民党が勝利し、残るひとつの小選挙区も公明党の議席になっている。民主党は全滅だ。民主党政権がどれだけ失望を買ったかわかろうというものだ。また投票率も低かった。国民が政治に失望しているのだ。
「郵政民営化」で小泉純一郎と竹中平蔵は薔薇色の未来を約束した。しかしよくなったことはひとつもない。郵政民営化の末路、かんぽ生命の不正どこまで続く泥濘ぞに書いたように「郵便局」ブランドを悪用して高齢者を騙してばかりだ。竹中平蔵の「お友達」である高橋洋一はなんとか「郵政民営化」を正当化しようとしているが無理がある。郵便局は国営に戻すべきなのだ。
電力会社もそうだ。千葉県の大規模停電について思うことでも書いたが、電気は電力会社10社による寡占状態だった。絶対に食いっぱぐれることのない、倒産することのない民間企業として繁栄してきた。自民党に個人献金を装った企業献金もしてきた。
倒産することのない民間企業なのだから国有化して「日本電力公社」を設立すべきであろう。公共料金は税金のようなものなのだから國が責任を持つべきなのだ。災害時に復旧を民間企業に委ねることは無責任だ。
安倍晋三は「電力自由化」をしたが、大口の利用者むしろ電力会社10社に回帰しているという。電力会社の国有化に何の問題もない。
新聞社のように東京を司令塔にしておきながら、電力会社10社が本社を置いていた地域にも本社機能を持たせ地方にも配慮する。それで規模のメリットの享受もできる。
原子力部門は「日本原子力発電株式会社」をこれまた国有化して國の責任で原子力政策を進めるべきだ。
原子力は危険なものだが、資源がない日本に原子力は欠かせない。また原子力発電所を設立する際の用地買収も「民間企業」には荷が勝ちすぎる。暴力団や解放同盟が群がってくるのだ。警察官、検察官、自衛官を天下りさせ、彼らに「反社勢力」を排除させる必要がある。関西電力の「収賄」。
東日本大震災で東京電力が実質的に破綻した際民主党政権も後を継いだ自民党政権も東京電力を国有化しなかった。国有化して株主と債権者に責任を取らせるべきだったのにそれを怠った。資本主義国家にあるまじきことだ。
日本は「上に行けば行くほど無責任になる」とはネットで拾った言葉だが、その通りだろう。この言葉には続きがあり、「下に行けば行くほど自己責任になる」だ。全く我が国のことながら嫌になる。
だから国民が政治に関心を持ち、権力者を見張らねばならないのだ。
現在の新自由主義、グローバリズムとは真逆だが、鉄道、郵便、水道、エネルギー産業の国有化を行い、大企業及び富裕層から税を多く取り大衆に再分配する大きな政府を志向したい。
カテゴリー変更。
大企業や富裕層から税を多く取り、大衆に再分配すべきだと考えている。そのような思想は極右ないしポピュリストと評されるからだ。
大企業や富裕層の代弁者であるマスコミにレッテルを貼られる存在でもある。彼らには都合が悪いのだ。
だから投票する際自分の思想に近い政党がなくて投票先にはいつも悩む。「古き良き自民党」がもう少し安全保障政策に積極的になった存在が私の理想だ。
今の自民党はグローバリスト政党に変貌してしまい、財界や外資、富裕層の利益しか代表していない。それでいて米国や支那には媚びている。腐りきってしまったのだ。
だから中曽根康弘死去で書いたように、国鉄分割民営化には反対で英国労働党の公約のように、鉄道、郵便、水道、エネルギー産業(電気、ガス、原子力他)を国有化すべきだと考えている。
英国の水道はサッチャーに民営化されたがろくなことがない。だが、日本の水道はだいぶ民間委託が進んでいるとはいえまだ「公営」だ。「国有化」して「国営日本水道公社」を設立する必要はない。民営化を止めれば良いのだ。小さな自治体は水道を広域化する必要はあるかもしれない。
~~引用ここから~~
宮城県、水道運営民間委託で条例案 全国初、22年度導入へ 2019年11月25日(時事通信)
宮城県の村井嘉浩知事は25日、上下水道事業の運営権を民間に委ねる全国初の「コンセッション方式」の導入に向けた条例改正案を、同日開会の11月県議会に提出した。閉会日の12月17日に採決される予定。
上水道へのコンセッション方式導入は、10月施行の改正水道法に基づき可能となった。県は、人口減少や施設老朽化で水道事業の収益が悪化することを踏まえ、上水道、工業用水道、下水道の3事業を官民連携で一体的に運営する「みやぎ型管理運営方式」を打ち出し、2022年度の導入を目指している。
実現すれば3事業について、今後20年間の総事業費の約7%に相当する247億円を削減できるという。条例改正案では、水道事業の運営権を受託する民間事業者の選定手続きや業務の範囲などに関する項目を盛り込んだ。
~~引用ここまで~~
宮城県の水道が民営化されようとしている。村井嘉浩宮城県知事が筋金入りの新自由主義者だからだ。前任の浅野史郎といい宮城県は知事に恵まれない。県民自らが選んだせいではあるが、地方選挙は実質選択肢がないのだ。
宮城県議会が「水道民営化」条例を否決すると良いのだが。宮城県議会、与野党問わず宮城県議に働き掛けたい。
中曽根康弘の業績とされる「国鉄分割民営化」だが、実質は地方切り捨てだった。北海道は不採算路線の廃止が相次いで酷いことになっている。

当時の「国鉄分割民営化」反対派の理屈だ。裏取りはしていないが、不採算路線の廃止で北海道全土にあった路線が、ほとんど次のように減ってしまったそうだ。

第44回衆議院議員総選挙(ウィキペディア)を参照して欲しいが、平成17年のいわゆる「郵政選挙」手では自民党が大勝したが、北海道の12の小選挙区のうち4選挙区でしか勝てなかった。
あの自民党に大変な追い風が吹いているなかでだ。北海道民は中曽根康弘の「国鉄分割民営化」をはじめとして自民党による北海道切り捨てに反発していたことがわかる。
しかしせっかく政権交代した民主党も「コンクリートから人へ」と称してさらに公共事業を減らしてしまった。北海道民は自民党の方がまだマシだと考えるようになってしまった。
平成21年の第45回衆議院議員総選挙(ウィキペディア)。いわゆる「政権交代」選挙では民主党が北海道の12の小選挙区のうち10の小選挙区で勝利している。中川昭一が比例でも落選してしまい、失意のうちに死んでしまったのは日本に取って損失だった。中川昭一が生きていれば安倍晋三の再登板はなく、中川昭一が内閣総理大臣になっていたのではあるまいか。
平成24年の第46回衆議院議員総選挙(ウィキペディア)。いわゆる「政権再交代」選挙では12ある小選挙区のうち11の小選挙区で自民党が勝利し、残るひとつの小選挙区も公明党の議席になっている。民主党は全滅だ。民主党政権がどれだけ失望を買ったかわかろうというものだ。また投票率も低かった。国民が政治に失望しているのだ。
「郵政民営化」で小泉純一郎と竹中平蔵は薔薇色の未来を約束した。しかしよくなったことはひとつもない。郵政民営化の末路、かんぽ生命の不正どこまで続く泥濘ぞに書いたように「郵便局」ブランドを悪用して高齢者を騙してばかりだ。竹中平蔵の「お友達」である高橋洋一はなんとか「郵政民営化」を正当化しようとしているが無理がある。郵便局は国営に戻すべきなのだ。
電力会社もそうだ。千葉県の大規模停電について思うことでも書いたが、電気は電力会社10社による寡占状態だった。絶対に食いっぱぐれることのない、倒産することのない民間企業として繁栄してきた。自民党に個人献金を装った企業献金もしてきた。
倒産することのない民間企業なのだから国有化して「日本電力公社」を設立すべきであろう。公共料金は税金のようなものなのだから國が責任を持つべきなのだ。災害時に復旧を民間企業に委ねることは無責任だ。
安倍晋三は「電力自由化」をしたが、大口の利用者むしろ電力会社10社に回帰しているという。電力会社の国有化に何の問題もない。
新聞社のように東京を司令塔にしておきながら、電力会社10社が本社を置いていた地域にも本社機能を持たせ地方にも配慮する。それで規模のメリットの享受もできる。
原子力部門は「日本原子力発電株式会社」をこれまた国有化して國の責任で原子力政策を進めるべきだ。
原子力は危険なものだが、資源がない日本に原子力は欠かせない。また原子力発電所を設立する際の用地買収も「民間企業」には荷が勝ちすぎる。暴力団や解放同盟が群がってくるのだ。警察官、検察官、自衛官を天下りさせ、彼らに「反社勢力」を排除させる必要がある。関西電力の「収賄」。
東日本大震災で東京電力が実質的に破綻した際民主党政権も後を継いだ自民党政権も東京電力を国有化しなかった。国有化して株主と債権者に責任を取らせるべきだったのにそれを怠った。資本主義国家にあるまじきことだ。
日本は「上に行けば行くほど無責任になる」とはネットで拾った言葉だが、その通りだろう。この言葉には続きがあり、「下に行けば行くほど自己責任になる」だ。全く我が国のことながら嫌になる。
だから国民が政治に関心を持ち、権力者を見張らねばならないのだ。
現在の新自由主義、グローバリズムとは真逆だが、鉄道、郵便、水道、エネルギー産業の国有化を行い、大企業及び富裕層から税を多く取り大衆に再分配する大きな政府を志向したい。
カテゴリー変更。












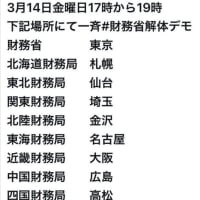
















経済に関して仰っておられたところが共感できました。
さして詳しい訳ではないのでご容赦願いたいのですが、国鉄民営化についてご教授願いたく思います。
私個人としてはNTTとこれは正解だったと思うのです。
それは、自動車交通網が発達した時代背景や運賃設定がままならぬ状態や人員の整理が出来ない現況では早晩多くの赤字路線は閉鎖されていたであろうし、何よりも黒字にもっていくことは困難だったのではないかと思うからです。
良く西日本の事故を例に挙げて批判される方が居ますがそれは国鉄時代から続く日勤教育が遠因だと思いますし、事故調ではたしかダイヤが原因だとははっきり書いていなかったと思うのです。
それに国鉄時代が安全だったかと言えば多くの事故がそれを否定しています。
業界或いは会社のある時期には必ずこの手の問題は出てくるものだと思いますが、それを乗り越えた先にこそ安全やサービス向上、そしてご褒美として黒字が待っているのだと思うのです。
民営化は確かに弊害がありますが、それそのものが害悪だとは思えないのです。(因みに郵政はクソだと思います。)
国鉄は確かに「働かない労働組合」が問題でした。国鉄を国営のまま地道に「働かない労働組合」に対処すべきだったと考えていますが、荒療治としてはあり得たかもしれません。
しかしたとえば郵便局は全国一律同じ値段で葉書や郵便物を送ることができる。それは国営だからです。遠方や離島、山間部などに送ることには多くの金が必要なのは言うまでもないでしょう。
近距離郵便や交通網が発達している都会へ運ぶことで黒字を上げて、その黒字で過疎地へ送る赤字になるサービスを維持するのです。
民間であれば離島や山間部へ配送する宅配便は割り増し料金を取られるでしょう。
まあ郵便局の場合は金融で郵政分野の赤字を補っていたのだと思いますが。
国鉄も同じです。莫大な利益を上げている、JR東日本、JR東海、JR西日本の黒字で、独立採算ではどうしても赤字になってしまうJR北海道、JR四国といった地方の路線を維持するのです。
都会の人間からすれば、
「俺達が高い料金を支払わされているのは田舎の赤字を補填するためだ。馬鹿馬鹿しい。」
そう考えても仕方ないところはあります。
しかしここで立ち止まってよく考えて欲しいのです。日本は狭い國だと言われます。その狭い日本で田舎の過疎地を人が住めないような限界集落にするのは問題がありませんか。
たとえば日本は島国ですから、国境離島に住んでいる人間は隣国との国境に住んでいます。離島では生活が成り立たなくなればみんな首都圏や関西圏、東海地方に移住してしまうでしょう。
そうなれば「対馬」は韓国に乗っ取られますし、「北海道」はロシアに、沖縄県ないし尖閣諸島(尖閣諸島は無人島ですが)は支那に奪われてしまいます。
山間部も同じです。誰かが住んで山の手入れをしない限り山は荒れていく一方です。人里と山の境界が曖昧になれば熊が住宅地に頻繁に出没するようになるかもしれません。山は海と繋がっていますから、漁業にも影響が出るでしょう。保水能力が落ちれば台風や豪雨の際被害が酷くなるかもしれません。地山治水は欠かせません。
政府が地方交付税交付金で田舎の自治体に東京などから多く徴収した税金を再分配しているのはそのためです。都会と田舎の国民は共栄共存の関係にあるのです。
企業が労働者に給与を支払い、その給与で企業の財とサービスを購入する。企業と労働者も共存共栄の関係にあります。労働者に支払う給与を減らせば一時的に企業は栄えますが労働者の消費が減り、企業の売り上げも減り、共倒れになります。
これはマクロ経済から見た視点ですから、ブラック企業などは労働者を酷使して儲けている面はあるでしょう。そこは労働組合や労働基準監督署あるいは裁判所の出番です。
小泉純一郎が三位一体改革と称して地方交付税交付金を減らしてしまいました。公共事業もです。これでは田舎では生活できません。東京の超一極集中が進んでいるのはこのためです。
一時的に東京は益々栄えるかもしれません。しかし田舎が衰退すれば、東京も遠くない将来衰退してしまうでしょう。
田舎でもなんとか暮らしていけるようにするには最低限のインフラが必要です。国鉄で言えば都会の「黒字路線」から補填して「赤字路線」を維持してやらなくてならないのです。地方交付税交付金や公共事業も同じことです。
そしてそうして田舎の集落を維持してやることが、國全体としては安く上がるのです。
そのため不採算路線、赤字路線を廃止する国鉄分割民営化はすべきではなかった。そう考えます。