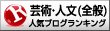「先生、神無月は今日で終わりだよ」と、若草山の鹿ではなく、濃い紫地の塩瀬の帯の鹿が、私に語りかける。
遠山に一もとの紅葉。「もみじ踏みわけ啼く鹿の…」古歌を思い起こす二頭の鹿が描かれたこの帯は、海老茶の小紋に合わせて、よく、11月の顔見世観劇の際に締めていたものだが、今年は出番がなかった。
もう3年ほど前になるだろうか。万城目学の『鹿男あをによし』がテレビドラマ化されて、新作の小説は、前世紀末に出現した『くっすん大黒』などの町田康以降、全然読んでいなかった私が、一挙に万城目ワールドに惹かれ、『鴨川ホルモー』が映画化されたころには、寡作の万城目作品を全部読み尽くしてしまった。
爆笑、やがて悲しき…という感じでもない、人情の機微をすくい上げた泣き笑いが同居する、何ともいえずチャーミングな世界が、読む者の心をとらえる。
万城目も町田も大阪の人間だ。
そういえば、もう十数年以前の三十代前半のころ、大正から昭和初期の小説をむさぼるように読んでいたとき、上司小剣や水上滝太郎の、大阪を舞台にした小説がとても面白かった。
ちょうどそのころ、大阪出身の友人が結婚することになり、ご実家に戻ることになった。彼女は私のようなデラシネとは全く違う、たしかご両親とも大阪に本社がある財閥系会社の勤め人で、ご両親の本家は船場にあるという話だった。
船場……。いかな世間知らずの私でも、その地名は、大谷崎の『細雪』や、花登筐の浪花商人ど根性もののテレビドラマ群で、子どものころからよく知っている。
ことさら他人に対して詮索癖の無い私は、詳しいことは聴かずじまいだったが、幼少のころ彼女は、学校から帰ると、きものに着替えて近所の友達と遊んでいたらしい。
思えば、私が日々着物を着て暮らす生活に強い憧憬の念を抱いたきっかけというのは、子どものころから茶の間に常にあった、そういうベタな時代劇からではなかった。
高校生のころ、幕末の志士に憧れて、月代を長く伸ばしたざんばらの着流し姿の浪人者のイラストを数多く手すさびに描いたりもしていたが、なんといってもその直接的銃爪は、学生時代に観た大林宣彦監督の『ねらわれた学園』だったのである。
たしか、主役の薬師丸ひろ子が、学校から帰宅すると制服から着物に着替えて生活していたという設定だった。それがなぜか、十代終わりの私の心に強く刻みつけられたのだ。
…これだ! この方法なら、半農半漁ならぬ、半洋半邦生活が実践できるはずだ!!

余談はさておき、そんなわけで彼女は、大阪に帰る前に江戸をよく見ておきたい、ということで、私にいろいろ案内してもらえないか、と言うのだった。
昭和60年ごろから一人で歴史散策をしてきたから、腕(?)に覚えのある私はとても嬉しかった。
そんなわけで、平成ひとケタの都下を、数回に分けて、休日のたび、案内した。そして一人ではあまり行かない、老舗の鍋料理などを出す店へも、何軒か訪れた。
ある日、上野から谷根千界隈を歩いていたときのことである。
上野の広小路の裏のほう、ほとんど池之端に近いあたりに、とり栄という鳥鍋屋があった。今でも存続しているだろうか。
まだ本牧亭があったころだったか、当時仲良くして下さった噺家さんに連れられて伺ったことがあって、そのときの美味しさと、店先に柳が植わっている一軒家の風情が忘れられず、ぜひとも彼女にも味わってほしいと思った。
しかし、予約が取れないので有名な店であった。私はドキドキしながら、アメ横の路地の商家の軒先のピンク色の公衆電話(まだ携帯など普及していない、緊急連絡はポケベルを鳴らしていた時代だった)で、電話をかけてみた。
すると、なんと奇跡的なことに、今夜はまったく差し支えなく、おいで下さい、ということなのだった。
私は雀躍して、彼女を案内した。ぎしぎしと階段を鳴らしながら二階の座敷へ上がった。
炭のよく熾った匂い、円形の鍋から淡くのぼり立つ白い湯気。
つやつやと輝くかしわ肉。そしてまた、みずみずしく円柱形に切られた白い長葱。
うっとりとしている私に、彼女は遠慮がちに告げた。
「ごめんなさい、私、白いネギ、食べられないんです」
ええぇぇえっっつ!!
そういえば、常日頃、蕎麦屋で黒いつゆがどうしても不気味で食べられないと言っていたことがあった。
そりゃー、可哀想なことをした…。この鳥鍋は白いネギだからこそ、オイシイのだ。
そしてまた切ないことに、本当に鶏肉と白ネギだけの、東京の下町式の鍋なのだった。
その時ハッと、京都出身の別の知人のことを想い出した。たしか彼女も関東へ来て初めて白いネギが食用とされてある、というのを知って驚愕した、と話していた。
関西ではネギは青いのだ。
せめて鶏肉をたっぷり食べてね…と、私は彼女のほうへカシワを寄せた。
行儀のいい彼女は、湯気の向こうでにっこりほほ笑んだ。
もう十数年前のことになるが、鍋の美味しい季節になると、白い湯気に目をぱちぱちさせながら想い出す、ちょっと心の痛む関東者の話である。
遠山に一もとの紅葉。「もみじ踏みわけ啼く鹿の…」古歌を思い起こす二頭の鹿が描かれたこの帯は、海老茶の小紋に合わせて、よく、11月の顔見世観劇の際に締めていたものだが、今年は出番がなかった。
もう3年ほど前になるだろうか。万城目学の『鹿男あをによし』がテレビドラマ化されて、新作の小説は、前世紀末に出現した『くっすん大黒』などの町田康以降、全然読んでいなかった私が、一挙に万城目ワールドに惹かれ、『鴨川ホルモー』が映画化されたころには、寡作の万城目作品を全部読み尽くしてしまった。
爆笑、やがて悲しき…という感じでもない、人情の機微をすくい上げた泣き笑いが同居する、何ともいえずチャーミングな世界が、読む者の心をとらえる。
万城目も町田も大阪の人間だ。
そういえば、もう十数年以前の三十代前半のころ、大正から昭和初期の小説をむさぼるように読んでいたとき、上司小剣や水上滝太郎の、大阪を舞台にした小説がとても面白かった。
ちょうどそのころ、大阪出身の友人が結婚することになり、ご実家に戻ることになった。彼女は私のようなデラシネとは全く違う、たしかご両親とも大阪に本社がある財閥系会社の勤め人で、ご両親の本家は船場にあるという話だった。
船場……。いかな世間知らずの私でも、その地名は、大谷崎の『細雪』や、花登筐の浪花商人ど根性もののテレビドラマ群で、子どものころからよく知っている。
ことさら他人に対して詮索癖の無い私は、詳しいことは聴かずじまいだったが、幼少のころ彼女は、学校から帰ると、きものに着替えて近所の友達と遊んでいたらしい。
思えば、私が日々着物を着て暮らす生活に強い憧憬の念を抱いたきっかけというのは、子どものころから茶の間に常にあった、そういうベタな時代劇からではなかった。
高校生のころ、幕末の志士に憧れて、月代を長く伸ばしたざんばらの着流し姿の浪人者のイラストを数多く手すさびに描いたりもしていたが、なんといってもその直接的銃爪は、学生時代に観た大林宣彦監督の『ねらわれた学園』だったのである。
たしか、主役の薬師丸ひろ子が、学校から帰宅すると制服から着物に着替えて生活していたという設定だった。それがなぜか、十代終わりの私の心に強く刻みつけられたのだ。
…これだ! この方法なら、半農半漁ならぬ、半洋半邦生活が実践できるはずだ!!

余談はさておき、そんなわけで彼女は、大阪に帰る前に江戸をよく見ておきたい、ということで、私にいろいろ案内してもらえないか、と言うのだった。
昭和60年ごろから一人で歴史散策をしてきたから、腕(?)に覚えのある私はとても嬉しかった。
そんなわけで、平成ひとケタの都下を、数回に分けて、休日のたび、案内した。そして一人ではあまり行かない、老舗の鍋料理などを出す店へも、何軒か訪れた。
ある日、上野から谷根千界隈を歩いていたときのことである。
上野の広小路の裏のほう、ほとんど池之端に近いあたりに、とり栄という鳥鍋屋があった。今でも存続しているだろうか。
まだ本牧亭があったころだったか、当時仲良くして下さった噺家さんに連れられて伺ったことがあって、そのときの美味しさと、店先に柳が植わっている一軒家の風情が忘れられず、ぜひとも彼女にも味わってほしいと思った。
しかし、予約が取れないので有名な店であった。私はドキドキしながら、アメ横の路地の商家の軒先のピンク色の公衆電話(まだ携帯など普及していない、緊急連絡はポケベルを鳴らしていた時代だった)で、電話をかけてみた。
すると、なんと奇跡的なことに、今夜はまったく差し支えなく、おいで下さい、ということなのだった。
私は雀躍して、彼女を案内した。ぎしぎしと階段を鳴らしながら二階の座敷へ上がった。
炭のよく熾った匂い、円形の鍋から淡くのぼり立つ白い湯気。
つやつやと輝くかしわ肉。そしてまた、みずみずしく円柱形に切られた白い長葱。
うっとりとしている私に、彼女は遠慮がちに告げた。
「ごめんなさい、私、白いネギ、食べられないんです」
ええぇぇえっっつ!!
そういえば、常日頃、蕎麦屋で黒いつゆがどうしても不気味で食べられないと言っていたことがあった。
そりゃー、可哀想なことをした…。この鳥鍋は白いネギだからこそ、オイシイのだ。
そしてまた切ないことに、本当に鶏肉と白ネギだけの、東京の下町式の鍋なのだった。
その時ハッと、京都出身の別の知人のことを想い出した。たしか彼女も関東へ来て初めて白いネギが食用とされてある、というのを知って驚愕した、と話していた。
関西ではネギは青いのだ。
せめて鶏肉をたっぷり食べてね…と、私は彼女のほうへカシワを寄せた。
行儀のいい彼女は、湯気の向こうでにっこりほほ笑んだ。
もう十数年前のことになるが、鍋の美味しい季節になると、白い湯気に目をぱちぱちさせながら想い出す、ちょっと心の痛む関東者の話である。