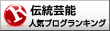♪ひびや あかがり かかとや脛に…(ご存知、長唄『供奴(ともやっこ)』!!)
手の甲の中指の付け根(拳を握ると一番尖がる部分ですね)が、なんだか痛いなぁ…と思っていたら、なんと、ひびのような、あかがり(皸=あかぎれのことですね)のようなものが出来ていた。
踵やすねでなくともできるんですねぇ…
ぁぁびっくり。平成31年の初春の乾燥たるや半端なかった。
わが愛用の特効薬、三宝製薬のトフメルA軟膏をすかさず塗りました。
朝一番、月一回の母の診察後、久しぶりに公園を突っ切って帰ろうと、井の頭七井橋へ立ち出ずる。
冬枯れの汀の眺めは、これまた何とも言えぬ風情があります。
とはいえ…水際立つ、とは人の形容なれども、実際のところ寒中の池の畔りは寒すぎて、立ち止まって暫し、逆しまの樹影の面白さ、水鳥のきびきびした潜りっぷり、波紋の行方など、愉しむには厳しいもの。
お茶の水の井戸の滔々たる水量に、ここは以前、毎朝、井戸端を箒で掃き清めてくれる寒山拾得なおばちゃんがいたんだよなぁ…と時の移るを悲しく思いながら、武蔵野の雑木林を見え隠れする家への近道も…
先だって整備された折、除草剤が撒かれたのか下草の藪もなくなってしまった。夏にはオシロイバナが群れて咲いて、素敵な日陰の小径だったのだけれども…
と、いつになく枯野の寂しい心地を宿しながら、公園から通りに至る、これまた昭和のころから大分すり減り細石の趣きさえ生じた段々を登ったら…白き囲いのとも移り、と、プチ替え歌したくなるような、可憐な水仙がひともと、咲いておりました。

端然として清々しい。
水仙といえば、ミュシャの絵にナルキソスを含んだのか鼻がツンと上を向いたポーズをとる艶やかに美しい女性(ニョショウ)を描いたものがありまして、20代のころ、その絵葉書を後生大事に持っておりました。
年ふるとスタイリッシュな美の極致に食指が動かなくなるのは、人間の嗜好の不思議というものでしょうか、遠い目で懐かしく想い出します。
しかし今朝は、この水仙花の印象から、さらにもっと遠い記憶の、八重咲スイセンを想い出したのです。
…岩波子どもの本の中の一冊。もう50年も前に読んだお話です。
猩紅熱にかかった坊やのぬいぐるみが、庭先で焼却されてしまうことに…。
そこへ現れたのが、ツムラ順天堂の中将姫のように、裳裾をたなびかせ、黄色い水仙の花芯の口からついと出てきたかのごとく空中浮遊する仙女。その挿絵が、脳裏に浮かんだのでした。
そのストーリーの顛末も忘却の彼方で、毅然としてぬいぐるみたちに残酷な運命を申し渡したのか、彼らの状況に寄り添い、何らかの手当てを講じて去っていったスーパーウーマンな妖精だったのかすら、まったく覚えていないのでしたが…。
木漏れ日の微かな陽だまりの中で、ひっそりと佇むその姿が、遠い日の子どもの心を呼び起こしたのでした。
あまりに気がかりだので、帰宅すると同時にありがたや文明の利器、インターネットで検索してみましたところ、『スザンナのお人形/ビロードうさぎ』であった、ということが判明。
長唄には♪…花の姿や 若衆ぶり…「水仙丹前」という、供奴の女性版ともいうべき賑やかで華やかな踊りがありますけれども、そんなわけで、わが里の花、水仙は、元禄スタイルのあでやかな立方さんの魅力にクラクラする、その丹前舞踊ではなくて、瑞々しくもひっそりと、寒中に咲き誇るイメージだったりもするのです。
この時季、お具合を悪くなさった方々にお見舞いを申し上げます。
よくご養生なさって、くれぐれもお大事に…
手の甲の中指の付け根(拳を握ると一番尖がる部分ですね)が、なんだか痛いなぁ…と思っていたら、なんと、ひびのような、あかがり(皸=あかぎれのことですね)のようなものが出来ていた。
踵やすねでなくともできるんですねぇ…
ぁぁびっくり。平成31年の初春の乾燥たるや半端なかった。
わが愛用の特効薬、三宝製薬のトフメルA軟膏をすかさず塗りました。
朝一番、月一回の母の診察後、久しぶりに公園を突っ切って帰ろうと、井の頭七井橋へ立ち出ずる。
冬枯れの汀の眺めは、これまた何とも言えぬ風情があります。
とはいえ…水際立つ、とは人の形容なれども、実際のところ寒中の池の畔りは寒すぎて、立ち止まって暫し、逆しまの樹影の面白さ、水鳥のきびきびした潜りっぷり、波紋の行方など、愉しむには厳しいもの。
お茶の水の井戸の滔々たる水量に、ここは以前、毎朝、井戸端を箒で掃き清めてくれる寒山拾得なおばちゃんがいたんだよなぁ…と時の移るを悲しく思いながら、武蔵野の雑木林を見え隠れする家への近道も…
先だって整備された折、除草剤が撒かれたのか下草の藪もなくなってしまった。夏にはオシロイバナが群れて咲いて、素敵な日陰の小径だったのだけれども…
と、いつになく枯野の寂しい心地を宿しながら、公園から通りに至る、これまた昭和のころから大分すり減り細石の趣きさえ生じた段々を登ったら…白き囲いのとも移り、と、プチ替え歌したくなるような、可憐な水仙がひともと、咲いておりました。

端然として清々しい。
水仙といえば、ミュシャの絵にナルキソスを含んだのか鼻がツンと上を向いたポーズをとる艶やかに美しい女性(ニョショウ)を描いたものがありまして、20代のころ、その絵葉書を後生大事に持っておりました。
年ふるとスタイリッシュな美の極致に食指が動かなくなるのは、人間の嗜好の不思議というものでしょうか、遠い目で懐かしく想い出します。
しかし今朝は、この水仙花の印象から、さらにもっと遠い記憶の、八重咲スイセンを想い出したのです。
…岩波子どもの本の中の一冊。もう50年も前に読んだお話です。
猩紅熱にかかった坊やのぬいぐるみが、庭先で焼却されてしまうことに…。
そこへ現れたのが、ツムラ順天堂の中将姫のように、裳裾をたなびかせ、黄色い水仙の花芯の口からついと出てきたかのごとく空中浮遊する仙女。その挿絵が、脳裏に浮かんだのでした。
そのストーリーの顛末も忘却の彼方で、毅然としてぬいぐるみたちに残酷な運命を申し渡したのか、彼らの状況に寄り添い、何らかの手当てを講じて去っていったスーパーウーマンな妖精だったのかすら、まったく覚えていないのでしたが…。
木漏れ日の微かな陽だまりの中で、ひっそりと佇むその姿が、遠い日の子どもの心を呼び起こしたのでした。
あまりに気がかりだので、帰宅すると同時にありがたや文明の利器、インターネットで検索してみましたところ、『スザンナのお人形/ビロードうさぎ』であった、ということが判明。
長唄には♪…花の姿や 若衆ぶり…「水仙丹前」という、供奴の女性版ともいうべき賑やかで華やかな踊りがありますけれども、そんなわけで、わが里の花、水仙は、元禄スタイルのあでやかな立方さんの魅力にクラクラする、その丹前舞踊ではなくて、瑞々しくもひっそりと、寒中に咲き誇るイメージだったりもするのです。
この時季、お具合を悪くなさった方々にお見舞いを申し上げます。
よくご養生なさって、くれぐれもお大事に…