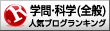中学生のときの芥川龍之介「邪宗門」、長じて谷崎翁「乱菊物語」を、あぁ、これからどうなるのだろう…!!と、激しく胸躍らせてページをめくって、「未完」という活字が、目に飛び込んできたときの、あのたとえようもない、中途半端な虚脱感。
生きている限り「つづき」は「つづき」であり得るが、物故した作家に続編執筆を求めるすべはないのだ。
長唄界で、繰り返し演奏される曲のひとつに「新曲浦島」という、海のさまざまな情景を描いた名曲がある。
坪内逍遥大先生が、日本にも国際社会にアッピールできる新しい演劇が必要である、という新思想のもと、一念発起して、長唄、常磐津、義太夫など、日本の伝統音楽でもって一大叙事詩的楽劇をこしらえた。明治三十九年、西暦にして1906年のことである。
しかし構想が壮大過ぎて、結局、長唄で作曲されたオーバーチュアの部分しか上演できずじまいだったという、未完の大曲。
力強く走る波がしら、夕暮れの凪いだ海面、嵐の轟く情景など、さすが逍遥先生の作詞もすばらしいが、長唄界の名手の手になる作曲も素晴らしい。演奏者も表現する愉しさを存分に味わえる、スペクタクルに満ちた、溌溂とした曲なのだ。
…で、新曲、というからには旧曲があるわけで、日本舞踊好きには実にポピュラーな、おさらい会には必ず誰かが出曲するというような、その名もズバリ「浦島」という珠玉の小品がある。お伽噺の浦島太郎を素材にした舞踊曲だ。
えーなに、浦島太郎の曲って、幼稚園のお遊戯会じゃあるましー、と、呟いた方は、お待ちなさい。長唄に、そんな芸のない曲が残っているわけがない。
これはね、さざ波のような旋律とともに、遙か水平線のかなたから、浦島太郎が艪を漕いで、ドンブラコと、現世に戻ってくるところから始まります。
そして、波打ち際で涙ながらにカニと戯れ、龍宮城での乙姫様との楽しかった日々を、ひとり想い出す。
楊貴妃と玄宗帝の白居易「長恨歌」になぞらえたような、ロマンチックな歌詞で綴るラブソングになっているのですね。
♪袖に梢(こずえ)の移り香が散りて、花や恋しき面影の…忘れかねたる比翼の蝶の、情け比べん仇桜…
旋律も美しく、もう本当に、ため息しか出てこないような、リリカルな叙情性に満ちた世界が、聴く者の感性を揺さぶる。
しかし、この曲もまた(古典であるから古風にメリハリつけずに弾く、という表現方法もあるわけではあるけれども)情感を込めて緩急つけて表現しないと、それが聴く者のハートに伝わらない、そんな曲でもあるのだ。
そして、ひとしきりロマンス懐古シーンが過ぎると、浦島の疑心を表すサスペンスに満ちたメロディが。
……あぁ、玉手箱、開けちゃおっかなー、どうしよっかなー。
どろどろどろん…と白煙が立ち、太郎はたちまちオジイサンになっちゃうのですが、そのあとの旋律が、またカッコイイ!!
この部分を弾くとき、私の眼の前にはいつも、とどろ巻き立つ浪をバックに、虚空を掴むかのように手を前へ突き出し、茫然自失たる浦島の姿が、劇画チックに浮かぶのだ。
もう二度と帰れない。帰って来たけど、帰れない。
山上たつひこの「うらしま」というホラー短編漫画もあったけれど。
かたや文政十一年(西暦1828)の江戸の歌舞伎舞踊、また一方は明治の近代的発想で作曲された、対極にあるようなこの新・旧二つの浦島、実は、両者ともに、ダイナミックな海の魅力を喚起し、演奏者の表現力を発揮できる、愉しい曲なのだ。
もう二度と戻らない…という切ないキーワードを思い描くとき、私は小学生のとき読んだ、安房直子「きつねの窓」という短編童話を想い出す。
あるとき主人公は猟に出かけた山中で、小狐を見かける。彼を追って深く山中に入ると、突如林が開け、桔梗屋という染物屋が目の前に現れる。追っていた小狐が化けているであろうその店の小僧に勧められるままに、両手の人差し指と親指を、桔梗のしぼり汁からつくったという染料で、美しい青紫色に染めてもらう。
その四本の指で菱形の窓をこしらえて覗いてみると、なんでも、自分が逢いたかった人に会えるというのである(もう何十年も前に読んだ話なので、違っているところもあるかもしれない)。
主人公は、もう会うことのできなくなったお母さんの姿を、その指の窓のなかに見出し、雀躍して家に帰るのだが、いつもの習慣で、ついうっかり手を洗ってしまうのだ。
この小説を想い出すたび、似たような切なさを持って私の脳裏に浮かぶのが、有島武郎の「一房の葡萄」。紫色の艶やかなブドウは思い浮かぶけれど、そのブドウをのせていた先生の美しい白い手はもうどこにもない、というような切ない文末だったように記憶している。
ともに初秋を彩る植物が介在する。
フランク・キャプラ監督らしくないけれど、むかーし「失われた地平線」という映画もあったなぁ。
夢の桃源郷・シャングリラへ行ったものの、人はどうしても遊び呆け続けていることができなくて、自分のいるべきもとの場所へ、戻ってきてしまうのだ。
秋はそんな、もう二度と再び巡り会えない人に、会えるような気がする季節でもある。
そしてここ2か月ほど、美しいタイやヒラメの舞い踊り…ならぬ、はたで見ているものの心の底が打ち震えずにはおられぬほど、一途でひたむきな表現者たちの舞台を追いかけて、龍宮城に深く潜行していた私は、Uボートの如く、再び浮上するすべを失った。
若い時に恋すると、失うものは何もないような気がするから、すべてをかけることも出来ちゃう。
歳とって恋をして、すべてを失っても、再び、怖いものは何もない、何もないのだけれども、しかし、そこまでして想う相手から何かを得たいか…という気力もなければ体力もない。フッ…とトレンチコートの襟を立て、ポケットに手を半分入れながら、ひとり笑みするのはそんな気持ちになったときだろう。
…恋や恋、なすな恋。
♪なれし情(なさけ)も、いまではつらや…(オジイサンになった「浦島」の詞章)。
そしてまた、深海の龍宮であったわが戦国鍋TVも、最終回を迎えて、私には戻る場所とてないのだった。
かてて加えて、久しくブログの扉を開かぬうちに、かの入り口は固く心を閉ざし、たしかこれであったはず…という呪文(パスワードですな)を申し述べても、私を中へは入れてくれないのだった。
…というわけで、パソコンの文書ソフトで原稿を書き、それを携帯へメールで送り、さらに唯一、認証で入ることのできる携帯からログインして、投稿するという…なんだか、親父さんに勘当を受け、表立っては自分の部屋に出入りもできない、井原西鶴『好色一代男』の世之介みたいになってきた。
あぁ、それとも、このふた月ほど私がいたのは、女護ヶ島だったのかしらねぇ……。
今日から、太陰太陽暦、平成廿三年の九月。
「新曲浦島」の詞章♪錦繍のとばり、暮れゆく中空…
変わり易い空模様の、雲流れゆく秋である。
生きている限り「つづき」は「つづき」であり得るが、物故した作家に続編執筆を求めるすべはないのだ。
長唄界で、繰り返し演奏される曲のひとつに「新曲浦島」という、海のさまざまな情景を描いた名曲がある。
坪内逍遥大先生が、日本にも国際社会にアッピールできる新しい演劇が必要である、という新思想のもと、一念発起して、長唄、常磐津、義太夫など、日本の伝統音楽でもって一大叙事詩的楽劇をこしらえた。明治三十九年、西暦にして1906年のことである。
しかし構想が壮大過ぎて、結局、長唄で作曲されたオーバーチュアの部分しか上演できずじまいだったという、未完の大曲。
力強く走る波がしら、夕暮れの凪いだ海面、嵐の轟く情景など、さすが逍遥先生の作詞もすばらしいが、長唄界の名手の手になる作曲も素晴らしい。演奏者も表現する愉しさを存分に味わえる、スペクタクルに満ちた、溌溂とした曲なのだ。
…で、新曲、というからには旧曲があるわけで、日本舞踊好きには実にポピュラーな、おさらい会には必ず誰かが出曲するというような、その名もズバリ「浦島」という珠玉の小品がある。お伽噺の浦島太郎を素材にした舞踊曲だ。
えーなに、浦島太郎の曲って、幼稚園のお遊戯会じゃあるましー、と、呟いた方は、お待ちなさい。長唄に、そんな芸のない曲が残っているわけがない。
これはね、さざ波のような旋律とともに、遙か水平線のかなたから、浦島太郎が艪を漕いで、ドンブラコと、現世に戻ってくるところから始まります。
そして、波打ち際で涙ながらにカニと戯れ、龍宮城での乙姫様との楽しかった日々を、ひとり想い出す。
楊貴妃と玄宗帝の白居易「長恨歌」になぞらえたような、ロマンチックな歌詞で綴るラブソングになっているのですね。
♪袖に梢(こずえ)の移り香が散りて、花や恋しき面影の…忘れかねたる比翼の蝶の、情け比べん仇桜…
旋律も美しく、もう本当に、ため息しか出てこないような、リリカルな叙情性に満ちた世界が、聴く者の感性を揺さぶる。
しかし、この曲もまた(古典であるから古風にメリハリつけずに弾く、という表現方法もあるわけではあるけれども)情感を込めて緩急つけて表現しないと、それが聴く者のハートに伝わらない、そんな曲でもあるのだ。
そして、ひとしきりロマンス懐古シーンが過ぎると、浦島の疑心を表すサスペンスに満ちたメロディが。
……あぁ、玉手箱、開けちゃおっかなー、どうしよっかなー。
どろどろどろん…と白煙が立ち、太郎はたちまちオジイサンになっちゃうのですが、そのあとの旋律が、またカッコイイ!!
この部分を弾くとき、私の眼の前にはいつも、とどろ巻き立つ浪をバックに、虚空を掴むかのように手を前へ突き出し、茫然自失たる浦島の姿が、劇画チックに浮かぶのだ。
もう二度と帰れない。帰って来たけど、帰れない。
山上たつひこの「うらしま」というホラー短編漫画もあったけれど。
かたや文政十一年(西暦1828)の江戸の歌舞伎舞踊、また一方は明治の近代的発想で作曲された、対極にあるようなこの新・旧二つの浦島、実は、両者ともに、ダイナミックな海の魅力を喚起し、演奏者の表現力を発揮できる、愉しい曲なのだ。
もう二度と戻らない…という切ないキーワードを思い描くとき、私は小学生のとき読んだ、安房直子「きつねの窓」という短編童話を想い出す。
あるとき主人公は猟に出かけた山中で、小狐を見かける。彼を追って深く山中に入ると、突如林が開け、桔梗屋という染物屋が目の前に現れる。追っていた小狐が化けているであろうその店の小僧に勧められるままに、両手の人差し指と親指を、桔梗のしぼり汁からつくったという染料で、美しい青紫色に染めてもらう。
その四本の指で菱形の窓をこしらえて覗いてみると、なんでも、自分が逢いたかった人に会えるというのである(もう何十年も前に読んだ話なので、違っているところもあるかもしれない)。
主人公は、もう会うことのできなくなったお母さんの姿を、その指の窓のなかに見出し、雀躍して家に帰るのだが、いつもの習慣で、ついうっかり手を洗ってしまうのだ。
この小説を想い出すたび、似たような切なさを持って私の脳裏に浮かぶのが、有島武郎の「一房の葡萄」。紫色の艶やかなブドウは思い浮かぶけれど、そのブドウをのせていた先生の美しい白い手はもうどこにもない、というような切ない文末だったように記憶している。
ともに初秋を彩る植物が介在する。
フランク・キャプラ監督らしくないけれど、むかーし「失われた地平線」という映画もあったなぁ。
夢の桃源郷・シャングリラへ行ったものの、人はどうしても遊び呆け続けていることができなくて、自分のいるべきもとの場所へ、戻ってきてしまうのだ。
秋はそんな、もう二度と再び巡り会えない人に、会えるような気がする季節でもある。
そしてここ2か月ほど、美しいタイやヒラメの舞い踊り…ならぬ、はたで見ているものの心の底が打ち震えずにはおられぬほど、一途でひたむきな表現者たちの舞台を追いかけて、龍宮城に深く潜行していた私は、Uボートの如く、再び浮上するすべを失った。
若い時に恋すると、失うものは何もないような気がするから、すべてをかけることも出来ちゃう。
歳とって恋をして、すべてを失っても、再び、怖いものは何もない、何もないのだけれども、しかし、そこまでして想う相手から何かを得たいか…という気力もなければ体力もない。フッ…とトレンチコートの襟を立て、ポケットに手を半分入れながら、ひとり笑みするのはそんな気持ちになったときだろう。
…恋や恋、なすな恋。
♪なれし情(なさけ)も、いまではつらや…(オジイサンになった「浦島」の詞章)。
そしてまた、深海の龍宮であったわが戦国鍋TVも、最終回を迎えて、私には戻る場所とてないのだった。
かてて加えて、久しくブログの扉を開かぬうちに、かの入り口は固く心を閉ざし、たしかこれであったはず…という呪文(パスワードですな)を申し述べても、私を中へは入れてくれないのだった。
…というわけで、パソコンの文書ソフトで原稿を書き、それを携帯へメールで送り、さらに唯一、認証で入ることのできる携帯からログインして、投稿するという…なんだか、親父さんに勘当を受け、表立っては自分の部屋に出入りもできない、井原西鶴『好色一代男』の世之介みたいになってきた。
あぁ、それとも、このふた月ほど私がいたのは、女護ヶ島だったのかしらねぇ……。
今日から、太陰太陽暦、平成廿三年の九月。
「新曲浦島」の詞章♪錦繍のとばり、暮れゆく中空…
変わり易い空模様の、雲流れゆく秋である。