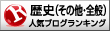「蘭蝶」で泣いた。久しぶりに聴いた。劇場で聴いたのは正しく十年ぶりだった。
三越劇場から出たら、東の空にぽっかりと月が浮かんでいた。そうだ、今日は十五夜だった。
日本橋の大通りを、息もつかずに南へ歩いた。こんな気分のときは、丸善でビールを飲むのだ。休日の日本橋はすいているから好きだ。普通のビヤホールでは嫌だ。一間三尺四方にひと気がない空間で、このじわじわとした感慨を反芻しながら、のどの渇きをいやすのだ。
今日のこの新内の会は、成駒屋が立方で出るというので、番頭さんに取ってもらった切符だった。新内のとあるお家元の弟子たちの披露目も兼ねた会、ということで、特に期待もしていなかったのだ。
歌舞伎長唄、という言葉があるように、舞台の地方(じかた)の演奏は、素の演奏会とちょっと違う。役者の邪魔にならないように演奏するのだ。
おなじみの曲に新趣向を組み入れた番組もご愛嬌、なんと八十回を重ねるという記念公演の、会主の口上も爽やかな、和気藹々とした会場の甘い雰囲気に、古典芸能の世界のいつものことだ…と、高を括っていた。だが、甘かったのは私のほうだった。
終曲は「蘭蝶」だった。すでに鼻をぐすぐすいわせていた観客が、声をかけた。
よっぽど思い入れがあるのだろう…と、そのときも私は冷静だった。
私がこの曲に思い入れがあるとするならば、九代目澤村宗十郎、丸にいの字の紀伊国屋が、歌舞伎座で最期に勤めた芝居、というだけだ。
あのころ私は仕事が忙しくなって、もうあまり歌舞伎座に行けなくなっていた。たしか、二十世紀最後、極月の歌舞伎座で、自分で手配したのではなく、知人が行けなくなったから、と、三階席の切符をくれたのだった。私はこの知人を、今でも恩人だと思っている。
そしてそれが、私が紀伊国屋を観た最後の舞台になった。
…そんなことをぼんやりと想っていた。ところが、で、ある。
後半の山場のクドキ、「♪縁でぇぇこそあれぇ…」と、会主が一声、語ったとたん、場内の空気が変わった。そして、私の料簡も。
三味線の調子がちょっと狂っていた。でもそんなことはどうでもいい。
そんなことは問題にならないほど、私は一瞬にして、大夫の語る声のそのたゆとう世界に連れて行かれた。……これが芸というものだ。大夫はおそらくこのクドキを、何千回となく語っているだろう。
「蘭蝶」は、恋にすべてをかけた女が、でも、更に、その男に命をかけて尽くしている女に義理立てして、その恋を思い切る話だ。
しかし、私はそんな理屈をすっかり忘れていた。もう、ただただ聴き惚れて、そしてただただ、感動していた。
理屈で感動するのじゃない。感性だ。
聴く者の感性を揺さぶる大夫の語りに、心の芯を掴まれて、私はただただしみじみとその声に聞き入っていた。これが芸の力だ。何年もかけて、積み重ね蓄積してきた、一朝一夕にはできない、芸の力量というものが、これなのだ。
幕が下り、また上がり、会主が終演の挨拶を述べたが「もう胸がいっぱいになってしまって…」と言葉少なに結んだ。福助も涙をぬぐっていた。
顔を直すのに化粧室へ直行した。こんなふうに、観劇終了後、お手洗いでしみじみと泣いたのは、たぶん、アン・リー監督の「グリーン・ディスティニー」以来だ。
あのとき私は、あの主人公の一途さに、もう胸がいっぱいになってしまって、観ている間は何ともなかったのに、今は亡き新宿松竹の、ひと気のないお化粧室で、やはりしめじめぐすぐすと泣いていたのだった。あれもやはり、二十世紀最後の年のことだった。
それからしばらく、サントラ盤を毎晩聴いて就寝していた。ヨーヨー・マのチェロの響きが、私を果て知れぬ余韻の岸辺へ誘うのだった。
そして、映画の中のチャン・ツイイーが演じた主人公がそうであったように、私も自分の身の落とし所に迷いかねて、砂漠をトホンと眺めていた。明日は白い霧の中にあった。
土曜日の丸善の喫茶室はすいていた。私は一間三尺四方に人のいないソファに身をもたせかけて、気持ちよくビールを飲み干した。
…さあ、早く帰って、私も三味線を弾かなくては。
三越劇場から出たら、東の空にぽっかりと月が浮かんでいた。そうだ、今日は十五夜だった。
日本橋の大通りを、息もつかずに南へ歩いた。こんな気分のときは、丸善でビールを飲むのだ。休日の日本橋はすいているから好きだ。普通のビヤホールでは嫌だ。一間三尺四方にひと気がない空間で、このじわじわとした感慨を反芻しながら、のどの渇きをいやすのだ。
今日のこの新内の会は、成駒屋が立方で出るというので、番頭さんに取ってもらった切符だった。新内のとあるお家元の弟子たちの披露目も兼ねた会、ということで、特に期待もしていなかったのだ。
歌舞伎長唄、という言葉があるように、舞台の地方(じかた)の演奏は、素の演奏会とちょっと違う。役者の邪魔にならないように演奏するのだ。
おなじみの曲に新趣向を組み入れた番組もご愛嬌、なんと八十回を重ねるという記念公演の、会主の口上も爽やかな、和気藹々とした会場の甘い雰囲気に、古典芸能の世界のいつものことだ…と、高を括っていた。だが、甘かったのは私のほうだった。
終曲は「蘭蝶」だった。すでに鼻をぐすぐすいわせていた観客が、声をかけた。
よっぽど思い入れがあるのだろう…と、そのときも私は冷静だった。
私がこの曲に思い入れがあるとするならば、九代目澤村宗十郎、丸にいの字の紀伊国屋が、歌舞伎座で最期に勤めた芝居、というだけだ。
あのころ私は仕事が忙しくなって、もうあまり歌舞伎座に行けなくなっていた。たしか、二十世紀最後、極月の歌舞伎座で、自分で手配したのではなく、知人が行けなくなったから、と、三階席の切符をくれたのだった。私はこの知人を、今でも恩人だと思っている。
そしてそれが、私が紀伊国屋を観た最後の舞台になった。
…そんなことをぼんやりと想っていた。ところが、で、ある。
後半の山場のクドキ、「♪縁でぇぇこそあれぇ…」と、会主が一声、語ったとたん、場内の空気が変わった。そして、私の料簡も。
三味線の調子がちょっと狂っていた。でもそんなことはどうでもいい。
そんなことは問題にならないほど、私は一瞬にして、大夫の語る声のそのたゆとう世界に連れて行かれた。……これが芸というものだ。大夫はおそらくこのクドキを、何千回となく語っているだろう。
「蘭蝶」は、恋にすべてをかけた女が、でも、更に、その男に命をかけて尽くしている女に義理立てして、その恋を思い切る話だ。
しかし、私はそんな理屈をすっかり忘れていた。もう、ただただ聴き惚れて、そしてただただ、感動していた。
理屈で感動するのじゃない。感性だ。
聴く者の感性を揺さぶる大夫の語りに、心の芯を掴まれて、私はただただしみじみとその声に聞き入っていた。これが芸の力だ。何年もかけて、積み重ね蓄積してきた、一朝一夕にはできない、芸の力量というものが、これなのだ。
幕が下り、また上がり、会主が終演の挨拶を述べたが「もう胸がいっぱいになってしまって…」と言葉少なに結んだ。福助も涙をぬぐっていた。
顔を直すのに化粧室へ直行した。こんなふうに、観劇終了後、お手洗いでしみじみと泣いたのは、たぶん、アン・リー監督の「グリーン・ディスティニー」以来だ。
あのとき私は、あの主人公の一途さに、もう胸がいっぱいになってしまって、観ている間は何ともなかったのに、今は亡き新宿松竹の、ひと気のないお化粧室で、やはりしめじめぐすぐすと泣いていたのだった。あれもやはり、二十世紀最後の年のことだった。
それからしばらく、サントラ盤を毎晩聴いて就寝していた。ヨーヨー・マのチェロの響きが、私を果て知れぬ余韻の岸辺へ誘うのだった。
そして、映画の中のチャン・ツイイーが演じた主人公がそうであったように、私も自分の身の落とし所に迷いかねて、砂漠をトホンと眺めていた。明日は白い霧の中にあった。
土曜日の丸善の喫茶室はすいていた。私は一間三尺四方に人のいないソファに身をもたせかけて、気持ちよくビールを飲み干した。
…さあ、早く帰って、私も三味線を弾かなくては。