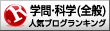新暦の正月は今日で終わりだが、旧暦の今日はまだ、平成廿二年十二月廿八日。
その昔、師走の二十八日は、門松を飾る日と決まっていた。うちの母はよく、一夜飾りはよくない、と言って、暮れの二十九日に松飾りをするのを強硬に拒んだ。
まあ、一夜飾りというのも、大晦日が十二月三十日(三十という一文字の漢字が変換できないので、遺憾ながらこの二文字表記にする)に決まっていた旧暦ならではの風習だ。
新暦だと31日という日にちが存在しますからね。正しくいえば三十一日は、「みそか」ではない。三十日だから「みそか」なわけで。
そしてまた、月の形は、旧暦では日にちによって決まっているのだ、ということも教えないと、ふと時代小説を書いてみようと思った現代人が、「暮れの二十八日。宵に町家の注連飾りを見上げれば、満月が浩々と輝いていた」…なんて書きかねない。
吉原を舞台にした歌舞伎の「晦日に月が出る廓(さと)も、闇夜があるから覚えていろ」なんて、ならず者の捨て台詞も、今日日の観客には効用がない。
…小学生の電話相談室のようになってきたので、このくらいに。でも学校ではこういうことを道理を説いて説明しないので、ますます日本古来の文化への、なるほど感、というのは薄れていってしまうのである。
詰め込み式に、季節感の微妙に異なる季語を記憶させたり、昔は一月から三月までが春だったのです、と宣言されても、暦自体が違うのだ、ということを教えなくては、昔の人はよっぽど強がりだったん?…というふうにしか納得できないだろう。
もう何年も前のこと。暮れに湯島天神に行ったら、境内の裏のほうで、鳶職さんが門松を拵えていた。
竹と松を、荒縄で器用に結い、美しく形づくっていく。その手先の見事さに、惚れぼれとして、しばし見入った。
職人の街だった江戸、そして東京。
江戸前のカッコよさ、というのは、こういうところにあるのだ。
熟練した指先から生まれる小宇宙。その技量。
撥先から生まれる音色で、宇宙がつくれる人もいる。…ああ、あやかりたい、蚊帳吊りたい。
松は常磐木(ときわぎ)ともいわれ、極寒の季節にも色を変えない常緑樹として、古来から尊ばれた。
「松・竹・梅」を「歳寒の三友」とまとめて呼ぶ。竹も、節を曲げずにまっすぐ伸びて、色を変えない。梅は寒いさなかに、百花に先駆けて咲く。
逆境にこそ、いさぎよく、気高く、志を変えずに。
日本人の美意識を、如実に表した三者。
歌舞伎に、この三友のうち二つと、桜の名前を冠した三兄弟が登場する『菅原伝授手習鑑(すがわらでんじゅてならいかがみ)』のお話は、天神様の縁日の二十五日に譲るとして…。
♪松の木ばかりが松じゃない…という小唄がありましたように、判じ物に、小石に松の葉を結んで想う相手に渡す、というのがある。
あなたに会えるのを「こいし(小石=恋し)く、まつ(松=待つ)」の心である。
門松は、春を待つ、こころ。
その昔、師走の二十八日は、門松を飾る日と決まっていた。うちの母はよく、一夜飾りはよくない、と言って、暮れの二十九日に松飾りをするのを強硬に拒んだ。
まあ、一夜飾りというのも、大晦日が十二月三十日(三十という一文字の漢字が変換できないので、遺憾ながらこの二文字表記にする)に決まっていた旧暦ならではの風習だ。
新暦だと31日という日にちが存在しますからね。正しくいえば三十一日は、「みそか」ではない。三十日だから「みそか」なわけで。
そしてまた、月の形は、旧暦では日にちによって決まっているのだ、ということも教えないと、ふと時代小説を書いてみようと思った現代人が、「暮れの二十八日。宵に町家の注連飾りを見上げれば、満月が浩々と輝いていた」…なんて書きかねない。
吉原を舞台にした歌舞伎の「晦日に月が出る廓(さと)も、闇夜があるから覚えていろ」なんて、ならず者の捨て台詞も、今日日の観客には効用がない。
…小学生の電話相談室のようになってきたので、このくらいに。でも学校ではこういうことを道理を説いて説明しないので、ますます日本古来の文化への、なるほど感、というのは薄れていってしまうのである。
詰め込み式に、季節感の微妙に異なる季語を記憶させたり、昔は一月から三月までが春だったのです、と宣言されても、暦自体が違うのだ、ということを教えなくては、昔の人はよっぽど強がりだったん?…というふうにしか納得できないだろう。
もう何年も前のこと。暮れに湯島天神に行ったら、境内の裏のほうで、鳶職さんが門松を拵えていた。
竹と松を、荒縄で器用に結い、美しく形づくっていく。その手先の見事さに、惚れぼれとして、しばし見入った。
職人の街だった江戸、そして東京。
江戸前のカッコよさ、というのは、こういうところにあるのだ。
熟練した指先から生まれる小宇宙。その技量。
撥先から生まれる音色で、宇宙がつくれる人もいる。…ああ、あやかりたい、蚊帳吊りたい。
松は常磐木(ときわぎ)ともいわれ、極寒の季節にも色を変えない常緑樹として、古来から尊ばれた。
「松・竹・梅」を「歳寒の三友」とまとめて呼ぶ。竹も、節を曲げずにまっすぐ伸びて、色を変えない。梅は寒いさなかに、百花に先駆けて咲く。
逆境にこそ、いさぎよく、気高く、志を変えずに。
日本人の美意識を、如実に表した三者。
歌舞伎に、この三友のうち二つと、桜の名前を冠した三兄弟が登場する『菅原伝授手習鑑(すがわらでんじゅてならいかがみ)』のお話は、天神様の縁日の二十五日に譲るとして…。
♪松の木ばかりが松じゃない…という小唄がありましたように、判じ物に、小石に松の葉を結んで想う相手に渡す、というのがある。
あなたに会えるのを「こいし(小石=恋し)く、まつ(松=待つ)」の心である。
門松は、春を待つ、こころ。