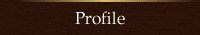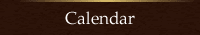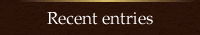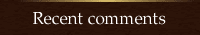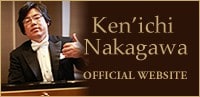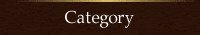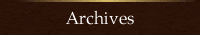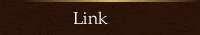お茶大ゼミ。
ラヴェルのピアノ曲が元でオーケストラにも編曲されている曲のゼミ。
本日学生が「高雅で感傷的なワルツ」を弾き、同時にピアノスコアをプロジェクターで投影、楽譜を見ながら聴き、そのあとオーケストラの演奏を同じくプロジェクターで投影してフルスコアを見ながら聴いて、そのあとオーケストラとピアノ違いを感じながら、そのコメントも含めて公開レッスン。
また、この曲に関しての時代背景からさまざまな曲に関するお話もしました。
ワルツについても。
またラヴェルの和声に関する分析、それがジャズの和声にも応用できるなどの話も五線譜を使いレクチャー。
ラヴェルに行くまでは最初にティエリー・ドゥ・メイの「テーブルの音楽」を学生三人が演奏。
本日は声で数を数えることなく、淀みない演奏をしました。
この曲の読み方、演奏の仕方は四年前?くらいにしましたが、あとは意図的に先輩から後輩へ口伝で伝えて会得することにしましたが、とても立派に伝統となってきているように思えました。
一見読んだら良いかわからない楽譜をしっかり形にする、読み方がわからなくとも、その三人のメンバーで奏法のコンセンサスを取って独自のオリジナルであっても形にする、などこれからさまざまな曲を演奏するために大切ではないかという心構えを、実演する事で会得してほしい願いがありましたが、立派に行っております。
また、このラヴェルの「高雅で感傷的なワルツ」を作曲するにあたってある意味きっかけになったかもしれないシューベルトの
「高雅なワルツ」
と
「感傷的なワルツ」
のスコアをプロジェクターで投影して、演奏を聴きました。
ということでてんこ盛りになりました。
プロジェクター、パソコン持参、スコア全ページをパワポで資料を作るのもそれなりに時間がかかるのですが、学生も中途退場せず本当によくついてきてするので、出来るだけの事はやりたいと思っております。
また、次のゼミの内容をじっくり考えたいです。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )