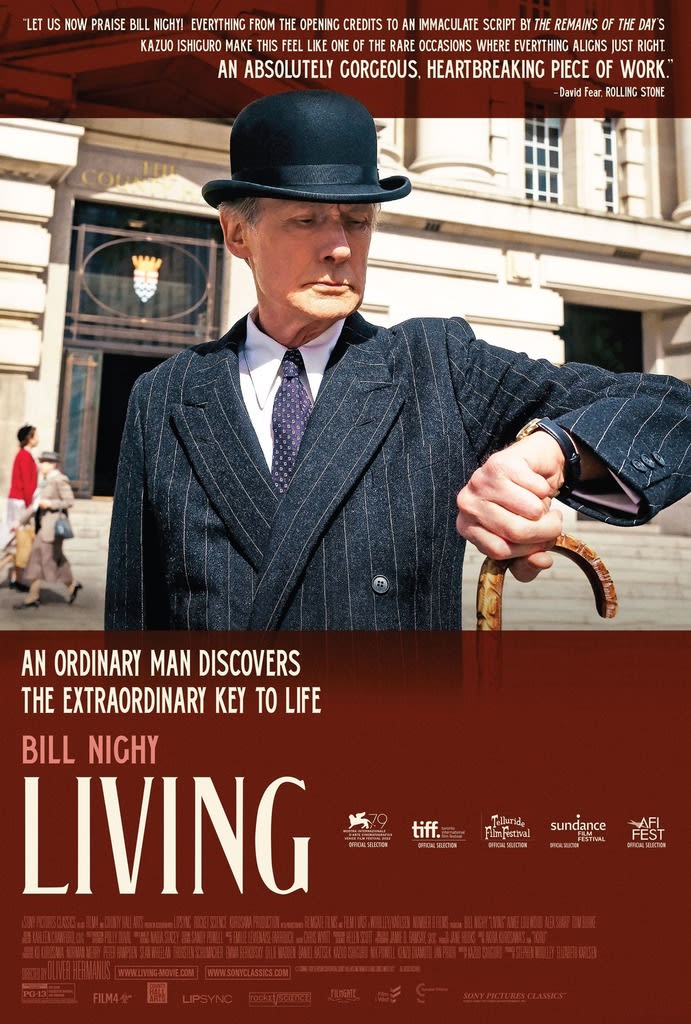ポーランドの巨匠イエジー・スコリモフスキ監督の最新作の主人公はなんとロバ。1966年のロベール・ブレッソン監督作『バルタザールどこへ行く』からインスパイアを受けたという本作は、1頭のロバ“イーオー”の目を通して私たちの住む世界を描く。イーオーは旅回りのサーカス一座で少女とパフォーマンスをしていた。ロバに生まれた宿命ゆえに荒くれの芸人達からは使役もされたが、それでも少女は“EO”と耳元で優しく囁いてくれる。ところがアニマルライツ団体によりサーカスの動物たちは行政に引き取られ、イーオーは何処とも知れない農場へ連れ去られてしまう。
イーオーが再び少女と巡り合うまでの感動映画か?違う。ボイスオーバーのないディズニー映画か?違う。少女とはあっさり決別し、イーオーの旅が始まる。暗い夜道から外れて森に入ると、そこにはトンネルがあって…なんとスコリモフスキは私たちをロバの深層心理へと導く。イーオーは野を駆けるサラブレッドに焦がれ(ひょっとすると自身を馬と勘違いしているかもしれない)、暴漢に襲われて重傷を負えば四足歩行のロボットになった幻覚を見る。そしていつしか目にした事もないであろう、映画女優イザベル・ユペールの淫夢を見るのだ。物言わぬロバに言葉と魂を与え、愚かな人間に翻弄されるイーオーの姿に“もののあわれ”を感じさせるスコリモフスキの魔力よ!88分間の午睡の末に場内に明かりが灯れば、私たちは『EO イーオー』の残像を脳裏に、夢現のまま映画館を後にするのである。
『EO イーオー』22・ポーランド、伊
監督 イエジー・スコリモフスキ