
8月上旬になると沖縄県島ではマンゴー「アーウィン」の収穫を終え、次年度の結果枝を育成するための作業として枝の剪定が行われています。
剪定した枝を「敷き草代わり」と言って、マンゴーの栽培施設内にそのまま放置している方を見かけることがあります。
しかし、これはマンゴーの病害虫防除の観点からお奨めできません。
マンゴーの栽培で特に問題となる病害に炭疽病と軸腐病があります(写真2)。
これらの病気はカビが原因で引き起こされます。

写真2.マンゴー果実における炭疽病と軸腐病の症状。
「やんばる美ら島マンゴーの作り方」より抜粋加工。
マンゴーの剪定枝や枯葉は、炭疽病や軸腐病の発生源です。
これらを毎年栽培施設外に持ち出すことで、徐々に発病率が軽減することが知られています(写真3)。

写真3.剪定枝を毎年片付けている農場では軸腐病の発生が減少する。
「やんばる美ら島マンゴーの作り方」より抜粋加工。
しかし、ここで「剪定枝を栽培施設外に持ち出すのが大変」という労力的な課題が浮上します。
そこで、今回は「ベンリークロス」を用いた「剪定枝を小分けにして持ち出す方法」を紹介します。
1.剪定を行う樹の近くに「ベンリークロス」を広げておき、その上に方向を揃えながら剪定枝を積む(写真4)。
2.適当な量が詰まれたら、布をグルッと巻いて、止め金具で固定する(写真5、6)。
3.「ベンリークロス」で固定された剪定枝を栽培施設外に持ち出す。

写真4.ベンリークロスの上に剪定枝を積む。

写真5.剪定枝をベンリークロスで包む。

写真6.止め金具で剪定枝がバラけない様に固定する。
これだけです。
「ベンリークロス」は沖縄県では主に花き類(菊など)の収穫時に用いられている資材なので、最寄りのJAの資材売り場で購入可能だと思います。
また、「小分けしても重いよ・・・」と感じる方は一輪車(猫車)に積んで持ち出しても良いかもしれません(写真7)。

写真7.廃棄された一輪車(猫車)を改造。軽くて、束にした剪定枝を運ぶのにも便利。
重労働となる剪定枝の持ち出し作業が少しでも楽になることを願っています。
○参考文献
・「やんばる美ら島マンゴーの作り方」.2008.北部農林水産振興センター.













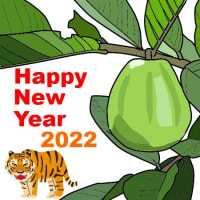








今回、敷草として剪定した枝を放置していたら、病気が発生するとのことでしたが、前年の剪定した枝でも、病気が出る恐れはありますか?
前年の剪定枝はハウスの外に放置していて、米ぬかや堆肥などは混ぜていません。
大量にあるので、マンゴーや野菜の肥料にしようと思っていました。
もしよろしければ、教えてください。
よろしくお願いいたします。
いつもブログを見ていただき、ありがとうございます。
>前年の剪定した枝でも、病気が出る恐れはありますか?
とのことですが、枝の太さや朽ち具合、胞子の繁殖具合によると思います。
細い枝でよく朽ちていて、胞子も見られないのであれば、病原菌よりも有機物を分解する菌の方が優性だと考えられます。
イメージとしては菌の椅子取りゲームの様なもので、病原菌が沢山の席を取ってしまえば病気の発生源になるということです。
剪定枝は大量に出るので処分に困りますよね。
分解する菌を優性にするためにはチッパー等で細かく砕くのが有効な手段だと思います。
また、マンゴーと共通の病害がない作物になら敷き草代りとして剪定枝が使えるかもしれません。