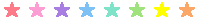出来たて、です。
ほやほやです。
湯気出てます。
徹夜しちゃいました。
だから、眠いです。
眠いんだけど、
今、かなりの躁状態だと、自分でも思います。
いつもなら∞のニュースをスルーする、この地方の朝のローカル番組で、
ひなちゃんの舞台の話題をやってくれたこともあって、
かなり、うきうきな朝です。
トーマの映画のインタビューも、ちらりと流れました。
このあと、寝ます。
娘たちが学校に出かけて行ったら、
はい。
自分でも、かなり、ヤバイカンジがします。
あとがきもどきの、まえがきもどきの、言い訳をするなら。
無駄に長くなってます。
ただただ、彼と何気ない日常を過ごしたかったばっかりに、
ことごとく妄想してたら、こんな風になりました。
途中で切るかどうか迷ったんですけど。
どこで切ったらいいのかがわからなくて。
切っちゃうと、繋がらなくなりそうで。
でも、
以前は分からなかったんですが、
ここへ遊びに来てくださる方が、大半が携帯からだということを考えると、
本当に、読んでいただくのに時間と手間とがかかるページ数になっているので、
どうしようかと思ったり。
でも、切るのは、イヤだったりする自分がいて。
矛盾の嵐。
そこで。お願い。
ここから始まる物語は、いつもよりもかなりページ数が多くなります。
可能ならば、PCからお読みになることをオススメします。
携帯からしか、という方には、ご面倒をおかけしますが、ぜひ、お付き合いをくださいませ。
STORY.34 赤と白と緑の季節に
「あ、雪や・・・」
窓の外を見てたメンバーが、ぽつりとつぶやいた。
「寒いはずやな」
暖かいはずの、このスタジオの中でも、
やっぱり、底冷え、言うんか、
足元には冷たい空気が淀んでる気がするわ。
この街の夜は明るくて、にぎやかすぎるほどに、にぎやかだ。
この季節は、特に。
街路樹には、きらめくイルミネーション。
濃い緑に、赤いリボン、白い綿菓子のような雪の飾り。
心浮き立たせる、さまざまなベルの音と音楽。
異教徒のお祭りが、なんでそんなに嬉しいんやろ、って、
ずっと思ってた。
ほんの数年前までは。
「なあ、どないする? 行く?」
ぼんやりしてた俺を覗き込んだ顔。
「何、考えてたん?」
「別に、なんも考えてへんよ」
「行くやんな?」
「どこに?」
「やっぱ聞いてへんかったやん」
「あかんわ、そのコ、行かへんわ」
「えー?なんでなん?」
「お前、今日、何日か忘れてるやろ」
言うが早いか、
そいつは、持ってたスケジュールのバインダーで、もう一人をどついた。
「痛いってー。どつかんでもええやん」
「24日やぞ、イヴやんけ」
「そんなん、わかってるよ。・・・あ!!」
「分かったか」
「明日、燃えるごみ出さなあかん!!」
「なんでや!!」
あほか、こいつら。
下手な小ネタやな。
どこで、笑ってほしいん?
「で? 何、用意したん」
背後から、別のメンバーが声をかけてきた。
「案外、用意してへんとちゃうん?」
「まさか、それはないやろ」
勝手なこと、言うてるわ。
買うてないわけ、ないやんか。
大事な大事な天使への贈りもんやぞ。
めっちゃ考えたわ。
「えー? ぬいぐるみかなぁ、おままごととか?」
「ままごと、ええなぁ。可愛いなぁ」
「ちっちゃい手で、何作ってくれるんやろ」
「うわー、ままごとの相手したりするん?」
だぁれも、ままごと買うたって、言うてへんやん。
こいつら、勝手なことばっかし言いやがって。
「どーでもええやん、そんなん。なぁ、もう帰ってええんやろ?」
「ああ、ええで。明日も、時間に遅れんなや」
「わかってるわ。ほな、お先」
一人のメンバーが、さっさと帰り仕度をして、スタジオを出て行った。
「じゃあ、俺も帰るわ」
「なん? 結局、行かへんの?」
「お前、何、聞いとってん。このコ、放っといて俺とメシ行ったらええやん」
「二人って、寂しない? あ、そっちは? 行く?」
「残念やけど、俺、まだ別のやつの撮り、残ってるし」
一人は、そう言って苦笑い。
もう一人は。
「僕、さっき、お弁当食べたし。もう眠たいし。今日はええわ」
大きなあくびをひとつ。
「あ、じゃあ、お前は行くやんな?」
ごそごそ携帯持ち出して、メール打ちはじめたそいつは、
「行かへん。用事、でけた」
あっさりと断った。
「またフラレたな」
「そいつ、俺とメシ行く気、絶対にあらへんわ。ええわ、もう。二人で行こうや」
なんや、可哀そうになってきたわ。
「ちょっとだけ、行ったろか?」
「あかんやろが。お前は早よ帰ってやれって」
「ほんでもさぁ」
「ええって、ええって。ちょっとで済むわけないもん。この人、きっとまたべろべろになるで」
「そうかぁ?」
「ええから、早よ帰ってやらんと、寝てまうで」
言われて、俺は腕時計を見た。
確かに、下手したら、もう寝てるかもわからん時間には、なってる。
「あ、ああ、ほな」
「ほなおつー」
「さいなら」
メンバーの声に押されるように、俺はスタジオを後にした。
カチャ・・・
「ただいまー」
玄関を開けた途端、
「ぱーぱッ!!」
ちっちゃな手を広げて、舞音が抱きついてきた。
「おま・・・、まだ、起きとったんか」
舞音を抱き上げながら、いつもの、おかえりのチュウや。
「ぱーぱ、くちゃい」
「ん? あー、煙草、吸ったからなー」
「いやん」
「いやん、て、お前、これがパパの匂いやんか。我慢せぇや」
「いやんもん。がやがやちて」
がやがや、て、なんや?
ここんとこ、だいぶお喋りの上手くなった舞音やけど、
まだわからん言葉が、ようけあるわ。
「ガラガラ、でしょ? 舞音」
舞音と俺のやりとりを、笑いをこらえて彼女が見てる。
「がりゃがや?」
言い直す舞音。
でも、やっぱし、間違うてる。
可愛ええなー。
この舌っ足らずなカンジ。
「あ。うがい、か!」
「手も洗ってね」
「あ、ついでやから、風呂入るわ。寒かったし。出来てる?」
「まのん、もー。ちゃぷん、しゅゆ」
「やぁだ、もう。舞音は、さっき入ったでしょ?」
「やーやーやー!! まのっもー。ちゃぷうん。パパ??」
ねだるように、舞音が俺の首筋に手をまわしてしがみつく。
「しゃあないな。たまには、ええか?」
俺は、彼女の顔色をうかがう。
「もう。舞音に甘いんだから。風邪ひかせても、しらないからね」
呆れたような、怒ったような表情の彼女が、そこにいた。
「なにスネてんねん。せやったら、一緒に入ろうや」
「入りませんッ!」
そう言って、彼女はくるりと背を向けた。
あかんやん。
スネてるやん。
子供にやきもちやいて、どないするん。
「なぁ、入ろうや、一緒に。入ってください、お願いします」
彼女の後ろから耳元に囁く。
くすぐったそうにしながら、
「お腹、空いてるんでしょ? その間に用意しとく」
俺を見上げて、彼女が微笑った。
ちゃぷ・・・
立ち上る湯気の中で、舞音がはしゃぐ。
細こくてちっちゃい身体やのに、
抱くと、ふんわり、押し戻してくる弾力、
ぷくぷくっとして、柔らかい肌。
「ぱーぱ、抱っこ」
さして大きくないバスタブの中、舞音が抱きついてきた。
膝に乗せるようにして、舞音を肩まで座らせる。
お湯よりあったかく感じる舞音の温もりが、俺に伝わってくる。
こうして触れ合ってるだけで、
なんでこんなに、優しい気分になれるんやろう。
イヤなことがあって、シンドイこともあって、
もうええわ、って思いながら、こうして家に帰ってきても、
舞音と他愛のない言葉のやりとりしてるだけで、
なんか、浄化されてく気がするわ。
子供って、不思議やな。
「なぁ、舞音、パパ、好きか?」
「しゅき」
「どれくらい?」
「んーーっと、んーーっと、んーーーっと、ぱっぱい」
そう言って両手を大きく広げた。
「ぱんぱんまー、ちて」
なんて?
なに?
ぱんぱんまーって。
よーわからんわ。
舞音の言葉は、独特やな。
そのうち、ちゃあんと言葉が通じるようになったら、
こんな可愛い言葉も、聞けんくなるんやな。
「ぱんぱんまー。ねー、ぱんぱんまーーー」
言いながら、お湯の表面をぴちゃぴちゃ叩く舞音。
水しぶきが飛んで、顔にかかる。
「やめろや、もう。なんやねん、ぱんぱんまーって」
にっこり笑ってる舞音。
どうやら、水音を立てる方が気に入ったらしい。
ま、ええか。
『舞音、もう上がる?』
ガラス戸の向こうから、声がする。
『ご飯の支度、出来たんだけど』
「おぅ。入ってこんの?」
『何言ってるのよ、入らないわよ』
「なんや、一緒に入ったらええのに」
『結構です』
「なぁ、入って来いって。スキンシップしようや」
『ご飯が冷めちゃうでしょ』
「ほな、あとで、違うスキンシップする?」
『違うスキンシップって・・・』
「舞音に、弟か妹、つくったろ」
『もう!』
「ええやん、な?」
『舞音、上がるの? まだなの?』
話、誤魔化しよったな。
恥ずかしがりめ。
「舞音、もうママが、出ておいでって」
水で遊び続けてる舞音をバスタブから出すと、軽く顔を拭いてやった。
「あったかくなったか?」
「ぱんぱんまー?」
あのな。
せやから、その『ぱんぱんまー』ってのが、いまいち、ようわからんねんけど。
こういう時の常套手段いうたら・・・
「ママに訊いてみ」
俺はそう言いながら、舞音の頭に手を乗せた。
「あい」
可愛い返事をひとつした舞音の頬は、ほかほかのピンク色だった。
ガラス戸に、舞音のシルエットが映る。
バスタオルでくるまれながら、舞音が彼女に尋ねてる。
「ぱんぱんまー?」
「うん、かわいいほっぺになったよ」
あー、やっぱり母親には通じんねんな。
すごいな。
「ビール、飲む?日本酒?焼酎?」
風呂上がりの俺に、彼女が問いかける。
小さな子供用の椅子に座った舞音がこっちを向いた。
「あー、じゃあ、とりあえず、ビール」
「まのっも、びゆ」
「あほぅ。ビールはあかんやろ」
「やー、びゆ」
駄々をこねるように、足をばたつかせてる舞音。
「・・・だってさ」
俺は、彼女の方を見る。
くすくす笑いながら、彼女は、舞音に吸い口の付いたコップを渡す。
「舞音、これ飲んだら、ねんねしようね」
「ねんね、いやー」
ふくれっ面の舞音。
「ええやん、無理くり寝かさんでも。そのうち、眠たなったら、勝手に寝るやん」
「そうだけど、風邪ひかせちゃうわ」
心配症やな。
これっくらいの子供って、風邪ひきながら育つんとちゃうん?
「ぱんぱんまー、しゅゆ」
舞音が、椅子から滑るように下りる。
「っと、お・・・、おお、危ないな。気ィつけや」
舞音の身体を受け止めようと俺は、手を伸ばす。
すとん、と尻もちをついた舞音は、にかにか笑いながら、その俺の手を引っ張る。
「? なに?」
リビングのTVの前、
舞音が好きなお遊戯やアニメのDVDが、きちんと整理されて箱に入ってる。
座り込んだ舞音が選んだのは、まるい大きな顔に赤いほっぺ、黄色い靴に、こげ茶のマントの正義の味方。
「ぱんぱんまー、しゅゆ」
俺に手渡しながら、身体を上下に揺すって、すでに、なんや楽しそうに踊ってる。
「これ、かけたらええんやな」
俺は、DVDをセットしてやる。
オープニングの音が鳴り出すと、待ちかねたように手を振り、足を動かしだす。
嬉しそう、やな。
ほんでも、こんなん、いつ買うたんやろ。
「クリスマスプレゼント、よ」
ダイニングの方から、彼女が言う。
「誰から?」
「お義母さんから、届いたの」
「おかんが? 舞音に? へぇ・・・」
「気に入っちゃって、一日中ずっと見ながら踊ってるわよ。エンドレスで」
「一日中って、大げさな」
「ハマったら大変よ、ってママ友が言ってたけど、本当だったわ」
「へえ、踊るん、好きなんや」
ちっちゃな手足を、一生懸命に動かして、見よう見まねで踊ってる舞音。
御世辞にも、画面と合うてるとは言われへんな。
こんなとこも、親に似るんか?
「冷めるわよ」
俺は、ダイニングに戻る。
テーブルに並べられた食事。
いつもなら、
野菜中心で、いろんな料理がちょっとずつ。
せやけど、今日は違う。
「ごめんね、ありきたりのメニューで。考えつかなくて」
チキンとサラダ。
パスタが2種類。
それに、スープ。
小さなケーキには、サンタのろうそく。
「こういうの、嫌いだって知ってるけど」
向こう側の席に座りながら、彼女が、言った。
「やっぱり、今日は特別だから」
「やりたいようにしたらええよ。こういうんも、舞音のためには必要な行事やろ?」
「うん、それもあるけど」
「けど、なに?」
俺は、サラダのレタスをつまんで口に入れながら、彼女を見る。
うわッ、なに?
なんで泣いてるん?
「ちょ、待って。あかんやん、なに? まだ食べたらアカン?」
「違う、ごめ・・・。いいの、食べて」
「いや、いいのって言われても、目の前で泣かれたら、メシ、食べられんし」
「嬉しかったから。あなたと、クリスマスを過ごすの」
「嬉しがるようなことか?」
そう言った途端に、俺は、思いだした。
彼女と出会ってから、クリスマスはいっつも仕事やったこと。
逢う約束してても、わずかな時間やったり、
ゆっくり食事もとれんような、そんなせわしなさ。
クリスマスに限ったことやないわ。
結婚しても変わらへん、俺のスタンス。
仕事やら、付きあいやら、仲間優先の約束。
つい後回しになる、おろそかになる、彼女との小さな約束ごと。
そのたび、微笑って許してくれてた彼女。
今夜にしたって、そうやわ。
もしあの時、メンバーと食事に行ってたら、
また、彼女とすれ違ってしまうとこやったんやな。
「なあ、ビール」
「あ、はい」
涙をぬぐった彼女が、冷蔵庫を開けてる。
「コップ、2コ、持っておいで」
テーブルに置かれたコップ。
冷えたビールを注ごうとする彼女の手を制して、俺は缶をその手からはずす。
「ええから、座り」
彼女が素直に、向こう側に座る。
笑顔の消えた、微妙な表情の彼女がそこにいる。
こんな顔させたくて、彼女と一緒になったんとちゃうやん。
何してんねん、俺。
「あ、私、飲めないよ」
一つ目のコップをビールで満たしたあと、
もうひとつにもビールを注ごうとした俺に、彼女が言った。
「飲めない、んとちゃうやろ。飲まないだけやん」
彼女がアルコールを口にしなくなったのは、舞音がお腹に入ったからや。
もともとは、俺の酒にも付き合ってグラスをあけて、
ケラケラ笑う、陽気な酒飲みやったもんな。
俺は、もうひとつのコップにもビールを注ぎ、ひとつを彼女に渡す。
「乾杯、しよ」
キンッ!
小さくグラスが音を立てる。
「メリークリスマス」
「メリークリスマス・・・」
俺がグラスに口を付けるのを見て、彼女もグラスを口に運ぶ。
彼女ののどが、かすかに動いた。
「にがッ」
眉をひそめる彼女。
「相変わらずやな、ビール、苦手か?」
「前より苦く感じるわ。味覚が変わったのかな」
そう言って、彼女はグラスを置く。
「なんか、すぐに酔っちゃいそう」
「酔ったってええやん。家なんやし」
「酔ったら眠くなるの、知ってるでしょ? 後片付けや舞音の世話もあるし」
「後片付けなん、出来る時でええやん。汚れもんが多少たまったかて、だぁれも文句言わへんで」
「うーーーん」
「舞音の世話くらい、俺にも出来るし」
「うーーーん」
「ほれ、飲んで」
俺は、彼女のグラスに、もう一度ビールを注ぐ。
「そう?」
にこやかに笑う彼女の、この顔を、もっと見ていたい、
そう、思った。
外は雪。
音もなく、雪。
家の中では、俺と彼女の、他愛のない日常。
彼女が守りたいと望んだ、たったひとつの世界。
俺と、彼女と、舞音。
重ねていく、ありふれた日々。
大好きも、大嫌いも、全部詰め込んで、
互いに違うからこそ、分かりあおうとする日々。
今更ながらに気づく。
大切なものは、いつもここにあるんだ、と。
彼女が守ってくれる、ここに。
舞音がいてくれる、ここに。
だから俺は、明日も立ち向かえるんだ。
一人でいても、ひとりじゃないから。
いつしか、BGMだった舞音のはしゃぐ声が聞こえなくなった。
「電池が切れたんか?」
俺は立ちあがって、TVの前を覗く。
こてんと倒れるように舞音。
「あーあ。やっぱり」
俺は舞音を抱き抱える。
「また、重くなったんやな」
眠った舞音の重さが、俺の腕に、確かな責任を感じさせる。
俺が守らなければならないものの、重みを。
ここからもっと、もっと、重くなるんやろな。
そのうち、こんなふうに抱きあげることすら出来んくなるんやろな。
「舞音、ベッドに寝かせてくるわ」
「うん、大丈夫? 出来る?」
「あほ。出来るわ、それくらい」
とは言ったものの。
「すまん、ドアだけ開けて」
苦笑しながら彼女が席を立ち、リビングのドアを開け、
ついでのように先に立って、寝室のドアを開けてくれた。
ベッドに降ろされても、ピクリともぐずらずに、すやすや眠ったままの舞音。
ほんまに電池の切れた人形みたいやな。
「おやすみ、舞音」
舞音のおでこに口付ける。
「もうすぐ、サンタが来るからな」
「サンタ?」
「おぅ」
「そういうの、信じてなかったんじゃないの?」
「信じてるわけちゃうよ」
「なのに、サンタ?」
「サンタはおるって、教えてくれたんはお前やろ」
「?」
「大切な人の笑顔を見たいと思う心がサンタなんやって、おまえ、そう言ったよな」
「うん」
「せやったら、俺の中にもサンタはおるし。お前の中にも、舞音の中にも、きっとおるやろ」
「舞音、サンタさんに会えるといいわね」
「会えるやろ。舞音ほど、ええコ、他におらんのやから」
くすッ、と小さく彼女が微笑った。
「親ばか、か?」
「ううん。ばかになれるから親なんだな、と思って」
「俺らも、ちょっとずつ親になってくんやな」
「ふたりで、一緒に、ね」
彼女の手が、俺の手のひらに重なった。
俺の肩にもたれかかった彼女の髪が、頬に触れた。
「俺のそば、離れんなや」
「え?」
驚いたように、彼女が顔を上げた。
「俺の隣に、こうして、いつまでも、おってくれるよな?」
じっと俺を見たあとで、こくん、とうなづいた彼女。
うつむいたまま、
聞きとれぬほどの、かすかな声でつぶやいた。
「サンタに逢えたわ」
「ん? なに?」
訊き返す俺に、「なんでもない」と彼女は笑い、
俺を見上げる。
「私たちも、もう、寝よ。舞音をサンタに逢わせてあげよ?」
「ん、そやな」
翌朝。
彼女の目を覚ましたのは、リズムも音階もめちゃめちゃな、
だけどとてもかわいい、ピアノの音色。
久しぶりに身体に入れたアルコールが、彼女の眠りを深くしたこともあって、
いつもより少しだけ遅い目覚めの時間だった。
隣に眠るはずの彼の姿も、
可愛い舞音の姿も、その部屋にはなく、ただ、遠くでかわいいピアノの音だけが響いてる。
起きた彼女の目に飛び込んできたのは、
枕もとの真っ赤なバラの花束と、
添えられた一枚のカード。
『愛してる、ずっと』
見慣れた筆跡の、その文字が、
彼女にとって、永遠のサンタクロースだった。
Fin.
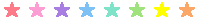
お気に召しましたら、
関ジャニWEBランキング
にほんブログ村ランキング
ぽちんっと押して頂けると、とっても嬉しいです。
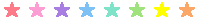
ほやほやです。
湯気出てます。
徹夜しちゃいました。
だから、眠いです。
眠いんだけど、
今、かなりの躁状態だと、自分でも思います。
いつもなら∞のニュースをスルーする、この地方の朝のローカル番組で、
ひなちゃんの舞台の話題をやってくれたこともあって、
かなり、うきうきな朝です。
トーマの映画のインタビューも、ちらりと流れました。
このあと、寝ます。
娘たちが学校に出かけて行ったら、
はい。
自分でも、かなり、ヤバイカンジがします。
あとがきもどきの、まえがきもどきの、言い訳をするなら。
無駄に長くなってます。
ただただ、彼と何気ない日常を過ごしたかったばっかりに、
ことごとく妄想してたら、こんな風になりました。
途中で切るかどうか迷ったんですけど。
どこで切ったらいいのかがわからなくて。
切っちゃうと、繋がらなくなりそうで。
でも、
以前は分からなかったんですが、
ここへ遊びに来てくださる方が、大半が携帯からだということを考えると、
本当に、読んでいただくのに時間と手間とがかかるページ数になっているので、
どうしようかと思ったり。
でも、切るのは、イヤだったりする自分がいて。
矛盾の嵐。
そこで。お願い。
ここから始まる物語は、いつもよりもかなりページ数が多くなります。
可能ならば、PCからお読みになることをオススメします。
携帯からしか、という方には、ご面倒をおかけしますが、ぜひ、お付き合いをくださいませ。
STORY.34 赤と白と緑の季節に
「あ、雪や・・・」
窓の外を見てたメンバーが、ぽつりとつぶやいた。
「寒いはずやな」
暖かいはずの、このスタジオの中でも、
やっぱり、底冷え、言うんか、
足元には冷たい空気が淀んでる気がするわ。
この街の夜は明るくて、にぎやかすぎるほどに、にぎやかだ。
この季節は、特に。
街路樹には、きらめくイルミネーション。
濃い緑に、赤いリボン、白い綿菓子のような雪の飾り。
心浮き立たせる、さまざまなベルの音と音楽。
異教徒のお祭りが、なんでそんなに嬉しいんやろ、って、
ずっと思ってた。
ほんの数年前までは。
「なあ、どないする? 行く?」
ぼんやりしてた俺を覗き込んだ顔。
「何、考えてたん?」
「別に、なんも考えてへんよ」
「行くやんな?」
「どこに?」
「やっぱ聞いてへんかったやん」
「あかんわ、そのコ、行かへんわ」
「えー?なんでなん?」
「お前、今日、何日か忘れてるやろ」
言うが早いか、
そいつは、持ってたスケジュールのバインダーで、もう一人をどついた。
「痛いってー。どつかんでもええやん」
「24日やぞ、イヴやんけ」
「そんなん、わかってるよ。・・・あ!!」
「分かったか」
「明日、燃えるごみ出さなあかん!!」
「なんでや!!」
あほか、こいつら。
下手な小ネタやな。
どこで、笑ってほしいん?
「で? 何、用意したん」
背後から、別のメンバーが声をかけてきた。
「案外、用意してへんとちゃうん?」
「まさか、それはないやろ」
勝手なこと、言うてるわ。
買うてないわけ、ないやんか。
大事な大事な天使への贈りもんやぞ。
めっちゃ考えたわ。
「えー? ぬいぐるみかなぁ、おままごととか?」
「ままごと、ええなぁ。可愛いなぁ」
「ちっちゃい手で、何作ってくれるんやろ」
「うわー、ままごとの相手したりするん?」
だぁれも、ままごと買うたって、言うてへんやん。
こいつら、勝手なことばっかし言いやがって。
「どーでもええやん、そんなん。なぁ、もう帰ってええんやろ?」
「ああ、ええで。明日も、時間に遅れんなや」
「わかってるわ。ほな、お先」
一人のメンバーが、さっさと帰り仕度をして、スタジオを出て行った。
「じゃあ、俺も帰るわ」
「なん? 結局、行かへんの?」
「お前、何、聞いとってん。このコ、放っといて俺とメシ行ったらええやん」
「二人って、寂しない? あ、そっちは? 行く?」
「残念やけど、俺、まだ別のやつの撮り、残ってるし」
一人は、そう言って苦笑い。
もう一人は。
「僕、さっき、お弁当食べたし。もう眠たいし。今日はええわ」
大きなあくびをひとつ。
「あ、じゃあ、お前は行くやんな?」
ごそごそ携帯持ち出して、メール打ちはじめたそいつは、
「行かへん。用事、でけた」
あっさりと断った。
「またフラレたな」
「そいつ、俺とメシ行く気、絶対にあらへんわ。ええわ、もう。二人で行こうや」
なんや、可哀そうになってきたわ。
「ちょっとだけ、行ったろか?」
「あかんやろが。お前は早よ帰ってやれって」
「ほんでもさぁ」
「ええって、ええって。ちょっとで済むわけないもん。この人、きっとまたべろべろになるで」
「そうかぁ?」
「ええから、早よ帰ってやらんと、寝てまうで」
言われて、俺は腕時計を見た。
確かに、下手したら、もう寝てるかもわからん時間には、なってる。
「あ、ああ、ほな」
「ほなおつー」
「さいなら」
メンバーの声に押されるように、俺はスタジオを後にした。
カチャ・・・
「ただいまー」
玄関を開けた途端、
「ぱーぱッ!!」
ちっちゃな手を広げて、舞音が抱きついてきた。
「おま・・・、まだ、起きとったんか」
舞音を抱き上げながら、いつもの、おかえりのチュウや。
「ぱーぱ、くちゃい」
「ん? あー、煙草、吸ったからなー」
「いやん」
「いやん、て、お前、これがパパの匂いやんか。我慢せぇや」
「いやんもん。がやがやちて」
がやがや、て、なんや?
ここんとこ、だいぶお喋りの上手くなった舞音やけど、
まだわからん言葉が、ようけあるわ。
「ガラガラ、でしょ? 舞音」
舞音と俺のやりとりを、笑いをこらえて彼女が見てる。
「がりゃがや?」
言い直す舞音。
でも、やっぱし、間違うてる。
可愛ええなー。
この舌っ足らずなカンジ。
「あ。うがい、か!」
「手も洗ってね」
「あ、ついでやから、風呂入るわ。寒かったし。出来てる?」
「まのん、もー。ちゃぷん、しゅゆ」
「やぁだ、もう。舞音は、さっき入ったでしょ?」
「やーやーやー!! まのっもー。ちゃぷうん。パパ??」
ねだるように、舞音が俺の首筋に手をまわしてしがみつく。
「しゃあないな。たまには、ええか?」
俺は、彼女の顔色をうかがう。
「もう。舞音に甘いんだから。風邪ひかせても、しらないからね」
呆れたような、怒ったような表情の彼女が、そこにいた。
「なにスネてんねん。せやったら、一緒に入ろうや」
「入りませんッ!」
そう言って、彼女はくるりと背を向けた。
あかんやん。
スネてるやん。
子供にやきもちやいて、どないするん。
「なぁ、入ろうや、一緒に。入ってください、お願いします」
彼女の後ろから耳元に囁く。
くすぐったそうにしながら、
「お腹、空いてるんでしょ? その間に用意しとく」
俺を見上げて、彼女が微笑った。
ちゃぷ・・・
立ち上る湯気の中で、舞音がはしゃぐ。
細こくてちっちゃい身体やのに、
抱くと、ふんわり、押し戻してくる弾力、
ぷくぷくっとして、柔らかい肌。
「ぱーぱ、抱っこ」
さして大きくないバスタブの中、舞音が抱きついてきた。
膝に乗せるようにして、舞音を肩まで座らせる。
お湯よりあったかく感じる舞音の温もりが、俺に伝わってくる。
こうして触れ合ってるだけで、
なんでこんなに、優しい気分になれるんやろう。
イヤなことがあって、シンドイこともあって、
もうええわ、って思いながら、こうして家に帰ってきても、
舞音と他愛のない言葉のやりとりしてるだけで、
なんか、浄化されてく気がするわ。
子供って、不思議やな。
「なぁ、舞音、パパ、好きか?」
「しゅき」
「どれくらい?」
「んーーっと、んーーっと、んーーーっと、ぱっぱい」
そう言って両手を大きく広げた。
「ぱんぱんまー、ちて」
なんて?
なに?
ぱんぱんまーって。
よーわからんわ。
舞音の言葉は、独特やな。
そのうち、ちゃあんと言葉が通じるようになったら、
こんな可愛い言葉も、聞けんくなるんやな。
「ぱんぱんまー。ねー、ぱんぱんまーーー」
言いながら、お湯の表面をぴちゃぴちゃ叩く舞音。
水しぶきが飛んで、顔にかかる。
「やめろや、もう。なんやねん、ぱんぱんまーって」
にっこり笑ってる舞音。
どうやら、水音を立てる方が気に入ったらしい。
ま、ええか。
『舞音、もう上がる?』
ガラス戸の向こうから、声がする。
『ご飯の支度、出来たんだけど』
「おぅ。入ってこんの?」
『何言ってるのよ、入らないわよ』
「なんや、一緒に入ったらええのに」
『結構です』
「なぁ、入って来いって。スキンシップしようや」
『ご飯が冷めちゃうでしょ』
「ほな、あとで、違うスキンシップする?」
『違うスキンシップって・・・』
「舞音に、弟か妹、つくったろ」
『もう!』
「ええやん、な?」
『舞音、上がるの? まだなの?』
話、誤魔化しよったな。
恥ずかしがりめ。
「舞音、もうママが、出ておいでって」
水で遊び続けてる舞音をバスタブから出すと、軽く顔を拭いてやった。
「あったかくなったか?」
「ぱんぱんまー?」
あのな。
せやから、その『ぱんぱんまー』ってのが、いまいち、ようわからんねんけど。
こういう時の常套手段いうたら・・・
「ママに訊いてみ」
俺はそう言いながら、舞音の頭に手を乗せた。
「あい」
可愛い返事をひとつした舞音の頬は、ほかほかのピンク色だった。
ガラス戸に、舞音のシルエットが映る。
バスタオルでくるまれながら、舞音が彼女に尋ねてる。
「ぱんぱんまー?」
「うん、かわいいほっぺになったよ」
あー、やっぱり母親には通じんねんな。
すごいな。
「ビール、飲む?日本酒?焼酎?」
風呂上がりの俺に、彼女が問いかける。
小さな子供用の椅子に座った舞音がこっちを向いた。
「あー、じゃあ、とりあえず、ビール」
「まのっも、びゆ」
「あほぅ。ビールはあかんやろ」
「やー、びゆ」
駄々をこねるように、足をばたつかせてる舞音。
「・・・だってさ」
俺は、彼女の方を見る。
くすくす笑いながら、彼女は、舞音に吸い口の付いたコップを渡す。
「舞音、これ飲んだら、ねんねしようね」
「ねんね、いやー」
ふくれっ面の舞音。
「ええやん、無理くり寝かさんでも。そのうち、眠たなったら、勝手に寝るやん」
「そうだけど、風邪ひかせちゃうわ」
心配症やな。
これっくらいの子供って、風邪ひきながら育つんとちゃうん?
「ぱんぱんまー、しゅゆ」
舞音が、椅子から滑るように下りる。
「っと、お・・・、おお、危ないな。気ィつけや」
舞音の身体を受け止めようと俺は、手を伸ばす。
すとん、と尻もちをついた舞音は、にかにか笑いながら、その俺の手を引っ張る。
「? なに?」
リビングのTVの前、
舞音が好きなお遊戯やアニメのDVDが、きちんと整理されて箱に入ってる。
座り込んだ舞音が選んだのは、まるい大きな顔に赤いほっぺ、黄色い靴に、こげ茶のマントの正義の味方。
「ぱんぱんまー、しゅゆ」
俺に手渡しながら、身体を上下に揺すって、すでに、なんや楽しそうに踊ってる。
「これ、かけたらええんやな」
俺は、DVDをセットしてやる。
オープニングの音が鳴り出すと、待ちかねたように手を振り、足を動かしだす。
嬉しそう、やな。
ほんでも、こんなん、いつ買うたんやろ。
「クリスマスプレゼント、よ」
ダイニングの方から、彼女が言う。
「誰から?」
「お義母さんから、届いたの」
「おかんが? 舞音に? へぇ・・・」
「気に入っちゃって、一日中ずっと見ながら踊ってるわよ。エンドレスで」
「一日中って、大げさな」
「ハマったら大変よ、ってママ友が言ってたけど、本当だったわ」
「へえ、踊るん、好きなんや」
ちっちゃな手足を、一生懸命に動かして、見よう見まねで踊ってる舞音。
御世辞にも、画面と合うてるとは言われへんな。
こんなとこも、親に似るんか?
「冷めるわよ」
俺は、ダイニングに戻る。
テーブルに並べられた食事。
いつもなら、
野菜中心で、いろんな料理がちょっとずつ。
せやけど、今日は違う。
「ごめんね、ありきたりのメニューで。考えつかなくて」
チキンとサラダ。
パスタが2種類。
それに、スープ。
小さなケーキには、サンタのろうそく。
「こういうの、嫌いだって知ってるけど」
向こう側の席に座りながら、彼女が、言った。
「やっぱり、今日は特別だから」
「やりたいようにしたらええよ。こういうんも、舞音のためには必要な行事やろ?」
「うん、それもあるけど」
「けど、なに?」
俺は、サラダのレタスをつまんで口に入れながら、彼女を見る。
うわッ、なに?
なんで泣いてるん?
「ちょ、待って。あかんやん、なに? まだ食べたらアカン?」
「違う、ごめ・・・。いいの、食べて」
「いや、いいのって言われても、目の前で泣かれたら、メシ、食べられんし」
「嬉しかったから。あなたと、クリスマスを過ごすの」
「嬉しがるようなことか?」
そう言った途端に、俺は、思いだした。
彼女と出会ってから、クリスマスはいっつも仕事やったこと。
逢う約束してても、わずかな時間やったり、
ゆっくり食事もとれんような、そんなせわしなさ。
クリスマスに限ったことやないわ。
結婚しても変わらへん、俺のスタンス。
仕事やら、付きあいやら、仲間優先の約束。
つい後回しになる、おろそかになる、彼女との小さな約束ごと。
そのたび、微笑って許してくれてた彼女。
今夜にしたって、そうやわ。
もしあの時、メンバーと食事に行ってたら、
また、彼女とすれ違ってしまうとこやったんやな。
「なあ、ビール」
「あ、はい」
涙をぬぐった彼女が、冷蔵庫を開けてる。
「コップ、2コ、持っておいで」
テーブルに置かれたコップ。
冷えたビールを注ごうとする彼女の手を制して、俺は缶をその手からはずす。
「ええから、座り」
彼女が素直に、向こう側に座る。
笑顔の消えた、微妙な表情の彼女がそこにいる。
こんな顔させたくて、彼女と一緒になったんとちゃうやん。
何してんねん、俺。
「あ、私、飲めないよ」
一つ目のコップをビールで満たしたあと、
もうひとつにもビールを注ごうとした俺に、彼女が言った。
「飲めない、んとちゃうやろ。飲まないだけやん」
彼女がアルコールを口にしなくなったのは、舞音がお腹に入ったからや。
もともとは、俺の酒にも付き合ってグラスをあけて、
ケラケラ笑う、陽気な酒飲みやったもんな。
俺は、もうひとつのコップにもビールを注ぎ、ひとつを彼女に渡す。
「乾杯、しよ」
キンッ!
小さくグラスが音を立てる。
「メリークリスマス」
「メリークリスマス・・・」
俺がグラスに口を付けるのを見て、彼女もグラスを口に運ぶ。
彼女ののどが、かすかに動いた。
「にがッ」
眉をひそめる彼女。
「相変わらずやな、ビール、苦手か?」
「前より苦く感じるわ。味覚が変わったのかな」
そう言って、彼女はグラスを置く。
「なんか、すぐに酔っちゃいそう」
「酔ったってええやん。家なんやし」
「酔ったら眠くなるの、知ってるでしょ? 後片付けや舞音の世話もあるし」
「後片付けなん、出来る時でええやん。汚れもんが多少たまったかて、だぁれも文句言わへんで」
「うーーーん」
「舞音の世話くらい、俺にも出来るし」
「うーーーん」
「ほれ、飲んで」
俺は、彼女のグラスに、もう一度ビールを注ぐ。
「そう?」
にこやかに笑う彼女の、この顔を、もっと見ていたい、
そう、思った。
外は雪。
音もなく、雪。
家の中では、俺と彼女の、他愛のない日常。
彼女が守りたいと望んだ、たったひとつの世界。
俺と、彼女と、舞音。
重ねていく、ありふれた日々。
大好きも、大嫌いも、全部詰め込んで、
互いに違うからこそ、分かりあおうとする日々。
今更ながらに気づく。
大切なものは、いつもここにあるんだ、と。
彼女が守ってくれる、ここに。
舞音がいてくれる、ここに。
だから俺は、明日も立ち向かえるんだ。
一人でいても、ひとりじゃないから。
いつしか、BGMだった舞音のはしゃぐ声が聞こえなくなった。
「電池が切れたんか?」
俺は立ちあがって、TVの前を覗く。
こてんと倒れるように舞音。
「あーあ。やっぱり」
俺は舞音を抱き抱える。
「また、重くなったんやな」
眠った舞音の重さが、俺の腕に、確かな責任を感じさせる。
俺が守らなければならないものの、重みを。
ここからもっと、もっと、重くなるんやろな。
そのうち、こんなふうに抱きあげることすら出来んくなるんやろな。
「舞音、ベッドに寝かせてくるわ」
「うん、大丈夫? 出来る?」
「あほ。出来るわ、それくらい」
とは言ったものの。
「すまん、ドアだけ開けて」
苦笑しながら彼女が席を立ち、リビングのドアを開け、
ついでのように先に立って、寝室のドアを開けてくれた。
ベッドに降ろされても、ピクリともぐずらずに、すやすや眠ったままの舞音。
ほんまに電池の切れた人形みたいやな。
「おやすみ、舞音」
舞音のおでこに口付ける。
「もうすぐ、サンタが来るからな」
「サンタ?」
「おぅ」
「そういうの、信じてなかったんじゃないの?」
「信じてるわけちゃうよ」
「なのに、サンタ?」
「サンタはおるって、教えてくれたんはお前やろ」
「?」
「大切な人の笑顔を見たいと思う心がサンタなんやって、おまえ、そう言ったよな」
「うん」
「せやったら、俺の中にもサンタはおるし。お前の中にも、舞音の中にも、きっとおるやろ」
「舞音、サンタさんに会えるといいわね」
「会えるやろ。舞音ほど、ええコ、他におらんのやから」
くすッ、と小さく彼女が微笑った。
「親ばか、か?」
「ううん。ばかになれるから親なんだな、と思って」
「俺らも、ちょっとずつ親になってくんやな」
「ふたりで、一緒に、ね」
彼女の手が、俺の手のひらに重なった。
俺の肩にもたれかかった彼女の髪が、頬に触れた。
「俺のそば、離れんなや」
「え?」
驚いたように、彼女が顔を上げた。
「俺の隣に、こうして、いつまでも、おってくれるよな?」
じっと俺を見たあとで、こくん、とうなづいた彼女。
うつむいたまま、
聞きとれぬほどの、かすかな声でつぶやいた。
「サンタに逢えたわ」
「ん? なに?」
訊き返す俺に、「なんでもない」と彼女は笑い、
俺を見上げる。
「私たちも、もう、寝よ。舞音をサンタに逢わせてあげよ?」
「ん、そやな」
翌朝。
彼女の目を覚ましたのは、リズムも音階もめちゃめちゃな、
だけどとてもかわいい、ピアノの音色。
久しぶりに身体に入れたアルコールが、彼女の眠りを深くしたこともあって、
いつもより少しだけ遅い目覚めの時間だった。
隣に眠るはずの彼の姿も、
可愛い舞音の姿も、その部屋にはなく、ただ、遠くでかわいいピアノの音だけが響いてる。
起きた彼女の目に飛び込んできたのは、
枕もとの真っ赤なバラの花束と、
添えられた一枚のカード。
『愛してる、ずっと』
見慣れた筆跡の、その文字が、
彼女にとって、永遠のサンタクロースだった。
Fin.
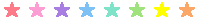
お気に召しましたら、
関ジャニWEBランキング
にほんブログ村ランキング
ぽちんっと押して頂けると、とっても嬉しいです。