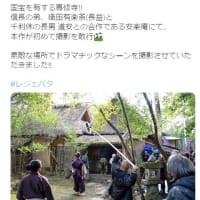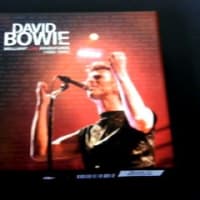本間美術館

市中山居の茶-本間家伝来の茶道具-
期間:5月25日(木)~7月4日(火)

三猿狂歌 沢庵宗彭筆
寛永六年(1629)紫衣事件により出羽国上山に配流となった沢庵。
この狂歌は配流3年目となった寛永九年(壬申)の歳首に配所での心境を吐露し詠んだもの。
青貝布袋香合
黒漆塗りの地に螺鈿で布袋を表す。顔は毛彫り。
伝来は利休、安楽庵策伝、堀式部、酒井忠勝より酒井家伝来の後に本間家へ。
青磁牡丹唐草文大花瓶(一対)
元時代、中国龍泉窯製。頸部には横筋、胴に牡丹唐草文を表す。
加藤清正が朝鮮より持ち帰ったとされ、清正の三男で二代熊本藩主忠広が庄内に配流となった際持参した。その後庄内藩酒井家に伝わった後に本間家へ。
その他にも、利休・遠州・石州・沢庵の茶杓、細川三斎所持の古瀬戸平茶碗、長次郎の黒樂(さび介)、ノンコウの赤樂馬盥茶碗に後陽成天皇筆「伊勢」・松花堂昭乗筆「円頓止観語」など内容豊富でした。
美術館の隣には

清遠閣
文化十年(1813)藩主酒井侯が領内巡視をする際の休憩所としてつくられた。

本間氏別邸庭園(鶴舞園)
清遠閣と共に築かれた池泉回遊式庭園
少し時間もありましたので酒田の街へ

本間家旧本邸
幕府の巡見使一行を迎えるための宿舎として明和5年(1768)に新築し、庄内藩主酒井家に献上した、二千石格式の長屋門構えの武家屋敷。

庭
船体を安定させる綿積石(海神石)として諸国から北前船で運んできた銘石を配しているそう。
お次は

相馬樓
江戸時代から酒田を代表する料亭であった「相馬屋」を改装し平成12年3月に開樓。
二階の大広間酒田舞娘による踊りや食事が楽しめるそう。残念ながら時間の関係で踊りは拝見出来ませんでしたが、舞娘さんに2階を案内してもらいました(1階は自由見学)。
撮影で吉永小百合さんや綾瀬はるかさんも訪れたそうです。

樓内にはには4畳半の茶室もあり、また竹久夢二美術館も併設されていました。
前回は大雨、今回は電車の遅れとなかなかゆっくり拝見できない酒田の街。三度目の正直で再訪したいと思います。