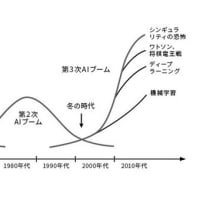富士通は定年後も役割に見合った処遇をする「モダナイマイスター」と呼ぶ認定資格制度の運用を始めた
日本経済新聞社は2024年度の日経サステナブル総合調査のスマートワーク経営編をまとめた。人材を多方面で生かそうとする企業の姿勢が鮮明となった。
シニア雇用では昇給につながる評価制度を導入した企業が4割を占めた。人材獲得競争が激しさを増すなか、多様性確保が企業の成長に直結するとみて、待遇改善などで人手の確保を急ぐ。
調査ではダイバーシティー(多様性)を推進するために導入している施策を聞いた。
シニアの活躍推進(継続雇用)のために「人事評価を実施し、昇給を実施」するとの回答が40.5%に上り、2023年度調査から7.8ポイント上昇した。「人事評価や業績評価を加味した賞与を支給」も61.3%と、同3.9ポイント伸びた。
富士通は4月、「モダナイマイスター」と呼ぶ認定資格制度の運用を始めた。
業務の遂行に必要なスキルを持つシニア人材を対象に定年前と同様の給与体系を適用し、役割に見合った処遇をする。
再雇用の上限年齢(65歳)を超えて働き続けることもできる。従来の再雇用制度では定年後に役職が付かず、給与水準は現役時代より減っていた。
新制度ではシニアの待遇改善のほか、マイスターが企業のシステム刷新に携わるIT(情報技術)エンジニアの「伴走役」として支援する仕組みにした。
基幹システムに長年使われていた大型コンピューターなどの技術知識と、一般的なサーバーで動く現代の情報システム構築の両方のノウハウを生かせるからだ。
IT業界では老朽化した基幹システムの不具合が増える「25年の崖」が予想され、エンジニア不足の深刻化が懸念されている。
富士通はマイスターを24年度中に計100人、26年度に計500人に増やす計画だ。

多様性の確保は企業の成長に欠かせない。調査では、女性や性的少数者(LGBTQ)などの活躍推進に向けた導入施策も聞いた。
女性関連では「女性特有の健康課題への理解を深めるための研修・セミナーの実施」が23年度比6.1ポイント増の56.5%、「不妊治療の通院に対する特別休暇の付与」が4.4ポイント増の38.7%だった。
LGBTQ関連でも「家族に関する手当や休暇の対象を同性パートナーに広げる」との回答が27%超に達するなど伸びが目立った。
日立製作所は4月、従業員が性別や国籍など多様性を尊重して働いた場合に人事考課を引き上げる制度を本格導入した。
半期ごとに設定する個人目標で、売上高や受注などの目標に加え、5%分を多様性に関する行動に割り当て、上司との面談で達成度合いを確認して人事考課に反映させる。
同社は海外勤務者の割合が約6割に達するなど、職場の人材が多様化している。新制度では「様々な文化や視点を持つ」「部門をまたがるメンバーで構成されるプロジェクトに参画する」など具体的な行動につながる目標を立て、その達成度合いが評価の対象となる。
国内では家族の定義に「同性パートナー」を追加し、各種勤務・休暇・福利厚生制度を適用するなどの施策を進めてきた。
4月には「日立グループ ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン(DEI)ポリシー」を改訂し、新たに2つのグローバルDEIトピック「LGBTQIA+、障がいおよびニューロダイバーシティ」を追加した。様々な価値観を持つ人が働きやすい職場づくりを進め、人材の獲得や定着につなげる。
味の素は30年度までに、リーダーシップ層で多様性を持った人材の構成比を30%に引き上げる目標を掲げる。
取締役とライン責任者(組織長、グループ長)の女性比率をそれぞれ30%に高める方針だ。
23年度には「国際間異動ガイドライン」を大幅に見直した。
23年度は270人弱が日本から海外に出向し、女性社員の能力開発支援プログラム参加なども含め、グループ全従業員の約1%(328人)がDE&I(多様性・公平性・包括性)推進活動に参加した。
男性育休、取得率6割
<picture class="picture_p166dhyf"><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5571266003112024000000-2.jpg?s=4fd4eebefe499551eecf71c84346f64d 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5571266003112024000000-2.jpg?s=4fd4eebefe499551eecf71c84346f64d 2x" media="(min-width: 1232px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5571266003112024000000-2.jpg?s=4fd4eebefe499551eecf71c84346f64d 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5571266003112024000000-2.jpg?s=4fd4eebefe499551eecf71c84346f64d 2x" media="(min-width: 992px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5571266003112024000000-2.jpg?s=4fd4eebefe499551eecf71c84346f64d 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5571266003112024000000-2.jpg?s=4fd4eebefe499551eecf71c84346f64d 2x" media="(min-width: 752px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5571266003112024000000-2.jpg?s=4fd4eebefe499551eecf71c84346f64d 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5571266003112024000000-2.jpg?s=4fd4eebefe499551eecf71c84346f64d 2x" media="(min-width: 316px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5571266003112024000000-2.jpg?s=4fd4eebefe499551eecf71c84346f64d 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5571266003112024000000-2.jpg?s=4fd4eebefe499551eecf71c84346f64d 2x" media="(min-width: 0px)" /> </picture>
</picture>
手不足が深刻化するなか、出産した女性の育児負担を軽減し職場復帰を後押しすることは、日本全体の課題となっている。
カギを握るのが男性の育児休業取得の促進だ。2022年の改正育児・介護休業法施行で社員に対する育休制度の周知や取得意向の確認も義務付けられた。企業は環境整備を急いでいる。
スマートワーク経営の調査でも、配偶者が出産した男性正社員の育休取得率は23年度に61%と、21年度(34%)比でほぼ倍増した。
この間、育休を連続1週間以上取得した人の比率も20%から49%に、連続1カ月以上取得した人の比率も10%から23%に高まった。
<picture class="picture_p166dhyf"><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5574189005112024000000-1.jpg?s=1948f650cd438f861b031368ba1fbf1e 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5574189005112024000000-1.jpg?s=1948f650cd438f861b031368ba1fbf1e 2x" media="(min-width: 1232px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5574189005112024000000-1.jpg?s=1948f650cd438f861b031368ba1fbf1e 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5574189005112024000000-1.jpg?s=1948f650cd438f861b031368ba1fbf1e 2x" media="(min-width: 992px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5574189005112024000000-1.jpg?s=1948f650cd438f861b031368ba1fbf1e 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5574189005112024000000-1.jpg?s=1948f650cd438f861b031368ba1fbf1e 2x" media="(min-width: 752px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5574189005112024000000-1.jpg?s=1948f650cd438f861b031368ba1fbf1e 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5574189005112024000000-1.jpg?s=1948f650cd438f861b031368ba1fbf1e 2x" media="(min-width: 316px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5574189005112024000000-1.jpg?s=1948f650cd438f861b031368ba1fbf1e 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5574189005112024000000-1.jpg?s=1948f650cd438f861b031368ba1fbf1e 2x" media="(min-width: 0px)" /></picture>

取得率が80%程度だった21年に社員向けアンケートを実施し、収入や業務の引き継ぎへの不安が取得の障害となっていることを確認。育児休業給付金の額を調べられるツールを提供するなど、不安の払拭に努めたことが奏功した。24年度に育休の社員から業務を引き継ぐ同僚の賞与を加算する仕組みも導入した。
伊藤忠商事は22年度から育児両立手当の支給を始めた。4週間以上育休を取得し子供が満1歳未満で復職した社員が対象になる。23年度に男性社員の育休の平均取得日数は25日となり21年度(8日)の3倍に増えた。花王は育休を取得する社員に育児とキャリアの両立ノウハウを教えるセミナーへの参加を求め、花王社員ではないパートナーの受講も推奨する。23年1月から男女とも10日間の有給育児休暇の取得も義務付けた。
23年4月には従業員数1千人超の企業には、男性社員の育休取得状況の公表も義務付けられた。
投資家が女性の活躍や人材の多様性を重視する傾向が強まるなか、男性の育休取得率の向上は企業価値も左右しそうだ。
【「スマートワーク経営」関連記事】

評価の方法
スマートワーク経営は「人材活用力」「人材投資力」「テクノロジー活用力」の3分野で構成される。
企業向けアンケート調査や公開データなどから13の評価指標を作成し、企業を評価した。
【アンケート調査の概要】
企業向け調査は2024年5月、全国の上場企業および従業員100人以上の有力非上場企業を対象に実施した。
有効回答は830社(うち上場企業774社)。なお、有力企業でもアンケートに回答を得られずランキング対象外となったり、回答項目の不足から得点が低く出たりするケースがある。
また一部指標においては日本経済新聞社の編集委員等(71人)の各社評価も使用した。
【3分野と測定指標】
3分野のスコアを測定する指標は以下の通り。
▽人材活用力 人材戦略とKPI、ダイバーシティー、多様で柔軟な働き方の実現、ワークライフバランス、エンゲージメント、現場力向上の6指標。
▽人材投資力 人材戦略とKPI、イノベーション推進・教育体制、人材確保・キャリア自律、多様なキャリアパス、先端分野人材の5指標。
▽テクノロジー活用力 テクノロジーの導入・関連投資、先端的テクノロジー活用の2指標。
【総合評価のウエート付け】
各分野の評価を4対2対1の割合で合算し、総合評価を作成した。
【総合評価・分野別評価の表記について】
総合評価は、各社の得点を偏差値化して作成した。★5個が偏差値70以上、以下★4.5個が65以上70未満、★4個が60以上65未満、★3.5個が55以上60未満、★3個が50以上55未満を表している。
また、各社の分野別評価は、偏差値70以上がS++、以下偏差値5刻みでS+、S、A++、A+、A、B++、B+、B、Cと表記している。
評価に使用した各種指標の集計結果やスコアの詳細データは日経リサーチが提供する。詳細はHP(https://service.nikkei-r.co.jp/service/smartwork)を参照。
(日経リサーチ 編集企画部)
賃上げは賃金水準を一律に引き上げるベースアップと、勤続年数が上がるごとに増える定期昇給からなる。
2014年春季労使交渉(春闘)から政府が産業界に対し賃上げを求める「官製春闘」が始まった。
産業界では正社員間でも賃金要求に差をつける「脱一律」の動きが広がる。
年功序列モデルが崩れ、生産性向上のために成果や役割に応じて賃金に差をつける流れが強まり、一律での賃上げ要求の意義は薄れている。
続きを読む
日経記事2024.11.14より引用
<picture class="picture_p166dhyf"><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5608107012112024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=638&h=1548&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=74d3b70cf36f54591a734eaf521a80d5 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5608107012112024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1276&h=3096&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=cab45800a7c5efec6be0120b0b50c40d 2x" media="(min-width: 1232px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5608107012112024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=638&h=1548&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=74d3b70cf36f54591a734eaf521a80d5 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5608107012112024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1276&h=3096&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=cab45800a7c5efec6be0120b0b50c40d 2x" media="(min-width: 992px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5608107012112024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=600&h=1455&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=28075e2ce8531bc100b039db158511b5 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5608107012112024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1200&h=2911&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=8f7484f0ac4a6ea3d05dc2bb12d161cb 2x" media="(min-width: 752px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5608107012112024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=600&h=1455&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=28075e2ce8531bc100b039db158511b5 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5608107012112024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1200&h=2911&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=8f7484f0ac4a6ea3d05dc2bb12d161cb 2x" media="(min-width: 316px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5608107012112024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=600&h=1455&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=28075e2ce8531bc100b039db158511b5 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5608107012112024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1200&h=2911&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=8f7484f0ac4a6ea3d05dc2bb12d161cb 2x" media="(min-width: 0px)" /></picture>
<picture class="picture_p166dhyf"><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5579494006112024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=638&h=656&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=762f05e45994e9b10ed0299b0efc981b 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5579494006112024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1276&h=1312&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=ebbc39097e233828d7d86fb1f226a91c 2x" media="(min-width: 1232px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5579494006112024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=638&h=656&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=762f05e45994e9b10ed0299b0efc981b 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5579494006112024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1276&h=1312&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=ebbc39097e233828d7d86fb1f226a91c 2x" media="(min-width: 992px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5579494006112024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=600&h=616&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=177d1db1cf2b98edcdbf84b1ed15e656 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5579494006112024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1200&h=1233&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=3fd0cea03a9bced332a8ede56124ec46 2x" media="(min-width: 752px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5579494006112024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=600&h=616&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=177d1db1cf2b98edcdbf84b1ed15e656 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5579494006112024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1200&h=1233&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=3fd0cea03a9bced332a8ede56124ec46 2x" media="(min-width: 316px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5579494006112024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=600&h=616&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=177d1db1cf2b98edcdbf84b1ed15e656 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5579494006112024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1200&h=1233&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=3fd0cea03a9bced332a8ede56124ec46 2x" media="(min-width: 0px)" /></picture>


 </picture>
</picture>