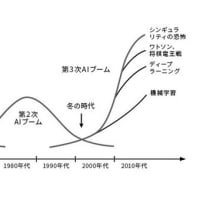国内の暗号資産(仮想通貨)の口座数が1100万を超えた。政府は安心して取引できるよう規制を通じて環境整備を図っている。
米国のトランプ政権が仮想通貨の規制緩和を目指すとの思惑から価格も高騰しており、ビットコインが実物資産の金のような存在になるとの見立てもある。
◇ ◇ ◇
流動性は金に近づく 日本暗号資産等取引業協会会長 小田玄紀氏
ビットコインには一獲千金を狙う投機マネーが支えているとの批判がある。この一面は否めないが、固執しすぎると大きな流れを見誤る。
今起きているのは、株式や債券に並ぶ投資資産としての地位確立の動きだ。英語でも「クリプトカレンシー(暗号通貨)」ではなく、「クリプトアセット(暗号資産)」と呼称の仕方が変化している。

おだ・げんき 東大法卒。
16年仮想通貨交換会社を創業し、代表取締役に就任。
その後にSBIホールディングスの傘下入り。23年から現職
なぜ機関投資家がビットコインを買い始めたのか。理由は流動性の高さにある。
2024年末時点で時価総額が10兆円を超えるトヨタ自動車など18社を合算すると297兆円。一方、ビットコインとイーサリアムを足すと320兆円とほぼ同規模になる。
1日あたりの取引量で比較するとさらに分かりやすい。ビットコインとイーサリアムで25兆円程度ある一方、東証の1日の売買代金は4兆〜5兆円と5倍の規模だ。
ビットコインは買いたいときに買えて売りたいときに売れる流動性の高い資産といえる。ビットコイン市場全体の5〜10%がビットコインETF(上場投資信託)の取引とされる。
ビットコインの時価総額は1月に約1.9兆ドル(290兆円)に達した。すでに銀(1.7兆ドル)を上回り、金の8分の1程度だ。金はETFの登場で流動性を手に入れた。ビットコインもETF拡大を通じて市場が金に近づく可能性がある。
ビットコインが法定通貨に置き換わるというシナリオが修正されてきたことも評価軸を変えた。ビットコインには国境を越えて送金できたり、商品・サービスを購入できたりする決済機能がある。
この機能が銀行にとって代わる新たな資金決済網をつくり、第2次大戦後に確立されたドル覇権を揺るがすのではないかとの懸念を先進国政府や中央銀行に抱かせた。
だが実際はビットコインが通貨機能を奪うことはなく、価値がドル資産に連動するステーブルコインも存在感を増している。今、ビットコイン脅威論を唱える人は少数派だ。
米トランプ大統領は1月の大統領令でステーブルコインなど民間の仮想通貨を振興する方針を示した。
目下の焦点は、米連邦準備理事会(FRB)が準備資産にビットコインを組み入れるかどうかだ。変動率の大きな資産を準備資産にすべきではないとの意見はある。
1日に1割変動したのはこの5年で20日程度だ。売買が増えれば変動率は下がる。議論に時間はかかるが準備資産組み入れは可能だろう。
こうした世界の大きな変化の中で、仮想通貨への対峙の仕方を考える必要がある。金融庁は改正資金決済法で規制しているビットコインを金融商品取引法でとらえなおそうとしている。
日本での仮想通貨口座数が1100万を超えるなか、投資家保護が重要になるとの考えからだ。
新たな規制方針はビットコインETFを解禁したり、最大55%の税率を株式と同じ20%に変更したりする地ならしになる。17年当時、世界のビットコイン取引の半数は円建てだった。
規制と技術革新のバランスを取れば、日本にマネーが戻る可能性は十分ある。
(聞き手は関口慶太)
◇ ◇ ◇
「投機バブル」が本質だ 京都大学名誉教授 川北英隆氏
ビットコインは大きく2つの理由で「デジタルゴールド」にはなり得ない。まず金には装飾品や工業用途での需要があるのに対し、ビットコインはこうした実用性が低い。
価値保存機能についても、仮想通貨の交換業者や資産管理(カストディー)企業での盗難・破綻リスクがあることを鑑みると、信頼性や永続性に欠ける。

かわきた・ひでたか 74年に日本生命保険入社、取締役財務企画部長など歴任。
同志社大教授などを経て現職。専門は証券市場など
にもかかわらず価格が上昇を続けているのは、1つの球根の価値が平均的な労働者の年収の10倍にまで高騰した後に暴落した、17世紀オランダの「チューリップバブル」を想起させる。
過去の価格上昇は将来的な値上がり益を約束するものではない。
ビットコインに投資資産としての価値があるのかどうかという議論をまず尽くすべきだ。
この議論を経ぬまま、年金基金などの機関投資家がビットコインの上場投資信託(ETF)をポートフォリオに組み込むことは受託者責任に反する。
ビットコインの採掘には多大な電力エネルギーを要する点でも、中長期的な視野に立ったESG(環境・社会・企業統治)精神にそぐわない。
仮想通貨業界では米政府によるビットコインの準備資産組み入れ構想に期待が高まっているが、実現はしないだろう。
投機性の強い仮想通貨を、法定通貨の番人である中央銀行が保有する不健全さは誰の目にも明らかだ。米連邦準備理事会(FRB)は賛成していない。
トランプ米大統領が仮想通貨業界に示す肯定的な姿勢は、業界に批判的だった前政権を否定するためのパフォーマンスだ。
トランプ氏は業界の潤沢な資金力や政治的支持を受け入れただけであり、仮想通貨そのものを理解しているようには見受けられない。
日本国内でも米国で先行上場したビットコインの現物ETF解禁の是非が議論され始めた。
ただビットコイン投資の規制緩和は、新NISA(少額投資非課税制度)拡充など長期での資産形成を促してきた従来の施策とは反対の方針だ。投機の世界に個人を呼び込むべきではない。
ビットコインETFを認めるのであれば、個人マネーや公的資金の流入は制限すべきだ。
もっとも、ビットコインなどの技術基盤であるブロックチェーン(分散型台帳)そのものを否定するつもりはない。
ブロックチェーンには現実の資産を裏付けにトークンを発行し、所有権の移転などをデジタルに記録する機能がある。こういったデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進に貢献する技術は社会的価値を高めていく。
かつてビットコインは法定通貨を代替するものになるという見方があった。貨幣とは国家が法のもと価値を保証して発行し、信用のおける中銀の供給によって流通するものだ。
ビットコインは民間が資産の裏付けなく発行している。いわば「たぬき村のお札」である。
ビットコインの大きな価値を占める送金機能は、中央銀行デジタル通貨(CBDC)の研究・開発が進めば、その優位性を失うだろう。
(聞き手は河井優香)
◇ ◇ ◇
米国は年金に採用進む ブロックストリーム最高投資責任者(CIO) ショーン・ビル氏
ビットコインは変動率が高いといわれるが、急速な普及による副作用にすぎない。
次世代インターネットといわれるブロックチェーン(分散型台帳)を基盤技術にしており、インターネットと同じように誰もが接続するようになれば、変動率は下がっていく。市場が成熟するにつれ金と同じ程度に収まるだろう。

Sean Bill カナダの仮想通貨会社で24年から現職。
米サンフランシスコ市職員退職年金基金の上級顧問などの経験も
その根拠は、ネットワーク通信の価値が接続されているシステムのユーザー数の2乗に比例するという「メトカーフの法則」にある。
現在10万ドル(約1500万円)を挟んで推移するビットコイン価格は短期的に、20万〜25万ドルに向けて上昇するとみている。
ビットコインは「デジタルゴールド」といわれるが、その理由は3つある。
まず供給が限定されている点だ。中央銀行は紙幣を刷ることでお金の供給を増やすことができるが、ビットコインは2100万枚と発行上限が決まっている。希少性があるため、インフレに強い資産になる。
さらに換金性が高く、ほとんどの国の通貨に交換できる。日本ではビットコインを円で売買するが、アメリカでは米ドルで売買される。
金と同じように世界中の通貨と交換できるので保有し続ける財産として価値がある。最後にデジタルにもかかわらず、偽造が不可能な点も金と同等の価値を有する理由になる。
コンピューターの計算作業に協力する見返りに新規発行されるビットコインを報酬として受け取ることをマイニング(採掘)と呼ぶ。
米証券取引委員会(SEC)が2024年1月にビットコイン現物の上場投資信託(ETF)を承認して以降、ETFが買い入れるビットコインの量は採掘によって生み出されるビットコインの量を上回っている。需要が供給を上回っていることが、ビットコインの価格を支える要因になっている。
19年に米カリフォルニア州のサンタクララバレー交通局(VTA)の最高投資責任者として年金基金を管理していた時、ビットコインの1〜3%の組み入れを提案した。
当時は株式や債券との相関が低かったため、資産に加えることでリターンを改善できた。
値下がりした場合の損失についても考慮した。ビットコインが50%の価値を失った場合も、年金基金はその損失を1〜2四半期以内に回復できると試算した。
最近では、資産運用大手ブラックロックが現在の変動率に基づきビットコインを1〜2%組み入れるよう推奨する報告書を発表するなど伝統的金融機関も分析が追いついてきた。
トランプ米大統領がビットコインをはじめとした暗号資産(仮想通貨)産業の支援を表明したことで、米国の多くの年金基金がビットコインを運用資産に組み入れるリスクとリターンをてんびんにかけている。
大統領周辺ではビットコインを政府の準備金に組み入れる構想も進んでいる。実際、ユタ州などいくつかの州では立法準備が進んでいる。実現した場合には政府が資産として認知したビットコインの需要が刺激され、価格は一段と上昇するだろう。
(聞き手は南泰葉)
◇ ◇ ◇
〈アンカー〉金融全体への影響、熟議を
トランプ大統領は2021年に「ビットコインは米ドルへの詐欺」と発言した。あれから4年。今度は「米国をビットコイン超大国にする」と手のひらを返す。
仮想通貨業界から流れる莫大な政治献金に目をつけたためだ。
米政治と仮想通貨業界との結びつきは簡単には崩れない。
シンシア・ルミス上院議員がビットコインを準備金として連邦準備理事会(FRB)が保有することを義務付ける法案を提出しているほか、ユタやケンタッキーなど20近い州が公的資金をビットコインに投じる準備に動いている。
中央銀行がビットコインを保有した場合の金融システムへの影響や、中央銀行デジタル通貨(CBDC)との共存可能性の議論は置き去りだ。
献金だけでなく学術研究にも資金を投じ、熟議を通じて可能性とリスクを見極める時だ。
(関口慶太)
【関連記事】
日経記事2025.2.23より引用
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(関連情報)
・ビット・コインとシークレットサービス、そしてブロック・チェーン関連記事 RJ人気記事
https://blog.goo.ne.jp/renaissancejapan/e/c1663b68c993d9843b59383abf758418
・ビットコインの生みの親、謎のサトシ・ナカモトは、本名が大分県別府市出身の「中本哲史」、アメリカでコンピューター・サイエンスを学び、アメリカ財務省に附属するシークレット・サービスに属する人物と推定します
https://blog.goo.ne.jp/renaissancejapan/e/eab8a5df3480e2ad4ce33706e320de83