今年はいつになく春の進みが早く、すでに稲荷山公園の桜は満開の時を迎えている。

コロナ前には「桜祭り」の舞台が設えられていた桜の木↓の下には小さなテントが張られていた。

こちら↓の桜はソメイヨシノに比べて白っぽい。

みっしりとまた手毬のような塊に丸くなって咲く桜の花。

北側斜面の桜も満開だ。

今年はいつになく春の進みが早く、すでに稲荷山公園の桜は満開の時を迎えている。

コロナ前には「桜祭り」の舞台が設えられていた桜の木↓の下には小さなテントが張られていた。

こちら↓の桜はソメイヨシノに比べて白っぽい。

みっしりとまた手毬のような塊に丸くなって咲く桜の花。

北側斜面の桜も満開だ。

普段、何気なく食べているマシュマロの袋の裏に「コーヒーマシュマロのふんわりムース(ベリージャム添え)」というのが載っているのに気付いた。

 材料(一人分):マシュマロ 7個、牛乳 カップ1/2、ラズベリージャム 小さじ2/1、ミックスベリー適量
材料(一人分):マシュマロ 7個、牛乳 カップ1/2、ラズベリージャム 小さじ2/1、ミックスベリー適量
マシュマロを耐熱容器に入れ、ふんわりラップをして1分レンジをかける。
そしてそこに牛乳を加えて30~60秒レンジをかけて取り出す。
マシュマロが溶けるまで泡立て器でかき混ぜ、容器に入れて冷蔵庫で冷やす。
とある。
1回目はその通りにやってみたのだが、マシュマロが容器の中で膨張してしまい、そのあと牛乳を入れて溶かすのがちょっと大変だった。
それで、牛乳にマシュマロを溶かせばいいので、牛乳をまず温めそこにマシュマロを入れて泡立て器でよくよく溶かし、容器に流し込んだ。

冷蔵庫から出して、ラズベリージャムもミックスベリーもなかったので、手元にあったブラックチェリーのジャムを乗せた。

甘みとジャムの適度な酸味がよくマッチして、ムースはふわふわにできたし美味しかった。
こんなに簡単にデザートが一品できちゃうなんてね
カタクリが稲荷山公園北斜面に咲き始めた。
未だ花の数は少なくて、斜面いっぱいになるにはもう少しかかるかな。

花弁がカールして太陽の光を喜んでいるよう。

満開の盛りを過ぎたコブシの木。

ぎっしりと密集する花・花・花・・・。

稲荷山公園の桜がちらほら咲き始めていた。

どっしりしたドイツパンが食べたくなって、仕事帰りに吉祥寺で下車した。
目指したのはこの街にあるドイツパンの専門店 『リンデ』。
『リンデ』。
この日求めたのは、ロッゲンミッシュブロート(左)と三角形のアルペンブロートの二種類だった。
ここではこちらの好みに合わせてパンをスライスしてくれるのでお願いして切ってもらう。
ドイツパン独特のどっしりしっかり、というパンで噛むほどに味わい深くなる。


三角のアルペンブロートは色々な種とチーズが混ぜられたライ麦パン、
ロッゲンミッシュブロートは「Linde」のロゴが入った酸味の効いたライ麦パンでどちらも美味しい。
普段はホームベーカリーでパン(最近は全粒粉パン)を焼いているが、たまにこんな風なパンが食べたくなる時がある。

手前の食パンが全粒粉のパン。
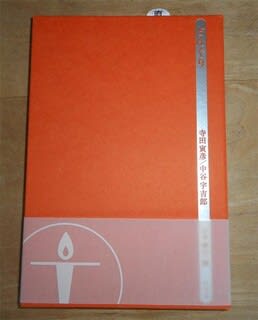
<灯光舎 本のともしび> 第1弾 「どんぐり」
 :寺田寅彦/中谷宇吉郎 著 古書善行堂店主・山本善行 撰
:寺田寅彦/中谷宇吉郎 著 古書善行堂店主・山本善行 撰
目次:どんぐり、コーヒー哲学序説、『団栗』のことなど、撰者あとがき
 :科学者として活躍しながら、随筆家としても数々の名筆を残した寺田寅彦と中谷宇吉郎。
:科学者として活躍しながら、随筆家としても数々の名筆を残した寺田寅彦と中谷宇吉郎。
今回は寺田寅彦の「どんぐり」「コーヒー哲学序説」と中谷宇吉郎「『団栗』のことなど」の三編を一冊の書籍にしてお届けします。~灯光舎HPより
京都の古書善行堂さんに注文していた『<灯光舎 本のともしび> 第1弾 「どんぐり」』と大阿久佳乃さんの『パンの耳』が先週届いた。
古書善行堂とはいえどちらも新刊本である。
この「どんぐり」は「本のともしび」として灯光舎からこれから刊行されるシリーズの第一巻ということで届くのを心待ちにしていた。
先ず、本を手にとってその佇まいの美しさに打たれる。
大事に読もう、大事に読みたい、そう読み手に思わせる佇まいである。
寺田寅彦という名は知っていても、しっかり読んだ記憶はなく、彼を師と仰いだ中谷宇吉郎を読むのはこれが初めてだ。
古書善行堂店主・山本善行 撰による「どんぐり、コーヒー哲学序説、『団栗』のことなど」の三作が収められているのだが、「どんぐり」と「『団栗』のことなど」が見事に響きあい、哀しさが深められ、本を閉じたときに心がしんとする。
そして最後の「撰者あとがき」を読むと、この本で選んだ作家に対する思い入れの深さ、膨大な作品の中でこれらを選んだ経緯などが語られ撰者の「本」に対する思いが伝わりあたたかな気持ちになる。
何度も手に取り読み返したい、そういう本がまた一冊ふえたことが嬉しい。
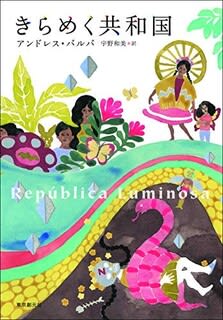
アンドレス・バルバ 著・宇野和美 訳
1994年、緑のジャングルと茶色い川をかかえる亜熱帯の町サンクリストバルに、理解不能な言葉を話す子どもたちがどこからともなく現れた。彼らは物乞いをしたり盗みを働いたりして大人たちを不安に陥れ、さらにスーパーを襲撃した。そして数ヶ月後、不可解な状況で32人の子どもたちが一斉に命を落とした。子どもたちはどこから来たのか。どうして死ぬことになったのか。社会福祉課の課長として衝撃的な出来事に関わった語り手が、22年後のいま、謎をひもといていく──。
現代スペインを代表する作家が奇妙な事件を通して描く、かわいらしさと表裏一体の子どもの暴力性、そして野生と文明、保護と支配の対比。純粋で残酷な子どもたちの物語。訳者あとがき=宇野和美~「BOOK」データベースより
物語の結末は読み手に最初の段階で伝えられているにも関わらず、ずっとつきまとう「どうなってしまうのだろうか?」という言いようのない不安を抱えながら、物語の残酷さから決して目をそらすことができない。
そしてその残酷さと裏腹に描かれる亜熱帯の街サンクリストバルの風景、町とそれを取り巻くジャングルの緑の深さ、そこにずっと漂う緊張感に胸が苦しくなる。
そして描かれる「きらめく共和国」の溢れる色彩と光がこの物語の残酷さを際立たせる。
回想録の形で語られる物語は、その形をとることで22年前のことを当時より更に明確に描き出し、そこにいた子どもたちと彼らを取り巻いていた大人たちの姿を突き付けてくる。