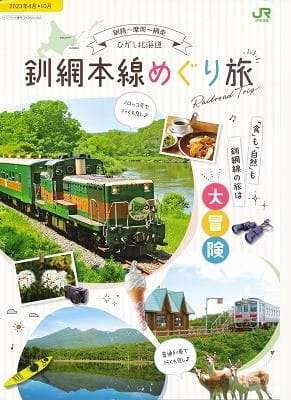列車は浜松海岸の昆布干場を横目に見て走り、

昆布盛駅に停車しました。
駅の名は、アイヌ語の「コムブモイ(昆布・湾)」に由来します。

駅の横にミズナラが葉を茂らせていました。
ミズナラで想い出すのが自転車で訪ねた稚内メグマ海岸のミズナラ群落です。
私はあの頃、ミズナラとカシワを見分けられませんでした。
両者は葉の縁のギザギザ(鋸歯)と、ドングリを包む部分(殻斗)の形が異なるのです。

国道142号線が花咲線に並走します。
国道142号は根室市と釧路市を結ぶ都道府県道で、国道44号が内陸部を通るのに対し、道道142号は海岸線に沿ったルートを走ります。
花の咲く季節に、起点から終点までをドライブしたい思いが募ります。

そんな道道142号にスチール製の柵が見えます。
これは吹払式防雪柵と呼ばれる設備で、近くで写した写真を以前のブログに載せましたので、興味のある方はどうぞご覧下さい。

昆布盛駅を出て8分程も走った頃、並走する道路の奥、牧草地の先に家屋が並びました。
根室の市街地です。

そして反対側の車窓に、ユルリ島が見えてきました。
お分かりでしょうか、牧草地の向こうに海が見え、その海に平たい島が浮かんでいます。

近寄って撮影した写真をご覧ください。
島を知らなければ、殆どの人が見落とします。

昆布盛台地からのユルリ島・モユルリ島 2020年撮影
島の位置を国土地理院の地図を用いて示すと以下の通りです。

出典:国土地理院ウェブサイト
私は列車が落石駅を出た頃から、ユルリ島・モユルリ島の姿を海上に求め続けていました。
先のページにも記しましたが、私は帯広畜産大学で自然探査会に所属しました。
そのクラブ顧問の芳賀教授が、1972年に根室教育委員会からユルリ島・モユルリ島海鳥類の調査を委託され、クラブの学生に調査に同行しないかと誘って頂いたのです。
昆布盛漁港から漁船でユルリ島に渡り、6月22日から26日までの5日間、ユルリ島カショノ浜の番屋で自炊し、海鳥類の調査を行いました。

私は海鳥類を初めて見ましたが、双眼鏡片手に、あれはエトピリカ、あれがケイマフリなどと教わりながら、両島で海鳥の営巣状態や分布状況などを調べ歩きました。

そんな調査で一番記憶に残ったのが、最終日に昆布盛漁港に上陸した後、漁師さんが振舞ってくれた浜茹での花咲ガニです。
あの花咲ガニは本当に絶品でした。
後にも先にも、あれほど美味いカニを食べたことがありません。
ということで、ユルリ島・モユルリ島で50年前に観察した幾つかの鳥を、大学後輩の千島淳さんのブログから、許可を得て拝借した写真で紹介します。

エトピリカ 撮影 千島淳

ウミウ 撮影 千島淳

ウトウ 撮影 千島淳

ケイマフリ 撮影 千島淳

チシマウガラス 撮影 千島淳
そして列車は日本最東端の駅として知られる東根室駅に停車し、

15時57分 花咲線の終着駅 根室駅に到着しました。

前回の「青春18きっぷ」 「青春18きっぷ」花の旅 北海道
「花の旅」の全て 「花の旅」 総合目次
筆者のホームページ 「PAPYRUS」