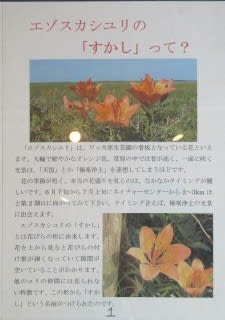車は陸奥湾に面した川内町から10分で脇野沢に到着しました。

脇野沢には天然記念物の「下北半島のニホンザル」を飼育する野猿公苑があります。

入園料の200円は、エサ代などの維持費に充てられるそうです。

サル山の横に、かすれた字の解説文が掲げられていました。
これだけを見ても、維持費に困窮している様子が分かります。
その内容を要約すると、
「この地区で昭和39年に十数頭のニホンザルの群れが確認され、昭和45年にニホンザルとその生息地が天然記念物に指定されました。
しかしその後、頭数の増加とともに農作物の被害が増加し、昭和59年に文化庁の許可を得てA1群72頭を捕獲し、この野猿公苑で保護 ・ 飼養している」
そうです。

私は昭和45年頃、下北半島北限のニホンザルを記録したNHKの番組を見た記憶があります。
その日以来、下北半島でニホンザルを一度見てみたいと思いましたが、野猿公苑のニホンザルは哀愁を漂わせていました。
今まで見てきた動物園のサル達とは異なる何か哲学的なものを感じさせます。
当然かもしれません、自然分布する世界最北限の過酷な雪国に生きる霊長類なのですから。
下北半島を旅するのであれば、唯一無二の脇野沢の野猿公苑を必ず訪ねるべきです。

脇野沢の野猿公苑を出る時、時刻を確認すると15時を過ぎていました。
今日はこの後、下北半島最東端の尻屋崎を訪ねますが、可能であれば、今日中に青森市街にたどり着いて、津軽三味線のライブを聞きたいのです。
果たして、うまくゆくでしょうか?
陸奥湾の渚沿いに続く国道338号を、東へ走り始めました。

やがて国道338号に松並木が現れました。
何故かは分かりませんが、この数年、旅するたびに、松や松並木に惹かれる自分を感じます。

この松並木が何処だったかを確かめようと思い、「国道338 松並木」で検索してヒットしたウィキペディアの「国道338号」を読んで驚きました。
国道338の始点は北海道の函館駅前だったのです。
函館市内は1.8㎞、その後津軽海峡フェリー航路19.0㎞を経て大間から下北半島を南下し、脇野沢、川内、むつ市、六ヶ所村、三沢市、を経て上北郡おいらせ町に至る総延長261.4㎞の国道なのです。
びっくりです。
このブログを書かなければ気付かなかった筈です。
そして、こんなことが起きるからブログ書きが楽しいのですが、
でもね~ こんな道草ばかりしてると、原稿が前に進まないんですよ。
困ったものです。
「花の旅」の全て 「花の旅」 総合目次
好奇心の植物観察
筆者のホームページ 「PAPYRUS」