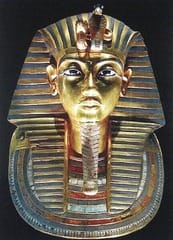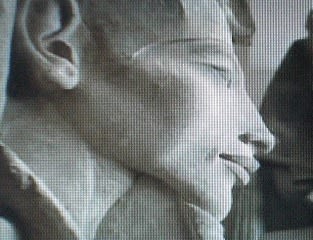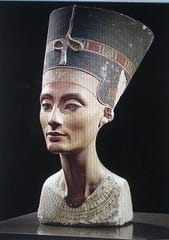容疑者Xの献身を見ました。
私は小説を読んで、映画も見たつもりになっていました。
不思議ですね。小説を頭の中で、映像化していたのですね。
今夜、見始めてから、あれ??見てないやと気づきました。
この映画は、なかなか良かったですよ。
小説より映画の方がいいと思いました。
こんなことは珍しいです。
大抵は小説の方が良くて、映画を見るとがっかりするのですが。
設定も面白いですね。天才数学者の頭脳と湯川博士の戦い、その数学者の頭でも
最後の女性が自首してくることが読めなかった。湯川博士も真理と私情とが自分の中で戦う。
雪山のシーンは、小説ではなかったような気がしますが、どうだったか?
女性が勤めているお弁当屋さんに、昔勤めていたスナックか何かの人が来るようなことがあったんじゃなかったな?と思いましたが、違ったかな?
でも、最後に女性が自首してきて、二人が泣き崩れるシーンが感動的でした。
あのような涙のシーンはあまり好きじゃなかったのですが、今回は、見ていて一緒に泣きたくなりました。
数学者が計算通りにいかなかったのです。自分は女性のために真実の愛を実現したという満足感でいたのでしょう。自分は人生に絶望して首つり自殺をしようとしているところに、突然のように現れて自分の人生を明るくしてくれた。そのことに感謝していて、今回のことがその感謝を示すことになるという満足感があったのです。しかし、女性の気持ちはそれでは済まないということに、数学者が気付かなかったのですね。
ただ、訳もなく殺されたホームレスが可哀そうですね。
本を読んだ時、そのことが納得いきませんでした。
そうだ、死体をアパートからどのように処理したかが、映画では説明されていませんでした。湯川博士が言ったようにバラバラにして川に捨てたのでしょうか?最後のシーンは川からそれを拾い集めているのかなと思いましたが、天才数学者は、女性が殺したことを否認しているということでしたから、バラバラ殺人は認めていないことになりますね。
高校生の娘さんは、刑事の追究からどのように逃れたのかということも気がかりでしたが、その部分は説明されませんでした。
私は小説を読んで、映画も見たつもりになっていました。
不思議ですね。小説を頭の中で、映像化していたのですね。
今夜、見始めてから、あれ??見てないやと気づきました。
この映画は、なかなか良かったですよ。
小説より映画の方がいいと思いました。
こんなことは珍しいです。
大抵は小説の方が良くて、映画を見るとがっかりするのですが。
設定も面白いですね。天才数学者の頭脳と湯川博士の戦い、その数学者の頭でも
最後の女性が自首してくることが読めなかった。湯川博士も真理と私情とが自分の中で戦う。
雪山のシーンは、小説ではなかったような気がしますが、どうだったか?
女性が勤めているお弁当屋さんに、昔勤めていたスナックか何かの人が来るようなことがあったんじゃなかったな?と思いましたが、違ったかな?
でも、最後に女性が自首してきて、二人が泣き崩れるシーンが感動的でした。
あのような涙のシーンはあまり好きじゃなかったのですが、今回は、見ていて一緒に泣きたくなりました。
数学者が計算通りにいかなかったのです。自分は女性のために真実の愛を実現したという満足感でいたのでしょう。自分は人生に絶望して首つり自殺をしようとしているところに、突然のように現れて自分の人生を明るくしてくれた。そのことに感謝していて、今回のことがその感謝を示すことになるという満足感があったのです。しかし、女性の気持ちはそれでは済まないということに、数学者が気付かなかったのですね。
ただ、訳もなく殺されたホームレスが可哀そうですね。
本を読んだ時、そのことが納得いきませんでした。
そうだ、死体をアパートからどのように処理したかが、映画では説明されていませんでした。湯川博士が言ったようにバラバラにして川に捨てたのでしょうか?最後のシーンは川からそれを拾い集めているのかなと思いましたが、天才数学者は、女性が殺したことを否認しているということでしたから、バラバラ殺人は認めていないことになりますね。
高校生の娘さんは、刑事の追究からどのように逃れたのかということも気がかりでしたが、その部分は説明されませんでした。