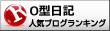以前に書いた事でもありますが地震や津波で自宅を失った被災者のうち
自宅を再建できる人を優先して仮設住宅に住まわせてあげるべきです。
下の記事の中にある公営住宅は石川県南部にある被災してない地域にあり
入居希望者が低調らしい。
だが仮設住宅もあくまで仮住まいです。
自宅を再建できない人は被災地に公営住宅が出来るまでは能登から離れるべきでしょう。
瓦礫の街は土埃も多くマスク生活となります。
阪神淡路大震災の仮設住宅でも孤独死が問題となった。
仮設住宅を終の棲家にしてはいけません。
県南部に元奥能登の住民が集まるコミュニティーを作ってみてはいかがかな?
自宅を再建できない高齢者が住む新しい集落を作り移住するのです。
公営住宅の希望者低調、仮設に集中 背景に地元志向 能登半島地震
配信
 </picture>
</picture>輪島市のキリコ会館多目的広場に完成した仮設住宅=石川県で2024年2月3日午前8時35分、滝川大貴撮影
能登半島地震で自宅を失った被災者の応急的な住まいとなる石川県内の公営住宅の利用率が、約6割にとどまっていることが県への取材で分かった。一方、被害が大きかった県北部の6市町で建設される応急仮設住宅の入居希望者は、予定戸数を上回っている。入居可能な公営住宅は県中南部に多く、地元に戻りたい被災者にとってネックになっているとみられる。元日の地震から1日で3カ月。いまだ住まいの確保が難航している被災者が多い実態がうかがえる。 【写真特集】輪島の孤立集落 募る危機感 県によると、提供可能な公営住宅739戸に対し、入居が決まったのは410戸(3月20日現在)。このうち、県営住宅は402戸に対して168戸にとどまる。県担当者は「県北部の公営住宅は被災して使えないものが多い。被災者は地元志向が強く、仮設住宅に希望が集中するのではないか」と説明する。 仮設住宅は3月22日現在、輪島市で1979戸が整備されるのに対し、約2倍の延べ4140件の入居希望がある。実際には、自宅が大規模半壊以上などの条件を満たしているかを審査して入居が決まるが、市担当者は「入居条件があっても現状、予定戸数を希望者が上回る」とみている。 他の自治体も予定戸数に対し、志賀町1・7倍、珠洲(すず)市と能登町1・6倍、七尾市1・5倍、穴水町1・2倍の希望がある。各市町は今後、仮設住宅の増設も検討する。県によると、3月末までに計約5000戸が着工された。【川畑岳志、山本康介】