

この本を読んでいますが、タカ長のボンクラ頭では理解できないことがほとんどで、なかなか「読了」にはなりません。
右側の本を読んでいて、タカ長の平素の不満に相通じることが書かれているのを見つけたので、そのことを話題にします。著者は福島原発事故を例に専門家への不満を書いておられますが、タカ長が「専門家」と言うのは日常テレビニュースなどで目にする専門家のことです。

「アメリカでトランプ大統領が誕生しました。日本外交はどのように対応したらよいのでしょうか。「専門家」は、、、、、、、、、、、。
と言うようなアナウンスの後に登場する「専門家」のことです。タカ長などマジメにニュースを聞いているわでではないので、その「専門家」のことを本気で考えたことは無かったのですが、その存在が気になりだしたのはコロナ禍が起きたころからだったと思います。
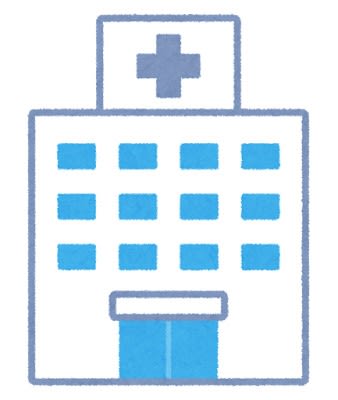
コロナ禍が起こったころ多くの高齢者が亡くなりました。しかし、子どもの死者はありませんでした。それより怖いのがインフルエンザ。
インフルエンザでは毎年のように死者が出ていますし、子どもがインフルエンザ脳症にかかると、命は助かっても後遺症が残って大変なことになりかねません。しかし、テレビに出る専門家はコロナ、コロナで、インフルエンザについて注意喚起していた「専門家」は、タカ長の知る限りゼロでした。
局側の意向があるのかも分かりませんが、それにしてもおかしい。それ以来テレビに出る「専門家」は、タカ長の中では軽くなりました。もう一つおかしいと感じたことがあります。この本の著者の思いに相通じることです。

重要なことは、不信の大きな原因が、専門家が説明に際して用いた「用語」が難しすぎたとか、開示された情報が少なかったとか、そうした問題だけではなかったということです。「専門家」たちが、自らも社会の中に生きる一人の「生活者」であるという感覚を失い、閉じられた集団の価値観だけを指針に行動しているのだという事実が一連の説明を通じて伝わってしまったことが、最大の問題だったと思います。(中村桂子)
タカ長があのころこのようなことを感じたのは、コロナの予防対策として言われていた「手洗い」のことです。「専門家」たちは外科医が手術前にするような「手洗い」をするように言っていました。まさに閉じられた集団の価値観、そこには「生活者」としての視点は見えません。
もし、国民の一人一人がこのような「手洗い」をしたら、昔の国鉄の「順法闘争」のようになるのではないか。走る列車がスムーズに走らなかったように、世の中がまともにまわらなくなるのではないか?
そのようなことがあって、タカ長の中では「専門家」が軽くなり、彼らの言うことを本気で聞く気がしなくなっています。


























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます